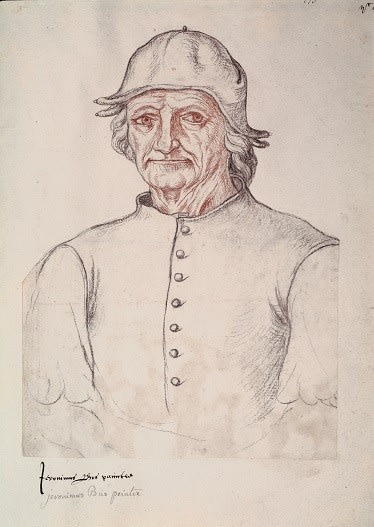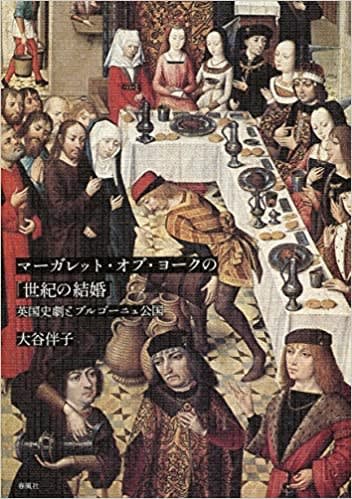さて、先に書いた ルーベンス《シャルル・ル・テメレールの肖像》(1)の続きを...
(2)ルーベンスはシャルルの顔を、どの先行作品を参考として描いたのか?

ピーテル・パウル・ルーベンス《シャル・ル・テメレールの肖像》(1618年頃)ウィーン美術史美術館
https://www.khm.at/objektdb/detail/1627
シャルル(Charles le Téméraire,1433 - 1477年)の肖像は、先に紹介した《エノー年代記》の少年時代や「アラス・コレクション」模写等も含め、意外に色々あるようだ。
で、ルーベンスがどの先行作品を参考したのか?と考える時、やはり観る人に「この肖像はシャルル・ル・テメレーだ」と容易にわかってもらえることが大切なポイントだったと想像する。ならば、各地に模写作品も残っているブルゴーニュ公家の公式ポートレート(?)が一番参考になると思うし、実際に見る機会も得やすいと思うのだ。
先ずは、一番有名な青年時代のシャルル像。この頃はまだ若々しいシャロレー伯。模写作品も各種あるようだ。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン(工房?)《シャルル・ル・テメレールの肖像》(1454年頃)ベルリン国立絵画館
ちなみに、ドイツ版Wikipediaによると、この作品はネーデルラント総督マルガレーテ(フィリップ・ル・ボーの妹)が所持していたものらしい。おじいちゃんの肖像画ね 。
。
そして、ディジョン博物館に残っているはオッサン壮年時代のシャルル。甲冑姿に「テメレール」らしさが出ているような気もするし、甲冑姿ということで参考になったかも 。
。

Unknown《シャルル・ル・テメレールの肖像》(オリジナルは1474年、16世紀半ばのコピー)ディジョン美術館
フランス版Wikipediaによると「1474年のオリジナル(?)の後の16世紀半ばのコピー。この肖像画は、亡くなった両親の遺体をディジョンのシャンモール修道院に葬送した1474年の日付を冠しており、当時、シャルル・ル・テメレールは素晴らしい鎧に身を包み、ディジョン入市式を行った。彼の入市式は盛大な祝祭として執り行われ、公爵(シャルル)は王になりたいという彼の願望を表明するスピーチをした。この機会に肖像画が作られたのかもしれない。このパネルの年代測定研究によると16世紀半ば以降のコピーと考えられる。」(少々意訳しました )
)
これら2作品だけでなく、残存するシャルルの肖像画に共通するのはクリンとした天パーっぽいクセ毛頭髪で、短い前髪があっちこっち向いているのがルーベンス作品にも踏襲されており、描かれた顔つきもなんとなく似せているような気がする 。特に鎧姿のシャルルはアイデア段階で参考になったような気がするのだけど、どうなのだろう??
。特に鎧姿のシャルルはアイデア段階で参考になったような気がするのだけど、どうなのだろう??
もちろん、ルーベンスは精悍で堂々とした騎士シャルルを描いており、「私は王になりたい!!」というその願望を絵にしたような、堂々とした王者の風格を持って描いているところが興味深いし上手いなぁと思う。
実際のシャルルはトリーア会議(1473年)で神聖ローマ皇帝フリードリッヒ3世に「私をローマ王にしろ!」と詰め寄った挙句、皇帝に逃げられたのだけどね。で、皇帝はこっそりトリーアから逃げだしたけど、父と一緒に会見したマクシミリアン1世(当時は14歳の少年)は、煌びやかな騎士姿のシャルルに魅了され憧れたようだ。
ルーベンス描くこの威風堂々騎士姿のシャルル像なら少年マクシミリアンが憧れるのも了解できるのだけどね 。
。
 。
。



 。
。











 、論文コピーしたのだが...(詳細は後日...)
、論文コピーしたのだが...(詳細は後日...) )
)
 )…
)…








 2018年「ブリューゲル展」を観た当時の解説には《マクシミリアン1世の肖像》となっていたものが、現在、美術館サイトでは《フィリップ・ル・ボーの肖像》になっているではありませんかっ
2018年「ブリューゲル展」を観た当時の解説には《マクシミリアン1世の肖像》となっていたものが、現在、美術館サイトでは《フィリップ・ル・ボーの肖像》になっているではありませんかっ