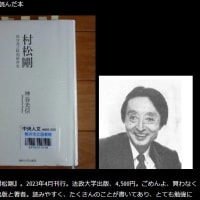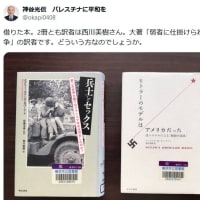▲ 今週の看猫;みけちゃん
▼ 新しい街でもぶどう記録;第303週

■ 今週の武相境斜面




■ 今週の草木花実





■ 今週の購書:清水知久、『アメリカ帝国』、1968年

米帝とは、アメリカ帝国の日本語の略称とwikiにある;

清水知久、『アメリカ帝国』、1968年を Amazon で購入。336円。この著者の名前さえ知らなかった。
帝国という語は、9・11の後から、盛んに使われた気がする。例えば、ネグリ&ハート、『<帝国>』、岩波新書では『アメリカ 黄昏の帝国』、『デモクラシーの帝国』などがある。21世紀に入り、学術用語の厳密性など気にしなくなったのか、気軽に使われるようになったのだろうか?
共産主義で「アメリカ帝国主義」という概念は使われれてきた。でも、学術的に使われていたとは知らなかった。最近、アメリカ研究についての本を見ていたら、清水知久、『アメリカ帝国』を知った。1968年だ。清水知久は、当時、日本女子大学の助教授。活動していた学会は、日本西洋史学会とのこと。
この世には、『米帝』という本は無さそうだ。チャイナで『美帝』という本の有無はわからない。
清水知久、『アメリカ帝国』では、アメリカ史の全体像を構成する軸は何かを考え、それは帝国性である。その帝国性は、領土的・商業的膨張、暴力を根幹とする他民族支配としての黒人奴隷制、インディアン絶滅の3つであるという説。
最近の1619 Projectと通じるのだろうか?というか、1960年代後半の米国でのニューレフト歴史学の影響か? これから調べる。
ところで、この清水知久、『アメリカ帝国』は、亜紀書房の亜紀・現代史叢書の一巻。亜紀・現代史叢書なんて、初めて知った。この叢書は他の巻に、インド現代史(石田保昭)、社会主義国家(菊地昌典)などがある。「1968年"革命"」の時代の"造反"教官(?)が著者となっている。
■