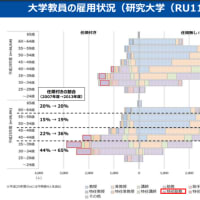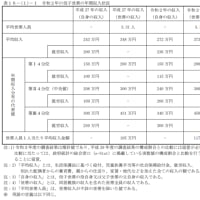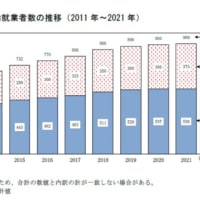今日、新聞社各社のWebサイトを見ていたら、同じテーマの記事が2つあった。
それは「読書感想文」についての記事だ。
朝日新聞:教育学者・斎藤孝さんに聞く読書感想文のコツ 本が苦手な子には
Huffpost::三谷幸喜さんが勧める「読書感想文」の書き方。「子どもの頃知りたかった」と反響呼ぶ
同時期に、「読書感想文」についての記事が出る、ということも珍しい気がする。
と同時に、夏休みの宿題の中でも「自由研究」と同じように「読書感想文」が、とても大変なものである、ということを示しているのだな~と、感じる。
確かに子どもの頃、読書感想文を書くのが苦手だった。
それは、自分の感想を素直に書くと、先生たちからは決して評価が高い内容とは、ならなかったからだ。
別に読書感想文で、先生から高い評価を受けようとは思わないのだが、批判めいたことが赤字で戻ってくるのがとても嫌だった。
そもそも、「読書感想文」を書くための「推薦図書」とか「課題図書」と言われる本を、面白いと感じたことがなかった、というのが本当のところだったように思う。
当然、読書感想文も「面白かった」という言葉は書けないし、「感動した」という言葉も出てはこない。
このような時、「主人公の気持ちになって」とか、「作者の思いを感じて」等ということを書くことが、推奨されるのだと思うのだが、残念ながら私にはそのような感性がなかったらしい。
そのため、「読書感想文」には良い思いではない。
というよりも、夏休みの宿題に「読書感想文は、本当に必要なのか?」と、以前から疑問に感じている。
「読書感想文」いうと、小中学生が書くもののように思えるが、見方を変えると「書評」のようなものでもある。
大人で「書評」が書ける人は、どれほどいるのだろう?と、常々思っているからだ。
まして、作者の思いなど、想像することはできるが、それはあくまでも私の中の想像でしかない。
あくまでも、私が想像した作者の思いであって、本当の作者の思いなのかは、わからないのだ。
事実、故橋本治さんはご自身のエッセイ(だったと思う)に、自分の作品が受験に使われ、設問に「作者の気持ち」を問われていて、その設問の解答にどれも当てはまらない、と書いていらっしゃった。
その一文を読んだとき、「わが意を得たり!」という気持ちになったのだ。
「作者の気持ち」は作者にしかわからないし、それを想像で感じる事は出来ても、想像そのものは読み手に任されるべきことのはずなのだ。
当然のことながら、他者が想像したことに作者でもなければ、その感想を書いた生徒でもない先生が、評価をすること自体どこかで大きなズレが起きて当然だろうし、そこには正解等はなく「思った・感じた・想像した」ということに、評価をするということに意味や理由があるのだろうか?と、思うのだ。
そろそろ「読書感想文」ではなく、夏休みに読んだ本とか体験した(遊び)リストに+一言感想のようなものにしても良いのでは?
「面白かった」という一文に、「何か面白かった?その時、どんなことを感じた?」という言葉を、先生が戻すことで、子どもたちは「何が面白くて、どんなことを感じたのか?」ということを、一生懸命に自分で考え「言葉にする」という面白さを発見し、子ども自身で興味や関心が整理され、まとめる力が育つのでは?と、自分の経験から感じるのだ。