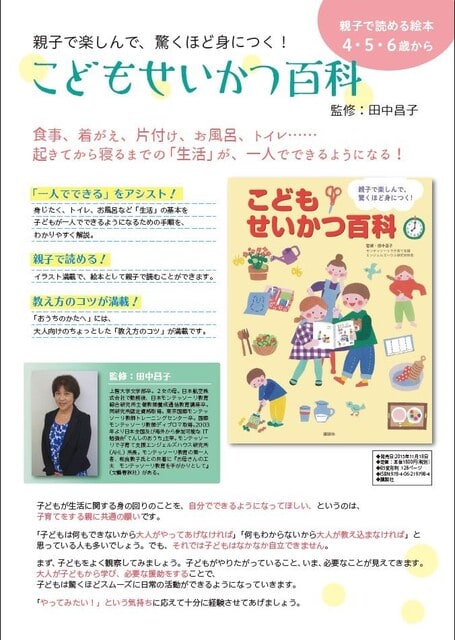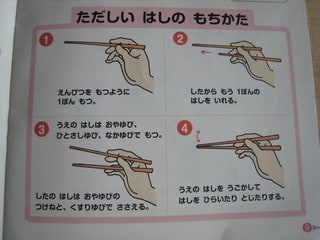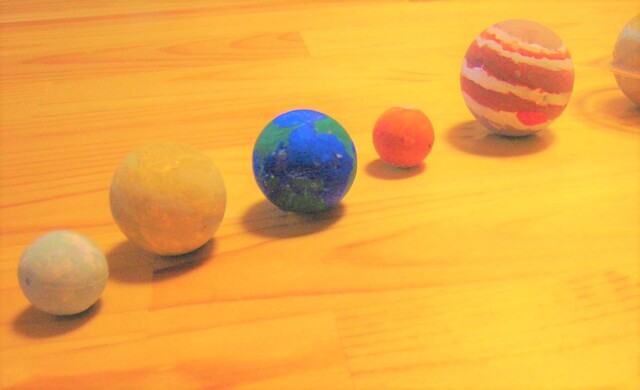ご覧いただきありがとうございます。
gooブログがサービス終了するため(2025年11月)
アメブロへお引越ししていますので、こちらもよろしくお願いいたします。
https://ameblo.jp/kodomonoie-aiai/
2015年10月11月 インファント・コミュニティの様子です。
↓絵の具でお絵かき、大好き。
こぼれにくい絵の具カップだから、小さな子でも安心です。
↓実物と絵カード合わせ。
秋の果物を揃えました。
↓ひも通し。ひとりではまだ難しいので、お手伝いしながら完成。
↓ボタン。長くつなげるよ。
↓穴あけパンチ。
↓トング。
↓ピッチャーで豆のあけうつし。
↓シールの大小を区別して貼ります。
↓前回一人でできなかったひも通し。一人で繰り返しやっています。
↓「ぞう。きりん。らいおん。しまうま。んー、ふらみんご!」
「そうだねぇ。フラミンゴに似てるね。これは、だちょうって言うんだよ」
↓初めての絵の具。筆が気になります

紙に色がつくと、不思議そうに、ぞうきんで拭いています。
紙に描いた絵の具は、拭いても取れませんけどね
繰り返しやっているので、新しい紙に替えてあげました。
やっぱり不思議そう。
終わりにするというので、紙をはずして、
イーゼルについている絵の具をぞうきんで拭くのを見せると、
汚れたぞうきんを、洗濯かごに入れて、新しいぞうきんを持ってきました。
絵の具は初めてだったけど、おやつの時こぼしたらぞうきんを使うので、
ぞうきんをどうするのか、理解しているようです。
(ぞうきんの種類は、色で区別できるようにしています。)
子どもたちが、自分でできるように、環境を整えておくことの重要性を
毎回、子どもたちから教えられています。 ぜひ、こちらもお読みください。
ぜひ、こちらもお読みください。
モンテッソーリ教育を初めて知る方へ
マリア・モンテッソーリ
モンテッソーリに関する書籍