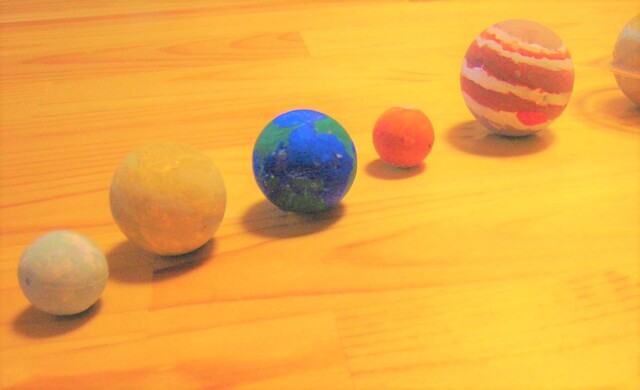2歳くらいのお子さんは、お母さんの真似をしたがりませんか?
そうじきをかけたがったり、洗濯物を干したがったり。
そんなときに、丁寧に教えてあげるとよいですね。
これは、わが家のほうきとちりとりですが、
息子が2歳くらいのときに、よく一緒に掃除しました。
子ども用のものを用意してあげるとよいと思いますが、
わが家の場合、「同じものが使いたい」というので、
これを使っていました。
そして、エコな掃除の仕方です。
1.要らない新聞紙を水にぬらし、しぼる
2.ぬれた新聞紙をビリビリにやぶる
3.掃除したい部屋にばらまく
4.集める場所を決めて、ほうきで掃く
5.ちりとりで集める
息子は、好きでよくやりました。
散らかしてるだけってこともありましたけど、
適当なところを見計らって、終わりにします。
これは、ぬれた新聞紙がほこりを集めてくれて、
舞い上がりません。
フローリングも畳の部屋も掃除ができます。
※息子ではありませんが、
使いやすいほうきとちりとり。
[REDECKER/レデッカー]ミニダストパンセット (白)
小さい子ほどやりたがります。
そんなときは「敏感期」です。
当然最初はうまくできないのですが、
教えるのが面倒、散らかすだけ、時間がかかる、
大きくなってから教えればいいと思っていると、
敏感期は過ぎて興味がなくなってしまうかもしれません。
事実、息子が大きくなってからと思っていたことって、
今になると、
「お母さんがやって」「めんどくさい」「時間がない」って。
「時間がない」
ホントにそうなんです。
小学生ともなると、家にいる時間が極端に少なくなるし、
夕方、学校の宿題やるだけで時間が過ぎ去っていきます。
通学時間が長いこともありますが。
幼稚園に入る前の親子の時間って、貴重だったんだなぁと
しみじみ思います。今更なんですけどね。
入園前のお子さんって、自己主張も強くなってきて、
大変だと思いますが、親子の時間、満喫してくださいね。 ぜひ、こちらもお読みください。
ぜひ、こちらもお読みください。
モンテッソーリ教育を初めて知る方へ
マリア・モンテッソーリ
モンテッソーリに関する書籍
















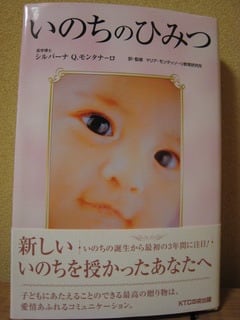
 子どもの感覚、大事にしてあげたいですね。
子どもの感覚、大事にしてあげたいですね。