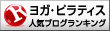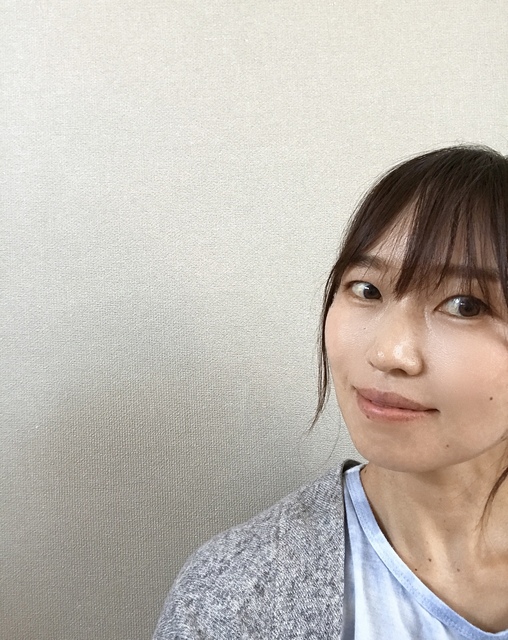ラーマーヤナは、古くからインドやアジアの国々で歌い、語り継がれてきたお話です。そして、人々の心に息づき、親しまれています。
ラーマーヤナをつくったバールミキという人はもとは盗賊でした。(盗賊だったところから、ラーマーヤナの歌物語をつくるまでに至った経緯が面白いです。)
十の頭と二十の手を持つ魔王のラーバナがいるランカの島はもともとは巨人の島で、巨人が天国にまで勢力を広げたのに腹を立てたビシュヌの神は、チャクラという円盤を巨人たちに投げつけ、海に落としてしまいました。巨人の大将のスマーリが娘のカカーシイにランカを取り戻すよう頼み、娘はきれいな少女になりすまし、そのときのランカの王をだまし、結婚して子どもを生みました。その子どもがラーバナ、クンバーカルナという悪魔と、清らかな心のビビシャナでした。一番末がスパルナカーという娘です。
主人公ラーマは、アヨージャという都の宮殿で、ダサラタ王とこころ正しいカウサルヤー妃のもとに生まれました。二番目の王子バーラタは悪がしこいカイケイー妃、ふたごの王子ラクシマナとサトルウグナはやさしいスウミトラ妃が母親です。
ラーマはジャナカ王の王女のうつくしいシータと結婚し、ラーマの父の引退のあと、アヨージャの王に即位しました。だれもがラーマの人柄を慕い、うやまうような、立派な人でしたが、カイケイー妃の策略で、ラーマは南のジャングルへ追放されてしまいました。妻のシータと、ラーマを慕うラクシマナもいっしょについて行きました。
3人は森に小屋を作り暮らし始めましたが、ちょうどランカ(セイロン島)から悪魔が遊びに来ていて、そのうちの一人が、魔王ラーバナの妹、スパルナカーでした。スパルナカーは、ラーマに気に入られたくて、誘惑したり、シータの悪口を言ったりしましたがラーマを怒らせてしまい、それが気に入らなくて、悪い策略を練るのですが、ラクシマナの矢に鼻と耳をおとされてしまいます。
腹を立てた魔王ラーバナは、シータをさらってランカへ連れて行ってしまいました。
そして、猿の一族と協力して、シータを探し、取り戻すための旅と、悪魔との戦いのお話が始まります。
ラーマの戦いには、猿をはじめ、いろいろな動物たちや、自然がラーマをしたい、力を貸します。鷹と太陽の神とのたたかいのお話や、太陽や月、海にも意思があるように、生き生きと描写されています。ヒマラヤの山や、自然の描写も美しく、うっとりと物語に引き込まれていきます。
なかでも、風の神の子、猿のハヌマーン(ハニュマーン)の活躍が輝きます。ハヌマーンは、ランカに捕らえられたシータの様子をみに、空を駆けるようにして海を渡って行き、シータを見つけ、ラーマにその知らせを届けます。また、悪魔とのたたかいのときに、毒矢が刺さってたおれたラクシマナのために薬草をヒマラヤに探しに行き、薬草を持ち帰り、ラクシマナの命を助けます。両脚を前後に開くハヌマナーサナのポーズは、ハヌマーンが海を渡るのを表し、ハヌマーンの強さや忍耐力、深い愛情や献身、忠誠心に捧げるポーズといわれています。
また、ラーマは、シータのみを助けるためにだけではなく、ラーバナに捕らえられたすべての人を助けるためにたたかいます。そういうところもすてきです。
ラーマはビシュヌの神様の7番目の化身といわれています。ビシュヌは世界がピンチのときに姿を変えて現れ、9番目はブッダ、10番目はこの世界の終末に現れる、と一説ではいわれています。
レグルス文庫、河田清史氏のラーマーヤナは、やさしく、わかりやすく、うつくしい文章で書かれています。レグルス文庫の紹介の文章も素敵です。