『限りなく透明に近いブルー』を再読する。再読というか、20代このかた限りなく読み返しているので正確には何度めか判然せぬが。ただし今回は2009年に出た新装版。解説が三浦雅士(なぜか名義は今井裕康だったが)から綿矢りさになり、「年譜」が割愛され、表紙がかわっている。
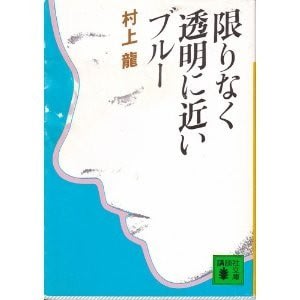
旧版の表紙。単行本とほぼ同じ。武蔵野美大中退の龍さんが自ら描いた。あとがきによると、リリーをモデルにしたものらしいが、お世辞にもうまいとは言い難い。そもそもあの「あとがき」自体がフェイクなわけだが、刊行から50年近くが過ぎた今もなお、純朴な青少年たちがころころと転がされてるようだ

この表紙の版もある。これも龍さん自身が監督した映画版のワンシーンから取ったもの。ぼくが17のとき買ってずっと手元に置いてたのはこの版だ

これが新装版。べつに限りなく透明に近くはない。ただのブルーである
龍さんの自筆になる年譜はなかなか面白かったんで、これがなくなったのは惜しいが、総じていえば、一冊の本としてはずっと良くなった。何よりも字体がいい。むかしの講談社文庫は活字がわるかった。小さいし、組み方もまずく、堅苦しい。
べつの小説に生まれ変わったようにさえ映る。
いい小説だ。純文学のことしかアタマになかった頃とは違い、マンガやアニメを見まくって、「物語」についてあれこれと思いめぐらせた今なればこそ、この小説の良さがわかる。ひとことでいって、面白いのである。
1976(昭和51)年に発表され(て一世を風靡し)た『限りなく透明に近いブルー』は、中上健次の短編「灰色のコカコーラ」を先行作品としてもつ。「灰色のコカコーラ」とは、クスリ(錠剤)を溶かして変な色になったコカコーラのことだ。この短編は集英社文庫『鳩どもの家』に収録されていて、その解説を龍さんが書いてるのだが、「ブルー」が今もなお熱く読み継がれてるのに対し、『鳩どもの家』はとっくの昔に絶版である。面白くないからだ。
(とはいえ佐藤友哉さんに『灰色のダイエットコカコーラ』なるオマージュ作があり、こちらは今も新刊で売っている。)
「灰色」と「ブルー」とを読み比べれば、村上龍という作家が、デビュー当初から「いかに書けば読み手を面白がらせることができるか」にとても気を使ってたのがわかる。
田舎から上京してフーテンをやってる若者の生態って点では同じだけど、ブルーが横田基地周辺に材をとり、セックス&ドラッグ&ロケンロール&黒人兵(政治的に正しくいえば「アフリカ系アメリカ人兵士」)たちとの乱交パーティー。なんて美味しいネタをこってり詰め込んできてるのに対し、灰色のほうは、新宿のジャズ喫茶で政治くずれや文学かぶれがうだうだクダを巻いてるだけ。BGMもジャズである。ンなもん、面白くなるわきゃない。
戦後生まれ初の芥川賞作家・中上健次は、6歳下の村上龍の登場により、「これではとても敵わんぞ」となって、紀州の「路地」に作品のトポス(根拠地)を移した。そんな見方もできるはずだ。
じっさい、東京を舞台にした中上作品はろくでもなくて、『讃歌』(文春文庫版は絶版で、いまは電子書籍化されている)もほとほと詰まらない。
ただ、ひとたび紀州をトポスに据えれば話は別だ。若き日の健次VS龍の対談集『俺たちの船は、動かぬ霧の中を、纜を解いて』(角川文庫版のタイトルは『ジャズと爆弾』)の巻末に、龍さんの「部屋」と中上さんの「神坐」、ふたつの短編がおまけみたいに付いてるのだが、ここは紀州の神事を題材とした「神坐」の圧勝である。並べてみると「部屋」のペラさが際立って、晒しものにすらみえる。
しかし、いまの若い子が予備知識なしに読んでどっちを面白がるかっていうと、やっぱ「部屋」のほうかもなって気もする。ペラいってのは、ある面、おシャレってことでもあるのだ。
『限りなく透明に近いブルー』も、一見すると、どろどろ、ぐちゃぐちゃ、もう腐った泥沼に喉元あたりまでどっぷりですわー、みたいな小説だが、「文学」としてみるならば、きらびやかで、おシャレである。
「汚辱の果ての生」をくるっと「美」に転じてしまうのが、「文学」ってもののもつ力のひとつなんである(ろくでもない力であり、このために有為な若者に道を誤らせたりもするのだが)。
そもそも頽廃とか、倦怠とか、それを具現化した「腐敗」やら「廃墟」みたいなものを「美しい」とみる感性を打ち立てたのはボードレール(1821~1867)だった。フランスの詩人、批評家。
文政4~慶応3だから、日本でいえばまさに幕末だ。
「近代の美意識をつくった」といってもいいくらいの人で、詩集『惡の華』は入手しやすいものだけで4種類の邦訳がある。直接の関係はないが、同タイトルの漫画(アニメ化もされた)もある。
散文詩集『巴里の憂鬱』もすばらしい。批評家としても目利きで、美術評論、音楽評論に健筆をふるった。
このボードレールの系譜のうえに、ロートレアモン(1846~1870)がいて、ジャン・ジュネ(1910~1986)がいて、バタイユ(1897~1962)がいる。みなフランスの物書きだけど、澁澤龍彦や栗田勇や生田耕作といった人たちの手になる良い邦訳があって、60年代から70年代前半の「政治の季節」には熱狂的に読まれた。ことさら文学青年ってわけじゃなくても、ちょっと尖った若者ならば、「読んでなきゃ恥」ってくらいのモンだった。
『限りなく透明に近いブルー』もまた、もちろん、直近の中上健次以上に、それらフランス作家(の翻訳)の影響下にある。
だから「ブルー」を論じるにあたり、まっさきにバタイユやジュネの名が出てこないってことがおかしい。小林秀雄のせいかどうかは知らぬが、どうも、この国の文芸批評はおかしいのである。
講談社文庫の解説をやってる綿矢りさも書いてない。今の若い子はジュネだバタイユだっつってもピンとこんだろうから、そこは言わなきゃわからんじゃないか。そういうことを前提として確立せんから、「リリーのモデルって誰なんですかー」とか「あのカンブリア宮殿の村上とかいうおっさん、あ、ハルキじゃないほうな、あれって昔、横田基地の傍ですげえことやってたんだぜ」とか、そんな中2レベルの話が、そこらに蔓延しちゃうのだ。
しかしまあ、それは1984年生まれの綿矢さんのせいだけじゃなく、前の版で解説をやってた1946年生まれの三浦雅士さんも書いてなかった。この小説が大騒ぎになった1976年この方、バタイユ、ジュネの係累として村上龍をきちんと論じたエッセイをぼくは読んだことがない。
『ジャズと爆弾』のなかで、中上健次はもちろん、そのことにちゃんと言及していたが、それだけでもう、「はい。この件はOKね」みたいに済まされている。おかしい。
「ブルー」に書かれたもろもろが、どこまで若き村上龍之助(本名)の体験で、どこからが虚構か、そこを解析するのは難しい。だけど、ひとつ間違いなくいえるのは、作家ってものは、自分の体験だけをたよりに作品を書くことなんてありえないってことだ。夏休みの絵日記じゃないんだからね。
どんな小説にも必ず「先行作品」はある。ジュネ、バタイユ、さらにはロートレアモン、ボードレールを念頭に置かずに『限りなく透明に近いブルー』を読むことは、そりゃあまあ、「何をどう読もうが個人の好き好き」って点では好き好きには違いないけども、「もったいない話だぞ。」とはいえる。
さて。『限りなく透明に近いブルー』、旧版と新装版との違いがもうひとつあった。文庫カバー裏の(編集者が付けた)コピーだ。
「福生の米軍基地に近い原色の街。いわゆるハウスを舞台に、日常的にくり返される麻薬とセックスの宴。陶酔を求めてうごめく若者、黒人、女たちの、もろくて哀しいきずな。スキャンダラスにみえる青春の、奥にひそむ深い亀裂を醒めた感性と詩的イメージとでみごとに描く鮮烈な文学。群像新人賞、芥川賞受賞。」
これが旧版。

これが新装版。べつに限りなく透明に近くはない。ただのブルーである
龍さんの自筆になる年譜はなかなか面白かったんで、これがなくなったのは惜しいが、総じていえば、一冊の本としてはずっと良くなった。何よりも字体がいい。むかしの講談社文庫は活字がわるかった。小さいし、組み方もまずく、堅苦しい。
べつの小説に生まれ変わったようにさえ映る。
いい小説だ。純文学のことしかアタマになかった頃とは違い、マンガやアニメを見まくって、「物語」についてあれこれと思いめぐらせた今なればこそ、この小説の良さがわかる。ひとことでいって、面白いのである。
1976(昭和51)年に発表され(て一世を風靡し)た『限りなく透明に近いブルー』は、中上健次の短編「灰色のコカコーラ」を先行作品としてもつ。「灰色のコカコーラ」とは、クスリ(錠剤)を溶かして変な色になったコカコーラのことだ。この短編は集英社文庫『鳩どもの家』に収録されていて、その解説を龍さんが書いてるのだが、「ブルー」が今もなお熱く読み継がれてるのに対し、『鳩どもの家』はとっくの昔に絶版である。面白くないからだ。
(とはいえ佐藤友哉さんに『灰色のダイエットコカコーラ』なるオマージュ作があり、こちらは今も新刊で売っている。)
「灰色」と「ブルー」とを読み比べれば、村上龍という作家が、デビュー当初から「いかに書けば読み手を面白がらせることができるか」にとても気を使ってたのがわかる。
田舎から上京してフーテンをやってる若者の生態って点では同じだけど、ブルーが横田基地周辺に材をとり、セックス&ドラッグ&ロケンロール&黒人兵(政治的に正しくいえば「アフリカ系アメリカ人兵士」)たちとの乱交パーティー。なんて美味しいネタをこってり詰め込んできてるのに対し、灰色のほうは、新宿のジャズ喫茶で政治くずれや文学かぶれがうだうだクダを巻いてるだけ。BGMもジャズである。ンなもん、面白くなるわきゃない。
戦後生まれ初の芥川賞作家・中上健次は、6歳下の村上龍の登場により、「これではとても敵わんぞ」となって、紀州の「路地」に作品のトポス(根拠地)を移した。そんな見方もできるはずだ。
じっさい、東京を舞台にした中上作品はろくでもなくて、『讃歌』(文春文庫版は絶版で、いまは電子書籍化されている)もほとほと詰まらない。
ただ、ひとたび紀州をトポスに据えれば話は別だ。若き日の健次VS龍の対談集『俺たちの船は、動かぬ霧の中を、纜を解いて』(角川文庫版のタイトルは『ジャズと爆弾』)の巻末に、龍さんの「部屋」と中上さんの「神坐」、ふたつの短編がおまけみたいに付いてるのだが、ここは紀州の神事を題材とした「神坐」の圧勝である。並べてみると「部屋」のペラさが際立って、晒しものにすらみえる。
しかし、いまの若い子が予備知識なしに読んでどっちを面白がるかっていうと、やっぱ「部屋」のほうかもなって気もする。ペラいってのは、ある面、おシャレってことでもあるのだ。
『限りなく透明に近いブルー』も、一見すると、どろどろ、ぐちゃぐちゃ、もう腐った泥沼に喉元あたりまでどっぷりですわー、みたいな小説だが、「文学」としてみるならば、きらびやかで、おシャレである。
「汚辱の果ての生」をくるっと「美」に転じてしまうのが、「文学」ってもののもつ力のひとつなんである(ろくでもない力であり、このために有為な若者に道を誤らせたりもするのだが)。
そもそも頽廃とか、倦怠とか、それを具現化した「腐敗」やら「廃墟」みたいなものを「美しい」とみる感性を打ち立てたのはボードレール(1821~1867)だった。フランスの詩人、批評家。
文政4~慶応3だから、日本でいえばまさに幕末だ。
「近代の美意識をつくった」といってもいいくらいの人で、詩集『惡の華』は入手しやすいものだけで4種類の邦訳がある。直接の関係はないが、同タイトルの漫画(アニメ化もされた)もある。
散文詩集『巴里の憂鬱』もすばらしい。批評家としても目利きで、美術評論、音楽評論に健筆をふるった。
このボードレールの系譜のうえに、ロートレアモン(1846~1870)がいて、ジャン・ジュネ(1910~1986)がいて、バタイユ(1897~1962)がいる。みなフランスの物書きだけど、澁澤龍彦や栗田勇や生田耕作といった人たちの手になる良い邦訳があって、60年代から70年代前半の「政治の季節」には熱狂的に読まれた。ことさら文学青年ってわけじゃなくても、ちょっと尖った若者ならば、「読んでなきゃ恥」ってくらいのモンだった。
『限りなく透明に近いブルー』もまた、もちろん、直近の中上健次以上に、それらフランス作家(の翻訳)の影響下にある。
だから「ブルー」を論じるにあたり、まっさきにバタイユやジュネの名が出てこないってことがおかしい。小林秀雄のせいかどうかは知らぬが、どうも、この国の文芸批評はおかしいのである。
講談社文庫の解説をやってる綿矢りさも書いてない。今の若い子はジュネだバタイユだっつってもピンとこんだろうから、そこは言わなきゃわからんじゃないか。そういうことを前提として確立せんから、「リリーのモデルって誰なんですかー」とか「あのカンブリア宮殿の村上とかいうおっさん、あ、ハルキじゃないほうな、あれって昔、横田基地の傍ですげえことやってたんだぜ」とか、そんな中2レベルの話が、そこらに蔓延しちゃうのだ。
しかしまあ、それは1984年生まれの綿矢さんのせいだけじゃなく、前の版で解説をやってた1946年生まれの三浦雅士さんも書いてなかった。この小説が大騒ぎになった1976年この方、バタイユ、ジュネの係累として村上龍をきちんと論じたエッセイをぼくは読んだことがない。
『ジャズと爆弾』のなかで、中上健次はもちろん、そのことにちゃんと言及していたが、それだけでもう、「はい。この件はOKね」みたいに済まされている。おかしい。
「ブルー」に書かれたもろもろが、どこまで若き村上龍之助(本名)の体験で、どこからが虚構か、そこを解析するのは難しい。だけど、ひとつ間違いなくいえるのは、作家ってものは、自分の体験だけをたよりに作品を書くことなんてありえないってことだ。夏休みの絵日記じゃないんだからね。
どんな小説にも必ず「先行作品」はある。ジュネ、バタイユ、さらにはロートレアモン、ボードレールを念頭に置かずに『限りなく透明に近いブルー』を読むことは、そりゃあまあ、「何をどう読もうが個人の好き好き」って点では好き好きには違いないけども、「もったいない話だぞ。」とはいえる。
さて。『限りなく透明に近いブルー』、旧版と新装版との違いがもうひとつあった。文庫カバー裏の(編集者が付けた)コピーだ。
「福生の米軍基地に近い原色の街。いわゆるハウスを舞台に、日常的にくり返される麻薬とセックスの宴。陶酔を求めてうごめく若者、黒人、女たちの、もろくて哀しいきずな。スキャンダラスにみえる青春の、奥にひそむ深い亀裂を醒めた感性と詩的イメージとでみごとに描く鮮烈な文学。群像新人賞、芥川賞受賞。」
これが旧版。
「米軍基地の街・福生のハウスには、音楽に彩られながらドラッグとセックスと嬌声が満ちている。そんな退廃の日々の向こうには、空虚さを超えた希望がきらめく——。著者の原点であり、発表以来ベストセラーとして読み継がれてきた、永遠の文学の金字塔が新装版に! <群像新人賞、芥川賞受賞のデビュー作>」
これが新装版。
これが新装版。
旧版のだってべつに悪くはないと思うが、「黒人」だの「女たち」だのといった表記が今日の人権感覚では耳ざわりなのか。しかし「もろくて哀しいきずな」とか「スキャンダラスにみえる青春の、奥にひそむ深い亀裂を醒めた感性と詩的イメージとで……」といったあたりは的確だった。
新装版のほう、「ロック」と書きゃあいいのになんで「音楽」なんだ?と思ったが、いちおうジャズも出てくるからかな。妙に律儀である。そんなことより注目すべきは、「退廃の日々の向こうには、空虚さを超えた希望がきらめく」だろう。
希望。これは旧版のほうにはなかった一語だ。ラストパート、リュウが「夜明けの空気に染ま」ったガラスの欠片に見る「限りなく透明に近いブルー」に「希望」の兆しを読み取っているわけだ。このくだりを導いたのは綿矢りさの「解説」だろう。綿矢さんは「救い」と書いてるけど、このばあいはほぼ同じとみていい。
綿矢りさの文章は「自分語り」をからめて生々しくてリアルで、じかに身体に響いてくる。旧版解説の今井裕康(三浦雅士)さんが「村上龍が、まさにその文体その方法において、現代というこの奇怪な生き物の核心に迫ったことは明らかだろう。」なんて高みから述べているのと対照的だ。作家と評論家との違いといえる。
ラス前のパート、リュウは重度のパニック障害みたいな按配となり、さしもの寛大なリリーにまで逃げ出されてしまうのだが、綿矢さんはその理由を、「彼もまた傷ついている。すべてを見尽くしたあと、彼は狂ったように苦しむ。」と書く。
さらにそれを敷衍して、「ひどい私刑が起こっても、女友達が暴力を振るわれてもリュウは見てるだけ、助けもしない。でも彼は実際は赤ん坊ではなく目の前で起こっていることを理解しているから、無言のうちに目の前の光景を身体のなかに通し、その度に傷ついている。電子レンジの光を浴びているみたいに、表面的にはなんの変化が無くても中から熱くなり破裂する。」と続ける。
臨界点を超えた、という感じであろうか。
そのあげくに例の「大きな黒い鳥」を視てしまうわけである。
この解釈は、ぼくがこの小説を初めて読んだ17の頃からずっと思い込んでたのよりも深くて、さすがだと思った。
ぼくはたんに、「仲間たちとの蜜月が終わって寂しかったせいだろう」と思っていたのだ。それも間違いではないが、リュウが「見る」という行為にあそこまで拘っているのを鑑みれば、そりゃあ綿矢さんの読みのほうが深い。
136ページ、ケイとヨシヤマ、レイ子とオキナワ、モコ、カズオ(この2人だけはカップルではない)たちが、「みんな帰っていっ」て、リュウは独りになる。
ちなみに、この中で、それぞれの母親と父親について繰り返し言及されるのはケイとヨシヤマだけである。2人は作中に現れた時からもうギクシャクしているが、そのきっかけとなったのもヨシヤマの母の葬儀(にケイが参列させて貰えなかったこと)だった。
レイ子とオキナワは、当時まだアメリカ領だった沖縄県の出身で、それにまつわる挿話もいくつか出てくる。
ケイとレイ子は日本人の母とアメリカ人の父をもつが、モコはちがう。のみならず、どうやら中産家庭の子女のようだ。リュウ自身およびモコ、カズオの3人は、そんなに逼迫した出自にはみえない。
(リュウがどうやって生計を立てているのかは、じつはよくわからない。巧妙にぼかされている。リリーに養って貰っているわけでもなさそうなので、たぶん親からの仕送りに頼っているのだろう。そう考えると少し笑ってしまう。)
そういった各々のキャラが、むろん事細かにではないが、ちゃんと描き分けられている。
内容のどぎつさや、全編を彩る詩的イメージや、基地問題(日米関係)といった要素に紛れてなおざりにされてきたけれど、『限りなく透明に近いブルー』はきっちりそういった人物造形をやってる小説であり、のちの「純文学系・物語作家(エンターテイナー)」村上龍は、デビュー当初からその片鱗をみせていたのである。
ともあれ、あそこまで無軌道な暮らしが何年も続くわきゃないので、破綻するのは時間の問題だったんだけど、ケイとの大喧嘩(というか一方的なDV)のあと、ヨシヤマは自殺を図り、入院し、一命は取り留めて戻ってきたものの、ここで7人の関係は修復不能の域に達したといえる。
でたらめなりに一定の親密さを保っていた空気は、どうしようもなく冷めていき、険悪さすら帯びる。
そして「みんな帰っていっ」て、独りになったリュウはリリーの部屋を訪れる。優しいリリーはいつものように迎え入れてくれるが、リュウがあまりにも異常な態度をとるもんで、怖くなって逃げ出してしまう。
「血を縁に残した(リュウ自身の血である)」ガラスの破片に、「夜明けの空気に染ま」った「限りなく透明に近いブルー」をリュウが見るのは、リリーを失い、ふらふらと外に彷徨い出て、「病院の庭」の草のうえまで辿り着いたあとだ。
それを「救いの色」と綿矢りさはいい、文庫裏のコピーもその意を汲んで「希望がきらめく」とうたった。2009年の新装版・解説において綿矢さんがそう書き記すまで、「限りなく透明に近いブルー」が「救いの色」「きらめく希望」だと明言した批評はなかった。これも奇妙な話である。奇妙な話である、と私は思う。
かつて中上健次は、つねに路上に屯する「フーテン」こそが、家の中やクルマの中に居てはわからぬ「微細な色調の変化」を感じ取ることができるんだよな、とこのくだりを評したものだ。
しかしもちろん、「救い」といい「希望」とはいっても、それは一瞬のできごとにすぎない。まるで錯覚か、一時の気の迷いとしか思えぬほどに。
「空の端が明るく濁り、ガラスの破片はすぐに曇ってしま」うのである。
とはいえ、「僕は地面にしゃがみ、鳥を待った。」と書かれる「鳥」はもう、あの「大きな黒い鳥」ではない。いずれ暖かい日の下で、「長く伸びた僕の影」に(腐れたパイナップルの切れ端もろとも)包まれるていどの、「灰色の」鳥なのだ。
青春の一局面の終わりと共に、リュウは、襲来してくる得体のしれない巨大な不安を、ひとまずは「対象化」できたのだった。
☆☆☆☆☆☆☆
参考資料
サイト「芥川賞のすべて・のようなもの」より、当時の芥川龍之介賞選考委員の選評を引用。
吉行淳之介(当時52歳)
「この数年のこの賞の候補作の中で、その資質は群を抜いており、一方作品が中途半端な評価しかできないので、困った。」「どこを切っても同じ味がする上にやたら長く、半ばごろの「自分の中の都市」という理窟のような部分に行き当って、一たん読むのをやめた。」「作品の退屈さには目をつむって、抜群の資質に票を投じた。この人の今後のマスコミとのかかわり合いを考えると不安になって、「因果なことに才能がある」とおもうが、そこをなんとか切り抜けてもらいたい。」
丹羽文雄(当時71歳)
「芥川賞の銓衡委員をつとめるようになって三十七回目になるが、これほどとらまえどころのない小説にめぐりあったことはなかった。それでいてこの小説の魅力を強烈に感じた。」「若々しくて、さばさばとしていて、やさしくて、いくらかもろい感じのするのも、この作者生得の抒情性のせいであろう。」「二十代の若さでなければ書けない小説である。」
中村光夫(当時65歳)
「他の六篇とはっきり異質の作品」「技巧的な出来栄えから見れば、他の候補作の大部分に劣るといってもよいのですが、その底に、本人にも手に負えぬ才能の汎濫が感じられ、この卑陋な素材の小説に、ほとんど爽かな読後感をあたえます。」「無意識の独創は新人の魅力であり、それに脱帽するのが選者の礼儀でしょう。」
井上靖(当時69歳)
「私は(引用者中略)推した。芥川賞の銓衡に於て、作者の資質というものを感じさせられる久々の作品だったと思う。」「所々に顔を出す幼さも、古さも、甘さも、この作品ではよく働いていて、全篇をうっすらと哀しみのようなものが流れているのもいい。」「題材が題材だけに、当然肯定もあり、否定もあると思う。肯定と否定とを計りにかけ、その上でどちらかに決めさせられるような作品である。そういう点も、この作品の持つよさとすべきであろう。」
永井龍男(当時72歳)
「これを迎えるジャーナリズムの過熱状態が果してこの新人の成長にプラスするか否か、(引用者中略)群像新人賞というふさわしい賞をすでに得ている、次作を待って賞をおくっても決して遅くはないと思った。まさに老婆心というところであろう。」
瀧井孝作(当時82歳)
「アメリカ軍の基地に近い酒場の女たち、麻薬常習の仲間たちのたわいのない、水の泡のような日常を描いたもの、と私はみた。この若い人の野放図の奔放な才気は一応認めるが……。」「私はこの人の尚洗練された第二作第三作をまちたかった。」
安岡章太郎(当時56歳)
「印象にのこった。」「候補に上る以前から、それこそ「はしゃぎ過ぎ」の感があるほど話題になった作品であるが、内容に較べて二百枚という長さは退屈である。」「何が言いたいのかサッパリわからない。ただ、この作品には繊細で延びのある感受性があり、それが風景描写などに生きている。」「私はこの作品に賞は出さない方がいいと思ったが、積極的に反対するだけの情熱もなかった。」
「印象にのこった。」「候補に上る以前から、それこそ「はしゃぎ過ぎ」の感があるほど話題になった作品であるが、内容に較べて二百枚という長さは退屈である。」「何が言いたいのかサッパリわからない。ただ、この作品には繊細で延びのある感受性があり、それが風景描写などに生きている。」「私はこの作品に賞は出さない方がいいと思ったが、積極的に反対するだけの情熱もなかった。」
「純文学」と「サブカルチャー」との境界があいまいになっていく時代の予感に各選考委員が戸惑っている様子がうかがえて、貴重な資料である(女性が一人もいないことと、委員の皆さんの年齢にもご注目)。ほぼ40年後の又吉直樹『火花』の受賞へのお膳立てはこの時に始まっていた。といってもいいのではないか。
☆☆☆☆☆☆☆
なお、「昭和を代表する文芸批評家のひとり」である江藤淳は、まともにこの作品を評することはなかった。ただし週刊誌「サンデー毎日」(1976年7月25日号)に以下の一文が「談話」として発表され、のちのちまで物議をかもした。
「社会学の述語に”サブ・カルチャー”という言葉がある。”下位文化”と訳されているようだ。国語としてあまり熟していると思われないが、村上龍の作品は、結局一つの”サブ・カルチャー”の反映にすぎず、その”表現”にはなっていない、というのが、私の感想である。」
残念ながらいまひとつ意味のわからぬ文章である。この人もまた、「純文学」と「サブカルチャー」との境界があいまいになっていく時代の予感に戸惑っていたのだ。
なお江藤氏は村上春樹についても終生まともな論評を残さなかったが、1980年に「文藝」の新人賞に投稿された田中康夫『なんとなく、クリスタル』には激賞に近い評価を与えた。
この評価の落差は、江藤氏じしんの「アメリカ」に対する屈折した思いに依るものだといわれているが、氏がかつて石原慎太郎が大好きであったのを考え合わせると、「一橋大卒で若くして寵児になって中年以降は政治家に転身するタイプの作家」に惹かれる資質があったのではないかとも思われる(どんな資質だ)。
いずれにせよ、この時期、第一線で活躍する作家も批評家も、「サブカルチャー」について何もわかってなかったわけである。「サブカルなんぞ知るものか。」で作家が務まり、批評家が務まる。むしろ知ってるほうが恥ずかしい。1970年代とは、まだそんな時代であった。









