「こんにちわッ、テディちゃでス!
まだまだァ、しょッくゥ~さめやらずゥ……」
「がるる!ぐるがる~…」(←訳:虎です!不安です~…)
こんにちは、ネーさです。
多くのユーザーさんたちと同様に、
未だgoo blog閉鎖の衝撃から立ち直れていません。
生き延びる道はどこだ?と情報収集しながら、
さあ、本日の読書タイムは、こちらの御本を、どうぞ~♪

―― 江戸の職人譚 ――
編者は菊地仁(きくち・めぐみ)さん、
著者は収録順に、乙川優三郎さん、野口卓さん、あさのあつこさん、
佐江衆一さん、南原幹雄さん、五味康祐さん、梶よう子さん、
2024年12月に発行されました。
《江戸の職人》をテーマとするアンソロジー作品です。
「へいわなァじだいのォ、たのしみィはァ~」
「ぐるがるるぐる!」(←訳:文化だよね断然!)
およそ260年続いた、江戸時代。
その特質は、なんといっても、
“戦争がない”
この一事に尽きます。
乱や、諍(いさか)い、
揉め事が無かった訳ではありません。
けれど、
数万人数十万人の生命が失われた、というような
大乱、大いくさは無かった――
これって、実はものすっごく大事な、重要極まることで、
そういう意味で江戸時代ってもっと評価されていい、
日本の風土や日本人の精神性にも
大きな影響を与えているんじゃないか、
と思うんですが、
本題に戻りますと。
平和な時代に必要とされるのは、
刀剣よりも、
うつくしいもの、おもしろいもの。
例えば、
この御本に収録されている作品に登場するのは、
小紋の意匠職人さん、
物知りな鏡磨ぎ師さん、
縫箔(ぬいはく)屋さん、
からくり人形師さん、
刀剣の鞘師(さやし)さん、
錦絵の摺師(すりし)さん、
と、物造りの達人さんたち。
「おしごとにィ、こだわりィ~もッてまスゥ!」
「がるるるぐるる!」(←訳:凝り性の研究家!)
私ネーさのおすすめは、
凝りっぷりが群を抜いている
佐江衆一さんの
『自鳴琴(じめいきん)からくり人形』。
黒船の到来に揺れる江戸、
そのお江戸の町の全域で、
最も闇が濃い場所……ともいえる、
伝馬町(でんまちょう)の牢に繋がれているのは、
からくり人形師の、庄助(しょうすけ)さんです。
庄助さん、
南蛮渡りの自鳴琴を自作して
異人女のからくり人形に仕組み、
世間を騒がせた罪で
五十日の手鎖になってしまったんです。
「ふァ? それだけェ??」
「ぐるるがっるるるる?」(←訳:人形を作っただけで?)
伝馬町牢奉行配下の同心、
黒田三右衛門(くろだ・さんえもん)さんは、
当初、庄助さんに反感を抱いていました。
なぁにが人形だ、
不届き者が、ふざけてんじゃねえぞ!と。
しかし、
からくりのことなど話すうち、
次第に怒りも解け、
同情すら覚えるようになったとき。
「わあァッ、じめんがァ!」
「がるるぅ!」
安政の大地震が江戸の町を襲います。
幸いにも命拾いしたものの、
三右衛門さんの眼に映ったのは、
倒れてゆく建物と、火災のしるしの赤い炎……
いかん、牢屋敷はどうなった?
「いそいでッいそいでッ!」
「ぐるがる~!」(←訳:炎が近い~!)
囚人たちは?
からくり人形師の庄助は?
みな、無事か。無事でいるか――
幕末期は、
多くのからくり師・発明家さんが誕生した時代、
でもありました。
実在したからくり人形師にして
芝浦製作所(のちの東芝)の創業者
『からくり儀右衛門』さんを想わずにいられない物語は、
歴史好きな活字マニアさんに、
激おすすめですよ。
古き江戸の、平和な日々を偲びつつ、
ぜひ、一読してみてくださいね♪



















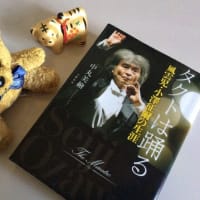
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます