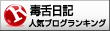生活環境の悪化を見るに忍びなく町内のゴミ拾いを始めたことは以前にも話したことがある。これは現在でも続けている。
朝晩の散歩にはスーパーのビニール袋と火バサミを持参して出かける。更にポケットにはビニールの小袋を数枚入れている。柔らかな犬の糞はこのビニール袋を手袋代わりにして拾うのである。
先日、面白い事態に遭遇した。
町内の丸山老人(仮名)は現役の頃はしかるべき地位の勤め人であったらしい。現在は老婦人との二人暮らしである。脳梗塞の後遺症から歩行が少し不自由である。このリハビリのために毎朝の散歩を欠かさない。ステッキを両手に持ってゆっくりと歩く。私は二丁拳銃ならぬ二丁ステッキのお爺さんと呼んでいる。徘徊する時間帯が同じなので毎朝のように顔をあわせる。時折は言葉を交わしたりもするが特に親しい間柄ではない。その丸山老人が私奴にこういうのである。
「お宅の方から犬を連れてくる人で毎日ゴミをひろってくれる奇特な人がおりますねぇ」幾ら厚顔無恥な私でも奇特な人だといわれてから、それは私でございますとは明し難い。だから「そうですか変わった人もいるもんですねぇ」と、答えておいた。丸山老人もうんうんと肯いていたから奇特なということは、変人だというのと本質的に余り変わらないのであろう。因みに、変人奇人の「奇」の字は、本来、田偏(たへん)に奇と旁(つく)るのであって、原義は矩形でない田圃を表すようだ。
さて、道々拾う塵芥(ごみ)の種類であるが、先ず圧倒的に数が多いのはタバコの吸殻である。そして、桜町で吸殻をポイ棄てするのはキャビンという銘柄の愛好者であることが顕著な傾向である。フィルターのところの巻紙がこげ茶色だから判りやすい。口紅(ルージュ)のついた細いタバコの吸殻は女性が棄てたものに違いない。そういえば咥えタバコで闊歩している水商売風の女性ともしばしば遇う。
次は、コンビニのビニール袋を含む菓子及び食品の包装紙である。ガムの銀紙や蓋にストローのついたマックの紙コップも多い。空き缶・空き瓶はそこいらにある自動販売機のところへ持ってゆく。しかし自動販売機の設置者の中には空き缶空き瓶の回収をしない不届き至極な輩(やから)もいる。
タバコの吸殻とノド飴の包み紙がセットで落ちていることから、吸殻をポイ棄てする輩は、タバコの吸い過ぎで傷んだ咽喉(のど)をノド飴をなめて治そうとしているらしい。泥水で洗濯するような話である。
次は、犬の糞である。これは毎朝毎晩必ずある。しかも大型犬のよりも小型犬のものが多い。一見上品そうな顔を装ったどこぞの奥様が自分の可愛い犬の糞を置いていってしまうのだ。これは何処の誰なのか凡そわかっている。
他人が見ていれば仕方なし拾うが、見ていなければ置き去りにする。一度は拾った糞の入ったビニール袋を植え込みの中へねじ込んで隠す程度の悪い小母さんもいる。なにしろ家へ持ち帰っても「糞(くそ)の役にも立たない」代物である。
ツツジの植え込みの陰で野糞をして、尻(ケツ)をパンツで拭いて、糞のついたパンツをかぶせてあるやつもある。こういう輩(やから)の糞は極端に臭い。
拾得物の中には珍品もある。木刀。釣竿。女性のパンティーはこれまで二回拾った。序でに言えば使用済みの生理用品もある。情けなく萎んだ使用済みコンドームにいたっては他人が使用したものでも見るに忍びない。陽気がよくなると堤防の芝生(しばふ)のところで盛り上がってしまうカップルがいるようだ。場所柄を弁えてもらいたいものだがこれも致し方ない。
6月からは釣具の包装などが覿面に多くなる。安倍川の鮎釣りが解禁になったからだ。
夏場はキャンパーのゴミ置き去りが多くなり片付けるのが大変になる。しかし生ゴミの大半はカラスやトンビの貴重な食餌(しょくじ)となることも事実だ。
好きなだけ散らかせばいい。桜町には堤防のゴミを拾う人が私の他にもう二人いる。一人は老婆(ろうば)で県営団地の回りだけが行動範囲であるが、もう一人の「旭日(あさひ)を拝む女性」は、年のころなら50代の10人並みの容姿である。
偶(たま)にすれ違うこともあるが彼女は目礼をして足早に歩き去る。そして、賎機山(しずはたやま)の稜線に旭日が昇ると立ち止まって暫(しばら)く拝むのを習いとしている。
興味がないわけではないが他人の信仰にはかかわらないことを信条としているので、これからも目礼だけの関係が続くだろう。
朝晩の散歩にはスーパーのビニール袋と火バサミを持参して出かける。更にポケットにはビニールの小袋を数枚入れている。柔らかな犬の糞はこのビニール袋を手袋代わりにして拾うのである。
先日、面白い事態に遭遇した。
町内の丸山老人(仮名)は現役の頃はしかるべき地位の勤め人であったらしい。現在は老婦人との二人暮らしである。脳梗塞の後遺症から歩行が少し不自由である。このリハビリのために毎朝の散歩を欠かさない。ステッキを両手に持ってゆっくりと歩く。私は二丁拳銃ならぬ二丁ステッキのお爺さんと呼んでいる。徘徊する時間帯が同じなので毎朝のように顔をあわせる。時折は言葉を交わしたりもするが特に親しい間柄ではない。その丸山老人が私奴にこういうのである。
「お宅の方から犬を連れてくる人で毎日ゴミをひろってくれる奇特な人がおりますねぇ」幾ら厚顔無恥な私でも奇特な人だといわれてから、それは私でございますとは明し難い。だから「そうですか変わった人もいるもんですねぇ」と、答えておいた。丸山老人もうんうんと肯いていたから奇特なということは、変人だというのと本質的に余り変わらないのであろう。因みに、変人奇人の「奇」の字は、本来、田偏(たへん)に奇と旁(つく)るのであって、原義は矩形でない田圃を表すようだ。
さて、道々拾う塵芥(ごみ)の種類であるが、先ず圧倒的に数が多いのはタバコの吸殻である。そして、桜町で吸殻をポイ棄てするのはキャビンという銘柄の愛好者であることが顕著な傾向である。フィルターのところの巻紙がこげ茶色だから判りやすい。口紅(ルージュ)のついた細いタバコの吸殻は女性が棄てたものに違いない。そういえば咥えタバコで闊歩している水商売風の女性ともしばしば遇う。
次は、コンビニのビニール袋を含む菓子及び食品の包装紙である。ガムの銀紙や蓋にストローのついたマックの紙コップも多い。空き缶・空き瓶はそこいらにある自動販売機のところへ持ってゆく。しかし自動販売機の設置者の中には空き缶空き瓶の回収をしない不届き至極な輩(やから)もいる。
タバコの吸殻とノド飴の包み紙がセットで落ちていることから、吸殻をポイ棄てする輩は、タバコの吸い過ぎで傷んだ咽喉(のど)をノド飴をなめて治そうとしているらしい。泥水で洗濯するような話である。
次は、犬の糞である。これは毎朝毎晩必ずある。しかも大型犬のよりも小型犬のものが多い。一見上品そうな顔を装ったどこぞの奥様が自分の可愛い犬の糞を置いていってしまうのだ。これは何処の誰なのか凡そわかっている。
他人が見ていれば仕方なし拾うが、見ていなければ置き去りにする。一度は拾った糞の入ったビニール袋を植え込みの中へねじ込んで隠す程度の悪い小母さんもいる。なにしろ家へ持ち帰っても「糞(くそ)の役にも立たない」代物である。
ツツジの植え込みの陰で野糞をして、尻(ケツ)をパンツで拭いて、糞のついたパンツをかぶせてあるやつもある。こういう輩(やから)の糞は極端に臭い。
拾得物の中には珍品もある。木刀。釣竿。女性のパンティーはこれまで二回拾った。序でに言えば使用済みの生理用品もある。情けなく萎んだ使用済みコンドームにいたっては他人が使用したものでも見るに忍びない。陽気がよくなると堤防の芝生(しばふ)のところで盛り上がってしまうカップルがいるようだ。場所柄を弁えてもらいたいものだがこれも致し方ない。
6月からは釣具の包装などが覿面に多くなる。安倍川の鮎釣りが解禁になったからだ。
夏場はキャンパーのゴミ置き去りが多くなり片付けるのが大変になる。しかし生ゴミの大半はカラスやトンビの貴重な食餌(しょくじ)となることも事実だ。
好きなだけ散らかせばいい。桜町には堤防のゴミを拾う人が私の他にもう二人いる。一人は老婆(ろうば)で県営団地の回りだけが行動範囲であるが、もう一人の「旭日(あさひ)を拝む女性」は、年のころなら50代の10人並みの容姿である。
偶(たま)にすれ違うこともあるが彼女は目礼をして足早に歩き去る。そして、賎機山(しずはたやま)の稜線に旭日が昇ると立ち止まって暫(しばら)く拝むのを習いとしている。
興味がないわけではないが他人の信仰にはかかわらないことを信条としているので、これからも目礼だけの関係が続くだろう。