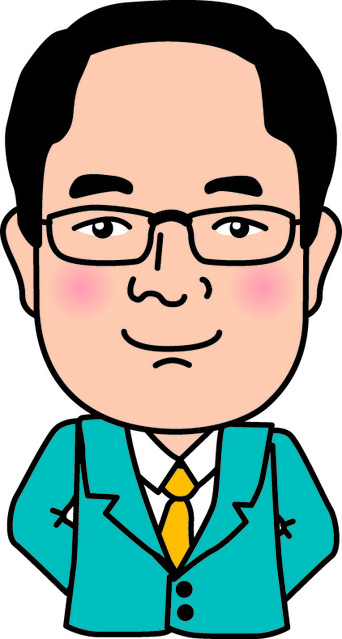みなさん、おはようございます。
はやいもので、今日はもう4日です。
今日から仕事始めの企業も、多いのではないでしょうか。
とはいえ、一般道路は、今日頃まではまだまだ空いていますので
まっつあんも3ヶ日にいけなかった用事を済ませるべく、朝から
バタバタと動いています。
私の今年の正月は、壊れたPCの修理のために、行方不明になった
取扱説明書等の捜索に時間を費やしたという感があります。
昨春に引っ越した際に、どうもどこかへ入り込んだようです。
いまだに見つからないのですが、メーカーに修理を出すことにしたので
当分の間は必要ないようです。
まもなく、光インターネットが自宅に開通するので、その際に無線LAN
を購入しようかと考えていますが、どの機種や方式が良いのかよくわかりません。
そこで本日は、PCの修理を依頼するために家電ショップへ行く時に、店員へ
色々質問してみようかと思っています。
通信速度や安全性、無線の届く距離、コスト、拡張性などが、主に知りたい点です。
さて、余談はそのくらいにして本題に移ります。
今春にセミナーを開催するかもしれないという話は、前回までのブログですでに
お伝えしたところですが、今回はそのすすめ方について書いてみたいと思います。
私のセミナーのすすめ方としては、「体験型セミナー」が良いのではないかと、
思っています。もちろん、経済セミナーといったものとは違う、研修的な要素を
含むセミナーの場合です。
私の体験上、2時間以上もただじっと座って聞き続けるのは結構辛いと思うのです。
ですから、一方的に話しつづける時間は極力短くして、大部分の時間は参加者と講師が
双方向のコミュニケーションを取れるようにしたいと思うのです。
もちろん、「習うより慣れろ」的考えにより、実践を通して理論を体で感じてもらいたい
という思いもあります。
いずれにせよ、セミナー慣れしたビジネスマンに満足してもらうためには、
退屈な大学教授の授業ではなく、予備校の人気講師のような、2時間があっという
間に過ぎてしまうようなセミナーにしたいと思います。
この正月は、このセミナー内容等を練る良い期間だったことはいうまでもありません。
でも、PCは壊れてしまいデータも消失してしまいましたけどね。
それでは今日はここまでにします。
おわり
はやいもので、今日はもう4日です。
今日から仕事始めの企業も、多いのではないでしょうか。
とはいえ、一般道路は、今日頃まではまだまだ空いていますので
まっつあんも3ヶ日にいけなかった用事を済ませるべく、朝から
バタバタと動いています。
私の今年の正月は、壊れたPCの修理のために、行方不明になった
取扱説明書等の捜索に時間を費やしたという感があります。
昨春に引っ越した際に、どうもどこかへ入り込んだようです。
いまだに見つからないのですが、メーカーに修理を出すことにしたので
当分の間は必要ないようです。
まもなく、光インターネットが自宅に開通するので、その際に無線LAN
を購入しようかと考えていますが、どの機種や方式が良いのかよくわかりません。
そこで本日は、PCの修理を依頼するために家電ショップへ行く時に、店員へ
色々質問してみようかと思っています。
通信速度や安全性、無線の届く距離、コスト、拡張性などが、主に知りたい点です。
さて、余談はそのくらいにして本題に移ります。
今春にセミナーを開催するかもしれないという話は、前回までのブログですでに
お伝えしたところですが、今回はそのすすめ方について書いてみたいと思います。
私のセミナーのすすめ方としては、「体験型セミナー」が良いのではないかと、
思っています。もちろん、経済セミナーといったものとは違う、研修的な要素を
含むセミナーの場合です。
私の体験上、2時間以上もただじっと座って聞き続けるのは結構辛いと思うのです。
ですから、一方的に話しつづける時間は極力短くして、大部分の時間は参加者と講師が
双方向のコミュニケーションを取れるようにしたいと思うのです。
もちろん、「習うより慣れろ」的考えにより、実践を通して理論を体で感じてもらいたい
という思いもあります。
いずれにせよ、セミナー慣れしたビジネスマンに満足してもらうためには、
退屈な大学教授の授業ではなく、予備校の人気講師のような、2時間があっという
間に過ぎてしまうようなセミナーにしたいと思います。
この正月は、このセミナー内容等を練る良い期間だったことはいうまでもありません。
でも、PCは壊れてしまいデータも消失してしまいましたけどね。
それでは今日はここまでにします。
おわり