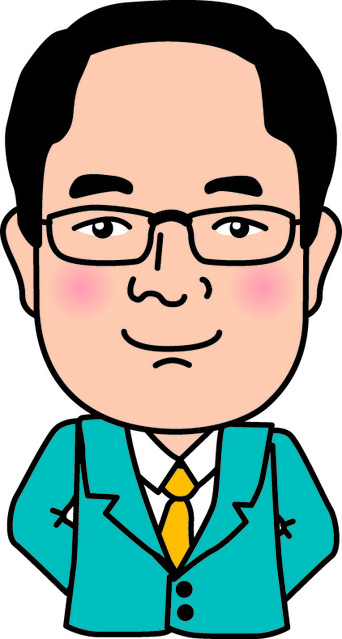まっちゃん家での毎年恒例行事の1つが、イオンでの初売りにいくことです。
毎年、いけないなあと思いつつ、ついつい福袋を買ってしまう意志の弱さを実感する
場面です。
そして、やっぱり今年も買ってしまいました。
まっちゃんが購入したのは、780円の健康グッズ福袋。
栄養ドリンク15本入+スポーツドリンク粉末(サバス、バーム)3セット、マスク1箱
などが入っており、販売店頭では地味~に売っていましたが、まっちゃんの目は
この福袋を決して見逃しませんでした。
それから、今年の7月で終了する地上波アナログ放送に対応していない、まっちゃんの
ビデオレコーダーを買い替えました。
初売りというだけあって、パナソニック製 500GB、Wチューナー内臓のブルーレイ
レコーダーが50%オフで、とってもお得でした。
気を良くした勢いで、夜は岐阜県内にある商売の神様「お千代保稲荷神社」へ行って
参拝とともに、おみくじを引きました。
引いたおみくじ結果は「大吉」。
今年は良い年になるんじゃないかと思っています。
それから、昨年購入した熊手を奉納し、新しい熊手を購入。
今年初めて、熊手に名入れをしていただきました。
帰りは名物の「ミソ串カツ」を立ち食いして帰宅。
今年も良い元旦でした。
3日は谷汲山へ夫婦で参拝し、昨年1年間無事で過ごせたことの報告と感謝を捧げると
ともに、今年1年間の家族全員の健康を願う予定です。
いつまでもこうした楽しい正月が迎えられるといいですね。
毎年、いけないなあと思いつつ、ついつい福袋を買ってしまう意志の弱さを実感する
場面です。
そして、やっぱり今年も買ってしまいました。
まっちゃんが購入したのは、780円の健康グッズ福袋。
栄養ドリンク15本入+スポーツドリンク粉末(サバス、バーム)3セット、マスク1箱
などが入っており、販売店頭では地味~に売っていましたが、まっちゃんの目は
この福袋を決して見逃しませんでした。
それから、今年の7月で終了する地上波アナログ放送に対応していない、まっちゃんの
ビデオレコーダーを買い替えました。
初売りというだけあって、パナソニック製 500GB、Wチューナー内臓のブルーレイ
レコーダーが50%オフで、とってもお得でした。
気を良くした勢いで、夜は岐阜県内にある商売の神様「お千代保稲荷神社」へ行って
参拝とともに、おみくじを引きました。
引いたおみくじ結果は「大吉」。
今年は良い年になるんじゃないかと思っています。
それから、昨年購入した熊手を奉納し、新しい熊手を購入。
今年初めて、熊手に名入れをしていただきました。
帰りは名物の「ミソ串カツ」を立ち食いして帰宅。
今年も良い元旦でした。
3日は谷汲山へ夫婦で参拝し、昨年1年間無事で過ごせたことの報告と感謝を捧げると
ともに、今年1年間の家族全員の健康を願う予定です。
いつまでもこうした楽しい正月が迎えられるといいですね。