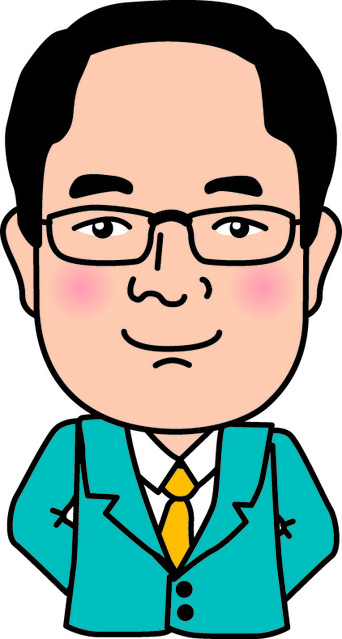今日は、新会社法における財務諸表について投稿します。
これまで、私たちが財務諸表を見る時には、主に貸借対照表、
損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(CF)を
見ているかと思うのですが、この中でB/Sについては
新会社法の施行に伴い、表示の仕方が大きく変わります。
まず、変更点について説明します。
・資本の部の廃止
従来、株主資本や純資産とも呼ばれていた「資本の部」が廃止
され、「純資産の部」が新設されます。
この純資産の内部構成は、株主資本、自己資本、純資産の3つであり、
従来の資本の部の「株主資本=自己資本=純資産」という意味合いとは
異なっています。
つまり、新会社法では、「株主資本<自己資本<純資産」となる内部構成
となるのです。
その理由は、株主資本に属する範囲は、資本金、資本剰余金、利益剰余金、
自己株式までであり、最も広範な純資産では、株主資本や自己資本を全て
含むことはもちろんのこと、新株予約券や少数株主持ち分も含むからです。
ところで、この表示方法の変更によって、企業においては混乱が
生じています。
それはなぜなのでしょか?
その一つは、決算短信の開示による、株主資本利益率(ROE)の計算方法
が不明なこと、です。
ROEは従来、税引後当期純利益/自己資本(株主資本)という計算方式を
とっていた財務諸表の一つで、株主にとっての投資収益性を端的に表す財務
諸表として知られている指標です。
このROEの算定方法をどうするか?というのが、微妙になってきたというのが
企業を悩ます原因になっています。
それは、上記に変更点を記載しましたが、自己資本の意味合いが新会社法では
大きく異なっているからです。
つまり、新しい株主資本は、純資産全体ではなく、より限定された部分を示す
言葉になっているのです。
これは困った、どうしましょう!ということで、この問題を解消するべく、
金融庁と東京証券取引所が打ち出した新しい「自己資本」の概念が以下のとおり
発表されています。
自己資本=純資産-(新株予約券+新株予約券)
この自己資本の算出方法により、短信上の計算がスッキリしたのですが、
短信上の表示も、以下のとおり変更されました。
株主資本当期純利益率 → 自己資本当期純利益率
株主資本比率 → 自己資本比率
あまりよくわからない変更点なのですが、この「あまりよくわからない」と
いう変更こそが、企業を悩ます原因なのです。
今年の株主総会では、こういった会計制度の変更点もあり、総会担当者を
例年以上に悩ませているのではないでしょうか。
これまで、私たちが財務諸表を見る時には、主に貸借対照表、
損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(CF)を
見ているかと思うのですが、この中でB/Sについては
新会社法の施行に伴い、表示の仕方が大きく変わります。
まず、変更点について説明します。
・資本の部の廃止
従来、株主資本や純資産とも呼ばれていた「資本の部」が廃止
され、「純資産の部」が新設されます。
この純資産の内部構成は、株主資本、自己資本、純資産の3つであり、
従来の資本の部の「株主資本=自己資本=純資産」という意味合いとは
異なっています。
つまり、新会社法では、「株主資本<自己資本<純資産」となる内部構成
となるのです。
その理由は、株主資本に属する範囲は、資本金、資本剰余金、利益剰余金、
自己株式までであり、最も広範な純資産では、株主資本や自己資本を全て
含むことはもちろんのこと、新株予約券や少数株主持ち分も含むからです。
ところで、この表示方法の変更によって、企業においては混乱が
生じています。
それはなぜなのでしょか?
その一つは、決算短信の開示による、株主資本利益率(ROE)の計算方法
が不明なこと、です。
ROEは従来、税引後当期純利益/自己資本(株主資本)という計算方式を
とっていた財務諸表の一つで、株主にとっての投資収益性を端的に表す財務
諸表として知られている指標です。
このROEの算定方法をどうするか?というのが、微妙になってきたというのが
企業を悩ます原因になっています。
それは、上記に変更点を記載しましたが、自己資本の意味合いが新会社法では
大きく異なっているからです。
つまり、新しい株主資本は、純資産全体ではなく、より限定された部分を示す
言葉になっているのです。
これは困った、どうしましょう!ということで、この問題を解消するべく、
金融庁と東京証券取引所が打ち出した新しい「自己資本」の概念が以下のとおり
発表されています。
自己資本=純資産-(新株予約券+新株予約券)
この自己資本の算出方法により、短信上の計算がスッキリしたのですが、
短信上の表示も、以下のとおり変更されました。
株主資本当期純利益率 → 自己資本当期純利益率
株主資本比率 → 自己資本比率
あまりよくわからない変更点なのですが、この「あまりよくわからない」と
いう変更こそが、企業を悩ます原因なのです。
今年の株主総会では、こういった会計制度の変更点もあり、総会担当者を
例年以上に悩ませているのではないでしょうか。