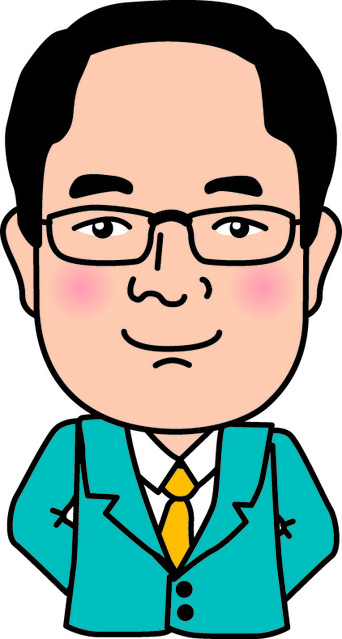自社買収をするという記事が掲載されました。
買収金額も国内最大2600億円超となるようで、相当大規模な自社買収となります。
自社買収については、MBO(マネジメント・バイ・アウト)というM&A手法を
取るようです。
このMBOとは、経営陣が企業や事業部門を買収して独立するM&Aの手法のことです。
今回のケースでは、すかいらーくの創業一族と経営陣が特別目的会社(SPC)を
設立し、TOB(敵対的買収あるいは株式公開買い付け)を実施するようです。
ところで、このすかいらーくの行動は一体何を意味するものでしょうか。
このブログでも、新会社法のM&A編で触れましたが、いよいよ企業が本格的な
M&A防止に向けて動き始めたことを意味しています。
つまり、来年から解禁される三角合併によるM&A手法を前に、すかいらーく
さんは究極の防衛策である自社買収を行い、非公開会社となることによって、
第三者からの買収を避けるという狙いがあります。
ちなみに、非公開会社とは、株式を一般株主に公開しないという意味です。
つまり、市場取引による株の売買は行われない、ということを指しています。
ですから大雑把に言うと、たとえばライブドアの株の場合、我々がライブドア株
を購入することはできないというのと、意味はほぼ同義といえます。
ということは、短期利益を追求する村上ファンドさんのような投資家でも
簡単に手が出せなくなる、ということです。
しかしこの自社買収には問題も残ります。
それは、自社買収するということは、コーポレートガバナンスという視点から
見たときに、すかいらーく株を所有するのは、すかいらーく関係者が大勢を占める
ようになるために、もし、すかいらーくが暴走した時には外部から抑止できなくなる
可能性が高くなる、ということです。
ということは、内部統制によった厳しい監視活動をこれまで以上におこなって
いかないと、すかいらーくの経営がおかしくなる可能性も捨てきれない、
ということなのです。
いわゆる、「市場によるチェック機能が働かない」という悪弊が生じるかも
しれない、ということなのです。
すかいらーくさんの経営は今後どうなるか、注意が必要ですね。
言い忘れましてが、すかいらーくさんが自社買収した理由は、買収防止策だけ
からではありません。
経営不振による事業見直しを迅速かつ柔軟に進める、という狙いもあるからです。