
『Wizardry シナリオ2 Knight of Diamonds』(ダイヤモンドの騎士)は、1982年にApple II用として発表されました。前作の追加シナリオという形をとったため前作を持っていないと遊べず、前作で育てたキャラを移動させる必要がありました。オリジナルのApple II版では、包装も簡易なもので厚紙にイメージ画が印刷されたものをビニールパックしただけのごく簡単なものだったようです。エキスパートキャラ用のシナリオであったため、ターボファイルがないとキャラを移すことができないFC用(90)では、先にシナリオ3が2として発表され、2と3を入れ替えての発売となりました。

こちらは、FC版と同じくゲームスタジオ製作のGBC版。原作では、ストーリー上にしか登場しない“ダヴァルプス”(DAVALPUS)の亡霊と対面できるのが一番の特徴。

物語は、リルガミンの街はニルダの杖の加護により外部より守られていた。リルガミンに生まれた邪悪な“ダヴァルプス”(DAVALPUS)には、この力が働かず、“マルグダ”(MARGDA)女王と“アラビク”(ALAVIK)王子は、ダイアモンドの騎士の鎧の力をかりて、この“ダヴァルプス”を討ち取ることに成功する。彼は死の間際に呪詛を放ち、城は崩壊して杖も地下深く失われてしまう。マルグダとアラビクの2人の行方も分からなくなってしまった・・・といったものです。ゲーム中には、“ダヴァルプス”“マルグダ”“アラビク”は※登場せず、プレイヤーの目的は、この失われてしまった“ダイアモンドの鎧”と“ニルダの杖”を城に持ち帰ることになります。※マルグダは、目的達成後に称号を付与

前作は10層からなるダンジョンでしたが、今作は6層と少なめ。各層には、それぞれ“ダイアモンドの騎士”の装備である、鎧、ヘルメット、盾、剣、篭手があり、それらは意思をもつマジックアイテムとしてプレイヤーに襲い掛かってきます。それらを倒し回収をして伝説の騎士の装備をそろえ、ニルダの杖を城に持ち帰るというのがゲームの流れとなります。写真は、FC版『ダイアモンドの騎士』と、おそらくゲーム本体より希少なのではないかと思われる、アスキーの攻略本。

このシナリオ、追加シナリオということもあって始めから強力なモンスターが登場したり、地下一階からMALORを必要とするなど難易度も上げてあります。ただし、前作でキャラを育てすぎていた場合には簡単に終わってしまったり、アイテムを集めるだけという単純さや、前作にみられたようなやり込み度も減ってしまうなど、それほど評判が良くなかったようです。国産RPG『ブラックオニキス』でも、同様のキャラを移動できる追加シナリオという形が踏襲されましたが、こちらも成功したとは言いがたい状況でした。

通常のTRPGではキャラとシナリオが独立しており、シナリオを横断しながらキャラを成長させてゆくという形式が一般的ですが、CRPGの場合にはこれはなかなか成功しないようです。過去にも『ソーサリアン』など意欲的な試みは行われているのですが、ほとんどの場合シナリオとキャラが一体となった(エンディングまでいけば終わりという)パッケージになっています。このシナリオを横断させながらキャラを育ててゆくという形が、上手くゆけばかなり楽しいと思うのですが、CRPGの場合1作の製作にかなりの時間と莫大な労力がかかってしまうので、それも難しいのでしょうね。

FC版の場合、キャラを移すことが容易ではありませんでした(別途ターボファイルを購入する必要がある)ので、シナリオ3が先に『ウイザードリィ2』として発売され、こちらは『ウィザードリィ3』として順序が逆になりました。FC版への移植の際に、このシナリオでもキャラの作成ができるように変更され、追加シナリオという形でなく一本の独立した作品になっています。オリジナルのボス敵も(WIZ4より持ってくる形で)準備され、コッズアイテムを集めた後にも新たなクライマックスが準備されていました。FC版の移植であるGBC版では、さらに階層が追加されて、オリジナル版では伝説でしかなかった“ダヴァルプス”(DAVALPUS)の亡霊と対面できるようになっています。原作のオリジナリティを大事にする人には向かないでしょうが、追加アレンジとしては良くできていたように思います。写真は、PS版『リルガミンサーガ』とその攻略本。またFC版では、ダイアモンドの騎士を連想させるシルバーのパッケージが、硬質な感じが出ていてなかなかよかったと思います。

Wiki ウィザードリィの項、ウィザードリィコレクション(書籍版)/ローカス













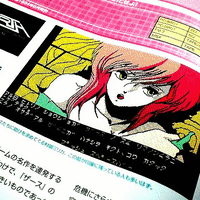




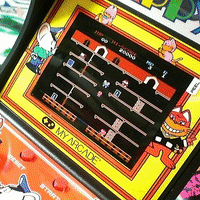

がありましたね。これはNP(任天堂パワー版)も同じです。
ファミコン版U+2162(ダイヤモンドの騎士)にも、とんでもないバグがありますね。
モンスターが複数のグループで現れ、先頭のグループが呪文無効化を有する場合、
その無効化能力を後続のグループが引き継いでしまうというバグです。
これにより、本来は呪文を無効化しないモンスターにも呪文が通じなくなります。
結局、アスキーのウィザードリィで致命的なバグが無いのは、
リルガミンの遺産(ファミコン版)のみですね。
狂王の試練場が一番好きなだけに残念でした。
ファミコン版のダイヤモンドの騎士はレベル1から始められるのですが、
終盤はコッズ・アイテムが無ければ話にならないのはオリジナル同様です。
結局、小手でTILTOWAIT連発がメインとなり、戦略性はありませんでしたね。
転職アイテムが豊富なので、訓練場で転職することもありません。
狂王の試練場の追加シナリオということで仕方ないかもしれませんが、
ちょっと期待はずれの作品でした。
それでも、並のRPGよりはハマるのは、さすがウィザードリィと言ったところですね。
PS版は、オリジナルと同じく狂王の試練場からキャラを移動できるのが良かったですね。それが、本来製作者側が狙ったことでしょうし。
FC版は、当時遊べませんでしたが、同じくゲームスタジオ製のSFC版で遊びました。迷宮の更に奥深く、とって付けたようにプレイヤーを待っているあの方・・・が哀愁を漂わせていい味出してましたね。