
『バブルボブル』(Bubble Bobble)は、1986年に登場したタイトーのアーケードゲームです。古くは『ちゃっくんぽっぷ』(83)より続くタイトーの固定画面のアクションゲームで、『フェアリーランドストーリ』(85)~本作(86)~『レインボーアイランド』(87/続編)~『ニュージーランドストーリー』(88/固定画面ではない)~『ドンドコドン』(89) という一連の流れの中にあります。また94年には『パズルボブル』(Puzzle Bobble)という、本作のキャラを使ったパズルゲームも登場しています。これらのタイトーの固定画面タイプのアクションゲームの中でも特に有名な作品で、本作を含めて6作品ほど続編やシリーズ作品が出ています。移植例も多くFC(ディスクシステム)、SEGA・マークIII(ファイナルバブルボブル)、コモドール64、MSX2、X68000、FM TOWNS、Windows、ゲームボーイアドバンス、ニンテンドーDS、PS2(タイトーメモリーズ)等で発売されています。
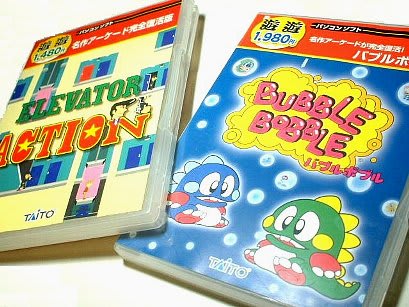
ゲームのシステムは、泡を吐く怪獣バブルン(2P:ボブルン)を操作して敵を泡に閉じ込め、それを割ることによって倒していきます。画面内の敵を全て倒すとクリアとなり、次のステージへと進みます。かわいらしいキャラとわかり易いルールで、あまりゲームに詳しくないライトな層でも気軽に遊べる作品で、それもヒットした理由のひとつだと思います。また敵を倒すとフード(ボーナスアイテム)へと変わり、ラウンドクリア時には画面上の泡が全てフードへと変化したり、大きなボーナスフードが落ちてくるなど、見た目の楽しさ(華やかさ)もありました。ただし用意されたステージは100面(200面)もあり、バブルンを助けるアイテムも50種以上と、(かわいらしい見た目とは裏腹に)かなりやり込み度の高い作品であったりもします。この時期のゲームらしく隠しコマンドも準備されており、タイトル画面でコマンドを入力することによって、オリジナル、パワーアップ(途中でやられてもアイテムの効果が持続する)、スーパーバブルボブル(裏面100面)などが用意されていました。この時期のタイトーのゲームとしても特によくできており、(個人的には)数多くのアイテムが登場する(54個)ナムコの『ドルアーガの塔』60面(120面)に匹敵する奥の深い作品だったように思います。

バブルンを助けるアイテムにもいろいろな種類があり、①パワーアップするもの…キャンディー(泡の連射、速度UP、飛距離UP)、シューズ(速度UP)、チャックンハート(無敵)、②助けるもの…時計(敵を止める)、パラソル(ラウンドワープ)、クロス(ファイヤーが吐ける、雷攻撃、画面が水没して敵を一掃)、ダイナマイト、スターティアラ、ブックオブデス(敵を全滅)、③ボーナスアイテム…ホーリーウォーター(画面上に花が咲きボーナスステージ)、杖(クリア時に巨大フードが降る)、リング(泡を吐く、ジャンプ、歩くごとに得点)、トレジャーボックス(ダイヤが降る)、銀の扉(隠しステージ)などがあります。これらは、ドルアーガの塔のように面ごとに決まっているのではなく、一定の条件(規定数ジャンプする、泡を吐く、泡を割るなど)をクリアすると出現し、取らなくともゲームの進行には関係ないものがほとんどでした。そのため出し方を知らなくとも、プレイしている間になんとなく出現するといった感じで、そのことがこのゲームの敷居を下げていたように思います。特に攻略本など見なくとも、何度もプレイしているうちに少しずつ上手くなり、少しずつ先のラウンドに進めるといった感じでした。このあたりのバランスもとてもよくできていたように思います。

個人的な思い出としては、86年の登場時にはそれほど遊んでいません。FC版もディスクシステムだったことや、マークⅢ版も登場が遅かった事、MSX版もMSX2対応などだったことから、ほとんど遊ぶ機会がありませんでした。90年代に入って暇をもてあましていた学生の頃、午前中からパチンコに行ったり、サウナに行ったりしていた時間に、ゲーセンによって(ゲームをするというよりは時間つぶし見たいな感じで)毎日1~2回ずつ日課のように遊んでいました。もう、この頃はゲームの攻略をするというつもりもありませんでしたので、行き当たりばったりに少しずつ進んでゆくといった感じで、50面くらいまではいったように記憶しています。50円で結構長く遊べて、特にアイテムの出し方等知らなくても少しずつ進めるといったこのゲームのシステムが、このゆるい時間になんとなくマッチしていたのだと思います。それ以降は、記憶の片隅に追いやられ思い出すこともなくなっていたのですが、2005年になって突然に電子ゲームとして甦ってきました。ということで、電子ゲーム版バブルボブル(Bubble Bobble)の紹介へと続きます。
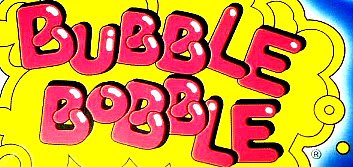
参考:Wiki バブルボブルの項、バブルボブル攻略、SEGA POWER













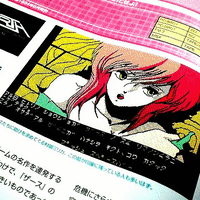




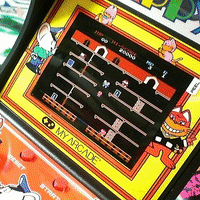

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます