 『襲い来る火砕流』 2015年6月8日
『襲い来る火砕流』 2015年6月8日5月29日午前、九州南海上屋久島付近の口永良部島の新岳が爆発的噴火したけど、その写真を観ていて昔の火砕流を思い出したね。
同じく、九州島原の雲仙普賢岳が大規模な人的被害をもたらしたのは1991年(平成3年)6月3日16時8分の大火砕流だね。
1990年(平成2年)11月17日に山頂付近の神社脇の二か所から噴煙が立ち上り噴火が始まったんだね。
しかし、12月には小康状態に入り道路の通行止めなども解除され、そのまま終息するかと思われたが、翌年2月12日に再噴火、
さらに4月3日、4月9日と噴火を拡大していった。5月15日には降り積もった火山灰などによる最初の土石流が発生、
さらに噴火口西側東西方向に延びて多数の亀裂が入りマグマの上昇が予想された。5月20日に地獄跡口から溶岩の噴出が確認されたんだね。
溶岩は粘性が高かったために流出せず火口周辺に溶岩ドームが形成され桃状に成長し、やがて自重によって4つに崩壊した。
溶岩ドーム下の噴火穴からは絶え間なく溶岩が供給され山頂から溶岩が垂れ下がる状態になった。新しく噴き上げるマグマにドームが押し出され
斜面に崩落することにより、破片が火山ガスとともに山体を時速70~100kmものスピードで流れ下る火砕流と呼ばれる現象を引き起こした。
ハワイ島のキラウエア火山の溶岩は、対照的に柔らかで火口から噴出して川のように流れ下るんだね。あれはあれでコワイけどね。

『九州島原 雲仙普賢岳の全景』
凄まじい勢いで走り下り猛煙が怒り狂うように辺りを包み込むんだね。これをメラピ型火砕流と呼ぶらしい。
この普賢岳の火砕流は、世界で初めて鮮明な映像として継続的に記録されたとある。折から梅雨時の豪雨も重なり
堆積した火山灰が流出する土石流も発生して、これらが流れ下るコースに当たる水無川沿いおよび島原市の千本木地区が大きな被害を受けた。
5月24日に最初の火砕流が発生して以降、頻繁に起こる小規模な火砕流の到達距離は、溶岩ドームから東方に約3kmに達していた。
火砕流の先端が民家から500mに迫った26日、水無川流域にある北上木場町、南上木場町等、五町に対して島原市から避難勧告が出された。
この状況を映像に捉え、世間に報道することの意義に燃えて報道各社は、普賢岳を真正面に捉えることが出来る北上木場町の県道を撮影ポイントとした。
この地は、溶岩ドームから4km離れており、さらに土石流が頻発していた水無川から200m離れた丘陵地となっていたんだね。
当時、報道各社は紙面にカラー写真を多用し始めており、普賢岳災害においても各社はカラー写真で競い合っていた。
5月28日に毎日新聞が火砕流の夜間撮影に成功すると競争は更に激しくなり、連日、10数台もの報道関係者の車両が並ぶ状況となった。
水無川沿いに土石流、火砕流が流れ落ちる勾配から、このポイントは、その脇に位置して小高い丘陵にもなっていることから安全と誤認したんだね。

いつしか、彼らにとって、この地を「正面」もしくは「定点」という呼び名が定着した。6月3日15時30分以降、小・中規模の火砕流が頻発し、
午後3時57分には最初の大規模な火砕流が発生した。この火砕流と火砕流から発生する火砕サージは報道陣が取材に当たっていた「正面」には
至らなかったものの、朝から降り続いた降雨に加えて火砕流から発生した火山灰が周囲を覆ったため、「正面」付近の視界は著しく悪化した。

「正面」の撮影地に他局の者らと日本テレビ報道局の小林浩司(当時26)カメラマンと狐崎敦(同30)ビデオデレクターが居た。
「おぉ~こりゃあ大きいぞ」 狐崎「NIB1からNIB3 中継車さんどうぞ」狐崎「これはデカイぞ」狐崎「3時59分」狐崎「NIB3から中継車どうぞ」
他局記者「手前民家に迫る勢いの非常に大きな火砕流が発生しています」狐崎「噴火」本部「NIB1からNIB3号さん」狐崎「NIB3です」

雨が降りしきる中、記者たちは中継に必死の様子。最期までカメラを回し続けた小林浩司カメラマンの焼け爛れたビデオの中のカセットは無事だった。
小林浩司は入社して2年目、必死に撮り続けた。狐崎敦はアフガンから帰って、其の足で普賢岳取材に赴いたんだね。
狐崎「今、凄い土石流です」 興奮したのか火砕流を土石流と称している。狐崎「今、凄い土石流です、今までで一番最大規模だと思われます」
狐崎「え~民家まで迫る勢いです、どうぞ」本部「了解」狐崎「今、回ってます」小林「レンズが濡れてるんです」狐崎「撮れ、撮れてるの?ちゃんと」
小林「はい、撮れてます」 黒煙が襲っている。狐崎「これ、来るよ、これ、火山灰こっちへ来るよ」狐崎「小林、ちょっと小林」 異臭が鼻をつく。
記者「4時6分になりました」記者「我々のところに到達した火山灰が周りを取り囲んでいます」
記者「非常に焦げ臭いような、土の匂いのような複雑な匂いが立ち込めています」「周りが霧がかかったような、茶色い霧がかかったような、そんな状態です」

火砕サージとは、火山の噴火の際に発生する現象のひとつで、火砕流に似ているが火山ガスの比率が高いため密度が小さく高速で薙ぎ払うように流動する
現象をいう。流動中の火砕流の先端からガスがジェット状に噴出することがあるらしいね。当然、高熱で全てを焦がし尽くす。
爆風の如く襲い来るんだろうね。猛烈な熱風が瞬時に辺りの木々を焦がして煤化した粉塵とともに突き進んでくる。熱湯を浴びるような感触だろうかね?
「火砕流:高温の火山灰、軽石などがガスと一団となって猛スピードで移動する現象で、通過域では焼失などの破壊等壊滅的な被害が生じる。
速度は時速100kmを超える場合もあり、発生後に避難することは困難。
火砕流の先端や周辺は火山灰を含む高温・高速の気流(火砕サージ)で、火砕流本体よりも広範囲かつ猛スピードで移動する」と云われてるね。
小林「臭いわ、これ臭いわ」 ターンしたビデオにパトカーが映っている。警察「大変危険な状態になっています」
「大変危険な状態になっています、下のほうまで避難されてください」「大変危険な状態になっています、下のほうまで避難されてください」
午後4時7分 「現在、大変危険な状態になっております」記者「ちょっとじゃあ、リポート一発とりますので」本部「NIB1からNIB3号さん」
現場が、相当、混乱している様子。パトカーに擦れ違って待機中のタクシーが移動している。
狐崎「3です、どうぞ」本部「3号さん、感度いかがですか?」狐崎「マルチの4です、どうぞ」
午後4時8分、一回目を上回る大規模な火砕流が発生した。「なんの音っ? やばいなっ」
小林浩司カメラマンの焼け爛れたビデオの中のカセットの録画録音は、ここで切れている。

『島原市・北上木場地区の民家を飲み込み水無川下流へ迫る大火砕流』 島原市白谷町から6月3日午後4時10分撮影。
もうもうととぐろを巻くような、怒り噴き上げて盛り上がるような煙の化け物が猛り狂ったように山肌駆け下って襲って来た。
その大火砕流は、溶岩ドームから東方3.2kmの地点まで到達した。
そして、其の火砕サージは、更に溶岩ドームから4km先にある北上木場町の報道陣がいる「正面」を襲ったんだね。
報道関係者は不測の事態に備えて即座に逃げられるよう、チャーターしたタクシーや社用車を南に向けてエンジンをかけたまま道路右側に止めていたものの、
視界が悪かったこともありほとんど退避できなかった。不測の事態は、不測であって事態発生に於いて、其の状況を思い知らされるんだね。
一方、同地の農業研修所の消防団員は火砕流の轟音を土石流が発生したものと判断し、水無川を確認するため研修所から出たところを火砕サージに襲われ、
多くの団員はそのまま自力で避難勧告地域外へ脱出したものの、重度の熱傷と気道損傷を負ってしまった。この消防団員の方が、
粉塵に覆われ視界の悪い山道を、焼け爛れて皮が垂れた両腕を前方に差しだし「逃げろ~、逃げろ~」って降りてくる姿が映像に映っていたね。
お茶の間のテレビのこの報道シーンには衝撃を受けたよ。広島原爆被災者の姿がダブるような映像だった。
人というのは、このような時、我が身よりも他人(ひと)さんを案じて危険から守ろうとする純な思いが優先するもんなんだろうかね。

『火砕流の犠牲となる約1時間前に撮影、北上木場町の報道陣がいる「正面」ポイント』
「正面」で火砕サージを諸に受けた北上木場町の報道関係者は学生のアルバイトも含めて16名、
クラフト夫妻と案内役のアメリカ地質調査所のハリー・グリッケンら3名の火山学者、警戒にに当っていた消防団員12名、
報道関係者に傭車され独断で避難できなかったタクシー運転手4名、避難を呼び掛けに来た警察官2名、
市議会選挙ポスター掲示板を撤去作業中だった職員2名、農作業中の住民4名の合わせて43名の死者・行方不明者をだす大惨事となった。
このように火砕流による多数の犠牲者が発生したのは、その危険性について、当時、充分な認識が広まっていなかったことが背景にあるんだね。
5月24日に発生した最初の火砕流は衝撃的だったものの、当時の報道関係者の認識は「かなりの高温ではあるが、熱風(火砕サージ)を伴うものとは知らず、
車で逃げ切れるだろうと思っていた」「熱いと知っていたが焼け焦げるまでとは知らなかった」という程度だったんだね。
これは翌25日の気象庁臨時火山情報にて、火山学者や専門家が議論の末、「24日の崩落は小規模な火砕流」と発表したものの、
住民の混乱を恐れたため火砕流の危険性について具体的な言及が一切無かったんだね。本来の「地質学的に小規模」の意味が、
「人的被害を出さない程度の規模」と、報道関係者は受け取ったんだね。

5月26日には、水無川上流の砂防ダム工事関係者が火砕流により腕に火傷を負ったが、「火傷程度で済むならば長袖のシャツを着ておれば大丈夫」と
いう噂が流れるなど、危険性について情報が広まらなかった。さらに5月25日から6月2日までの火砕流の発生回数は小規模なものを含めて165回に達したが、
その中で比較的規模の大きな火砕流であっても全て水無川上流の砂防ダムでせき止められていた。
こうしたことから報道陣に火砕流に対する馴れが生じてしまい、避難勧告地域内ではあったものの溶岩ドームから4km離れた上、
小高い丘陵地であった「正面」への安心感も手伝って、この一帯への取材が過熱することになったらしいんだね。
オレが、いつも云ってるだろうが、自然をなめてはいかんのだよ。「よう云うてるな」 そうだろ。自然から見た人間なんて蟻と一緒だよ。
しかし、解(げ)せんのは、「古い台詞やねえ」 クラフト夫妻と案内役のアメリカ地質調査所のハリー・グリッケンら3名の火山学者が、
このような事態を予測できなかったってところだよ。当然、火砕流には、火砕サージが伴って、火砕流到達地点より先走ることを理解していたはずだよ。
報道関係者らと違って火山学者だからねえ、火砕サージの恐ろしさも認識してるはずなんだけどね?
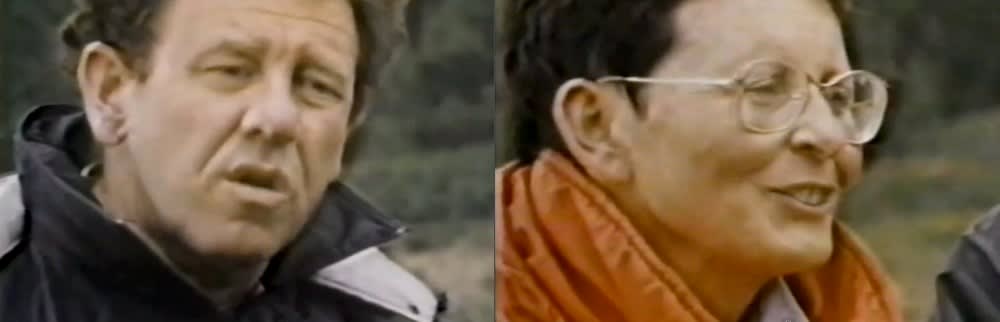
『火山学者モーリス・クラフト・カティア・クラフト夫妻』
フランスの著名な火山学者モーリス・クラフト、カティア・クラフト夫妻は、この20年間に調査と撮影のため、世界の120箇所の噴火中の火山をまわり
この時も西インド諸島の火山調査に訪れていたが、早めに切り上げて爆発兆候にある雲仙岳に赴くため5月に来日した。。
ヘリコプターの調達が不調に終わり、仕方なく「正面」地点よりも前の3km地点に陣取り火砕流を写真に収めようと構えていたらしい。
「正面」地点から3km先といえば、もう、火口に真近だよ、溶岩ドーム崩壊とともに焦げて無くなる位置になる。
普賢岳は、通常の火口からの噴流ではなく噴出した溶岩ドームが崩壊して火砕流が発生するんだね。考えられないけど読みを誤ったのかね?
クラフト夫妻は、1000度にもなる火口付近まで接近して多くの迫力ある火山映像を提供することで知られていたんだね。
雪山は死んだ山、火山は恋人と云うほど活火山に惚れ込む気の入れようの二人だったらしい。本望だろうね。
日本の火山学者も、この二人の研究や映像に恩恵を受けているから指図するようなことも云えず、学者グループは、報道陣の「正面」より、
なお、噴火口に近い、まるで、噴火口の真下まで接近して、カメラポジジョンを取っていたという。ほとんど自殺行為だね。

わざわざ他国の火山活動を調査に訪れてんだから、それらの認識を新たに構えていそうなもんだけど、この大火砕流は、彼らの予測を上回ったのかねえ?
察するところ、噴煙と降雨が重なって視界を奪われ火砕流の発生の予測が働かなかったために判断が遅れたのかも知れないね?
君子危うきに近寄らず、読みを利かせて難を逃れる手でいかんとエライ目に遇う。避難を呼びかけに向って巻き込まれた警察官2名が気の毒だね。
前線に行かずして生の報道あり得ずの精神の記者たちは戦死だね。この記者たちよりも後方に居ては役割果たせずで警戒に当った消防団員12名は
職務を全うして殉職した。この消防団員のほとんどが地元農家の跡取り息子だったことは、その後の農業復興に甚大な被害をもたらしたんだね。
雇車のタクシーで待つ運転手4名は、咄嗟に走り出せば車内に守られて逃げれたかも知れない。でも、仕事に忠実だったが故に機を逸したね。
この悲劇は、報道関係者の勇み足が、要らぬ犠牲者を増やした要因として糾弾され報道の有り方に猛省を促す警鐘となった。
市議会選挙ポスター掲示板を撤去作業中だった職員2名、農作業中の住民4名については、なんで、また、こんな非常時にと思ってしまうね。「アホ」
「上司が行けって云ったんだろ」「こげぇな時にぃ?」「仕事にこげん時あげぇな時ってねえっ撤去すろ」 その上司は、どんな気持ちになっただろかね?
ど田舎だろ? 一日、二日ズレても支障ないで。火砕流が頻発してんのに農作業って、退屈だったのかねえ? 田舎の人の考えは、よう解らんわ。

今から24年前の出来事だったね。先人の犠牲から学んで早々に避難した口永良部島の島民は、全員が無事脱出できて幸いだったね。

『大野木場小学校を襲う火砕流』 円形の部分、校内から子供が飛び出して逃げてくる。とある。

『町民が避難した小学校の脇を奔り下る火砕流』 凄い写真だね。

『火砕流の直撃を受けた様子だね』

『普賢岳火口付近の神社』

『島原城の後方に猛煙を上げる火砕流』

『この上下の写真は、被害の状況から火砕流の直撃は免れているが火砕サージの熱風を受けたようだね』




仕上げを急いだので、写真の説明を取り込むのを忘れたよ。全て、写真は、雲仙普賢岳火砕流に関するものです。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます