
福田恆存/村田元史演出「カクテル・パーティ」劇団昴公演 昭和56年 三百人劇場
一昨年の9月に続き、今年の2月16日、日本演出者協会主催の「日本の戯曲研修セミナー」に招かれ、福田恆存「龍を撫でた男」について話をしました。この戯曲については以前に当ブログでも触れたことありましたがあらためて、正面から本格的に、となるとなかなか難解であることが実感されます。
最初に、福田による「作者のことば」を挙げておきます。これはこの戯曲が発表された『演劇』昭和27年新年号に掲載されたもので、その後の自作解説に比べて、執筆直後の、一番素直な気持が出てゐるやうに感じられます。また、福田の各種の全集や評論集には未収録なやうですので、全文を示す価値があるでせう。
この芝居にはじつは三つの下敷があります。それは三つの作品のシチュエイションをまねたといふことです。翻案とすべきかもしれませんが、それではわたくしの良心が許しません。あんまり種あかしをすると、作者のオリジナリティーを疑はれる心配があるので、こゝにはそのうち、いちばん罪の軽いやつを申しあげることにします。みなさんのうちにはエリオットの「カクテル・パーティー」の幕切をおぼえてゐるかたがあるかもしれませんが、わたくしは「龍を撫でた男」の第一幕をそこからはじめたらどうなるだらうかと思つて筆をとりました。もちろん、日本はクリスト教国ではありませんので、登場人物の性格や役割は当然ちがつてまゐります。わたくしはライリー卿とエドワードとを同一物(ママ)にしてしまひましたし、殉教者シーリアを喜劇化してしまひました。「カクテル・パーティー」の精神病医は落ちついたものですが、「龍を撫でた男」のそれは、最後に気が狂つてしまひます。どうも困つたことですが、やむをえませんでした。わたくしにはこれをまともな演劇の形式美にまで高める力がないよう(ママ)です。
私はここで言はれてゐる「三つの下敷」にこだはつてみました。一つは「カクテル・パーティ」であることは作者本人が明らかにしてゐますが、あとの二つのうちの一つは、ルイジ・ピランデッロ「エンリーコ四世」(「ヘンリー四世」の名で、昭和42年、劇団雲によって上演された)ではないか、といふのが私の昔からの思ひ込みでした。
それは本記事では触れません。発表のために、「龍を撫でた男」を通じて「カクテル・パーティ」を再読・再考して、前の記事にも書いた現代的な信仰の問題がここで深く追求されてゐることを納得できるやうに思ひました。これを土台として現代劇を作らうといふのは、宗教的感情=超越的なものに関する感覚が失はれてゐることを劇にする、といふことで、いはば裏側から悲劇を創造する試みと言へさうです。
以下ではこの見地から「カクテル・パーティ」を分析し、さらにその問題意識を日本的に受け継がうとした「龍を撫でた男」についても少し考へます。
T.S.エリオットの三幕の詩劇「カクテル・パーティ」(1949年初演)は典型的な家庭劇のやうだが、エウリピデス「アルケスティス」(B.C.438)から想を得た、といふ作者の言葉がある。前作「一族再会」は、アイスキュロス「オレステイア三部作」、特にその二作目の「供養する女たち」を踏まえて作られてゐることは、登場人物が突然ユニゾンで、コーラス(コロス)として詩の朗唱のやうなことをしたり、この世のものではない妖女エウメニデス(復讐の女神)の幻影を見る、などのキーポイントがあるが、「カクテル・パーティ」とエウリピデスの関係は、本人が言はなければ誰にも気づかれなかつたらう。
「アルケスティス」の概要は以下。
かつてアポロンはテッサリア地方ペライの領主アドメトスの世話になり、その恩返しのために、アドメトスの命に危険が迫つたとき、代りに死ぬ者がゐたら、助かるやうに取り扱ふ。その時が来て、アドメトスの老親は身代りを拒むが、まだ若い妻アルケスティスは受け入れる。そのときちようど訪問してゐた遠縁のヘラクレスが、事情を知つて、墓所に潜み、アルケスティスを連れに来た死神の使ひと格闘して撃退し、彼女を取り戻す。
古代の劇らしく、大らかなものだ。ハッピーエンディングの悲劇。もつともこれはサチュロス劇(能楽の番組中の狂言みたいなもの)扱ひだつたらしいが、何しろ、劇とはこれでいいのではないかと思へてくる。
見せ場はあるのだから。アルケスティスとアドメトス(と彼らの息子)の別れの愁嘆場。→アドメトスと、結果としてアルケスティスを死なせることにした父ペレスとの諍い。→ヘラクレスが助けたアルケスティスを、アドメトスは最初妻とはわからず、館に入れることを拒む取り違へのおかしみ、が最後に付け加わる。
このうち特に真ん中の、アドメトス「あなたはもう充分に生きたのに、なぜ息子のために死んでくれないのだ」vs.ペレス「いくら生きても命は惜しい。他の者のために死ぬ気にはなれん」、といふ言ひ争ひは、現在読んでも非常に生彩がある。エウリピデスは討論の場面が得意で、恐らく理の勝つた人だつたのだらう。それでニーチェは彼を嫌ったのだが。それはともかく、観客は場面ごとの、俳優の所作や朗唱される詩句の美しさを愉しめばいいのであらう。
しかし近代になると、観客の中でも、一部かも知れないが、全体の辻褄がどうたらかうたら言ひ出す人も出てくる。この話の発端は、アポロンがタナトス(死神)に頼み込んで交した約束事である。その変更には、なんらかのもつともらしい理屈付けがあつて然るべきではないか。ヘラクレスの武勇で、力尽くで破るとは、神たるアポロンに相応しい行ひとはとうてい思へない、云々かんぬん。
もう少し文芸批評風に言ひ直すと、この作の中心であるはずの犠牲のテーマにきちんとした決着がつかず、無理矢理救はれて犠牲ではなくなるだけなので、肩透かしを食らはされたやうな気になるのだ。かういふものを今書けば、「お前はバカか?」と言はれかねないので、書けない。
夫婦の和合と犠牲のテーマを並び立たせるためには、犠牲者は夫婦のどちらかであつてはならないのはもちろん、夫婦以外の誰かが彼らのために犠牲になるのもいけない。たとへ一見さう見えるとしても。
すると結局どこかで肩透かしを食わせる必要が出てくる。問題は、その肩透かし自体にもつともらしい理屈をつけられるかどうかだ。
「カクテル・パーティ」の七人の主要登場人物は明白に二つのグループに分かれる。劇が起こるのはエドワード+ラヴィーニアのチェイムバイレン夫妻+シーリア+ピーターの恋愛(か?)関係、特に前三者による三角関係の中でだ。もう一方の、ジューリア+アレグザンダ+ライリー卿の三人は、最後まで正体不明だが(と言ふか、「正体」は問題にされない)、狂言回し兼道化として要所要所に顔を出し、軽快に劇を進め、全体としてチェイムバイレン夫妻の不和を解消する働きをするやうだ。
舞台はチェイムバイレン家のカクテル・パーティ(飲み物主体の簡易な立食パーティ)から始まる。招待状を出して客を呼んだのに、この家の主婦のラヴィーニアがゐない。田舎の伯母さんから病気の報せがあつて、と夫のエドワードは言ひ訳するのだが、客(上記の五人)は誰も信用してをらず、要するに嘘であることは一見気軽な会話のやり取りからわかるやうになつてゐる。
やがて四人が帰り、ライリー卿(この時は「見知らぬ客」と表記されている)だけが残ると、ホストのエドワードは初対面の彼に現在の夫婦の問題を聴かせたいといふ誘惑を押さえきれない。ラヴィーニアはパーティの準備を済ますと、短い手紙を置いて家を出て行ってしまったのだ。エドワードは彼女に戻つてきてほしいと思つてゐる。しかし、それはなぜか? と問はれると、答へは見つからない。そんな彼にライリーが言ふ。
これでもう階段が終つたとおもふ、するとあなたの予測に反してもう一段のこつてゐたりしますね。さあ、あなたはどうなりますか、たちまちぐらつとくるでせう。まさにその瞬間、あなたは、そのいぢの悪い階段のおもひのまゝどうにでもなる一箇の客体と化してしまつたわけだ。
階段の思ひのままといふより重力の、と言つたはうがいいやうに感じるが、何しろ、それまで自由に主体的に動いてゐるとばかり信じ込んでゐたものが、当然あると思つてゐたものがない、ただそれだけで、その「自分自身」は失はれてしまふ。
考へてみれば、我々はいつどこで生まれて死ぬかについて、自分の意思など関係ない、現代では偶然としか言ひやうのないものに従つてゐるだけの存在なのだ。そんなものが、自分自身に対しても、他者に対しても、どのやうな「責任」が持てるのか?
最後にライリーはラヴィーニアはやがて戻ってくる、とだけ告げて去る。すると帰つたはずの連中が、忘れ物をしたとかなんとかの口実で次々に戻つて来る。
シーモアは、エドワードと特別な関係だつたので、彼に対する口実はいらない。しかしその関係はもう終はりにしなければならないやうだ。エドワードは彼なりのやり方でシーモアを愛してゐるが、結局彼女の望むやうな者にはなれないし、彼女の望むものを与へることはできない。それが今やはつきりしたからだ。
次の日、ラヴィーニアは帰宅する。彼女の不満、といふか不安は、エドワードが自分を理解しない、いや、理解するに足るほどの価値を認めてゐないのではないか、といふところにある。そんな女と一緒に暮らしてゐるのは結局彼の不幸ではないか。それ以前のエドワードは、「ほんたうの自分」であり得たはずだ、と。
これに対してエドワードは、「きみは相変らずぼくのためにひとつの人物像をでつてあげ、そのあげく、ぼくをぼく自身から遠ざけようとしてゐるだけ」だと断ずる。ラヴィ-ニアの言う「ほんたうの自分」など、あつてもなくても、欲しくはないのだ。自分自身とは彼にとって牢獄だ。エドワードは言う。
なぜぼくは自分の牢獄から出られないのだらう? 地獄とはなにか? 地獄とは自我のことだ。地獄とはひとりぼつちのことだ、そこには他人はたんなる影としてしか映つてゐない。なにから逃げだし、なににむかつて逃げていかうといふのか、なにもありはしない。はじめからひとりぼつちなんだからねえ。
これをラヴィーニアは理解しないのだが、エドワードが嘘をついてゐるわけではないことがわかつただけでも、一つの収穫である。彼にとつて他人は「影」にすぎないとすれば、シーモアが特別であるわけではない。嫉妬するには及ばないのだ。
第二幕になつて精神科医であることが明らかになつたライリーは、彼らは「似たもの夫婦」なのだと評する。「自分のことを愛する能力なしとおもひこんでゐる男と、自分はいかなる男にも愛されないだらうとおもひこんでゐる女」だから。帰するところは「おなじ孤独」。
お互いに相手をすっかり理解できないことだけは理解し、許しかつ諦めること。お互いの中に自分と同じ孤独を感じ取ればそれでよしとする。それで人間は、人間同士も、なんとかやっていける、とライリーは言う。
日常生活の軌道に乗つて着実に自己を維持し、過剰な期待をしりぞける習慣を身につけ、自分にも他人にも寛容になるのです。つまり、常識的な行動に即して、あるものだけを与へ、あるものだけを取るといふわけです。(中略)おたがひに理解しあへぬことを知つてゐる二人の人間が、朝に別れ、夕にはふたゝび相寄つて暖炉の火を眺めながらとりとめない会話を交はし、自分たちが理解できず、また自分たちを理解できぬ子供を育てていくことに、すつかり満足してゐる。
よく考へれば、人間にできる「まともな道」はそんなものだらう、と納得できる。しかし、かういふ言ひ方は、「よく考へ」させるところが問題なのである。そんなのは畢竟ごまかしでしかない、人間にとつて本当の価値ではない、といふ声がどこからか挙がることを予感させるところが。
現にシーモアはさう言ふ。「それはあたしの心を凍らせるでせう」と。「いまさらだれかと馴れあひの生活をはじめるなんて、あたしのばあひ、どう考へても不誠実としかおもはれませんわ!」と。自分は病気なのかも知れない。しかしその自分はかつて何か夢を見た。それを忘れたくない。「それを胸のうちに温めてゐることさへできれば、ほかにはなにも要りませんし、どんなことにも堪へていけます」。
かつて彼女はその夢をエドワードにかけた。しかしそんなものに応へるのは生身の人間には土台無理なことだつた。彼がもつと大胆な、身の程知らずの男であつたとして、シーモアとの関係を維持しさらに発展していかうとすれば、その果てには破滅しかない。人は通常絶対の次元では生きられないからだ。
ライリーは彼女には次のやうに語る。前に述べた「炉辺の幸福」に至るのとは違ふ「第二の道」がある。あるいは、彼女が求めるものが見つかるかも知れない道が。しかしその道は「だれもこれを知るものがない、だからこそ信仰が必要なのだーー絶望から生まれる信仰がね」。
シーモアは第二の道を進む。その後の彼女の運命は最終幕で明らかにされる。戒律の厳しい教団に入つて、衛生状態も政情も最悪な東洋のある島へ赴いて、現地の病人の看護をする奉仕活動に従事してゐた。内乱が起こり、教団の他の者も逃げ出す中で、瀕死の病人を見捨てずに踏み止まり、最後には十字架に架けられて亡くなった。
それはシーモアの宿命だつた。彼女が庇つた病人もすぐに亡くなつたのだから、その献身は無駄だつたやうにも思へる。しかしそれは妥協のない勝利の生涯だつた。他人はその勝利になんら手を貸してゐないのと同様に、その悲惨に対してなんの責任もない。これがライリーの最後のご託宣である。
福田恆存は昭和26年に「カクテル・パーティ」の飜訳を刊行すると、そこに精密な解説を付した(『福田恆存全集 第二巻』に収録)。そこでは原著者の意図は、「それは(精神≒神の)存在証明ではあつても、あくまで不在証明を方法としてゐる」とされてゐる。「愛と精神と神とのみごとなアリバイをつくるために、エリオットには一分の隙もない巧緻な構成が必要だつた」と。
ある危機的な状況で、「自分とは何か」といふ問ひが立ち上がる。それで「自分」の中を覗くと、そこには何もないことに気づいて、愕然とする。自分が自分であることの根拠も意味も、見つからない。それでも、生きてゐる以上、何かをしたり言つたりせずにはゐられないのだ。
突然家を飛び出して、多分、離婚といふ危機を招いたラヴィーニアは次のやうに述懐してゐる。
あたしはなにかの機械に手をつけてしまつた。それがいまも動いてゐるんだわ。あたしにはとめることができない。いゝえ、機械とはちがふわーー機械だとしてもそれを動かしてゐるものがほかにゐる。でも、だれでせう? だれかの手がいつも感じられるの……、あたしは自由ぢやない……、でも、けつきよく、あたしが動かしてしまつたんだわ。
情況、つまりドラマを、動かす本当の作因は舞台の外にある。自我といふ牢獄に閉込められた人間には、それが見えない。我々近代人は、畢竟空つぽな人間(hollow men)にがらくたを詰め込んだやうなものなのだ。確かなものを見出さうとして、ぬるま湯のやうな日常から離れて困難な道を歩むとしても、その先に「絶対」があるのかどうか、それは誰にもわからない。
しかし、近代人にとつてなんとか受け入れられさうな信仰の可能性は、ここを通るしかない。自己の矮小さを知り、その反対側に、すべてを動かすものの手を感じ取ること。自己とは、その手に操られる人形のやうなものであることを敢えて自認して生きること。福田は後にこれを演戯と呼んだ(「人間、この劇的なるもの」)。
以上は、歴史的に絶対者の観念とは無縁だつた日本ではどういふことになるのか。その実験が、「カクテル・パーティ」訳出の翌年に書かれた「龍を撫でた男」になる。
見やうによつては、ここでライリーは、意地悪な質問を突きつけられたやうなものだ。「他人事だから、偉さうなことを言つたり、有益なことができたやうに見えるが、これが自分の身の上に起きたことだとしたらどうだ? 果たして、どれくらゐのことができるのかね?」と。
エドワード+ライリーはここでは佐田家則といふ精神科医である。妻帯者だが、かつて事故で子どもを亡くしてゐる。義母は心神喪失状態となり、義弟は戦争から復員して以来、何もせずにぶらぶらしてゐる。家則はそんな妻の血族と同居して、養ふ。彼らを理解するのではなく、非常な寛容をもって臨み、支えようとする。何も要求せず、決して責めず、すべてを受け入れる感じで。
危険は二つある。第一に、すべてを受け入れ、認めるのは、相手に対する全くの無関心と見分けがつかない。第二に、すべてを認めるなど、人間にできることではない。
家則は実は、絶望から夢想へと激しく気分の変わる妻に最初から苛立つてゐて、それを押さへてゐることが示される。妻のはうでは、自分たちが家則なしでは一日も生きていけないことはわかつてゐるが、そのやうな惨めな状態に対する不満を、時に夫にぶつける。要するに甘えなのだが、それもまた、家則は受け入れるだらう。受け入れねばならぬはずだ、と、甘えの上で生きてゐる妻とその弟はなんとなく思ひ込んでゐる。
かういふ家族に、劇作家とその妹の女優が絡む。前者は妻の、後者は家則の誘惑者として。このうちの女優がシーモアに当るわけだが、現実の生活など退屈なだけでなんの価値も意味も認められない、と言ふところだけが共通してゐて、絶対の、永遠のものを冀求してゐるわけではない。狙つた男をモノにする恋愛ゲームに耽るだけで、それからどうするかなど考へてをらず、空騒ぎするだけの、喜劇的な存在で終わるしかない。
主人公に戻ると、家則は一見エドワードより悲劇のヒーローに近い。頑張つて一つの世界を支えてをり、やがて敗北してそれができなくなることまで予感してゐる。「ぼくだけは気ちがひにならないとでもいふんだね……」というのが、全二幕のうちの第一幕の幕切れの科白である。
それでもここにゐるのはヒーローのパロディーでしかない。家則は「炉辺の幸福」にそれほどの価値を見出してゐるとは思へない。ただ、妻が憧れ、劇作家が唆す「情熱的な生き方」など、その場限りの迷妄に過ぎない、といふ醒めた目を持ち、概ね同じことの繰り返しである生活に耐えるために寛容であらうとする。帰するところは自分を守るため、それ以外にはない。
つまり、我が国では、寛容を支える精神性はどこにも見つからないだけではなく、「どこにもない」ことに気づく契機もないやうなのだ。「どうにも困つたこと」だが、このやうな内面性の中で自我とそれを支える全体性・絶対性を求めることが、評論家で演劇家であつた福田恆存の生涯の仕事になつた。

桜の園 初演の舞台写真
ヘンリック・イプセンが近代劇の父なら、アントン・チェーホフは現代劇の父と呼ばれるに相応しい。「人形の家」の初演は1879年、「かもめ」は1896年で、17年の間隔しかないが、物事が起きるときには連続して起きるものなのだらう。具体的には、近代写実劇が完成すると、その限界も目につき、以降の作家は乗越えを目指さざるを得ず、そこで最初に大きな成果を挙げたのがチェーホフといふことになりさうだ。
最大のポイントは、イプセンが一般市民(といつてもけつかう富裕なブルジョワだが)を題材とした悲劇的な作品を完成させたのに対して、チェーホフは近現代での悲劇の不可能性を、劇の根底の一つとして見せたところにある。
今まで折に触れて述べてきたが、ギリシャ劇から、17世紀フランスのラシーヌやモリエールまで、悲劇は王侯貴族や神話上の人物を描くもの、喜劇は一般庶民を、と決まつてゐた。
単純な話、例へばシェイクスピアの「リア王」「マクベス」「ハムレット」などで、主人公の言動が国家全体を揺るがす大事になるのは、彼らの身分が高いからだ。リア王が王様でなければ、たとへ大金持だつたとしても、アホな頑固ジジイに過ぎない。当事者以外からは笑はれるのに相応しいので、喜劇になる。
さうは言つても、一般庶民でも、自殺もすれば人殺しもする。嫉妬もすれば熱烈な恋もする。これをドラマに仕組めないものか? いはゆるブルジョワが、たくさんお金を稼いだおかげで社会の中枢に成り上がるにつれて、その要請は自然に強くなる。
イプセンは初期の頃、韻文で、「ブラン」や「皇帝とガリラヤ人」のやうな壮大な歴史劇を主に書いたが、「青年同盟」(1869)や「社会の柱」(1877)などの、現代を舞台とした劇も手掛けてゐる。しかし「人形の家」が決定的なのは、第一に緊密を極めた構成、第二に平凡な家庭の主婦にドラマ性≒悲劇性を見出した点にある。
先蹤はと言ふと、西洋古典悲劇の系列の最後に位置するジャン・ラシーヌであつたらう。極限まで狭められた場所と時間の中で、際立つた個性の持ち主たちが言葉をぶつけあひ、うねるやうに、しかし一筋に結末にまで行き着く。過去の情況説明も舞台上の「現在」の進行中に、過不足なく伝へられる。現代でも依然として、映画やTVドラマを含めた、せりふによる劇作品のお手本であらう。
しかし、「人形の家」がイプセンの名をヨーロッパ中に広めたのは女性解放運動の文脈で受け取られたからだ、といふのは、皮肉としか言ひやうがない。彼はこれまで、自由主義の立場からした社会諷刺を鏤めた劇をいくつか書いてきたのに、「人形の家」では、その種のものは一番後景にまで退いてゐる。因みにヒロインのノーラは、女性の権利、なんぞとは一言も口にしてゐない。
ノーラはフェミニストではなく、ボヴァリストなのだ。夢と現実の区別がつかないのではなく、夢の実現を容易にあきらめず、ために破滅に至る。この生き方は悲劇のヒロインたるに相応しい。ただ、エンマ・ボヴァリーもノーラ・ヘルメルも、女王でも王女でも、貴族の令嬢でもなく、ブルジョワの主婦である。
その身分の者は、「真実の愛」などといふものを求めてはいけないか? いけなくはない。ただ、いつまでも保ち続ける、あるいは保ち続けてゐるかのやうなふりをする義務はない。まして、命を賭けてまで。さういふのは貴族のもの、即ちノーブレス・オブリージュ(高貴な義務)なのだ。そんなものからは免れてゐる庶民が、何を場違ひな、といふ感じは、決して拭へない。
簡単に言えば、「ボヴァリー夫人」を読んだり、「人形の家」を観たりする人のかなり多くが、「なんか、大げさなんじゃないか?」との思ひを抱いてしまふ。
後者については、この家庭は自分が思ひ描いてゐたやうな理想的な場所ではなかつた、夫は自分を一人前の人間とは看做してゐなかつた、と気づいたときの幻滅の大きさをできるだけ思ひ遣るとしても、それで、夫だけならともかく、三人の子どもまで捨てて出て行くのは、やり過ぎではないか? 私が実際に会つた中でも、さういふ感想を言つた人はけつかう、女性の中にも、ゐる。
では、彼女のやうな人間の身の程はどんなものか。「桜の園」に登場する、農奴上がりの商人・ロパーヒンは、眠れない夜には時々次のやうに考へると言ふ。
神よ、あなたは実にどえらい森や、はてしもない野原や、底しれぬ地平線をお授けになりました。で、そこに住むからには、われわれも本当は、雲つくやうな巨人でなければならんはずです……。(神西清訳で引用。以下同じ)
これを聞いたヒロイン・ラネーフスカヤの反応は、
まあ、巨人がご入用ですつて……。お伽話のなかでこそ、あれもいいけれど、ほんとに出てきたら怖いわ。(以上第二幕)
ここで象徴的に言はれてゐるのは、彼らはどこからみても巨人≒英雄ではなく、ちつぽけな人間であつて、しかもそのことを自覚してゐる、といふことだ。これが大前提。
それだけでも、「桜の園」の主要人物はヒーローとはなり得ない。力も、覚悟すらなく、切迫した状況に投げ込まれれば、正面から対峙できず、ひたすらやきもきしてウロウロする者たち。彼らを描くのは悲劇ではあり得ない。
チェーホフは短編小説家として広く名を知られるやうになる以前から劇作を志し、挫折を経験してゐる。「イワーノフ」の改訂版(1889)は成功したが、それは、この頃までモスクワやペテルスブルクの上流人士の間では流行語だつた「余計者」としてのインテリゲンツィアを採りあげたところが大きいやうだ。
しかしその同じ年に書かれた「森の主」は上演を断られてゐる。当時の劇の主流だつた悲劇の、衰退・通俗形式たるメロドラマからして、この劇は筋の起伏も大仰な情熱の発現も乏しく、要するに退屈だと看做されたのだ。
その後7年間劇作に手を染めなかつたが、1896年には「かもめ」を完成した。初演は失敗して、チェーホフに深い絶望を与へたが、2年後、コンスタンチン・スタニスラフスキーの演出によるモスクワ芸術座の再演は大成功で、ためにこの劇団も作者も名声を確立した。以後のチェーホフの多幕物四作品は、すべて同じ劇団・演出によつて演じられてをり、ヨーロッパの演劇革新運動の主要な拠点となつた。
「かもめ」は最初から喜劇と銘打たれた。普通に言つて笑ふ要素はほとんどない(ラテン語まで使つた言葉遊びや言ひ間違ひによる擽りは少しあるやうだが)、むしろ陰鬱な印象が残る作品だといふのに。それを敢えて喜劇としたのは、当時の劇界や劇作品のあり方に対するチェーホフの強い反感の現れだらうが、内容的には諷刺を主眼とするところがこの名に相応しいと思へたのかも知れない。ただそれも、非常に独特のやり方で、だが。
エレオノーラ・ドゥーゼ並だといふ元大女優と、ツルゲーネフ並だといふ流行作家を登場させ、彼らの贋物性が描かれる。それは自分自身がけつかう自覚してゐるので、彼らは決して道化ではない。今更ドタバタ何かやつたりはしない。男や女を求める以外には。
ドラマはより若い世代が起こす。彼らの名声に憧れる若い女と、彼らの古くさい芸術に反発して新形式を求める若い男が、そのために破滅するのだ。自分たちの情熱によつてではなく、その対象の空虚さに直面することで。これは悲惨ではあつても、悲劇ではない。
しかしだからと言つて、この若い男・コースチャが自殺する結末は、私には、ノーラの家出以上の唐突感がある。劇にまとまりをつけるための強行手段ではなかつたか。そんなふうにさへ感じる。
それもあつて私は、この後1899年に上演された「ワーニャ伯父さん」からの三作こそ、本当に革新的な、真のチェーホフ劇と呼ばれるべき作品なのではないかと考へる。
すぐに目につく特徴は以下。ここまでの、二十歳そこそこで書かれて作者の死後に題名が欠けた状態で原稿が発見されたものを含む四作は、すべて主人公と言つていい男が変死することで終はる。題名のない戯曲のプラトーノフは女に撃ち殺され、あとの三人、イワーノフ、ジョルジュ(ワーニャの前身)、コースチャはすべてピストル自殺。
それが、「森の主」が改作された「ワーニャ伯父さん」になると、ワーニャはピストルを振り回すものの誰も殺さず自殺もしない。最後に劇を締めくくるのは、彼の姪・ソーニャの「でも、仕方ないわ。生きていかなければ!(中略)長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じつと生き通していきませうね」から始まる有名な長科白。死ぬより辛く、勇気も要るこの決意の切なさは、誰の心にも沁みるだらう。
このやうに、死ぬことでせめて格好をつける男たちに代って、女性の苦悩を経た覚悟が残るのは、次の「三人姉妹」にも引き継がれる。「もう少ししたら、なんのために私たちが生 きてゐるのか、なんのために苦しんでゐるのか、わかるやうな気がするわ」
なんのために生きてゐるのか≒自分とは何かは、やはり呪はれた問ひとしてある。しかも現代人は、とりわけ女性は、ヒーローとして自らの選択や行為の結果そこにぶつかるより、愛ある(と、見えただけ、を含む)関係から弾き出されて孤独になって、自分自身と向き合ふ。問ひに答へられる者はゐない。もしも全能の神があるなら、きつと、死後に教へてくれるだらう。
かうして、英雄ではない、さうなることもできない≒さうなることを期待されてゐない者たちに相応しい必然性を備えた現代劇は出来上がった。
ただしチェーホフの最後の戯曲は、情況の深刻さや感情の激発を押さえたより穏やかな雰囲気のもので、「かもめ」以来初めて喜劇と銘打たれてゐる。「桜の園」の初演は1904年1月で、その5ヶ月後に彼は亡くなつてゐるが、健康を害してゐたとはいへまだ四十四歳で、死を意識してゐたかどうかは定かではない。
例えば「三人姉妹」にはあつた死(主人公とは言へない男のだが)も、「桜の園」の劇の進行中にはない。死は、六年前、ラネーフスカヤの息子が川で溺死したこと、そして、最後に皆に忘れられて館に取り残された老僕が、たぶん遠からず迎へることが予想される。言はば、桜の園消滅の、舞台外の序章と終局を成してゐる。
もう一つ、これは今まで述べた内容の点より重要かも知れない。登場人物が各々自分の思ひに捕はれ過ぎてゐて、会話がすれ違う場合が非常に多い。愛も憎しみも、人間以外のものへの憧れも執着も、ちやんと他者に受け取られて、返されることはほとんどなく、いつの間にか虚空に消えてしまう。これは「かもめ」以後の特徴だが、「桜の園」では最も露骨に目につく。
イプセンの、何が焦点であるかが常に明確なドラマとはおよそ逆であり、言はば、筋の一貫の代わりに雰囲気の一貫が置かれてゐる。現代劇を拓くためには、この要素が何よりも大きかつたらう。
いや、そんなことより、皆が自分の穴の中に籠もつてゐて、他人に同情はできても、本当に関わり合うことはめつたにできない。また、自分自身の運命の主人公にもめつたになれない。それこそ我々がちつぽけな存在であることの何よりの証左なのだ。喜劇の手法を応用して、舞台上に現出されたこのリアルこそ、最も憂鬱で、最も恐るべきものであらう。
例えば、ラネーフスカヤには、守るべきものはあり、それが桜の園だ。「桜の園のないわたしの生活なんか、だいいち考へられやしない」(第三幕)とまで言ふ。しかし、全力を挙げて守らうとするのかと言ふと、かなりズレてゐる。
桜の園とは何か。「世界ぢゆうに比べものもない美しい領地」〈第四幕〉とも言われる宏大な土地で、ラネーフスカヤが生まれ育ち、結婚後もしばらくは過ごした館がある。ただし楽しい思い出だけではなく、六年前に夫がシャンパンの飲み過ぎで亡くなると、続いて愛息の事故死に見舞はれた。それで堪らなくなつた彼女はフランスへ赴くのだが、その時は男が一緒だつた。その後、この男に彼女は持ち金全部を搾り取られた挙句、捨てられて、故郷に戻つてきた。これが劇の始まり。
この劇には明確な時期の指定はないが、ロシア革命(1917年)以前に始まつてゐた貴族階級の没落を背景にしてゐるのは明らか。農奴解放(1861年)の結果、もとは絶対服従だつた使用人たちが、時には主人一家を馬鹿にした態度をとるやうになつている。
それにラネーフスカヤ自身、貴族階級出身ではあっても、貴族ではない弁護士と結婚し、そのうへ前述のような次第で、身持ちがいいとは言へないので、(たぶん、本家みたいな)伯爵夫人の伯母さんからは嫌はれてゐるといふ、言はば正式な貴族からは外れた存在なのだ。
性格は、よく言へば優しい好人物で、頼まれるとどんどん人に金をやつてしまふ。そのため(だけではないだらうが)、借金の抵当になつた桜の園を守る実務的な能力は、兄・ガーエフともども、全くない。これが第一幕から強調されてゐるので、「彼らは桜の園を守り通すことができるか」のサスペンスは半ば以上失はれてしまつてゐる。
ラネーフスカヤが桜の園を失ふのは、ただ世間知らずのためだけではない。別荘地として分割して貸し出せば、所有権を手放さなくてもすむ、といふロパーヒンの提案を二度に渡つて断るのは、「俗悪」だからだ、と言ふ。
桜の園がばらばらに解体されて、新興成金たちが我が物顔に(借地権はどの程度のものかわからないが、その範囲では「我が物」に違ひない)闊歩する、桜の木も木材として伐られるのにも耐えなければならない。さうなつたら、そこはもう何よりも貴重な桜の園などではない。わかつてゐないのは、財務状況にしか興味のないロパーヒンのはうなのだ。
と、正面から主張して議論を続けるなら、作品の対立軸は明確になり、価値あるものを守らうとして挫折する人間の悲劇として劇構造も安定する。ギリシャ悲劇も、イプセンの劇も、そのやうになつてゐる。
しかし、ラネーフスカヤはすぐに話を逸らしてしまふ。彼女は、理屈はわからず、感情のみで動く人物として最初から最後まで振る舞ふので、「全くどうしようもない」といふ印象しか残らない。
同じやうなことは、最終的に桜の園を買い取ることになるロパーヒンについても言へる。「新陳代謝の意味では、猛獣が必要」であり、「君の存在理由」(第二幕)は要するにそこにある、と、他人についてはやたらに鋭い見方を発揮する万年大学生のトロフィーモフに評される彼だが、最初から奪ふ者として登場するわけではない。
彼は農奴の子どもだつた時代に優しくしてくれたラネーフスカヤを心から慕い、なんとかして助けたいといふ善意に満ちてゐる。が、本当の意味でそれができる手段は持ち合はせてゐない。
かくてこの両者は決して噛み合はず、劇の中心はなんなのか、単純明快な筈なのに、ひどく曖昧な印象が残ることになる。
このやり方でチェーホフは、劇中から本当の悪人を取り除くことに成功した。
「三人姉妹」では、最初野暮な田舎娘として登場したナターシャが、三姉妹のただ一人の兄弟の妻となると、次第に家庭内の主導権を握り、姉妹を閉め出す。その過程が、そんなに目立つわけではないが、主筋ではある。彼女は市会議長と不貞を働いてゐる疑いが濃厚で、この男の手先として、女性が象徴する繊細で優美なものを押しのけて滅ぼす力の象徴になつてゐる。
これはチェーホフ劇では珍しいはうの例である。桜の園は繊細で優美なものの象徴には違ひないが、それを滅ぼすのは、個人の顔のない時代の流れとしか言ひやうがない。ガーエフやラネーフスカヤがもつとしつかりしてゐて、このときは桜の園を守り通せたとしても、二十年も経たないうちに革命によって失はれてしまつたらう。我々はそのことを知つてゐるのだから、所詮は空しい努力だとしか言へない。
最後に、喜劇につきもののはずの笑ひについてもう一度考へておかう。
第三幕、桜の園の競売の日だというのに、館では舞踏会が開かれる。このチグハグさは、まさに喜劇的だが、それで笑ふためには、競売場で無力を曝け出しているガーエフや、雰囲気に巻き込まれて(だらう)競売に参加することになり、勢いのままに桜の園を競り落とすことになつたロパーヒンの姿などを眼前に展開させる必要がある。
しかし、彼らが登場するのは、すべてが終わってからで、ラネーフスカヤは泣くことしか出来ず、他には、なんとかして母を慰めようとする娘のアーニャがいるばかり。とても笑へない。
もう一つ、最終幕(第四幕)で、せっかく機会を作ってもらったのに、ロパーヒンはどうしてワーリャ(ラネーフスカヤの養女で、桜の園の管理をしてゐる)に求婚しないのか。お互ひに思ひ合つてゐることは、第一幕から明らかにされてゐるといふのに。教養のないことへのコンプレックスから脱却できないので、金儲け以外のことには臆病になつてしまふのだ、といふ説明は一応つくが、それにしても。
ワーリャのほうでも、女性からプロポーズはできない、といふ当時の常識に縛られて、ただ泣くばかり。最後に、半ば無意識のうちに傘を振り上げるが、ロパーヒンがぎよつとすると、「わたし、そんなつもりぢやなかったのに」と言ひ訳をして、二人の関係は完全に終はる。
いつそ叩いてやればよかつた。そこからてんやわんやの滑稽な騒動が始まり、結婚という幸福な結末に至るのは、喜劇作家たちがよくやる手だ。それがないのは、思ひ切つた行動ができない平凡な者たちを描くといふ、悲劇とは正反対の方向に、針が振り切れている感じがある。
「絶望の虚妄なるは希望の虚妄なるにまさに同じ」といふ言葉が思ひ出される。チェーホフは、自分自身はちつぽけだし、世界に意味が見出せないからと、何も出来ずにゐる男を最も嫌つた。生きるとは、人と人の間で、何かをやり続けること以外ではない。もしそこに意味があるとしたら、その果てにしか見えてくることはないだらう。「ワーニャ伯父さん」や「三人姉妹」の女性たちが言ふ通りに。

「紙風船」 UPSつつじヶ丘アトリエ公演 平成19年
メインテキスト:川口一郎「二十六番館」(昭和7年。『川口一郎戯曲全集』白水社昭和47年より引用)
岸田國士「紙風船」(大正14年)
本年9月16日に、日本演出者協会関西ブロック主催「日本の戯曲研修セミナーin大阪202」に招かれて、川口一郎「二十六番館」について話をする機会がありました。
この戯曲は今では知る人も少なくなりましたが、戦前の日本戯曲の中で一番西洋演劇に近づいた作品だと思います。と、言うより、当セミナー中のディスカッションと俳優さん達のリーディング(朗読劇、最小の所作は含まれる)、それに三人の若手演出家による演出プランの発表、を通じて、そう確信するに至ったと言うべきでしょう。お招きいただきました演出家の山口浩章氏には、この場を借りて心からお礼申し上げます。
それともう一つ、研究者の端くれとして招かれて、一応レクチャーをすることになったので、考えてみて、ある問題に改めて直面する思いをしました。それは日本の近代劇の問題ですが、大きく言えば日本の近代の特質そのものに結びついているでしょう。
となると広大すぎる主題で、私は当日までまとめきることはできず、舌足らずで終わってしまいました。少し心残りなので、もう一度愚考を進めてみようと思います。日本で西洋風の劇を創る困難、を通じて日本の精神的な近代化の困難、その一側面を瞥見しようとする試みとして。
それでも一応、戯曲「二十六番館」のあらましを紹介しておく。
舞台は1927年のニューヨーク。ただし登場人物八人は全員日本人。二十六番館とは日系移民が住みついている安アパート(家主はユダヤ人)で、あと一ヶ月で取り壊される予定になっている。ここに住む、商売でけっこう成功した山下夫妻は、息子の良一の嫁にと、妻の姪の春子を日本から呼び寄せる。しかし渡米してきた春子は、長尾安二郎という現地の大学で勉強中の青年と懇ろになり、妊娠する。このため安二郎は、プロフェッサーになる夢を断念し、春子と結婚するが、この子は生後間もなく亡くなる。希望を失った安二郎は、自暴自棄な言動が目立つようになり、仕事も辞める。この夫婦も二十六番館に住んでいるので、春子は、新たな住居も探さなくてはならないという実際上の悩みと、安二郎がこうなったのは自分のせいだと思う自責の念の、双方から苦しめられている。
以上はいわゆる設定で、幕が上がる前にこれだけのことはすんでいる。
これだけでもある程度察することができると思うが、これはdisillusion(幻滅、幻想破壊)を中核とした劇なのだ。ギリシャ悲劇以来最もポピュラーなドラマツールギー(作劇術)の一つで、「かくあるべき自分」と「現にかくある自分」の落差でドラマが展開する。
例えばソフォクレス「オイディプス王」は、スフィンクスの呪いから都市国家テーバイを救った英雄王だと思われ、自分でもそう思っていた者が、実は父を殺して母を娶るという人間として最もやってはいけないことをやった人間だった。眼も眩むような激しい転落。
ただこれは、「運命の転変」ではない。厄災が外からやってくるわけではないからだ。主人公オイディプスは、幕が上がる前に、決定的な行為はすべて成し終えている。劇中で起きるのは、彼自身がそれを認識することだ。
アリストテレス「詩学」にあるように、アナグノリシス(認知)によってペリペティア(急展開)に至り、我々は主人公を通じて、「〈私〉とは何か」→「人間とは何か」という問いが立ち上がる場面に直面する。これこそ最も劇的な瞬間だ、と観じる感性が西欧では主流、とまで言えるかどうか、太い流れにはなっていて、そこで今我々も劇(ドラマ)とは例えばこういうものだと、漠然と考えている。
そこで、近代劇でもこのパターンはしばしば使われている。ヘンリック・イプセン「人形の家」(1879)のヒロインは、三人の子がいる主婦だが、自分と夫は理想的な夫婦だと信じている。正確には、不安を抱えつつ、信じようとしている。それが幻想だと分かった瞬間に彼女は家を出る。規模は全然違うとは言え、すべてが明らかになった末に放浪の旅に出るオイディプスと同じ道を辿るのだ。
ただ、こういうふうに、舞台上でアナグノリシス→ペリペティアが露骨に起きる劇は少ない。そんなことは現実にはめったにないからだ。だから劇になる、とも考えられるが、他方、「作り物(フィクション)」感はなるべく少ない方がいいという近代リアリズムからの要請もある。
そこで、例えば、アントン・チェホフの主人公達は、劇の開始時点でもう幻想から醒めかかっている。ただし、諦めきれないので、「人生とはもっと美しい、意義深いものだったはずだ」などと嘆いている。
それでどうなるのか? どうにもなりはしない。最初の頃の作品でこそ、主人公は自決したりして、自己の幻想に言わば復讐を遂げるのだが、「ワーニャ伯父さん」(1897)と「三人姉妹」(1900)では、彼ら/彼女らの境遇は劇が始まったときと終わるときで変わらず、皆幻滅の人生を歩み続ける。自分たちと悩みや苦しみにはどんな意味があるのか、神はご存じであって、そうであれば私たちにもやがて、多分死後に、分かるだろう、と言って。
一方、「二十六番館」の安二郎は次のように嘆く。
若々しい情熱も冷めちゃった。(微笑して)春ちゃん、お前じゃないが、お伽噺の世界だったね。[中略]僕は僕らしく生きる必要があるんだ。[中略]僕等はね、この大きな機械の、有ったって無くったって、全部の運転にゃあ、一向差し支えのない一部分なんだ。その癖僕等は、次第に、擦り減ってゆくんだ。
これはいかにもチェホフ的な科白であり、その影響は顕著である。ただチェホフ劇は田舎が舞台で、主人公たちは直接にはそこの味気ない単調さに苦しめられている。近代的な巨大都市の、絶えず動き続ける文明=経済機構(≒機械)の中で、自分たちは、いくらでも取り替えのきく部品でしかないと感じる者の悲哀は、今でこそありふれているようだが、「二十六番館」発表の時代ではかなり新しかったろう。
その違いはあっても、両者の劇の開始時点で、主人公達は幻想をほとんど失っていて、それを自覚もしていることは共通する。劇中で起きるのは、言わば最後のダメ押しのようなものである。
「それだって意味があるはずでは?」「意味ねえ……。いま雪が降っている。なんの意味があります?」(「三人姉妹」)。人生に究極的な意味などない。あっても、人間には見つからない。この苦い認識を抱えて生きていかなくてはならないのは、根本的な人間の条件だと思うが、具体的な現れ方は各々違う。
「二十六番館」の安二郎は、妻に未来の希望を語るのだが、一方で、本当はそれを信じておらず、手っ取り早く自分の人生に決着をつけようとしているように見えるところもある。それがはっきりせず、どっちつかずなのは、弱点と言えるかも知れない。最後の彼の死は、事故死なのか自殺なのか? 後者だとすれば、彼はチェホフ劇では「かもめ」のコスチャに似ている(後者の自殺も、私には唐突感が残る)。
好意的に見れば、これには作者は解答を出さず、上演に際して演出家や演者が自分で考え出す余地を敢えて残したのかも知れない。
ここではこれ以上この問題に深入りすることはやめて、なぜこのような幻滅の劇が日本ではあまり見かけないのか、それは日本の近代の特徴と関連しているのではないか、という見通しを辿りたい
ざっくり言って、日本人には「私とは何か」「人生の究極的な意味は」などとしつこく問いかける思想的な、心(精神)の習慣は、なくはなくても、乏しい。
それはいいことでもある。だいたい、こういうのは呪われた問いであって、いつでもどこでも誰でも納得できる一定の答えなどあり得ないのはもちろん、厳しく、妥協なく問い詰めようとしたら、そのこと自体で人間は不幸になるしかない。だからこの劇形式は日本語では悲劇と呼ばれる。いや、不幸になってもなお、「意味」や「真理」を求める試み自体に人間の偉大さがある、というのが西洋の思想的感性。そんなことは神様仏様にお任せして、微力な人間は、目の前の生活に一所懸命取り組もうというのが日本的な良識、と一応言えると思う。
しかし、明治以降、日本は開国して、西洋世界と付き合わねばならなくなった、というより、向こうの文明を目の当たりにしたら、戦争で勝てるはずがないことはいやでもわかってしまったから、その点では西洋化するしかなかった。それは西洋文明の地球全体に渡る進展に巻き込まれた、ということを意味する。
そこで日本は、驚くべき能力を発揮して、アジアの中で随一の進歩を成し遂げた。もちろん、表面的には。あまり人間の内面の、精神などには拘らないで、目に見えるものに懸命になる日本的現実主義がこの場合功を奏した可能性が高い。
とは言え、表面の底にはそれを支える深層がある。機械ならともかく、資本主義経済や議会制民主主義のような制度は、人間が直接運営するので、精神の部分は関係ない、というわけにはいかない。日本人はそれも学んだ。実用とは離れた思想問題でも、例えば朝永三十郎『近世における「我」の自覚史』(1916)というような研究書も出ている。
だから、「(男女を問わず)個人の人格」の大切さも、理屈としては、わからないことはない。しかしそれを、たとえ外国語が出来るインテリの家庭であっても、実際の生活の中に浸透させるとなると、そう簡単にはいかない。そして劇は、特にリアリズムの演劇は、日常の振る舞いに基礎を置いて創られるものだ。
日本の普通の主婦が、夫に向かって、「あなたは私をペットのように可愛がるだけで、一人の人間として見てくれなかった」などと実際に言ったとすれば? 少なくとも戦前なら、何かのパロディにしか見えなかったのではないだろうか。「板につかない」絵空事に過ぎない、と。絵空事には絵空事の需要があるが、そんなに高いわけはない。供給側でも、翻訳劇をやればよしとして、戯曲の段階から新たに創っていこうなどとは滅多に思わないのが当然なのである。
因みに「人形の家」の文芸協会による初演は明治44(1911)年、同年にはたまたま平塚らいてう主幹の『青鞜』も発刊されていて、最初期のフェミニズム(女性参政権運動)が開花した年でもある。そのためかどうか、「人形の家」は女性解放を訴える劇とされ、今日までそのレッテルが貼り付けられている。一人の女性の、家庭での悲劇と見られることはほとんどない。また因みに、この時期、女権に目覚めた、今で言う「意識高い系」の女性をからかう劇も、いくつか出ている。
こういう点で、演劇は、社会の真の姿を映し出す鏡になり得る。などと言うと、抽象的な話の常として、どんな根拠や感覚に基づいてどんなことを言おうと、曖昧なところは残るし、逆に、どんなに曖昧でも、それなり(かな?)のことは言えそうにも思える。それは承知の上で、演劇に即して、別の視点を取り上げてみよう。
近代日本の産み出した階層と言えば、なんと言っても給与生活者、即ちサラリーマンである。
江戸時代には農民が全人口の八割以上を占めていた。それが、厚生労働省の資料によると、大正期の1920年代で、第一次産業は産業別就業人口の六割を割り、第二次産業で20%、第三次産業がそれより少し多くて、合わせると五割近くを占めている。第二次産業の代表は工場労働者、第三次は広い意味のサービス業で、ものを売る仕事、の違いはあっても、会社勤めの点では共通している。そして大企業の多くが東京・大阪などの大都市にあるので、地方からの流入者も急速に増えた。
これには農村から見ても有利な点があった。戦前の日本は基本的に長子相続で、土地を含めた全財産を長男が相続する。すると次男、三男は、他家に養子に出るか、さもなければ生活の基盤からして新たに築かねばならない。そこで、経済的に余裕のある家庭はそういう子を旧制中学校まで進学させ、いわゆるホワイトカラーの事務や営業職に就ける。そうでなければブルーカラーの労働者、当時の言葉では職工となる。これがさらに亢進して、農村の過疎化を招くのは戦後のこと。
さて、このようにして急速に、多数発生したサラリーマンたちこそ、日本の近代化を根底で支えた存在であることにまちがいはない。しかし特に、前者のホワイトカラーを描いた文芸作品は、この時代、ほとんど見当たらない。私が知らないだけの場合には、ご存じの方のご教導をお願いしたい。
後者の、工場労働者なら、小林多喜二や德永直のプロレタリア文学に登場するが、それはもちろん社会主義リアリズムの実践例としてである。後にプチブル(←プチ・ブルジョワジー。多少の知識と事務能力で資本家に仕え、革命を阻害する愚か者たち、ぐらいのニュアンス)と呼ばれて蔑まれた階層は、洟もひっかけられない感じなのだ。
超例外としてある岸田國士の初期の戯曲を見ると、その理由がなんとなくわかる。四作目の「紙風船」は、当時としては郊外の(現在の京王線沿線あたりだろう)、たぶん貸家に住む結婚一年後の若夫婦を描いている。
倦怠期にしては少し早すぎるようだが、たまの日曜日、彼らにはやることがない。「散歩か」「散歩でもなんでも……」。彼らは、生活にも、お互いにも、これと言って具体的な不満はない。なんとも言いようがない落ち着かない感じがあるだけ。
お前が、さうして、おれのそばで、黙つて編物をしてゐる。お前は一体、それで満足なのか。そんな筈はない。おれの留守中に、お前は、どこか部屋の隅つこで、たつた一人、ぼんやり考へ込んでゐるやうなことがあるだらう。おれは外にゐて、お前のその淋しさうな姿を、いくども頭に描いて見る。百円足らずの金を、毎月、如何にして盛大に使ふか、さういふことにしか興味のないおれたちの生活が、つくづくいやになりやしないか。今更そんなことを云つてもしかたがないと諦めてゐるかも知れない。しかし、お前は決して理想のない女ぢやないからね。おれは、今のお前がどんなことを考へてゐるか、それが知りたいんだ。かういふ生活を続けて行くうちに、おれたちはどうなるかつていふことだらう。違ふか。それとも、お前が、娘時代に描いてゐた夢を、もう一度繰り返して見てゐるのか。
これはいくぶんかチェホフ風の科白だが、もっとずっと漠然としている。それは岸田劇の主人公たちの階層が一段低いことに関係する。チェホフ劇の主人公達は、皆けっこう金持ちで、働かなくても食っていけるブルジョワだった。対して、こちらはプチブル。何より、学歴と会社での地位以外には資産がない。
彼らは、田舎の土地と、現在でも消えたわけではない煩わしい地縁血縁から逃れ、自由を手にしている。どこへ行ってもいいし、いなくてもかまわない。よく考えると、人間は元来は、皆そうなのかも知れないが、故郷で、どこそこの家の誰それという、何世代かにわたってその場に住みついた一族の一部となると、その存在の、共同幻想中の重みは、格段に違う。そのしがらみの重しから外に出たからこそ、自由な個人となった。
しかし、この個人のなんという頼りなさ。自立しようにも、どこに軸足を置けばいいのだろう? 教養か?
女性について言えば、勤め人として、学歴が高くなった男の伴侶となるべく、女学校進学者の数も増えた。そこで学んだ「理想」や「夢」とはなんだろうか? 百円ぐらいの金(ざっと現在の六、七万円に当たるだろうか。生活費を差し引いた若いサラリーマン家庭の、いわゆる可処分所得は今でもそんなものだろう)でどうなるものではないことは明らかだが、では?
社会的にはもう一つ、ここで、専業主婦が大量に発生したことは注目される。農家を初めとする第一次産業の家庭では、嫁さんも、手伝いという形であれ、労働に携わるのが当り前だった。これは商家でもそうだろう。家事労働しかしない主婦は、人口の5,6パーセントを占める武家階級にしかいなかった。
それで、サラリーマンは江戸時代の武士の末裔である、という人もいる。その最大のエートス(実生活上の倫理)は、かつては主家(藩)に対する忠節だったものが、その対象が会社に変わったのだ、と。これはある程度当たっているかも知れないが、するとここにも個人が生きる余地はないことになる。
「紙風船」の家庭は夫婦二人きりで、戦後の「核家族」に似ている。専業主婦は家を守るのだ、と言っても、目下その家には舅姑も、子どももおらず、第一大半が、貸家の仮住まいなのだ。
そういう家には、ひいては、そこで暮らしている自分たちには、なんの意味があるのだろう。夫婦二人で一日中顔を合わせていると、ふと、そのような呪われた問いが立ち上がることがある。「あたし、日曜がおそろしいの」「おれもおそろしい」。ここに、意識と現実の乖離から来る、幻滅は認められる。しかし、一見してあまりに些細なので、これを文芸で、特に劇で表現しようとする試みは滅多にない、ということである。
「二十六番館」の価値を最初に認め、演出まで務めたのが、この岸田國士だった。
舞台は紐育だが、人物は悉くわが移民の群である。そこには、「根こそぎにされたもの」の姿が、特殊な雰囲気のうちにそれぞれ面白く描き出され、諧調に富む心理的リズムが、この無装飾に近い「ビルディングの物語」を、切々たる「生活の詩」ともいふべきものにしてゐる。(「川口一郎君の『二十六番館』」昭和7年)
アメリカへの移民となると、日本の共同体から完全に離れた「根こそぎにされたもの」(デラシネLes déracinés。元来はフランスの右翼作家モーリス・バレスの言葉で、もちろん悪い意味)であって、その自由な気楽さは譬えようもない。
「こんな暮らしいいところはないじゃないか。〈中略〉毛唐のうちへ奉公すりゃあ、こづかいぐらいはすぐ出来る。あきたらやめる。困ったら、また働くさ」。これを言う登場人物は寡婦である。男はなかなかこの心境には留まれない。地縁血縁はほぼ全く関係ないが、この地にはまた別のエートスがある。いわゆるアメリカン・ドリーム、社会的な成功がすべて、という。
この戯曲には四人の男が登場する。一人は、一応成功して小金を貯めたが、いまだにアメリカ風に馴染めず、日本へ帰りたがっている。その息子はかなり軽い性格だが、その分迷いなく金儲けに邁進しようとする。もう一人は、生業につかぬ一種の無頼漢で、「おれの生活には何かしら、不足なものがある」と不安を抱いている。
最後の一人が前述の安二郎で、夢破れた後の自分をどう扱ったらいいかわからない様子でいる。妻の春子は新たに妊娠したことを彼には言えずにいたが、安二郎もそれを知っていて、親子三人の家族で「根気よく始めるか」と言う。
しかし一方、彼が「普通の生活」を恐れていたことは、春子の科白でわかる。「その落ち着いた生活って言うのを、安二郎さんはひどく気にするの。[中略]結婚生活の破綻というのも、そんなところから起こってくるんですって」。これに前述の「僕は僕らしく生きる必要があるんだ」という当人の科白。彼にとって、家族と根気よく暮らしていくなど、およそ身の丈に合わず、一旦は春子のために妥協しようかとも考えたが、最後にはそれは無意味だ、という思いを克服できなかったのかも知れない。
このようなプチブル、は差別語なので、小市民と言ったほうがいいだろうが、その悲劇を描いた作品として「二十六番館」は先駆的な作品と言えるのではないだろうか。アーサー・ミラー「セールスマンの死」は、第二次世界大戦後の1949年の作だ。
そう言えば、大学を辞めた後の安二郎は、重いサンプル・ケースを抱えてあちこち歩く仕事をしていたというのだから、セールスマンだったのだろう。「人生に固い地盤はなく〈中略〉靴をぴかぴかに磨き、にこにこ笑いながら、はるか向こうの青空に、ふわふわ浮いている人間」だからこそ、「夢に生きる」者。最後に奇妙な、曖昧な死を遂げるところまで、ウィリー・ローマンと安二郎は共通する。
さて、以上を踏まえて、またもう少し時間をかけて、近代日本で最も意識的な劇作家・別役実の小市民劇について考えてみたいと思います。

上原正三画 赤い烏の居る風景 昭和41年
メインテキスト:『別役実戯曲集 マッチ売りの少女/象』(三一書房昭和44年)
別役実『言葉への戦術』(烏書房昭和48年)
Ⅳ さりげなく過ごすこと
雨が降つてゐる
いろいろなものをぬらしてゆくらしい
かうしてうつむいてすわつてゐると
雨といふものがめのまへへあらわれて
おまへはさう悪いものではないといつてくれさうなきがしてくる
八木重吉の詩「雨」。「赤い鳥の居る風景」の主人公〈女〉のモノローグ中にそっと引用され語られたとき、強い印象が残り、忘れられなくなった。その時の私は、尾形龜之助同様八木重吉も、名前を知っている程度で、別役実が「八木重吉氏について」(初出は昭和42年企画66「赤い鳥の居る風景」初演時のパンフレット。『言葉への戦術』所収)で種明かしをしてくれているのを読むまでは、この詩自体を知らなかった。
八木には他にも「雨」という題の詩があり、こちらのほうが比較的よく知られているようだ。
雨のおとがきこえる
雨がふつてゐるのだ
あのおとのやうにそつと世のためにはたらいてゐよう
あめがあがるやうにしづかに死んでゆかう
別役は、八木重吉は不気味だ、という。そう言われれば、確かに。この祈りの真摯さは疑うべくもない。しかし、それはどこへ向うのか。まっすぐに、天へ? そうだとしたら、それがわかっているなら、どうして詩人は「うつむいてすわつて」いなければならなかったのか。「おまへはさう悪いものではない」と言ってくれる「雨といふもの」をなぜ希求しなければならなかったのか。
彼岸のことは知らない、人と人の間のこの世では、特にこの日本という風土では、どこかに具合良く収まるためには、彼の一見静謐な祈りの背後の情念は強すぎる、とは言えそうだ。そのため、まるで宙に浮いた風船のようにふわふわと、行き着く先もなく淋しく漂っている。そんな印象になる。
そのような自我、別役の用語を使えばタマシイ、のために文学がある。それが証拠に八木重吉も、純一な信仰生活の傍ら、詩を遺した。それはそれとして、「特にこの日本という風土では」の部分にこだわってみたい。
初演の二年後、劇団青俳によって「赤い鳥の居る風景」が再演された時の上演パンフレット中の一文「イーハトーブ伝説について」では、日本におけるゲゼルフシャフト(堺屋太一の訳語だと、機能体的組織)の成立し難さが語られている。この一文は宮澤賢治論としても示唆的だが、賢治は私にとって別役実と同じくらい巨大な存在なので、ついでのように論評する気にはなれない。その他の部分を紹介しよう。
「日本の精神構造に、「家」の概念はあっても「街」の概念はない事、つまり「自然村」の概念があって「自由都市」の概念のない事、これはこれまで多くの社会科学者が指摘してきた」。例えば大塚久雄はゲマインシャフト(自然共同体)・ゲゼルフシャフトなる概念を戦後日本で流行らせた一人だが、彼は日本の庶民に自由で自律的な個人の意識が乏しいことを問題視していた。そのような個人同士が約束(契約)して作った社会なら、無謀な戦争に全員がなすところなく巻き込まれる、なんてことはなかったはずだ、と。
これを要するに、近代人の観点からして日本人はオクレている、見倣うべきお手本は海外の先進国にあり、ということで、それなら、知識人の役割は、日本の哀れな一般民衆の啓蒙・善導にある、という、まことに脳天気な結論になる。
そう言われたくないなら、最低でも次の二点にはきちんと目配せすべきだろう。第一に、近代的個人なる観念は、観念としてなら確かに西洋にはあるようだが、実際に社会で呼吸して動き回っているものかどうか。第二に、実態はもちろん観念としてもそんな個人が根付かない日本的風土とはなんなのか。オクレている、とだけ言って済まされるような問題ではないはずだ。
最も簡単に言うと、「私は私である。私は私以外の何者でのない」と言い得る「個人の観念」、もっと言えば「個人の物語(フィクション)」はあることにしよう、とする社会的合意が、西洋の、知識階層にはあり、書物に書かれているので、日本の知識階級はそれを学んだ。けれども、現実の生活の場で、社会的合意を結ぶことはもちろん、それがあるべきなんだと主張することも、容易ではない。
劇の例だと、本当の人間同士の結びつきはどうあるべきか、家庭内で、一見、堂々と主張する女性が、西洋近代劇の劈頭に登場した。これについてはずいぶん前に紹介したが、このヒロイン・ノラは、女性の地位云々の社会的な理念より、ずっと個人的なロマンスを夢見て生きている。それでも、「夢見る権利」は当然のこととして要求する・個人の資格でそうする、ことはまちがいない。それと彼女が一介の主婦であることは矛盾せず、少なくとも舞台上のリアリティは損なわれない。【とはいえ、彼女の末路はたぶん悲惨なものになりそうなのは、予想できる。それを含めてのリアリティなのだ。】
日本ではこれは非常に難しい。なぜか。別役実は、次のように考えた。「日本の精神風土を村落共同体から都市共同体へ移行させたものは「(近代的)国家」の理念であって如何なる「自我」の自発的な衝動でもなかったのである。ただ「自我」は、既に無理やりに都市化されてしまった状況下で、被害者的に目覚めたに過ぎなかったのだ」(「イーハトーブ伝説について」『言葉への戦略』所収)
これも以前にあげた夏目漱石の言葉だと、日本の近代は「外発的」であった、ということに重なる。諸外国、特に欧米列強と伍してやっていくためには、政治・産業・軍事のすべてをあちらふうにしていく必要が感じられたからそうしたのであって、個々人内部の欲求は問題ではなかったのだ、と。
それでもなんでも、外面的な近代化は成し遂げられた。それも、アジア諸国の中では珍しいぐらい、うまく。ここで「自我」なるものはなんらかの役にたったのか? 答えはどうもノーらしい。ただしかし、身分制は撤廃されたし、政治家は(制限つきだが)選挙で選ばれるようになった。理念としては個人を前提としているはず、というところで、個人意識=自我は言わば後付けで目覚めることになった。
近代化によって学校に通う期間が長くなり、直接生産には関わらず、宙ぶらりんの状態で、余計なことを考える時間が一般的に増えたことも、この事情に大きく与っている。この土台の上に、「反抗する若者像」が誕生した。
さらに、自我が「被害者的に目覚めた」とは次のようなことである。とにもかくにも近代社会であるなら、個我が生きる道はあるはず、と思ってみても、家の内部にも外部=社会にも具体的には見つからない、という発見によって、反対側に、そのように発見するものとしての、自我が発見された。言い方はややこしいが、自然主義文学の作家たち、田山花袋や島崎藤村が描いた自己とは、そんなものだった。
そこに流れる最も大きな感情は、詠嘆としか言い様がない。苦悩、という言葉もよく見かけるけれど、個人が反抗して、現実の壁にぶつかって、苦しむ、という形のものはほとんどない。そのようなドラマはこの日本では、どうもリアリティを持ち得ない。個人は反抗以前に、無力な自分に絶望し、嘆くだけ。
もっと積極的に社会の現実を変えようとする人物は、後にマルクス主義によって登場した。しかしこれも、個人を生かそうとするものではなかった。むしろ個人には、唯物史観の、革命の正義のために、その他すべてを犠牲にすることを要求する。戦前、彼らは弾圧され、紛れもなく「被害者」になったが、それが即ち彼らが「正しい」証とされた。
被害者ではない自己は、どこまでも置き去りにされる運命だったのだ。西洋でも同じような実態はあるだろう。しかし日本では、個人を物語るはずの近代文学ですらそこを超えられなかったところが、精神的に大きな問題なのだ。
別役実は本シリーズその1で述べたように、「体制が圧制的なら私は反逆的である」というような「私」の成立を「安易な公式」とみなした。この時別役は学生運動(その多くが戦前のプロレタリア運動の意識と方法論を引きずっていた)から離脱し、文学的な出発を遂げたのだろう。
「マッチ売りの少女」と「象」では、広い意味の戦争被害者が、心の傷の置き場が見出せないままジタバタする有様を描いた。それは、戦争中の現実なんて忘れ、置き去りにすることによって復興を遂げた「市民社会」の欺瞞を告発するものともみなされた。しかしこのテーマは、もっと深く掘り下げることができる。
特に悲惨な体験をしたわけではなく、従って「被害者」とは言えないのに、なぜか、社会との折り合いをつけられない者たち。「甘えているだけだ」と言えば言えるが、それだけに、彼らの内面を思い遣り、文字上なり舞台上で可視化することは難しい。「ひきこもり」とか「ニート」などの言葉が一般化した現在でも、そうだ。「赤い鳥の居る風景」は、小此木啓吾の「モラトリアム人間」などの言葉もまだなく、若者と言えば、反抗する学生たちが典型のように感じられていた昭和42年の段階で、そのような、ある意味で地味な、精神の危機を描いた。
この劇は、全六場で構成されているが、一~三場と四~六場で明確に二つの部分に分かれており、実質的に現在の英米演劇の主流である二幕ものになっている。別役実が影響を受けたと言うアーサー・ミラー「セールスマンの死」も二幕で、前半(第一幕)で緊張をはらむ展開のうちに周到に伏線をはりめぐらし、後半(第二幕)の最初に一気にカタストロフにもっていく手法は、ここから学んだと思しい。しかし、主人公は、ウィリー・ローマンを原型とする漂泊者ではなく、それを言わば受け止める側である。
こちらの「側」は「市民」と呼ばれる。かつてのマルクス主義に基づいたプロレタリア文学や社会主義リアリズム演劇には、「小市民(プチブル←プチブルジョワジー)」なる差別語があった。大ブルジョワから抑圧され差別される存在でありながら、僅かばかりの所得・財産への未練が捨てられず、革命を邪魔する立場になる、どうしようもない愚物、というような意味だ。
周知のように、日本では、高度経済成長の結果、そもそも「革命」を理想とする観念形態(イデオロギー)がどんどん色褪せていった。昭和50年代には国民の九割が中流意識を持つようになったと言われ、そうなるとブルジョワもプチブルも革命家も、社会のどこに位置づけられるのか、さっぱりわからなくなったのだ。
この「一億総中流」自体もまた、バブル期を経て雲散霧消してしまった、というのが別役の見方である。ここには「生活感覚」はあっても、相変わらず「哲学」はないところが最大の脆さであったかも知れない。それをも含めて、彼は、「この小市民の台頭と没落の過程に、昭和という時代の、最も大きなドラマを感じ取」(『東京放浪記』平凡社平成25年P.217)り、これを劇作の大きな柱にしていく。
「赤い鳥の居る風景」はその第一作になる。別役劇で初めて、前述のように「市民の側の論理」が正面から描かれたからだ。幼い娘の屈辱的な体験を、「忘れることだ」としか言えない「マッチ売りの少女」の初老の夫婦にも、原爆被害者である「象」の主人公の情念を、逸らし、無視する、舞台には登場しない「社会」を構成する大多数にも、それなりの理由はある。それを考慮しない「糾弾」は、方向が変わった弾圧であるしかない。
もちろん、劇として、「大多数」を描くのは難しい。そこには危機(crisis=分かれ道)が、目につくような形では、ないから。別役はそこで、この論理によって破れ、傷つきながら、最後に敢えてそちらを選ぶ者をヒロインに据えた。これだけが、自分が「小市民を肯定的に扱った作品」(同上)だと彼が言うのは、そういう意味である。
幕が上がると、葬儀の場面。参列者は傘をさしていて、「セールスマンの死」の最後の場面を引き継いでいることが、さりげなく暗示されている。
亡くなったのは、「模範的にして平凡な市民」である廃品回収業吉田幸三郎氏と令夫人芳子さん。彼らはまだ若い盲の娘(〈女〉と表記される)とその弟を遺して自殺したのだが、書き置きも遺言もなく、なぜ死を選んだのか、誰にもわからない。そこへ誰も知らない〈旅行者〉が現れ、故人にお金を貸したのだと言う。ほんの僅かの、言うにも足りないほどの額であり、何も請求に来たというわけではないのだが、と。
次に「この町と、これを取りまく七つの町の代表によって」結成された委員会から派遣された〈男〉が登場して、〈旅行者〉を連行する。今のところ、吉田夫妻に関してわかっていないことはほとんどなく、しかし自殺の理由は不明。ただ、借金の話は初耳だったので、調べなければならない。「人は原因なしに死んではならない。それが委員会の思想」だから、と。〈女〉は、以前旅行者が家に訪ねてきたのを思い出す。
第二場は〈女〉の回想シーン。ある晩、一家四人は食卓についていた。そこへ、遅れて、父の古い知人だという〈旅行者〉が訪ねてくる。彼には家族がなく、各地の「お友達」の家を巡り歩いている。いつもひとりぼっちだから「久し振りにこうしてやさしい人たちに囲まれて、胸がいっぱいなのです」。一番怖いのは、そのお友達がお友達でなくなっていることだ。「つまり、私が扉を開ける。こんばんは、みなさん。ところが、みんなみんな向こうを向いて、振り向かない。シンとしている」。
以上で彼がウィリー・ローマンの、そして「マッチ売りの少女」の〈女〉の、「象」の〈病人〉の後継者であることは明らかだ。少し違うのは、このような立場自体に妙に意識的なのだが、そうなる理由はわからないところだ。彼は、一人の「お友達」から別のへと、ピンポン玉のように弾かれて生きている。それは、「まるでちょっとしたバクチです」と言う。どうして一つの場所にゆっくりしていないのか? あきられるからだ。「私はあきられる前に旅立つのです」。
彼はすっかりすねてしまっていて、人の表情に浮かぶちょっとした不快感にも敏感に反応する、そういうところがますます嫌われる。〈旅行者〉はそんなドツボに嵌まっているのだ。この夜も、〈父〉(吉田氏)がふと席を立とうとしたのを見逃さない。「あなたは今、私をケイベツしましたよ」と。〈父〉はこの難詰をそらさず、まっすぐに答える。「君の云う通りだよ。私はお手洗いに行く必要なんかなかったのさ。ちょっとムッとしてね。つまらないことさ」
市民の論理はこのようにさりげなく舞台に現れた。中身は、忘れることだ、という「マッチ売りの少女」の夫婦と同質ではあるが、それをはっきりと主張し、さらにそれをも「つまらないこと」のうちに含める。まるで、何かにこだわることが、「何かをするってこと」自体が悪い、とでもいうように。因みに、「象」でこう言った人物は原爆被爆者というれっきとした被害者であって、平凡な市民ではない。
なぜそうなのか、と〈旅行者〉は疑わずにはいられない。その穏やかな日々の底に流れているものは何か、自分はそこから疎外されているという思いを捨てられないから。そういう自意識を持ってしまったから。
第三場で時は元にもどる。委員会の調査で、〈旅行者〉は高利貸しだったことがわかる。吉田夫婦にも多額の金を貸していた。夫婦はそれを苦にして自殺したのだと推測され、彼はこの町とそれを囲む七つの町から追放される。立ち去る前に、なぜ自分がそうなったのか、〈女〉に語る。既に「ずっと昔に、私は追放を受けているのです」と。
小学校へ上がったばっかりと云っていいかもしれない。その頃私は、どんなふうにみんなと、遊んだり、ケンカをしたりしていいのかわからなかった。私が努力すればするほど、みんなから離れるのです。私には友達がいませんでした。その事で私は、みんなに非難されました。私の両親も、その頃は健在でしたが、その事で私を叱りました。少し大きくなって、あれは中学の頃かもしれません。ちょっとした事で私は、人にお金を融通しました。ごくささいなお金です。でも、その人は返してくれなかったのです。私は、返してもらうために何度か、その人の家へ通いました。私にはどうしても必要なお金だったからです。とうとうそれは返してもらえませんでしたが、その家に通ううちに、私には、そういうやり方での交際ということを知ったのです。
「正常なつきあい、人間と人間との、愛と憎しみの関係」を「とりもどすために」と〈旅行者〉は言うのだが、これはおかしい。「つきあい」も「関係」も、彼には最初からなかったのではないか。社会が悪いわけでも、たぶん、家庭のせいでもない、だから、何かを要求するわけにもいかない。ただ、金銭の貸借関係になれば、公的(?)に、他人に要求はできる。とんでもない勘違いとしか言い様がないが、他には何もできなかった。
おそらく、こんな自己を入れる容器=物語は日本同様西洋にもない。ただ日本だと、「そんなに我を張ってはいけない」とする意識は、西洋よりも強いのだろう。それだけ、突出した個人には馴染みがないのだ。
この述懐の後で、〈旅行者〉は〈女〉に結婚を申し込む。そうすれば〈女〉は委員会が肩代わりした借金を返さなくてもすみ、〈旅行者〉は、彼女の町の住民になれる。「住むということは、住みつくということは、とてつもなくどぎついことに違いない。利息を一分一分上げてゆくように、一日一日をくらしてゆく」のだ、と彼は言う。
〈女〉は、「父と母は、私と弟に、盲の私とまだおさない弟に借金を負わすために死んだ」ことがわかった、だから誰の力も借りずに返していくことが本望のはずだ、と言ってこの申込みを断る。
第四場から姉弟の新しい生活が始まる。〈女〉は編み物をし、〈弟〉は、〈女〉の決意を「えらい」と言う町の人々の好意で、会社勤めを始める。
しかし物事はすぐにうまくいかなくなる。〈弟〉は理由もなく脅え初め、会社を休み、町中を走り回る。「僕はこんなに苦しんでいるんだから、そのうちにきっと救われるだろって」、しかしそれはやっぱり「虫の良い話」に過ぎないことはわかっていたので、止まれず、倒れ、自分で立ち上がったのだが、それを見ていた不良の〈若い女〉に助けを求める。
助ける、とは、どんなふうに? 彼は「ウスノロ」だから、不良にはなれない。でも、ついてきたければ来るといいわ。〈女〉の前でそう言われたので、〈女〉は〈弟〉に、選ぶように言う。「つらいほうを選びなさい」と。「逃げてはいけないわ。どっちへ行けば逃げることになるのか私にもわからない。でも……」。〈弟〉は、会社に戻る、と言う。「逃げたりはしない。今度こそやるよ」と。そこへ警官が来て、〈弟〉が盗みを働いて、追いかけてきた男を刺したことを告げる。
第五場。刑務所(だろう。そこはリアルに描かないのは、「不条理劇」の特権)で、〈女〉は〈弟〉を激しく追い込もうとする。
〈弟〉はくたびれていた。公園のベンチで、男がいきなり立ち上がった。鞄を取って、走った。追いかけてきた。振り向いた。許してもらえるかと思って。殴られた。刺した。カッとしたのではない。ただ怖かった。
彼は自分のやることの意味はわからず、やった後でもわからない。許される? 救われる? それは、甘えというよりは空想でしかない。そうではなく、人と人との間で「現実に」生きる自分というものは、〈弟〉にはどうしても見つけられない。
でも、本当はみんながそうだ。みんな怖いのだ、と〈女〉は言う。父も母も怖かった、そしてそれに耐えていた。自分もまた……。「決心しなければいけませんよ。あなたは、刑務所でしばらく生活して、それから、今云った人たちのもとへ帰ってくるのです。それがあなたの借金なのです」。
「今云った人たち」とは、父母の葬儀にも参列した町の人々だが、〈弟〉を待たず、事態をよりいっそう悪い方へと動かす。彼を「可哀そうだ」と感じて、減刑運動を始めるのだ。まだ若い子が、ひねくれてしまわぬように、思いやりが必要だ。姉は目が不自由なのだから、署名を取りに歩かせれば効果的だろう、ついでにお金も集めればよい……。
「世間」がこんな具合なのでは、〈弟〉は自分を作っていくことはできないだろう。抵抗のない水の中では泳ぐことができないように。彼はもっと追い込まれる必要がある。〈女〉は〈弟〉を逃がす決心をする。
第六場。【この冒頭で、〈女〉が、最初に紹介した八木重吉の詩を呟く。】脱走の企てを辞めさせようとする町の人々を、〈女〉は懸命に説得する。
私には、みなさんの今の思いやりがとても良くわかります。でも、あの子には、恐らくわかっていません。あの子は、どこまでもその思いやりに支えられようとするでしょうし、そうなったら当然、町の人たちは戸惑うでしょう。そのすき間の中で、また何かが起こるのです。私にはそれが恐ろしい。あの子が泣けば泣くほど、町の人たちは泣けなくなります。そしてそのすき間は大きくなります。私はいつも、そのすき間の中で息を殺しております。どうしていいかわからないのです。私はあの子にその事を教えてやらなければなりません。お父様とお母様がそうであったように、つつましく、重々しく、厳粛に生活することを教えてあげなくてはいけないのです。
あの〈旅行者〉はやはりまちがっていた。「住みつく」とは、利子を一分一分上げていくように、人間同士の緊張感を次第に高めていって、存在の手応えをつかむことではない。借金を少しづつ返していくように、つきすぎもせず離れすぎもしない微妙な距離を、他者との間に保つことだ。そのためにこそ、勇気が要る。「あの子の中に、盗む勇気と壊す勇気と火をつける勇気ができた時、あの子にとって、盗まないで、壊さないで、火をつけないで、しかも逃げないで生活することが、大切になるはずです」。
勇気。耐える勇気。何に耐えるのか。「自己」の無意味さに。そう言っては身も蓋もないが、とりあえず、他人に、自己が自己であることの確認を求めても無駄だ。いやそれは、最大の不躾というものだ。誰もそんなことをするだけの義理もなければ力もないのだから。あるときふと、目の前に「雨のようなもの」が現れて、雨のようにそっと何かを囁いてくれるのを待つより他に、人間にできることはない。この頼りなさ、寂しさに耐えること。それができて初めて、人は、人と人の間で生きて行くことができる。これが、特にこの日本の、市民社会とやらの逆説なのである。
最後に、脱走した〈弟〉は、なんとか〈女〉のもとにたどりつくが、後から撃たれていて、落命する。「何故、正面からうたなかったのかしら……。この子は、どんなふうにして死んでいいのかもわからなかったに違いないわ。ただ、走っただけよ。私たちの中へ……」
すべてが去り、一人残された〈女〉が、市民として生きて行く決意を語る。「私、きっとつつましいしとやかな女の人に見えてよ。お買物の途中でどこかの奥さまにお会いしたら、私、少しわらって、おじぎをするわ。こんばんは、奥様、いやな雨でございますわねえ……」。激しい葛藤を経た後の諦念とともに幻視される「街」。我々はそれを見るのではなく、感じるべきなのであり、だからこそこのヒロインは盲目と設定されているのだろう(実際、盲人としての特徴は劇中ほとんど書き込まれていない)。二十世紀に初めて現れた日本型小市民、それを描く劇は、このようにして創始された。
【上原正三は別役実の中学校時代の美術教師で、「赤い烏の居る風景」はその代表作。別役実はこの「カラス」を「トリ」と読み違えたまま、戯曲のタイトルとした(『別冊新評 別役実の世界』新評社昭和55年)。その寓意は、「不燃焼の「自我」が他者と対した時、意識の底辺をチラチラかすめ飛ぶ赤い危険信号」(「イーハトーブ伝説について」)だとのこと。】
 眞鍋卓嗣演出「象」ボリショイドラマ劇場2018年
眞鍋卓嗣演出「象」ボリショイドラマ劇場2018年メインテキスト:『別役実戯曲集 マッチ売りの少女/象』(三一書房昭和44年)
Ⅲ ジタバタすること/しないこと
「象」には三人の被爆者が登場する。
〈病人〉とその甥らしき〈男〉と、彼らが入院している病院の〈看護婦〉。対話、というより多くの場合むしろモノローグの交錯、は主に前二者の間で交わされる。
他の登場人物をざっと紹介すると、
〈病人〉の〈妻〉。太りすぎが怖ろしくて家で一人で泣いていると〈病人〉からは言われ、台所わきの部屋で電気をつけずに寝ていたと〈男〉には言われる。このように語られる範囲での彼女の人物像は、別役実の発表された最初の戯曲「AとBと一人の女」中の、登場しない〈一人の女〉を思わせる。第二幕(「象」は全三幕)で〈病人〉との関係が耐えられず、実家に帰ってしまう。
〈医者〉。インターホーンで〈病人〉たちの話を盗み聞きしているらしい。「打ちとけて話をしてみようじゃないか」などと言って、〈病人〉に敵意を持たれる。
〈通行人1〉。なぜか〈妻〉に近づいて、手伝いを申し出る。他に、第二幕の全く独立したエピソード中で、〈通行人2〉を無理やり「決闘」に引き込んで、殴り殺してしまう。
以上のメンバーが〈病人〉を取り巻く不安定な世界を構成する。
舞台にはまずコーモリ傘を持った〈男〉が登場し、詩的な隠喩に満ちた長いプロロゴス(序詞)を語る。こういう部分の科白は戯曲では詩のように分かち書きされている。
「みんさん、こんばんは。/私は、いわばお月様です」「あるいは……。あるいは、おさかなです。/いわば淋しいおさかな」「もう一つの方向へ……/私の涙の流れる方向へ……。/暗い深いところへ……」
舞台上にベッドに横たわっている〈病人〉と、かたわらでおにぎりを食べている〈妻〉が現れ、次に〈医者〉が担架に乗せた死体を運んで舞台を横切り、最後に〈妻〉が帰るまで、〈男〉のモノローグは続く。
〈妻〉と入れ替わりに登場する〈看護婦〉は、舞台前面の〈男〉に直接語りかけて、病院への道筋を教え、ついでに注意を与える。「それから、もし患者さんがどなたかに声をかけましても、お相手をなさいません様に。あなたの足音を聞いているのです。きっと耳を澄ましておりますから……」
これで〈男〉はようやく〈病人〉のもとにたどりつく。とりとめのない話が交わされてから、〈病人〉は語り始める。
原水爆禁止大会でシャツを脱ぎ捨てたとき、人々は熱狂的な拍手をするだろうと思っていたのに、みなシュンとしていた。それが言わば彼の転落の始まりだった。
それ以前の、後に「あの街」と呼ばれることになる場所で、ケロイドを見せたときの思い出。
そうさ、あれも最初は嫌な仕事じゃなかった。
俺は見物人にヒロシマの、あの時に様子を話してやったり、一寸気の利いた冗談を言って笑わせたり、カメラの為に新しいポーズを考えたりしたもんだ。
俺がシャツを脱いで見物に背中を向けると、一斉に、ホオッと云う様なため息が聞こえる。
それは悪くなかったよ。
それに俺は、あの、シャッターのカシャリと落ちる軽い音も好きだった。俺が一寸背中の筋肉を動かす度に、それがカシャリ、カシャリと鳴るんだよ。
実に、何と云うか折目正しい感じでね……。
そうだ、あれはいつだったかなあ。一度小さな女の子がお母さんと一緒に見に来てね。その子が、俺の背中のケロイドをさわってみたいと云ってきかないのだよ。
ははは、おかしな子だったねえ。
俺もうつるものでもないからと思って、さわらせてやったのさ。
おそるおそる手を伸ばしてね、一寸さわってすぐひっこめたよ。
可愛い子だった……。
ホオッというため息、折目正しいシャッターの音、おそるおそる差し出される小さな手。これらが〈病人〉にとって貴重だったのは、ひそやかでも確実さをもって世界のほうから彼へと送られてきた信号だったからである。それに触れている限り〈病人〉もまた、世界とのつながりが感じられて、安定していられた。
しかしあるときそれは、「目の前からスウッと黒い波が引いて」いくように、遠ざかってしまう。
(暗く)あの原水爆禁止大会があってからいけなかった。
俺は気が付いたんだよ。
奴等が本当は何を見たがっているのかと云う事をね。
眼を見るんだ。
俺の目を……。
背中のケロイドよりも俺の眼をのぞきこもうとするんだよ。
俺がシャツを着始めると奴等はじっと穴があく程俺の眼を探ろうとするんだ、わかるかい。
作中、「原水爆禁止大会」や「ヒロシマ」などの固有名が出てくるのはここだけ。だからこそ、我々は思い巡らす。これらについて、どれほど多くの言論が費やされてきたことか。さらに、どれほどの言葉が、被爆者救済のために使われたことか。それはもちろん、必要なことであったろうし、有効でもあったろう。
しかし〈病人〉の求めるものはそこにはない。彼はあるとき、まったく唐突に、原爆という、個人の身の丈をはるかに超える巨大なものに生身で出会ってしまった。そのため、普通の日常は奪われてしまった。
第一幕二場で、一場に引き続いておにぎりを食べている〈妻〉に向って、「お前には計画ってものがないんだよ」と、正しい食べ方について長々と講釈を垂れる割合と有名な場面【例えば、山崎哲が「うお伝説」(昭和57)で引用してる。】があるが、これは、今や遠いものになってしまった日常性への〈病人〉のこだわりを示している。別役劇では同じモチーフは、「一軒の家 一本の木 一人の息子」(昭和52)などに繰り返されている。
日常はもどってこないし、救済もされない。そこで〈病人〉は、巨大なものから受けた聖痕を曝し、それでも一人の人間として生きてきたし、これからもそうしなければならない事情そのものを、人々の前に提出しようとする。これが、時間が経つにつれて、あからさまに難しくなる。
原子爆弾が人類最大の厄災であることが広く知られるようになればなるほど、人々はそこでひとつの「芸」が行われたなどとは信じず、隠された「意図」を探ろうとするから。ずれはどんどん大きくなり、〈病人〉の焦りは募る。ついには、人々と自分との間に憎しみがあるのだと思いみなし、「あの街」行って殺されることさえ夢想する。「情熱的に生きたいのさ」と彼は言う。
それに対して、第二幕で発症し、同じ病室へ運び込まれた〈男〉には、そんな彼の空回りがよく見える。「つまり、誰もが野心的であるとは限らないし、全ての敗残者が悲壮であるとは限らない。往々にして人はさり気ない」と冒頭のト書きに記されている彼は、さり気なく生きること、それができなければさり気なく死ぬことを望んでいる。
僕もそう考えたけれども、もう誰も僕達を殺してくれる人なんかいないんです。本当ですよ。
「ケロイドが、伝染(うつ)るといけないから」なんて云う人が居ますか?
誰もそんなこと云いやしない。誰も云いやしませんよ。そうじゃなくて、いいですか、これは本当の話ですが、原爆症の男の人とでなければ、結婚しないという娘さんがいるんですよ。当りまえのきれいな娘さんなんです。それからケロイドのある女のひととでなければいやだっていう男の人も居るんだそうですよ。
現に、ここでこの間まで働いていた看護婦さんは、そういった男の人にもらわれていったんです。
ねえ、それじゃまるで僕達は愛し合ってるみたいじゃありませんか?
そうでしょう。僕達を殺したり、僕達の悪口を言ったりするのは禁じられているんです。そう云うシクミになっているんですよ。だからみんなニコニコしています。愛しているみたいなんです。
かつて〈病人〉を迎えた熱狂はもうない。日常の側からひそやかに送られてきた信号も。「ケロイドが伝染る」なんぞという誤解ないし心ない言葉も、露骨な反感さえ、ない。これらは正負いずれの方向にもせよ、人間の自然の感情から出た、〈病人〉のケロイド、というかそれを積極的に見せる行為への反応だった。
それにひきかえ、被災者を見たら必ずお気の毒と思え、などと決められた、言わば制度化された優しさの中には、彼の情念に対応するものは何もない。
〈病人〉はそれを理解しないか、理解しないふりをする。長い入院生活でろくに歩けなくなっているのに、「あの街」へ、ゴザとオリーブ油を載せたリアカーを引いていくのだと言い出す。行って、カミソリで体を傷つけて血を流してでも、自分がどんなに一所懸命か、見てもらうのだ、と。
〈男〉にとってこんな厭わしいことはない。そんなことをすれば〈病人〉と人々の間のズレが、それこそ原爆並みに巨大化するだけではないか。
病人 (前略)
俺はね、知ってるんだ。分かったんだ。
今日行かなければ、きっと、もう行く日がないよ。そうだろう。
今日だけははってでも行かなければならない。
ね、お前、行かしておくれ。
俺はね、決心したんだ。行こうって。この事が判るかい。(ベッドをおりる)
男 (同じくベッドをおりて)叔父さんはっきりして下さい。
いいですか、もう僕達は何もしてはいけないんです。何をしてもいけないんです。何かをするってことはとても悪いことなんです。どんなに辛くても黙ってじっと寝ていなければいけないんですよ。
(後略)
あくまで出て行こうとする〈病人〉に〈男〉がむしゃぶりつて、〈病人〉はあっさり死んでしまう。
全登場人物がボンヤリ現れ、〈妻〉の依頼で〈通行人1〉が用意したリヤカーに〈病人〉の死体を乗せて運び出す。行く先は、「あの街」。コーモリ傘を広げた〈男〉以外は、それについて行く。
開幕の時と同じような、ただしずっと短い〈男〉のモノローグで、劇は終わる。「何故、拍手をしないんです。/叔父は、そう思ってたんですがね。拍手をするだろうって……」
以上で私は、この戯曲の主筋を紹介して、分析した。他に、脇筋がいくつかある。その中で、第三の被爆者〈看護婦〉について触れておこう。
彼女は〈病人〉とは全くからまない。〈男〉と短い会話を交わし。舞台奥を横切り、あとは〈男〉が話題にするだけ。
第一幕では、丈夫な百姓と結婚して子どもを産むのだと言う。第二幕では、その子は生まれてすぐに死んでしまったと言われる。これでもう〈看護婦〉は登場しない。第三幕、〈医者〉は彼女は結婚などしなかった、すぐ先の病室で寝ている、と〈男〉に言う。しかし〈病人〉によると、一度は病院から裸足で走って出て行ったが、連れ戻されたのだそうだ。
〈看護婦〉が子どもを産んだ話は、嘘だったのかも知れない。それでも彼女は、〈病人〉と同様に、戦おうとしている。
被爆者が普通人の生活を取り戻し、「ケロイドのある女のひととでなければいやだ」などとは言わない男と結婚し、さりげなく、子どもを産み、その子が育っていく。その過程こそ「それら(原爆の)結果として表現された様々なもの」を「究極に於て拒否する」(「ヒロシマについての方法」前出)だろう。
成功した人はたくさんいるだろう。が、失敗した場合には……。もがき、あがき、「手足をバタバタさせる」(「それからその次へ」前出)のだろうか。別役は、劇の中であえてそうさせて、その向こうに、彼らが全人生を賭けて耐えねばならなかった特異な時間を間接的に見据えようとする。このようにして、「見る」試みは、ヒロシマへの鎮魂の歌にもなるのである。
【作品後に現れた主な関連事項の内二つを挙げておきます。
(1) 別役実は「マクシミリアン博士の微笑」(昭和42年、初演も同じ)で、もう一度ケロイドを取り上げた。『別役実第三戯曲集 そよそよ族の叛乱』に収録されているが、タイトルに「三場」と記されているのに、二場までしかない、たぶん未完成作。『別役実第二戯曲集 不思議の国のアリス』の「あとがき」には、「上演後大幅な書直し計画をたてたまま手がつかず、そのままになっている」とあり、その後改稿されることはなかった。また、別役実がヒロシマを題材としたのもこれが最後になった。
内容は、被爆した子ども達のケロイドを手術で隠してやりながら、彼らにヒロシマの「あの時」のことを語らせようとする、マクシミリアン博士(舞台には登場しない)の意図をめぐって、〈助手〉、自身被爆者である〈看護婦〉、それに〈子供〉の三者が葛藤するさまを描いている。ヒロシマの「語り難さ」は「象」よりストレートに出ているが、反面ずっと生硬なディアレクティークで進行し、別役劇としては珍しいぐらい「近代劇」に近い印象が持たれる。
(2) 〈男〉のモノローグ中にちりばめられている詩的なイメージのうち、「淋しいおさかな」は、最初の童話集のタイトルになった(三一書房昭和48)。しかしそれより、戯曲「スパイものがたり」(昭和44年、初演は翌年。『第二戯曲集』所収)のスパイのほうが重要である。自分は「とめどなく怪しい大きなバケモノを、宇宙にブラ下げるための小さなピン」だと言うスパイは、紛れもなく〈病人〉の後継者だが、彼自身が「おさかな」になぞらえられていることは、最後の場で巨大な釣り糸が空から降りてくることでわかる。彼は寂しさのあまり思い出の地球を買収して食べてしまった挙句、電信柱を登って釣り糸の方向へと昇天する。】

Hiroshima mon amour, 1959, directed by Alain Resnais
メインテキスト: 『別役実評論集 言葉への戦術』(烏書房昭和47年)
Ⅱ ヒロシマの語り難さ
「原爆一号」と呼ばれた男がいる。
本名を吉川清といい、三十四歳のとき、広島の電鉄会社からの夜勤明け、帰宅した瞬間に被爆、奇蹟的に一命をとりとめ、翌年妻とともに広島赤十字病院に入院した。
背中一面に負ったケロイドは、生存者中最大のものであるところから、まず医療関係者の間で有名になり、昭和22年、『ライフ』『タイム』など外国人記者団の取材を受ける。このとき『ライフ』誌に載ったケロイド写真にATOMIC BOMB VICTIM No.1 KIKKAWAというキャプションがついたのが、上の通り名の由来。
26年、たぶん病院の待遇改善を求めたことが仇となって強制退院させられ、原爆ドーム横にみやげもの屋「原爆一号 吉川記念品館」を出す。翌年「原爆被害者の会」を結成したが、後に内部の軋轢のために脱退している。
昭和30年は第一回原水爆禁止世界大会広島大会があり、それに先立ち被爆者諸団体を結成した「広島県原爆被害者団体協議会(広島県被団協)」が結成されると、常任理事に就任する。38年平和都市建設法によって彼の店は壊され、44年からはバー「原始林」を経営した。61年に亡くなっている。
以上のような経歴は、原爆被害者としてはそれほど珍しくないのだろう。たった一つ、特別な名前で呼ばれたことを除いては。この名は元来、吉川本人よりは、彼の背中一面のケロイドにつけられたものだった。そして彼は、半ば以上自らの意思で、だろう、これをずっと引き摺って生きた。つまり、原水爆禁止大会などの機会に、背中を聴衆の目に曝し続けた。
現在では土門拳の写真集『ヒロシマ』(研光社昭和33年)などでその姿を見ることができる。新藤兼人監督「原爆の子」(27年)やアラン・レネ監督「ヒロシマ モナムール」(1959年。日本公開時の題名は「二十四時間の情事」だが、これはどうにも気に入らないので、使わない)などの映画にも出ている。いずれも当然のように、ケロイドを見せて。
こんなことで目立つのは、いいことばかりではない。吉川自身の著作『「原爆一号」といわれて』(ちくまぶっくす昭和46年)にはこうある。
“原爆一号”といえば、大きなケロイドのあることをよいことにして、図々しくも自ら“原爆一号”などと称して、売名とケロイドを売り物にして生きているいやらしい奴ぐらいにしか思っていない人もまた、少なからずあったようである。
その証拠に、そうしたたぐいの非難や中傷をいやというほどに、直接間接に聞かされてきたものであった。中には悪意に満ちたものもまれではなかった。
非難や中傷は、まず諸肌を脱いでケロイドを人目に曝す手段のあざとさ(に、見えてしまう)に由来する。結果として吉川個人が目立つことへの反感もあった。自分が作った「原爆被害者の会」を辞めた事情を初め、彼の本に出ている具体例はたいていそれである。
しかし、そういうはっきりした形をとる以前の、彼の背中を目の前にした人々の微妙な戸惑いは、書かれない。たぶんそれは言葉にならない、してはならないものだ、と感じられたから。
今そこを簡単に述べておこう。背中一面のケロイド、それは正に、科学技術がもたらした蛮行の証である。それでも、原爆ドームとは違って、彼は生きている。そこにあるのは、我々同様生活している男の生身である。それを目にするについては、男の明確な意思が働いている。我々はそれを、どう扱ったらいいのか。
外国人記者団の前で服を脱いだときの心持ちを、「見とりやがれ。このオレの身体を、ピカで生き残った証にしたるけんの。そうでもせにゃ、やれんわい」と表現している。決して歴史になり終わらない生々しさ。それに対して誰が、何をできるのか。それとも、何もできない無力さを認めるべきなのか。そのような決意を、この意思は言わず語らずのうちに迫ってくる。
取敢えず我々は、戸惑い、立ち尽くすしかない。やがて目を逸らして、忘れるだろう。それでも、その前に、戸惑い立ち尽くすこと自体に、何か意味はないのだろうか。
「ヒロシマ モナムール」のシナリオを書いたマルグリット・デュラスは、映画冒頭部分のシノプシスに、次のように記している。
何について、彼らは話しているか? まさしく、ヒロシマについて。
彼女は彼に向って、自分はヒロシマですべてを見たのだと言う。彼女が見たものが画面に現れる。それは、怖ろしい。しかし、それに対し、彼の声は否定的な調子で、空しいさまざまの映像を非難するだろうし、また彼は彼女がヒロシマで何も見はしなかったのだということを、個人の立場を離れて、我慢がならないといったふうに、繰返し語るだろう。
彼らの最初の言葉のやりとりは、従って寓意的なものとなるだろう。それは結局、オペラの言葉のやりとりとなるだろう。ヒロシマについて話すことは不可能なのだ。なしうるすべてのこと、それは、ヒロシマについて話すことが不可能であるということについて話すことである。ヒロシマについての認識は、精神の陥る典型的な罠として、先験的に設定されているので。(マルグリット・デュラス 清岡卓行・坂上脩訳『ヒロシマ、私の恋人/かくも長き不在』筑摩書房昭和45年。太字は引用者。以下同じ)
この映画に吉川のケロイドの画像を使ったのはたぶん日本のスタッフで、デュラスはそのことも、吉川本人のこともあまり知らなかったのではないかと思われる。彼女は日本へ来たこともなく、従って広島を直接目にしたことはなかった。フランスにいて、ヒロシマの語り難さに、そしてそのことこそが語らねばならないことに、思い至ったのである。
【吉川のほうは、映画好きを自認していて、「原爆の子」「ヒロシマ モナムール」から「はだしのゲン」(昭和55年作)に至るまで自著でコメントしている。しかし、「象」については全く言及がない。たぶん、知らなかったのだろう。】
「象」は別役実の発表された戯曲の二作目に当り、現在に至るまで彼の、そしてまた戦後日本戯曲の代表作に数えられている。別役もまた、吉川のことはよく知らず(内田洋一『風の演劇 評伝別役実』―後出―によると、土門拳の写真で見たぐらいがせいぜいらしい)、デュラスの戯曲「セーヌ・エ・オワーズの陸橋」は評価しているが、「ヒロシマ モナムール」から直接何かインスピレーションを受けた、ということはなさそうである。しかし彼は偶然にもこのフランスの女性作家と非常に近いところから創作した。
以下では、上記を含めて、「象」で採用された方法論について、別役自身の遺した言葉から考えてみよう。『言葉への戦術』には、初期に上演された際のパンフレットに書いたものが三つ収められている。まず年代順に題名・年・上演団体を記し、以後は①~③の番号で記述する。
① 「赤い鳥のいる風景――「ヒロシマ」との関係を探るために――」・昭和42年・企画66
② 「盲が象を見る」・昭和43年・早稲田小劇場
③ 「ヒロシマについての方法」・昭和45年・青年座
【現在知られている「象」は改訂稿であって、戯曲は『新劇』昭和40年8月号に発表され、同時期の7月青年芸術劇場(青芸)によって俳優座劇場で初演された。別に初稿があって、昭和37年劇団自由舞台の旗揚げ公演として、鈴木忠志の演出で所も同じ俳優座劇場で上演されている。翌38年自由舞台の機関誌『劇場評論』No.2に戯曲が掲載されたとのことだが、私は未見。
ところで少し気になるのは、①には、別役が初めて広島を訪れたのは昭和41年の秋だと記されていることだ。すると「象」は、改訂稿も、実際の広島を見ずに書かれたことになる。それはデユラスと同じではあるのだが、どうも①の調子はそれには相応しくない。因みに私は『新劇』昭和40年8月号所収のテキストは確認しており、その後再び改稿されていないことは断言できる。
偶然だが、③には、原民喜が、原爆投下以前に、レストランの丸天井が崩れる幻覚に襲われたことを書いたエッセイが紹介され、「記憶の修整」と呼ばれている。同じことが別役にもあったのかも知れない、ぐらいに思って、以下の引用文を読まれたい。】
(前略)私はひなたくさい原爆記念館に陳列されたゆがんだ弁当箱や、ケロイドの写真の前でどうしていいのかわからなかった。それらは、奇妙に生々しいのだが、ちっとも具体的ではなかった。その時なのだろう。私の中構築されていたかに見えた「ヒロシマ」がガラガラと崩れ去っていったのは。そして、ドームを中心に広がる、荒涼としたものだけが残ったのだ。
原爆資料館の弁当箱は、究極の暴力によってそれが使われていた日常の場から引き離された。その歪んだ形から、暴力の恐ろしさは偲ばれるだろう。いずれにしろ、そこにあるものはあくまで終わってしまったものの結果であり、一見きわめて明確である。
数多の言葉がその上に積み重ねられる。そういう行為を、我々は普通、ヒロシマを語り、理解することだと呼んでいる。
けれどもし、それをもう一度、日常性の過程にもどすことができたなら、歪みは耐え難いほどの具体性を備え、ゲンバクの、それがある日突如として一般人の生活の場に侵入してきたことの「意味」を語るのだろう。
そのために必要なのは、まず第一に、「見る」ための新たな方法である。②にはこうある。【以前にも引用した】
象は、当時、われわれ「目明き」にとってハッキリしていた以上に、現在、ますますハッキリしてきたかに見える。ほとんど理解し尽くしたかに……。
しかし、どんな「目明き」が、象を「太い柱である」とか、「大きなうちわ」であるとか、「厚い壁」であるとか断言できるだろうか……? また「太い柱」である、と断言することによって、それにつながって広がる量と、それに対する不安を、誰が、それ以上に感じ取れるであろうか……?
ある漠然とした空間がある。その空間については、盲が象を見るようにしてしか、見ることが出来ないという奇妙なメカニズムが存在する。陰湿なマイナスの世界である。
(中略)
盲は何故象に手を触れたか? 漠然とした巨大なものに対して、一つの関係を築きたかったからである。目明きが笑うか笑わないかは、盲の知るところではないし、象が果たして、柱であるかないかも問題ではない。盲は、むしろ、象と自己との何かを探ったのである。盲にとってこそ象は理解されるべきだというのは、知るということがこういうことだと思うからである。
デユラスの言う「精神の陥る典型的な罠」を回避するためには、迂回路を辿る必要がある。
リトルボーイの破壊力、その被害の総体を示すことは、言わば象の画像を見せ、象の表面積と体重を測ってみせるようなものだ。そういうことを我々は「象を理解する」ことだと思っている。別に間違ってはいない。が、その「分かり方」によってかえって見失われるものがある。
途方もなく巨大なものと、比べればあまりにもちっぽけな人間との関係。
別役が舞台上で表現しようとしたのは、ある状況のために必然的に「誤った認識」に陥るしかない人間の視点だった。象の一部を「うちわ」とか「大きな柱」と断定することで、象は「そうではない、何か巨大なもの」だと、漠然と、不安のうちに意識される。そしてまた、その「正体」は極められないからこそ、反対側に「それをそう感じずにはいられない自分とは何か」、という問いも立ち上がる。
③にはこうある。
その日原子爆弾がヒロシマに落とされた事実を、政治的な経済的なカラクリをもって説明する事など何でもない。それは被爆者の悲劇を、被爆当時の苦しみや、その後の病状や、生活の困窮や、社会的な差別の実情で説明するのと同様である。それら結果として表現された様々なものを無限の彼方に据え、それを究極に於て拒否するものを自らのうちに確かめる行為こそ、先ずもってなされなければならない。そこにしか、ヒロシマに対する方法はないのである。
「私はヒロシマですべてを見た」「君はヒロシマで何も見なかった」という「ヒロシマ モナムール」冒頭の男女(岡田英次、エマニュエル・リヴァ)の対話は、見ようとすればするほど見えなくなるものがあることを示している。その上で、消えない心の傷を抱えて、一夜限りの愛を交わす彼らの孤独な魂の響き合いの彼方に、何かが、本当に語るべき、見るべき何かがあることを暗示する。
一方、別役が劇を展開するために使った動力(ドラマトゥルギー)は、独特の「芸」だった。
別役劇の主人公としてお馴染みの漂泊者は、アーサー・ミラー「セールスマンの死」を原基とするが、最初芸人として現れた。
【「セールスマンの死」は、昭和35年、早稲田小劇場の前身である自由舞台が、鈴木忠志演出・小野硝主演という、「象」の初演と同じコンビで上演しており、このとき別役は舞台監督をつとめた。その影響については、別役自身が岩波剛のインタビュー「別役実氏に聞く」(『悲劇喜劇』昭和53年4月号)で以下のように言っている。
「あのウィリー・ローマンの形象に対する思い入れというのが非常に強かったんじゃないかという感じがするんですよ。ぼくの場合、たいてい男が主人公になってでてくるのですけれどもね、それはどうも、ずっと連続して、ぜんぶウィリー・ローマンの変形ではないかという感じがする」】
もちろん、ケロイドが芸であるはずはない。ただし、それを積極的に人に見せようとする決意は芸そのものだ。そのことは、カフカの短編小説「断食芸人」を劇化した「獏」(昭和46年。『別役実第三戯曲集 そよそよ族の叛乱』所収)の時にはっきりと明言される。
ところで断食芸人は、興行師と共に一つの街に現われ、想像を絶するほどの長時間の断食を宣言し、それに挑戦してみせるわけであるが、実に思いがけないところに矛盾を露呈するのである。断食芸人の芸人たるゆえんは、断食もまた芸であるとしたその決意のうちにあるのであって、実際の断食行は単にその結果にすぎないのであるが、観客はそう見ない。観客には、結果としての断食行しか見えないから、それが芸であるならば、それは断食する事なしにあたかも断食をしているが如くにふるまう芸に違いない、と考えてしまうのだ。つまり、こっそり食べる芸である。(「断食芸人の悲哀」初出は『朝日新聞』昭和46年10月)
背中のケロイドを見せつけられたとき、我々は疑わずにはいられない。これは同情を惹こうとする行為なのか。もっと端的に、目立ちたいのか。彼はどうしても孤立する。
もっとも、孤立ならずっと以前に始まっていたのだろう。生産にも、共同体の維持にも、歴史を振り返ることにすら関係なく、ただただ彼個人の事情と思いを突き出しているだけなのだから。しかし、個人的なこのような思いを、個人的だという理由で無視し去るのであれば、「人間そのもの」も消えてしまうだろう。
共同性にも歴史にも回収されないから、対応するとすれば神しかいない人間性のこの部分は、「魂」と呼ばれるのに最も相応しいのである。「私に言わせれば、農夫には魂なんか必要ではないが、旅芸人には、スパイや裏切り者にそれが必要なように、魂が、それこそ必要なのである」(「「獏」創作雑感」初出五月舎「獏もしくは断食芸人」上演パンフレット昭和47年1月)
以後、別役劇は、スパイ、裏切り者、そして元のセールスマン、などなど様々に姿を変える魂の持ち主たちを主軸として展開する。だから、「象」こそ別役実の出発点と呼ばれるべきなのだ。
つけ加えるならば、ここには、現代の意識的な作家に固有の、メタ演劇(演劇についての考察を含む演劇)のレベルもある。断食を、またケロイドを芸にするという奇妙な決意は、演劇に携わる決意と同質とされるのだ。
大げさな言葉を使えば、人間が文明の内に演劇という奇妙な装置を仕掛け、それを操作しているという事実こそが、感動的なのでなければならないのだ。人間が演劇をするという奇妙さは、断食を芸として売る奇妙さと比較して勝るとも劣らないのである。(前出「断食芸人の悲哀」)
別役は演劇が初源に持っていた衝撃と感動を、多少とも現代に蘇らせようとする野心を持った劇作家だったのだ。その奇妙な決意において、彼自身が、断食芸人や原爆一号と共通点を持っていた。

坂手洋二演出「マッチ売りの少女」新国立劇場平成15年
メインテキスト:『別役実戯曲集 マッチ売りの少女/象』(三一書房昭和44年)
【別役実氏が3月3日に亡くなった。直接の死因は肺炎だが、コロナではないそうだ。巨星墜つ、というべきできごとで、実際そう表現した雑誌やネット上の記事も見かけるが、新劇に関する認知度自体が高くない日本では、さほどの話題にならなかったのは仕方ないことである。
学生時分から同氏のファンを続けている私としては、一言なかるべしの気分にはなったが、現在このブログ以外には文章を発表する場所もなく、そこでは西尾幹二『歴史の真贋』に取り組んでいた。それに3ヶ月かかってしまった。今となって、遅ればせながら、改めてこの大劇作家に関する考察を示して、献花に代えようと思う。
一言以上にはなるが、いつものように断片的に、期限も決めず、だらだらと語るしかない。一応の方向性はあって、それは広大にして複雑微妙な「別役ワールド」の、私なりの見取り図を作ることである。興味とお時間があったら、どうぞお付き合い下さい。】
Ⅰ 加害―被害関係
以前のシリーズ「悲劇論ノート」は、西洋演劇の一典型の発生についてスケッチしたものだ。「お前は誰だ」と問う状況があり、それに答えようとする者がいる。この関係は逆から見れば、「この状況とはなんだ」と問う「私」を描く劇、ということにもなる。問いに対する答えをみつけようとするところに「私」がいて、「私」によって状況はある一連のまとまり・意味を持つようになる、とも言い換えられるだろう。
最初期の典型例は例えばこういうものだ。ある都市国家が外敵に攻撃される。あるいはまた、ある都市国家に得体の知れない疫病が蔓延する。どちらの場合も「答えるべき私」はこの都市国家の王であり、このような危機に対応することを当然の責務として求められる。そこで、全力を挙げて対応すると、それによって、その人間の、自分でもよくわかっていなかった「真の姿」が現れてくる。
「劇的」というと、通常こういうものを思い浮かべるぐらい、この構造は強固である。しかし、いくつかの問題点はわりあいと昔から認識されていたようだ。
例えば、ある一個人の決断と行為が、多くの人に致命的な影響をもたらすことなどめったにあるものではない。せいぜい、家族など、ごく近しい人々が困ったり逆に喜んだりするばかりだ。リア王が、金持ちなだけの庶民の爺さんだったら、でたらめな遺産分配をしても、騒動は遺産相続者の範囲に限られる。他人にとっては、「もうろく爺さんのために酷い目に合ったな。お気の毒だね」で終わり。
彼らの決断も行動も、あくまで「わたくしごと」あって、「おおやけ」には見えない、ということだ。当然、これを見世物としても、大した迫力は出ない。
即ち悲劇とは、神話上の英雄か、王侯貴族を主人公とするものだ。この定式は、コルネイユやラシーヌによって最後期の悲劇が創造されたフランス古典主義時代(17世紀)まで変わらない。すると、身分制社会が崩れた近代では、悲劇は自然に作れないことになってしまう。
一応断っておいた方がいいだろう。他人に対して大きな権力を揮って、従って大きな影響力を持つ者は、近代でもいる、いや、近代でこそたくさんいるのではないか、と疑問を持つ人もいるだろう。20世紀に登場したヒトラーやスターリンや毛沢東ほどたくさん人を殺した権力者は、古来そんなにいるものではない。
しかしこのような政治劇では、人間同士の対立相克より、社会システムの圧力のほうがはるかに存在感が大きい。権力者でも、システムの中の巨大な歯車のようで、その非人間性こそが恐いのである。
【別役実には、このようなメカニズムの核を描いた作品もある。このシリーズの、後の方で述べるつもり。】
悲劇はこういうところには不向きだ。それはあくまで、「人間とは何か」を問うものだからだ。
一方で、一般庶民を主人公にした劇形式も古来ある。これは喜劇と呼ばれる。
何かがおかしい。おかしいのは、主人公(たち)か、周囲のほうか、ともかく、何らかの「解決」が求められそうな状況がある。ただ、主人公は王侯貴族のようなノーブレス・オブリージュ(高貴な義務)を背負う者でもなく、特に優れた能力があるわけでもない。彼らはただジタバタし、その努力とははずれたところで、ものごとは、「解決」といえるかどうか、微妙な、一応の結末を迎える。
階級制が崩壊したというだけでも、現代で可能なのは喜劇、ということになるのは明らかなようである。しかしより問題なのは、いずれにもせよ、「私」と「状況」の差・ずれ、によって「私」が際立つ、その構造のほうなのだ。すべての前提には、「私」と外部の「状況」、合わせて仮に「世界」と呼ぶことにすると、それには「あるべき姿」があるはずだ、なければならない、という、普段は特に意識もされない信念がある。この信念を敢えて意識し、純粋に追求されたところに宗教、即ち神及び神々の概念が生まれる。
近代は、前述した社会システムの複雑化と、神(的なものを含む)を中心としたあるべき世界像の揺らぎとが相まって、「私」像の追求もより困難になった。時代状況と切り結ぶ野心と意欲をもった表現者は、これを無視するわけにはいかない。パフォーマンスの世界に限っても、様々な形式が模索されねばならなかった。
日本にはまた、西洋に比べれば、ということだが、独自の問題もあった。
『マッチ売りの少女/象』所収の「それからその次へ(あとがきにかえて)」に引用されている「「戦争体験」論の意味」(高橋和巳編『戦後日本思想大系13 戦後文学の思想』筑摩書房昭和44年所収)で、橋川文三が次のように書いている。
われわれの精神伝統の中には普遍者――超越者の契機が認められない。存在するものはただ感性的現実であるか、それとも、それと全く関わりない純粋な理論の体系のみである。意味はただ「手足をバタバタさせる」ような実践の中か、演繹的な理論体系への信仰の中にしか見出されない。それは実践と理論とが、普遍者と主体との緊張関係によってうらづけられるときにのみ、統一的な原理として機能しうることが無視されているからである。
例えば戦争体験は、戦争によっていかに周囲や自分が酷い目に合ったか(感性的現実)を語るか、マルクス主義、中でもレーニンの「帝国主義論」など(純粋な理論の体系)を持ってきて、その(唯物史観上の)歴史的意味を語るか、どちらかになる。
両者は結びつくこともあるように見える。後者は前者を引用して、戦争の悲惨を印象づけ、さて人類はこのような段階から脱し、殺し合いも差別も迫害もない世界へと進化していく段階にある、などと説くので。
それでいてここでは、悲惨な体験をした人間の、一回限りの生の意味は、全く無視されている。問題はただ、悲惨のみなのだ。理論家たちは、それを利用しているだけ、と言える。
「理論」という言葉を拡げて、ある時代、少なくともある階層には支配的な、例えば愛国心とか忠義とかいう理念や観念まで入れると、それが「当り前」である時、これを否定、どころか疑う人間など、洋の東西を問わずめったにいるものではない。
強固な理念が時には個人に悲惨をもたらすこともあるのは、日本でもわりあいと古くから知られていた。森鴎外「阿部一族」のタネ本は江戸時代にあり、武士階級にとって至高のエートスである「忠義」が、現実との間に軋轢を生じる場合もあることは、ある人々の目には映じていたことがわかる。
その狭間に落ちて苦しみ、ついには全滅した人々は気の毒だ。しかし、それで終わり。これをもって、忠義の徳性を疑問視する、など、絶対に認められない、それ以前に、頭に浮かびもしない。個人はせいぜい、「すまじきものは宮仕えぢやなア」(「菅原伝授手習鑑」)というような詠嘆の裡に丁重に葬られ、忠義のほうは無傷で生き延びる。
そのかわり、戦後のように、ひとたび、一世を挙げて「ダメ」ということになると、全くもって捨てて顧みられなくなる。個人も理念も、この国では究極の意味は持ち得ないのだな、と思い知らされるできごとで、その影響は前回と前々回に述べた。
この両者、個人と理念が共に生き延びるためには、意外なようだが、この世のすべてを超えた不動の場所で究極の価値を設定したほうがいい。それが以前述べた福田恆存の信念で、橋川とは前提からして全く違うが、今回それには触れません。
福田に即して改めて述べます。
超越的な価値が信じられるなら、「私」はちっぽけな、相対的な存在でしかないが、社会も国家も、この世の目に見えるすべてが相対的なのだから、必ず従わねばならない道徳的な義務は消える。また、ちっぽけな「私」が、いつも究極の価値に沿うように生きられるものではないが、折に触れてそれを気にかけ、それと現在との距離を測ることで、一貫した意味を持つ、語るに足る「自分」が生じる。「普遍者と主体との緊張関係によってうらづけられ」た「統一的な原理」はこれを介することで初めて見つかる。
「普遍者――超越者」とは、橋川の場合でもキリスト教の唯一絶対神に近い、と別役からも見えていた。しかし、だから「われわれの中に、普遍者の意識を創り出すことがどうしても必要である」(橋川)などと言われても、どうしたらいいのか、日本人ならたいてい反問したくなるのももっともだ。
別役実はこれに対して、「ヨーロッパに於ける主体が、そうした普遍者との緊張関係の中に全く閉鎖され、統一的な原理体系のないアジア・アフリカにこそ無限の可能性が秘められている事を、既に我々は知っている」と言う。学生時分(昭和50年前後)、こんなことがよく言われていたことは知っているが、私はこちらにも、いかがわしさを感じた。だいたいこういうのは、ヨーロッパの「原理」に対する劣等感を裏返して見せたようなものではないか。
我々が別役実に傾倒したのは、それが西洋的であれ東洋的であれ(論理的なところ、かなり西洋的に見える)、一つのドラマの形を作り出して見せたからである。考えてみれば、ギリシャ人も唯一絶対神の観念はないままに悲劇を創り出したのだった。道は幾筋かあるはずなのだ。
ただ、せっかくだから、この極めて意識的な劇作家の思いを論理的に語ったものを、もう少し見ておこう。
「それからその次へ」は、戯曲集のあとがきでありながら、昭和17年に亡くなった詩人尾形亀之助を本格的に論じたもので、その後『尾形亀之助詩集』(思潮社昭和50年)に「研究」として収録された。以下の引用文で「彼」というのは、尾形のことである。
(前略)彼にとって問題であったのは、その漠然たる全状況が暗黙に強要する「君は?」と云う問だったのだ。勿論、問われる「私」は問う「全状況」によって規定されているのであり、当然「私」を答える事は「全状況」を問う事と同義なのであるが、彼はこの出来すぎた公式に拠る事をしなかった。「体制が圧制的なら私は反逆的である」と云う安易な公式の中には、既に体制に対する検証の余地も、従って「私」に対する検証の余地もないのであり、彼はそれを見抜いていたに違いない。
「体制が圧制的なら私は反逆的である」とは、別役も若い頃には関わった学生運動(昭和46年の新島基地反対闘争には、「一兵卒として」現地へ行った、と、一度だけお会いしたとき述懐なさっていた)中の言葉のようだが、出典は知らない。【知っている人は教えて下さい】
「圧制的な体制に『否』を言わないなら、お前はそれを認めていることになるんだ」みたいなことを言う奴は私の周囲にもまだいて、それこそ圧制的ではないかと思ったものだ。今の我々は、それこそ既に知っている。こういうことを言っていた「反体制」組織の一つが、まるでカリカチュア(誇張された戯画)のような、暴力による圧迫を実行したことを。
対立する両者は、「対立している」という堅固な構造に規定され、自然に「似たもの同士」になる。この過程を経た「私」が、「確立された/成熟した自己」とか呼ばれることもあるようだが。それまで含めて、「対立」はプロットが明瞭で、スリリングではあるので、これまで無数にドラマの題材になってきたし、今後もそうだろう。
そこからずれたドラマを作ろうとするなら、人気作家になることはできなくなる。もっとも、広く見たら、対立の構図がすっかり放棄されたわけではない。「自他合一」だの、「私心を捨てる」だのといった、これも相当いかがわしい「日本主義」など、もちろん問題ではないし、「私」の実感にのみ語るべきアプレオリな真実のすべてがある、という私小説的伝統に拠ろうというのでもない。
ただ、世界と「私」とを(「それからその次へ」など、別役の初期の評論では「おおやけ」と「わたくし」とも呼ばれている)、「夫々に相互的な、従って不確実な「一つの関係」」にまで戻し、「その「関係」を探る」ことを試みるのだ、と言う。
具体的にはどういう試みか。尾形亀之助の詩の場合は、彼の作品集と別役の評論(これがなかったら、私は終生尾形の名前も知らなかったろう)に当ってもらうとして、別役が劇を組み立てた方法は。
【別役実の戯曲は、標目に固有名はほとんど使われず、登場順に、男1、男2……女1、女2……などと表記されています。このシリーズの〈 〉内は、これを示します。】
処女作ということになっている「AとBと一人の女」(昭和36年初演、『別役実第二戯曲集 不思議の国のアリス』所収)は、加害ー被害関係という、最も典型的な対立を使っているが、この両者の関係性が反転するスリルに、劇の焦点がある。
出世作の一つである「マッチ売りの少女」には、上と同じ構造に、終戦直後の時期という、昭和生まれの日本人にとっては疑うべくもない大状況が背景として持ち込まれる。
舞台には古風なテーブルとやや上手(客席から見て右側)に小さなサイドテーブルがある。そこで、まずアンデルセンのよく知られた童話を少し変えたものが、姿は現さない〈女〉によって、「思いがけなく、すぐ耳の近くで」読み上げられると、初老の夫婦が登場し、「厳重な規則」によって「夜のお茶の道具」を並べる。お茶の作法や隣人についての、無意味だが、もっともらしくはある会話が交わされているところへ、最前の〈女〉が尋ねて来る。
この〈女〉は夫婦には初対面だが、自らを「善良にして模範的な、しかも無害な市民」と呼ぶ彼らは、お茶の時間のお客として彼女をもてなす。最初は〈女〉も慎ましやかだ。「私、ただ、あたたかい所で、やさしい人達と一緒に、静かにお茶をいただきたかったのです。外はとても寒いのです。雪が降っています。誰もいないのです」。
初対面の対話にはありがちなぎごちない間の後、〈女〉は突然過去を語り出す。自分はマッチを売っていた。あ、そう、じゃ、あんたはマッチを買って欲しいんだね。いえ、それはずっと昔、私が七歳の頃でした。そうか、思い出話をしたいのか。
そうだ、いや、そうじゃない。〈女〉はマッチそのものを売っていたのではない。忘れていたのだが、ある小説を読んで思い出した。
何を? それは、対話ではなく、〈男〉(初老の夫婦の夫)の朗読風の語りで伝えられる。
その街角で、その子はマッチを売っていた。マッチを一本すって、それが消えるまでの間、その子はその貧しいスカートを持ちあげてみせていたのである。ささやかな罪におののく人々、ささやかな罪をも犯しきれない人々、それらのふるえる指が、毎夜毎夜マッチをすった……。そのスカートがかくす無限の暗闇にむけて、いくたびとなく虚しく、小さな灯がともっては消えていった……。
かぼそい二本の足が、沼沢地に浮くその街の、全ての暗闇を寄せ集めても遠く及ばない、深い海のような闇を支えていた。闇の上で、少女はぼんやり笑ったり、ぼんやり哀しんだりしていた……。
あれは私だったのです、と〈女〉は言う。「思い出して頂けましたでしょうか」。つまり、〈男〉が客になったということか、と我々(観客)が思っていると、〈男〉はそれを肯定も否定もしない。「あの頃のことは忘れることです」。〈妻〉も「思い出してどうなるのです。……みんなどうしようもなかったのです。あなたのせいではありませんよ」。
〈女〉は応じる。「でも、私は忘れるわけにはいかないのです。……思い出してしまったからです」。
いや、忘れてもよい。でも、ただ一つ、知りたい。あんなことを、七つだった自分が、一人で思いついたはずはない。誰かが教えてくれたのだろう。「あなたですか?……覚えておりません?……私、あなたの娘です」。
そんな筈はない。〈男〉と〈妻〉には、確かに娘がいた。が、小さい頃に電車に轢かれて死んでしまった。それを二人とも見ていた。
いえ、と〈女〉はさらに言う、間違いはないのです。市役所の戸籍係の人に詳しく調べてもらいましたから。……ということであれば、その市役所で事実関係を徹底的に調べる(今だったらDNA鑑定もある)のが普通の流れだが、別役劇は決してそんなふうには進まない。
もしかしたらそうなのかも知れない、いえ、たとえそうでなくてもかまわないじゃありませんか、「なんか、かわいそうですから」と〈妻〉は言い、三人はけっこう楽しげに、一家団欒という感じで、お茶の席に着く。ここまでが、この一幕物劇の、いわば第一場、前半に当る。
後半はより禍々しい雰囲気なる。
〈女〉には〈弟〉がいて、この場に入ってくる。「このうちは、私達のおうちですよ」と言われ、お茶を飲み、ビスケットを食べる。そして、思い出話として、幼い頃〈男〉に虐待され、左腕が不自由になった、と言う。待ってくれ、そんな筈はない、自分には息子はできなかったのだし、人に暴力を振るったこともない、とさすがに〈男〉が怒鳴ると、「静かにして下さい。お願いです。子供達がちょうど、眠りかけたところなんです」。〈女〉には幼い子どもも二人いて、この場には入れていないが、家の中で、小さな寝息をたてているらしい。
〈女〉は、「お母様、やっとお会い出来たのです。ずい分、歩いたのです。……お父様とお母様にお、ひとめお会いしたくて……」と言いながら眠ってしまう。夫婦は、「可哀そうな人達と云うのは、どんなふうであれ、可哀そうなんだからね」「やさしくしてあげましょう」と、〈女〉たちを泊めることにする。
しかし、目を覚ました〈女〉は、今度は〈弟〉がビスケットを一枚余分に食べたと言って責める。私がどんな思いをしてあなたを育てたと思っているのですか。その私が、空腹だからといっていやしいことをしていい、と教えましたか。お父様とお母様にお謝りなさい。なぜ私の言うことが聞けないのです、私が卑しい女だからですか。言いなさい、あなたが余分に食べたために、誰が飢えなくてはいけないんですか……。そして激しい暴力を振るう。
〈弟〉は何も答えず、されるがままになっている。〈男〉が止めると、今度は〈女〉が脅えて、「許して下さい。お母さま、私はいけないことをしました」と床に突っ伏して動かなくなる。最後のあたりを引用する。
弟 (静かに)お姉様に触らないで下さい。お姉様は卑しい女です。だからお姉様は触られたくないのです。
(中略)
女 (遠く)マッチを……マッチをすらないで……。
弟 (つぶやくように)お父様はマッチをお買いになった。お父様はマッチをお買いになった。お父様はマッチをお買いになった。毎夜毎夜、お姉様のために……。毎夜毎夜お姉様のために……。
男 いや……(妻に)そんなことはない。そんなことはないんだよ。
弟 でも、僕は責めません。でも、どうしても、僕は責めるわけにはいきません。お姉様がおっしゃったからです。責めてはいけない。責めてはいけません……。
赤ん坊の寝息が聞こえない。凍死したのかも知れない。
この戯曲は、戦中戦後の悲惨を忘れ、高度経済成長の道をひた走る日本への批判が根底にある、とずっと言われてきた。市民社会の欺瞞を撃つ、というのは、あの頃の、演劇のみならず、文学・映画・劇画・音楽などまで含めた若き表現者達の多くに共有されたテーマだったのである。直接的な行動としては、60年安保闘争と68年(昭和43)の新宿騒乱をピークとした学生運動の、空前の盛り上がりがあった。
しかし、当時から、この「闘争」の危うさは、見える人には見えていた。
だいたい、欺瞞を撃つ、と言って、撃つべき対象は具体的に何か。いわゆる大人か。しかし、その大部分は、戦争の被害者だったとしか言いようがない。金儲けにしか興味がないじゃないか、と言ってみても、その金で大学へ入ったのが全学連や全共闘のお兄さんたちだった。即ち、「反抗者」たちにしてから、市民社会の外で生きていたわけではない。それに、大学進学率は、急速に伸びていたとはいえ、1975年(昭和50)でやっと三割強。ある程度余裕のない家庭出身でなければ入れない。それを忘れて、豊かさを追求する大人たちを一方的に非難するなら、欺瞞に欺瞞を上塗りするようなものだ。
そのため、だろう、「自己否定」なる言葉もよく聞いた。どこまで本気か、と思ったが、一世を風靡する思潮なら、時に人を極限にまで導く。現実に、連合赤軍の「総括」から新左翼党派相互の内ゲバへと、若者たち自身に攻撃対象が移っていったのが1970年代だった。
「マッチ売りの少女」にも、上と同種の不毛な過激さが溢れていて、あるいは、予言的、とも言えるかも知れない。
〈女〉と〈弟〉はタチの悪いタカリ、という見方も可能だ。自分たちがいかに惨めな弱者か、できるだけ実演を交えて訴え、なんの関係もないけれど、今何もしないのは、見捨てたような、後ろめたいような気にさせる。「お前がどんなに我慢をしてきたのか、わかって頂なさい」と、〈弟〉を上半身裸にしてアザだらけの体を見せるところなんぞ、その気配が濃厚だ。
事実弱者で、社会の被害者ではあるが、それを誇張して、演じる。私も、まだ、駅にいる傷痍軍人を二、三回見たことがあるが、あれがよく体現していた暗さ(傷痍軍人が登場する別役劇もある)……なんて言っても、見たことがない人にはわからないな。こういうのが社会の表面からは消えたのが、バブル以降の日本社会で、昔の日本ならでは、このような乞食稼業が成り立ったものだろうか。それからは、「他人とは無闇に関わるな」が一般庶民のモットーになった。
一方、〈女〉と〈弟〉の言うことは、部分的には事実だ、と仮定してみよう。〈男〉はかつて、幼い娘の陰部を束の間見るために、マッチを買ったのかも知れない。まことに、「ささやかな罪」としか言えない。忘れる、つまり「なかったこと」にするしかないのだ。「みんなどうしようもなかった」のだから。もっと大きな、売春や強姦も、幼い子どもを飢えと寒さで死なせてしまったことをも、忘れたからこそ現在がある。忘れたからこそ、他人に優しくできる。
欺瞞だ、と言われるなら、いかにも。しかし、他にどうしようがあったのか? もっと広く見て、いかなる欺瞞もなしで生きていける人なんて、この世にいるのか?
〈女〉は、全く個人的に、それが耐えられない、と、言葉ではなく、全身で訴える。「なんのため」は知らずにやったあのことは、深いところに刺さった棘のように、内面の、深いところに残っている。忘れたりしたら、これに決着をつけることは永久にできなくなる。だから、「なんのため」は除いて、ひたすら追求する。
では、〈女〉の本当の父が現れ、自分がさせた、そうでなければ生き延びることはできなかった、と告白し、謝罪したとしたら? 「決着」になるのだろうか。そうなれば、ことは一家庭の、個別的なできごとでしかなくなる、それがはっきりするだけではないか。
そこを超えた社会的歴史的な広がりを持つためには、罪―罰あるいは許し、に関する普遍的な原理がなければならない。言い換えると、この世を超越した何ものかだけが、時代の罪を、欺瞞を、裁いたり、許したりできる。それがないなら。
「手足をバタバタさせる」ことを、強く、執拗に、理不尽に続ける。忘れることも、忘れられることも、許されることも拒否して。それがここで採用された方法である。
それでいて全体を、上品で慎ましい枠の中に収め、狂気とはうらはらな安定感を出す。
このようにして、少女の貧しいスカートが包み込む、ちっぽけだが深い闇を、当初の生々しさをもって、一瞬だけ蘇らせることができる。本当は誰もが知っているのに、黙契として、見ないことにしてきた暗部。暴露でも糾弾でもなく、ただ、あることだけを示す。生身の肉体という、この上なく具体的なものを素材とする劇芸術にだけ、こういうことができるのである。
【多少「研究」と呼ばれるに近いことを記しておく。〈女〉が読んで「思い出す」きっかけになった小説は実際にあるのではないか、と思う。
第一候補は、野坂昭如の同名小説「マッチ売りの少女」だが、やや微妙。『野坂昭如コレクション1』(国書刊行会平成12年)の、大月隆寛の「解題」によると、この小説は『オール読物』昭和41年12月初出。戯曲のほうは、『劇的なるものをめぐって――鈴木忠志とその世界』(工作舎昭和52年)の「年譜」によれば、早稲田小劇場の杮落としとして鈴木忠志演出で初演されたのが同じ昭和41年の11月。『オール読物』の「12月」が「12月号」であって、もっと早い月に刊行されていたのだとしても、別役がこれを読んでから戯曲を書いた、にしては時期が早過ぎるようだ。
同じ時期に同名の、同じタイプの街娼、に近い者を題材とした二作品が出たというだけで、どうしても因縁めいた話にはなる。ただ、内容的には、野坂の小説のヒロインは、24歳だが、荒れた生活のために40以上に見える、つまり実際は「少女」ではない悲惨極まりない女。戦争との関係もなく、暗闇でマッチが点っている間だけ陰部を見せるという設定以外は、別役劇との共通点はない。
これも大月によると、こういう女性は大阪には実在したのだという。私が聞いた話としては、東京新宿でも、戦後もかなり後の時期まで出没していた、というのがあるが、今は確かめようもない。】
 Greek Theatre
Greek Theatre悲劇の起源は集団の、歌舞であつたとされる。集団はコロス(コーラスの語源)、歌舞はディテュランポスと呼ばれた。後者はアジア出身の神ディオニソス(ローマ名はバッカス)に由来する。農耕神だつたが、葡萄から酒が造られることが普通になるにつれて酒の神となり、やがて演劇の神ともなつた。この過程のどこかで、大神ゼウスの息子の一人ともされたのは、この神の存在感がギリシャで非常に大きくなつた証である。
劇の成立については、ディオニソスが象徴する酩酊状態の陶酔・狂乱に、太陽神アポロンの理性が奇跡的に合体したもの、といふニーチェ「悲劇の誕生」の説明がある。それに対する内容面での違和感は、本シリーズ第二回で述べた。しかし、劇の形式面に限定すれば、やはり魅力的な見方である。理性は、パフォーマンスにどのやうな箍(たが)を嵌めたのか、考へてみよう。
コロスは、ディオニソスに仕へる者、例へばこの神の眷属として知られるサチュロスに扮して、歌ひ踊つた。やがてその中心部で、一人の男が、語り始める。ローマ時代にはペルソナ(パーソナリティの語源)と呼ばれることになる仮面をつけて、神話や歴史上の人物を名乗ることもあった。これが俳優だが、ヒュポクリテスと呼ばれた。英語のhypocrite(偽善者)の語源である。最も早い段階の俳優(おそらく、兼劇作家)として名を残すテスピスは、「人前で嘘ばかり言つて恥づかしくないのか」と、ギリシャ七賢人の一人にしてアテネの立法者ソロンに詰られてゐる(「プルターク英雄伝」)。
俳優とコロスの間で演じられた「劇」はどのやうなものであつたか。彼はコロスの代表ではない。後代の劇作品だと、その立場の者は「コロスの長」として、俳優に語りかけることもある。つまり、俳優はコロスから独立してゐる。ならば必ず対話(ディアレクティケ)が生じる。例へば、「お前は何で、何をしようとするか」といふやうな問ひかけと応へがあつたらう。ここから劇が、第一歩を踏み出したのである。
やがてアイスキュロスが、俳優を二人登場させ、さらにソフォクレスが三人にした。それ以後、ギリシャ期には、一作品中の俳優の数が増えることはなかつた(ただし、無言の登場人物、兵などの現在のエキストラ、それに子役はノーカウント)さうだ。
その真偽を私が確かめられるはずはない。ただ、このことを気にしながら、特に作品が残つてゐる最古の劇作家(兼俳優)アイスキュロスの戯曲を読むと、西洋演劇の「発展」の跡が目に浮かぶやうな気がする。
アイスキュロスの作物で現在まで完全な形で残されてゐるのは、「オレステイア三部作」を三つと数へて七作。そこでは、いろいろな劇形式が試みられてゐる。
「ペルシャ人」が一番古い形に近いのではなからうか。ここでの実質的な主役は、ペルシャの元老たちに扮したコロスである。題材は紀元前480年のサラミス海戦。ギリシャ悲劇の多くが神話を題材としてゐる中で、例外的に、歴史的な事実、それも、執筆時期から見てごく近い過去の出来事を描く。
ペルシャが大軍を率ゐてギリシャを襲つたいはゆるペルシャ戦争の最中、元老たちは戦の行方を案じてゐる。そこへ登場するのは王妃アトッサ。夫のダレイオス王は既に亡く、まだ若い息子のクセルクスが跡を継いで遠征に出てゐる。彼女のキャラクター(いはゆる性格と、劇中での役割の両方を示すものとして、この語を使ふ)は、コロスと殆ど変らない。悪夢のために戦況に不安を感じながら、待つばかりだ。
そこへ伝令が悲報をもたらす。これを第二の俳優が務めたと思しい。サラミス海戦でペルシャ海軍は完敗、そのために、エウロペの地(ヨーロッパ)に侵入した陸軍もまた、壊滅の危機に瀕してゐる(史実とは少し違ふのは看過)とのこと。
悲嘆にくれたアトッサの語り乃至歌とコロスの歌舞が順に演じられた後、アトッサの祈りに応じて、先王ダレイオスの亡霊が現れる。これは先程伝令を務めた俳優が早変はりで演じたのだらう。彼は、この戦は若いクセルクスの思ひ上がりから生じたもので、もともと無理な企てであつた、もう二度とギリシャを相手に兵を挙げてはならぬ、と宣託をくだす。
これを受けて、アトッサが退場し、コロスが再び嘆きの歌と踊りを披露した後、やうやう逃げ帰ることのできた当のクセルクスが登場し、最後の愁嘆場となる。これは、第一の俳優が、アトッサから変はつたものだらう。仮面のおかげで、一人二役から何役でも、女から男への変化でも、簡単にできる。衣装はどうしたか、コロスの演舞のおかげで、着替へる時間もある。ただし、敗軍の将らしき扮装までしたものかどうか、たぶんこの時代のギリシャには、そのやうなリアリズムは要求されてゐない。
以上で、この劇の三人の登場人物が、いずれもヒーローとは呼べないことは明らかであらう。彼等は劇中、決定的な行動に踏み出すわけでもなく、オイディプスのやうに新たな認知(アナグノリシス)を得るわけでもない。ゆゑに、急展開(ペリペティア)もない。それら「劇的」なるものがすべて終はつた後に登場して、嘆いたり反省したりするばかりだ。
さういふ劇は他にもある。日本の能楽など、たいがいそんなものだ。しかし、描写といふことができる映画ではなく、舞台で、歌も踊りもなかつたとしたら、けつかう退屈するのではないだらうか。西洋近代の、いはゆるストレート・プレイ(せりふ劇)と結びつくには、もう何段階かを経る必要があつた、といふことである。
見逃せない要素は他にある。「伝令」あるいは「使者」の役割だ。固有名が与へられてゐないところからもわかるやうに、彼の性格などは全く問題にされない。重要なのは語りのはうである。もつとも、戦場から命からがら逃げ帰つた兵の一人といふポジションはあるが、それを除けば、まるで吟遊詩人のやうだ。「イリアス」におけるトロイ戦争さながら、海戦の模様を、具に、朗々と語る。
思ふに、アイスキュロスが成し遂げたのは、叙事詩とディテュランポスとの合体ではなかつたらうか。吟遊詩人なら、戦や英雄の物語を直に聴衆に語り聞かせる。今、彼が語る相手は、別の人物に扮した者達だ。観客は、話を聞くと同時に、その話によつて、強い影響を受ける者達(を演じる者達)を見る。詩や歌舞から受ける感銘はそのままだつたとしても、以前と同じ立場にゐるわけはない。
それはコロスと俳優との対話によつて既に始まつてゐたが、ここにはもつと大規模な、歌舞と叙事詩と俳優のそれぞれに明確な立場を与へることになる全体の枠がある。観客はその外側の、メタ(Meta。「間に」「後に」「超える」などの意味)と言はれるに相応しい位置にまで押し上げられたか、あるいは押し込められたのだ。
もう一つ、「伝令」は、外部から、知らせをもたらす者だ。つまり、直接目に見へない「外部」があり、明確に意識される。観客が見るのは、それに対応した、「内部」である。ここにも枠が出来上がつてゐる。舞台が文字通りの枠である額縁(プロセニアム・アーチ)を備へるのはもつとずつと後のことになるが、象徴的な意味でなら、もうできてゐた。

悲劇のヒーローたるに相応しい主人公は、「テーバイ攻めの七将」に登場する。オイディプスとイオカステの子の一人エテオクレス。彼とポリュネイケスとの、テーバイの王位をめぐる骨肉の争いの顛末は、第5回に記した。
この劇はアルゴス軍によるテーバイ攻略戦を描く。全体が壁で囲まれたこの都市国家には、全部で七つの門があり、そこへアルゴスの七人の武将が、各々籤で持ち場を選び、押し寄せる。コロスは戦き怯えるテーバイの女達を演じる。エテオクレス(第一の俳優)は彼女たちを叱つたり宥めたりする。ところへ使者(第二の俳優)が、アルゴス軍の様子を伝へに来る。
使者、実態は物見の兵士、の報告に応じてエテオクレスが適確(なのだらう)な命令を下してテーバイを守り、それを周りで聞いて一喜一憂する「輿論」をコロスが示す。この三者が緊密に結びついて劇は進むが、アクションは城塞都市の、壁の外側で起こつてをり、それは使者の言葉によつてのみ舞台にもたらされる。
だからここでも彼の朗誦だか雄弁だかは決定的に重要である。それはどんな調子だつたか、講談のやうに、「さて四番目の門外に、大音声で呼ばはるは、魁偉なるヒッポメドン、大なる円形の盾を振り回せば威風辺りを払ふなり」といふ感じだつたか、どうかわからないが、何しろ高い調子で観客を引き込んだものだらう。それに対してエテオクレスが、冷静に、テーバイの将から適材を選んで防御に行かせる。
かくして報告=戦況が進み、最後の、第七の門に来たのはポリュネイケスであることが告げられる。これを迎へ撃つのはエテオクレス自身しかない。
と、彼が言うのを、女達(コロス)が止める。他に武将が残つてゐないわけではなし、王自らが戦闘に出る必要はない。何しろ、相手は血を分けた兄弟ではないか。オイディプスが彼らに下した呪ひは知つてゐる。しかしさうであればなほのこと、自ら怖ろしくも厭はしい運命に飛び込むなんて馬鹿げてゐる。
エテオクレスは聞き入れない。禍(わざわひ)を蒙らねばならないなら、(臆病者の)恥辱は避けるべきだ、と。彼は、怒りつぽいといふ父祖伝来の気質に負けるのでも、他者(例へば、神)によつて敷かれた破滅への道を盲目的に辿るのでもない。自分の宿命だと感じたものは必ず全うせねばならぬと感じるほど、自分自身であることに固執する人物なのだ。ここにヒーローがゐる。
「救ひを求める女達」にはヒーローは登場せず、主役はコロスである。五十人の娘(これがコロス)が従兄弟の五十人に求婚されるが、なぜかこの結婚を嫌つて他国に逃れ、その地の領主の庇護を求めるといふ、思ひ切つて荒唐無稽な筋立て。
注目すべきなのは、ここにも「伝令」といふ役名の者が登場するが、彼は従兄弟たちの使ひで、力づくで娘たちを連れ去ろうとし、領主に追ひ払はれる。つまり、悪役である。前述の二作では使者・伝令の語りで伝へられた外部の悪意が、ここで当の伝令の、人間の姿で現れ、コロスと対立して、舞台に目に見える緊張をもたらす。「人間の劇」に向かふ、さらなる一歩の跡が、ここに見出される。
「縛られたプロメテウス」では、のつけに四人登場する。もつとも、そのうちの一人は終始無言。主人公のプロメテウスも、最初は無言だから、吹き替へ役を使ひ、セリフのある二人のうち一人が、先代市川猿之助(現猿翁)ばりの早変はりでプロメテウスになり代はつて、一人取り残された後の長い独白を語る、といふこともできなくはない。が、そんなことをしても全く有害無益な演出だとしか、少なくとも今日の目からは見えないだらう。
劇の主要部は、俳優二人でできるやうになつてゐる。
プロメテウスは、天から火を盗んで人間に与へた神話で有名だが、この作品中の彼は、火のみならず数や文字、さらには薬まで、文明と呼ばれるものの一切を人間に教へ、ために人間を未開のままにしておきたかつた大神ゼウスの怒りを買つて、大岩に縛り付けられる。
そこへ、彼に同情的かあるいは敵対する者(神)が順繰りにやつて来て、対話する。最後に伝令も来るが、ここではヘルメスといふ固有名と、ゼウスの意向を伝へて頑迷な主人公を諭す、明確なキャラクターが与へられてゐる。
コロスはと言ふと、海の妖精たちで、プロメテウスの味方となり、最後に彼とともに奈落に落とされる。
すべてをひつくるめて、俳優二人+コロスによつて構成される劇のお手本のやうなのだが、最初の、やや喜劇的な趣のプロロゴス(→プロローグ)だけさうなつてゐない。
登場するのは主人公の他、彼を引つ立てて来るクラトスとビアー。前者は権力、後者は暴力の意味で、ゼウスの手先、といふより、大神の属性を擬人化したものだ。後者が終始無言なのは、暴力の比喩として適切なのかも知れない。それにしては、権力が少ししやべりすぎるやうな気がするのだが。
それはさうと、最後にへバイトス(ローマ名はバルカン)が出てくる。これはゼウスの息子で火と鍛冶の神、つまりプロメテウスから火を盗まれた張本人なのだが、彼に同情的である。しかし父神の命令はもだし難く、しかたなく(実際に何度もさう口にする)、プロメテウスを鎖で縛り、その鎖を大岩に打ち付ける。
このヘバイトスこそが三人目なのだ。敵対する二者の間にゐて、どつちつかずの曖昧な態度を取る。
それは、劇の主要プロットである敵対関係を外から眺める「第三者」の視点であり、やがてこの関係が揺れ動き、変化することを予兆させる。どう変はるのかは、本作を第一とする三部作(ギリシャ悲劇はたいていさう構成されたものらしい)の残り二つが散逸したため、わからない。
それでも、人間関係(いや、神間関係、だが)を複雑化させる要素が、人間(神、だが)の姿で現れたことには、重要な意味が窺へる。
三部作構成の劇で、唯一完全な形で残つてゐる「オレステイア」になると、劇の結構が複雑になり、それにつれて俳優の役割が増す。
もつとも、第一部「アガメムノン」は「ペルシャ人」とそつくりの雰囲気で始まる。物身の兵士の独白によるプロロゴスの後、コロスが演じるアルゴスの長老達が、戦地に赴いて十年になる王アガメムノンを案じる。トロイ攻めの初端、ギリシャ艦隊が、逆風のためアウリスの港から出て行けなかつた時、ギリシャ連合軍総大将であるアガメムノンが、娘のイピゲネイアを神への生贄にしたことも、彼らの歌の中に出て来る。
やがて伝令が、ギリシャの勝利、アガメムノンも直ちに帰還する、との報告をもたらす。この作の伝令の役割はこれで終はり。コロスは喜んで王妃クリュタイメストラに告げるが、王妃のはうでは物見の兵からの知らせで、既にこれを知つてゐた。彼女は、この劇の初めから終はりまでを見通してゐるただ一人の人物なので、この設定が相応しい。
さて、アガメムノンの凱旋。ここまでで、この劇は半分近くの時間を費やす。のみならず、カッサンドルの神懸りをちょうど中間にして、外部からの働きかけ、それに対する集団(コロス+俳優)の反応、で進行する劇が、名前を持った人物たち相互の関係性に基づくものへと変はる分水嶺が、認められるやうである。
後者の中でも、クリュタイメストラの二重性を帯びた言動は際立つてゐる。彼女は最初優しい言葉で夫を労ひながら、後で殺害する。即ち、単なる悪役ではなく、裏切者といふ、人間関係を根底的に揺さぶり複雑化させる人物なのである。イエス・キリストの物語(福音書)が、神とローマ帝国との軋轢の他に、ユダといふ裏切者の存在によつて、印象深くなつてゐることが思ひ出される。
一番顕著な例としては、夫がいやがるのに、譲らず、玉座への道に高価な布を敷きつめて、その上を歩かせる。大戦争の勝利者にはこれが相応しいのだ、と。これはそのままアガメムノンの死への通路を彩る、禍々しい演出となる。
この後、戦利品として、女奴隷にされたトロイの王女カッサンドルの場となる。クリュタイメストラはアガメムノンと彼女の両方と言葉を交す(もっとも、カッサンドルのときは、彼女が頑に沈黙してゐるので、一方的な語りかけ)のだから、俳優が二人だとしたら、アガメムノンを演じた者がカッサンドルに早変はりすることになる。後で二人の死体が並ぶことを度外視しても(それは、他の、無言の役者でもすむ)、「縛られたプロメテウス」の時と同様、そのやうな演出に好ましい効果があるとは思へない。
【三部作最後の「慈しみの女神たち」では、アテナ、アポロン、オレステスの三名が同時に舞台に出て話す必要があるので、アイスキュロスも後期は、俳優を三人にしたとみなすべきなのだらう。】
カッサンドルは、アポロンに愛され、真正の予言の能力を与へられたが、後に同じ神の憎しみを買つて、その予言は誰にも信じられなくなつた。予言のアイロニーを体現してゐるので、ギリシャ神話中でも有名な人物の一人である。
この劇中で彼女は、クリュタイメストラが去つて、コロスの中に残されると、それまで無言で凝然としてゐたものが、狂乱の態になり、アルゴス王宮に澱む血腥さを訴へ、次いで自らの死を予兆する。ここには俳優がただ一人だつたときの名残があるかも知れない。しかしすぐ後に、自身とアガメムノンとの実際の死が来るので、これ全体が、敷き詰められた布と同様、殺人の衝撃を強調するエピソードとして、劇全体の中に組み込まれる。
殺害者クリュタイメストラはと言ふと、自分がやつたことを少しも隠さうとしない。長老たち(コロス)は彼女を非難するが、それをものともせず、これは殺された娘イピゲネイアの仇討だから、正当だ、と主張する。アガメムノンがギリシャの盟主としての義務を果たさうとしてしたことが、彼女には単なる殺人でしかない。
もっとも、それだけで彼女が夫を殺したのかどうか、疑問の余地はある。アガメムノンの従兄弟アイギストス(彼は彼でアガメムノンを恨む理由があることは、煩雑なので省略)と通じてゐて、彼を次の王にするのだから。真の動機は、愛憎の縺れと権力の奪取だつたのかも。いづれにもせよ、立場を替へれば、人間の行為は様々に評価され得る、といふ世の常が、非常に端的に現れてゐる。
第二部「供養する女たち」で、彼らの前に、オレステスが現れ、父が殺されたことの報復を成し遂げる。ところがそれは、母殺しの大罪を犯すことであつた。その顛末は第3回で述べた。彼は母親に比べると単純な人物だが、置かれた状況が既にアポリアになつてゐて、彼を縛り、決断とさらにその結果、さらにその決着、へと導く。彼の場合、それが即ち、「オレステスとは何か」に全力で応えることなのである。
このやうにして、劇の発動する場が、外部の声に対する応答から、複数(最低三人)の人物の関係内部へと移された。これが必然の道程かどうかはわからない。しかし、西洋演劇が現に辿つた道ではある。

Medea, 1969, directed by Pier Paolo Pasorini
悲劇の中の女性たち。これはけつかう難問である。悲劇は本来男性原理に基づく、といふことはつまり、そこで偉大と呼ばれるものは、明らかに男性の属性であると考へられてゐる。男は、理想的には、運命に翻弄されながらも、能動的に動くべきである。いかなる過酷で無慈悲な運命であらうとも、それを「自分自身のもの」であるとして引き受ける。これがヒーローなのだ。
女性は、本来受動的なものとされ、「運命を引き受ける」ことは原理的にできない。だからまた、悲惨な境遇になつても、ただそれを嘆くことしかできない。さうみなされてゐる。ひとまづさう言つていいであらう。
だが、悲劇作品の内部に限つてみても、これで終はれるほど話は単純ではない。人間世界そのものがさうであるやうに、悲劇もまた、男だけで構成されるわけではないからだ。
女とは子どもを産む性である。これが「女性問題」と呼ばれるものの、太古から変はらない根源であらう。他の動物以上にこのことが、ときにやつかいになるのは、有史以来、人間が家族共同体を作つて生活してきたからだ。それは圧倒的多数の場合、血縁を紐帯の根拠とする。
血縁に基づかない親子関係、日本でいふ養子が、どのやうに行はれ、どのやうに制度化されてきたか、人類史上の多様なヴァリエーションを私はほとんど知らないが、だいたいにおいて、それも血縁関係をモデルとしてきた、とみなしてよいのであらう。
さうであれば、「誰が誰の子どもか」は、常に決定的な重要事とされてきたのもごく自然である。さらに理由を挙げるならば、それはまず個人が人間世界で生きるときの、「自分自身」についての根拠、いはゆるアイデンティティの初源になる。次に、それとうらはらに、親―子関係は、最初の人間関係として、様々な人間関係から成る社会の、秩序の根本となる。
オイディプス神話が、今でも衝撃力を失はないのは、正に後者の理由からである。ある男が、一人の女の子であると同時に夫。ある子どもたちの父であると同時に兄。このやうな関係性の混乱を目の当たりにすると、我々は自分たちの足下が完全に掘り崩されたやうな感覚を味ふ。しかもこれは、物理的に不可能な話ではない。
母子相姦によつて子どもが産まれることは実際には稀であるとしても、正式な夫ではない男の子(即ち、家族外の子ども)を産んで、家族の正当性を脅すことなら、簡単にできるし、またなされてきた。女は、子どもを産むことによって、人類を未来へとつなげるが、その同じ能力で、社会秩序の破壊をもたらすこともできる。
男の中に潜む女への根深い恐怖感はここに由来する。あらゆる文明で、インセストタブーが、さらにその中でも母子相姦が最も強く禁止されてきたこと、またたいていの文明で、女性の「貞操」こそ最も強く守られるべき徳目とされてきたこと、などはその結果であらう。
後者の場合、「守る」主体とされるのは女である。少し考へれば、フェミニストならずとも、その不条理には簡単に気づくだらう。女だけで不貞が働けるわけはない。男は女に、「汚れなく」生きることを求めながら、一方で、女を「汚さう」とつけ狙ふ者でもある(ついでに言ふと、この二者の相克と相乗の効果によつて、男の欲望は亢進するやうになつてゐる)。それでゐて「汚された」女は、恥づべき(誰に対して?)存在とされる。
ただしこの欺瞞は、あながち男を利するものとのみ見るのは当たらない。「弱き者よ、汝の名は女なり」とハムレットは言ふが、本当に弱いのは男のはうである。子どもの父親は本当は誰か、確実に知る手段は男にはない。それでゐて、そこに基礎を置く「家の秩序」を守るやうな顔はせねばならぬのだから。
即ち、自分には最終決定権がないものを、どうにかしよう、せねばならぬ、などとあがくところが、弱さになる。男性原理とはざつとそんなものであり、悲劇が発生する源の一つはさういふところにある。
オイディプスの母にして妻でもあるイオカステは、彼より一歩先にことの真相を知り、知つたとたんに自害してしまふ。残された男は、一人で過酷な運命と向き合ひ、死に所を求めて各地を放浪する。
彼は最も汚れた者だからこそ、忌避されるのと同時に神聖視もされる。この有様を描いたソフォクレス「コロノスのオイディプス」では、かつて予言に翻弄されたこの男が、自分の子どもたち(であると同時に兄弟姉妹)に恐ろしい予言をくだす。テーバイの王家の悲劇は、まだ続く。
オイディプスとイオカステの間には、四人の子どもがあつた。二人の息子と、二人の娘。オイディプスの追放後、彼が予言したとほり、息子二人のうちどちらが王位を継ぐか、争ひが起きる。民衆を味方につけた次男エテオクレスが長男ポリュネイケスを破つて王となるのだが、これを不服とするポリュネイケスは、アルゴスの王と結び、軍を起こして、都市国家テーバイを囲む。
攻防戦の最中、兄弟二人は、自ら剣を取つて城外で切り結び、相討ちになつて、ともに斃れる。戦そのものは、テーバイがすんでのところでアルゴスを撃退して、終はる。
この後テーバイ王となるのは、イオカステの弟クレオン。彼は「オイディプス王」の中で、王位を窺つてゐるのではないかとの嫌疑をかけられると、自分は王族として尊敬を得てゐるのに、王者のやつかいな義務は免れてゐる、なんでこんなけつかうな身分を自ら捨てるものか、と反駁してゐた。これは彼自身に関する的確で、悪しき予言となつた。
王としての彼が最初にやらなければならなかつたやつかい事は、苛酷な命令を下すことだった。王家の兄弟二人のうち、エテオクレスは現に王であつたのだし、国を守るために死んだのだから、鄭重に弔はれなければならない。一方ポリュネイケスは、反逆者なのだから、名誉ある葬儀など行はれてはならず、死骸は、テーバイの城壁の外にそのまま捨ておかれるべきである。元は王子であつたといふ彼の出自は、この場合処置を緩和する理由にはなり得ない。かへつて、王者の義務を蹂躙した者として、重く処罰されるべきであらう。
よつてまた、禁令を破つて、ポリュネイケスを慰霊しようとする者があるなら、直ちに死罪とされる。
この布令に真向うから逆ふ者が現れた。ポリュネイケスとエテオクレスの妹アンティゴネ。彼女は、ポリュネイケスの骸の上にいくつまみかの土をかけることで、彼を悼む気持ちを示した。この簡素な行為によつて、また、アンティゴネは西洋文芸史上最も有名な女となつた。
アンティゴネの動機は、彼女の行為と同じぐらゐ簡明である。家族のうち誰かが死んだとき、これを埋葬するのは、太古、神々によつて定められた掟である。その後に人間社会に生じたいかなるものも、国家でも、やめさせることなどできはしない、と。
クレオンはなんとか姪を説得しようとする。国家に対する忠誠心を発揮した者と、反逆者を同じやうに扱ふならば、国家は保たれない。国家からの命令が簡単に破られるのを見逃しても同様。彼はさらに、さうであるからこそ、国家は外敵から国民を守ることができるのだ、と付け加へてもよかつたであらう。
因みにこれは、現在の民主主義国家でも充分に通じる論理である。例へば、日本の刑法のうちで、刑罰が「死刑又は無期懲役」ではなく、ただ「死刑」だとだけ書いてある罪、つまり、これに該当すると裁判所が判断したら、自動的に死刑が確定する、最も重い罪はなんだかご存知だらうか。それは第八十一条の、「外患誘致罪」。「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」。これこそが、国家に対する最大の裏切り行為だと考へられるからだらう。
ポリュネイケスのやつたことは正に外患誘致であり、現代日本でも最高の重罪とされる。クレオンは、特に頑迷な君主と呼ばれるべき者ではない、といふことだ。
しかし、彼にはアンティゴネを納得させることはできない。当然であらう。彼女は、クレオンにも、彼が体してゐる国家正義にも、好んで敵対する者ではない。それとは関係ないところで、「家族」を成立させようとする者だ。その結果彼女自身がどうならうと、国家がどうならうと、そんなことは二の次の関心事でしかない。
国家は彼女を罰することなら簡単にできる。しかし彼女に罪を認めさせることはできない。アンティゴネとクレオンの拠つて立つ原理は、元来全く次元が違つてゐるのだから。
ソフォクレス「アンティゴネ」で最後に登場する彼女は、死を賭して掟を守る女丈夫ではなく、石室に幽閉されることになった自らの運命を嘆き、テーバイの民の同情を乞ふ弱き者、即ち「女」、になつてゐる。その果てに、自ら縊死する。
この最期とは関係なしに、彼女の名は、父オイディプスと並ぶほどに、ある象徴として、人々の胸に残つた。象徴の具体的な意味は、時代により場所により違つてくるとしても、中心にあるのは常に「家」そのもののイメージであらう。東洋人も西洋人も知つてゐる、郷愁を誘つてやまない懐かしの我が家。アンティゴネが守らうとし、つひに彼女自身がその化身とも見られるやうになつたのは、まちがひなくそれである。
家族の原理と国家の原理の対立について、少し詳しく考へておいたほうがいいだらう。国家とは人工物であり擬制だが、家族は自然な共同体だと思はれがちなことは。
間違ひだと言ふつもりはないが、これは比較相対した上での観念である。共同体である以上、どちらも、人々の手で作られる。さうであれば、人が壊すこともまた、できる。
だから、最小の共同体であつても、保ち守るために、それ自体の論理と倫理が必要とされる。それが常にその成員個々にとつて都合のいいやうに働くとは限らない。即ち、家族がその存続や体面のために、成員のうちのある者に犠牲を要求することもある。
エレクトラは、母の父殺しによつて損はれたアトレウス家の正義を回復するために、母殺しを弟オレステスに要求する。その母クリュタイメストラは、夫アガメムノンが、長女イピゲネイアを殺したことの復讐をしたのだ、と主張してゐる。
トロイ遠征の最初、海がずつと荒れてゐて、軍船を出すことができなかつた。ギリシャ連合軍の総大将であるアガメムノンは、その責任から、海神ポセイドンを鎮めるための人身御供として、自分の娘を差し出したのだつた。これがアトレウス家の悲劇の発端であり、後は家族内部で、復讐の連鎖が続いたのである。
「アンティゴネ」の場合と同じく、ここでもきつかけは国家(的なもの)の公と家族の私の対立だと言へる。それに第一、悲劇の主要登場人物は王侯貴族、少なくとも英雄に決まつてゐるので、どんな場合でも、幾分かは公人である。純粋な家庭内の悲劇(悲劇と呼ばれてもいいとすれば)は、18世紀の、市民劇の登場まで待たねばならなかつた。
しかし、共同体のメカニズムそのものは変はらない。ギリシャ時代でも、現代でも。国家でも、家族でも。
昔、ラジオで、五十代の男が、こんな身の上話をするのを聞いた。彼はリストラされて、無収入の身となつた。すると家族から、「家長としての義務を果たしてくれ」と言はれるやうになつた。「義務を果た」すとは、「金を稼いでくる」といふことであり、彼は保険に入つてゐて、それは自殺でも貰へるタイプなので、早く言へば、「仕事がないなら、死んでくれ」といふことらしい、と。
貴族の、ノーブレス・オブリージュ(高貴な義務)は消えても、「家長の義務」は消え去りはしない。それがあつたはうが得だと思ふ人がゐる限りは。それは同時に、あるおかげで辛い目に合ふ人もまた、一定割合で存在するといふことでもある。
アンティゴネが体現する家族の原理は、上とは全く違ふ。家族であつた以上、彼が何者であり、何をしようとも、無条件で受け入れられるべきだ、と彼女は主張してゐる。ただし、彼が死んだら、といふ最低限の条件はついてゐるやうではあるが。
人は死ねばもう個人ではない。「人類全体の共同性」とでも言ふべきものがあるとすれば、そこに収まるべき者だらう。そして、そこへ送り出すのに最も相応しい者は、人にとつてこの世の最初の共同体である家族を措いて他にない。
国家もまた、戦死者を慰霊する。特に、無名兵士は。その祀りこそ、国家共同体の根源だと、例へばベネディクト・アンダーソン『幻想の共同体』に書かれてゐる。共同体を守るために死んだ、名も知れぬ兵士たち。彼らの生と死とを意味有らしめようとするなら、国家がなければならぬ。
それは幻想だからと言つて、簡単に捨てられるわけはない。いつたい、幻想、別の言葉では物語、以外に人に意味をもたらすものがあらうか。そして、「意味」なしで生きられる人がゐやうか。国家が人々に、生きる糧になるやうな意味を供給するのをやめるまでは、あるいは、より一般的でもあれば具体的でもありさうな物語の供給源が他に見つかるまでは、我々はその存続を認めねばならぬのである。
その反面、「意味」を保つためには、反逆者は排除されねばならぬので、例へば靖国神社には西郷隆盛は祀られてゐない。かういふのもある程度はしかたない。ただ、このやうな明確な原則だけしかこの世にないとしたら、人は必ず、生きづらさを感じるだらう。
家族が祀るのは、現在か過去に家族である/あつた者である。社会的な属性は関係ない。それをすべて失つてもなほ、残るものがある。さう思ふことで、我々は限りなく慰撫される。
アンティゴネは、特に男が、浮世(憂き世)の遍歴の末に、「残るもの」を求めて、最終的に帰るべき「家」を象徴する。「母」ではないので、生殖の生々しさはなく、「姉」のやうに弟を指図することもない、「妹」であることもまた、それに相応しい。
女を「家」の象徴とするのは、男の身勝手に過ぎないかも知れない。しかし、繰り返すと、これは、「家」に関する実質的な最終決定権を女に委ねた、といふことである。男にとつて都合がいいとばかりは言へない。
ギリシャ悲劇の中には、アンティゴネとは真逆に、「家」の徹底した破壊者となる女も登場する。コリキスの王女メディア。
金羊毛を求めてやつてきたイアソンに恋したメディアは、一族に逆ひ、弟を殺してまで、彼の目的を遂げさせ、一緒に故国から逃亡する。彼らの間には二人の子どもが生まれるが、コリントスの王がイアソンを見込んで、娘婿にと望むと、イアソンはあつさり心変はりをして、異郷の女は捨てることに決める。メディアはその復讐に、まづコリントス王と王女とを魔法で焼き殺し、次に二人の息子をも、その手にかける。
メディアは魔法使ひの悪女として古来知られてゐたが、ここまでやらせたのはエウリピデス「メディア」の独創であるらしい。しかし、より重要なポイントは他にある。この劇では、最後の決定的な行為に至るまでの彼女の逡巡と苦悩に焦点がおかれてゐる。
メディアもまた妻であり母であった。つまり、「女」だった。それがそのまま、罪のないわが子を殺す鬼女になる。本当に恐ろしいのは、超自然の魔などではなく、人そのものなのである。この真実こそ、2500年の時を越えて、我々の心を揺さぶる力になつてゐるものだらう。
論理的には、この子殺しには辻褄が合はないところがある。メディアは、ことを起こすに当たつて、世継ぎのないアテナイ王に、自分の知識で子供を授けてやらうと申し出、引換へに、彼の庇護を求めてゐる。取引はうまくいき、堅い約定(破つた場合には呪ひがふりかかるといふ担保付きの)をとりつけることができた。それなら、コリントス王父娘殺害後、二人の子をともなつてアテナイへ逃れることも可能だつたはずである。イアソンからすれば、新たな結婚はなくなり、古い家族は失ふ、といふ結果は同じではないか。それで充分に復讐は果たせてゐる。
我々が納得するのは、論理よりはむしろ感情の次元でである。イアソンとメディアのかつての親密な関係から生じたものの完全な否定。先にそれを捨てようとしたのは男のはうであつたのだけれど、それでもやつぱり男は、深い打撃を受けざるを得ない。男といふものは、一度捨てたものであつても、自分を待つてゐてくれはすまいかと、自分には最後に帰るところが残されてゐて欲しいと期待する、そこまで身勝手な生き物なのだ。
メデイアはここを痛撃して致命傷を与へる。「家」に関する最終決定者として、保ち守るのではなく、憎悪と絶望以外のすべてを無に帰す女。そのやうな者として、彼女は現在に至るまで、人々の悪夢の中に棲みついてゐる。

ギリシャ時代から幾世紀かを経て、神といへば、人間とはまるで次元の違ふところにまします者といふ信仰がヨーロッパで一般的になると、悲劇もまた、より直接に人と人の「あひだ」で起きるものを題材とせざるを得なくなる。そこで「誤解」は大きな役割を果たす。
誤解(misunderstanding)とは何か。理解(understanding)しそこなふ(mis)ことである。人と人のあひだではそれは、コミュニケーションの「意味」を取り違へることを指す。ディスコミュニケーション状態が続いて起こる。そこで人は、「私」は「あなた」とは違ふ、と痛感させられる。即ち、人間の個別性が際立つ。その結果、人間関係が緊張し、揺れ動く。これはそのまま、劇、と呼べさうである。
とはいへ、単なる思ひ違ひによつて右往左往するのは、悲劇のヒーローには相応しくないと考へられてゐたのだらう。古代では、さういふ者は喜劇の主人公になつた。
しかしまた、悲劇と喜劇とはそんなに遠いものではない。少し目のつけどころを変へれば、滑稽なものが悲惨にも、またその逆にも、見える。さういふものだ。
シェイクスピアは、「間違ひの喜劇」以来、実際にはありえないやうな誤解(双子を使つた、人物の取り違へなど)に基づいた喜劇を多数書いてゐる。悲劇ではさすがにそれは使へなかつたが、もつと深刻な認識の違ひなら、ほとんどすべての作品に見られる。
「マクベス」は、予言の言葉の曖昧さ、その二重性(double sense)そのものを劇の動力にしてゐる。オィディプスなど、ギリシャ悲劇のヒーローが躓いたものが、ここでは最初から企まれたものとしてある。このやうな予言をもたらすものは、もはや神とは呼ばれない。「魔」である。それでも、予言の性質は変はらない。結果だけを、正確に告げるのだ。
多少の工夫はあつて、一番有名な「バ―ナムの森がダンシネーンに向かつて来ない限り、マクベスは滅びない」は、「バーナムの森が……来るとき、マクベスは滅びる」を二重否定で表現してゐる。かう言はれると、最後だけが印象に残つて、「マクベスは滅びない」といふことだと思ひ込むのは、なるほど、ありがちな人間心理である。それだけマクベスは、神話的な英雄から、普通の人間に近づく。
彼がからうじてヒーローであるのは、予言の真の意味が明らかになつた後でも、戦ひをやめないからだ。
「バーナムの森がダンシネーンに向かつて来やうと、敵のお前が女の胎から生まれた者でなからうと、俺は最後まで戦ふぞ。盾などは捨てる。かかつてこい、マクダフ! 先に『待て、もういい』と言つたはうが地獄行きだ」。
この絶望的な戦ひは、まちがひなく彼のものである。即ちここに、他の何者でもない、彼自身がゐる。
「オセロ」では、主人公を致命的な誤解に導くのは、超自然的な魔ではなく、邪悪な意図を持つた人間である。「リア王」になると、意図と呼べるほどのものさへなく、人の世によくある単純な追従を、主人公がそれと見抜けなかつたところから、国家全体の破滅に到る大騒動が始まる。
それには一応理由があつて、彼らは、他人の上に絶大な権力を揮へる高い身分の者たちなので、単なる思ひ違ひが、一個人の範囲をはるかに超えたところまで被害を及ぼしてしまふのだ。さうでなければ、シェイクスピアも、他の誰も、これを悲劇の題材とすることはできなかつたであらう。
それはさうでも、彼らの誤つた認識の下に始めた行為によつて、最も影響を与へられるのは彼ら自身であることは疑へない。
そんなのは当たり前だ、と思へるかも知れないが、さうでないことは現実にいくらもある。リアが、三人の娘のうち上の二人に領土を譲つた直前か直後に、安らかな死に見舞はれたとすれば、彼の誤解によつて傷つくのは、追従を言ふことを潔しとしなかつたために冷たく扱はれた末娘のコーデリアと、彼女を支持する人間たちだけといふことになるだらう。例へばそんなやうなことは、けつかう起きるものだ。
別人の悲劇だと、ラシーヌ「フェードル」では、テゼー(テセウス)は新しい妻フェードル(パイドラ)と息子との間に起きたことについて偽の情報を与へられ、その誤解に基づいて罪のない息子を呪ひ殺す。フェードルは、義理の息子への恋慕と、その結果彼を死なせてしまつたことへの自責の念に耐えきれず、自害する。一人残されたテゼーは、嘆くことしかできない。誤解し、決定的な行為をしたのは彼だが、彼は悲劇のヒーローではあり得ず、むしろ、妻と息子の悲劇の外側に置き去りにされた男である。
だから、ヒーローの資格は、彼が何に基づいて何をしたか、に掛かつてゐるわけではない。その動機はなんであれ、彼が現にしたことの結果を、全身で受け止めることこそが要件なのだ。オセロは自死によつて、リアは狂乱によつて、自らの誤つた動機による行為の結果に対応する。彼らが「責任をとつた」ことになるのかどうかは難しい。しかし、彼ら自身と、彼らの行為とを改めて結びつけるやうな結末はつく。完結した悲劇が、そこに立ち現れるのである。
いはゆるシェイクスピア四大悲劇のうち、最後の一つについてこれを見ると、どういふことになるだらう。主人公の境遇はオレステスとよく似てゐる。彼は身内の者によつて殺された王を父に持つ。そして母は、父の殺害者と結婚してゐる。これだけの条件がそろつたら、彼がやることは単なる復讐劇では終はれない。
と、我々は予測する。劇の観客の特権は、実際は自分よりはるかに優れてゐるはずの人物が見通せない未来まで見通し、彼らがドラマのただ中にゐるがゆゑに斟酌できない事情まで考慮に入れることができる点だ。アリストテレスは、劇は叙事詩に比べると、限られた場所で起きた、より短い時間のできごとを描くので、鑑賞者が全体を見通しやすいのが長所だと言つてゐる(「詩学」)。
ならば我々は、観客席に坐つた以上、かう思ふ権利があるのだらう。
「なるほど、こんな複雑な事情なのでは、ただ父親の仇を討つだけでは終はれないな。もつといろんな葛藤が生じるのだらう。よろしい、それを見せてくれ。全く予想もつかない事件が起きてもいつかうにさしつかへない。でも、最後には、ああ、かうなつたのはかういふ事情からなのだな、と必ず納得させてくれよ」。
これに反して、最後まで見たのに、見通せない事情が劇の中にまだあると感じられたら、我々はひどく居心地の悪い思ひをしなければならなくなるだらう。
もっとも、現代では、観客の、当然だつたはずのこの特権に挑戦するのだ、などと言つて、敢えて見通しを与へないままに劇を終へる劇作家も珍くない。さういふ時には、我々は別のやり方で納得する。わけのわからない劇世界の向かうに、世界をそのやうなものとして提示したがる作者の、心情を読み取るのである。それで感動ないしは満足が得られるのかどうかまではわからない。ともかく、劇がイベントとして、興業として成り立つ以上は、劇を作る側と受け取る側に、なんらかの黙契が存在してゐなければならない。それは確かなはずだ。
「ハムレット」の見通しの悪さは、たぶん上に述べたやうなこととは違つてゐる。主人公は、何をどうなすべきか、最後の最後になるまでよくわかつてゐないやうだ。それだけなら、劇の世界でも物語の世界でも、よくあることだ。しかし、主人公とともに我々観客も、もしかすると主人公以上に、よくわからないまま、置き去りにされるかのやうな感覚がある。そんな劇と、我々はどのやうな黙契を結べるのだらうか。
たぶんそのために、「ハムレット」は古来多くの批評家を悩ませてきた。いつたいこれは悲劇なのだらうか。
人と人のあひだで、彼のものとされた役割を担ふこと、さうすることによつて、他の誰でもない、彼自身になること、自分の目にも他人の目にも。それが悲劇のヒーローの最低条件であるはずなのだ。役割は、苛酷なものほどよい。悲愴な感じが強まるから。オイディプスは知らぬうちに父を殺して母を娶り、しかも王者の義務として自らそれを明らかにする。オレステスは王の一族に連なる者の義務として、母殺しの大罪を犯す。このやうな並はずれた「義務」を背負ひきれる者が果たしてゐるのだらうか。ゐてもらひたいものだ。その願望と可能性をこそ、悲劇は示すのである。
現実に生きてゐる者であれば、次のやうに言つたところで、我々は同じ人間として、人間の弱さを知るなら、決して非難はできないはずだ。
「オレは好きこのんである者の子どもとして生まれてきたんじやない。それなのに、お前はだれそれの子だから、当然何々をすべきだとか、すべきではない、とか、すべてオレ自身のせゐでもあるかのやうに言はれるなんて、全く不当だ」
これで役割から逃げ出す者は、つまり平凡な人間である。とはいへ、こんな言ひ草がけつかう普通に聞かれるやうになつたのは、比較的近年のことであるかも知れない。「お前はAだ。だからaをやるべきだ」と言はれるのに対して、「オレは本当にAなのか。オレがaをやらねばならない理由は本当にあるのか」と問ひ返すのは、他人にばかりではなく自分にも問ふのは、自分自身に対する意識、即ち「自意識」と呼ばれ、優れて近代の産物だと考へられるから。
ところで、ハムレットはかう言ふ。
「この世の関節がはずれてしまつたのだ。なんの因果か、それを直す役目を押しつけられるとは!」
王子である彼自身に与へられた役目を、「なんの因果か」と、理由の分からぬもののやうに言ひ、「押しつけられた」とそれを担ふことへの不満も口にする。彼は「近代的自意識」の持ち主なのだらうか。さうも見える。それはこの端倪すべからざるヒーローの、特質の一つである。
最初に亡霊が城壁に出現する。急死した先王ハムレットそつくりの姿をしてゐて、いかにも不吉だが、このときは見た者に予兆をもたらすだけで、何も告げない。
次に、舞台は、一夜明けて、新王クローディアスの戴冠式直後の場面になる。ここで初登場する、父と同じ名を持つ王子は、昨晩の予兆も知らぬまま、不満をかこつてゐる。
父の死の直後、父の弟、即ち彼の叔父が、王位と、先王の妃にして彼の母ガートルートの両方を手に入れた。「オイディプス王」と同じ設定。王が急に変はつた場合、王妃はそのままで、つまり新たな王と再婚する、といふことは、古来どれくらゐ実例があつたかは知らない。しかし、先王の所有物をそつくり引き継ぐのが次の王だとすれば、妻もその中に含まれるのも、女性の人格があまり尊重されない時代にあつては、自然なことに思はれたらうとは想像がつく。
ただ、さうだとすると、「新王は、妃の夫にはふさはしくない」と言へば、それはそのまま、王たるに相応しくないことになるだらうか。多少の疑問は残るが、シェークスピア劇の鑑賞では、細かいことにこだわるのは禁物であるやうだ。ともかく、王子が最初に口にする不満はそれである。
「おなじ兄弟とはいふものの、似ても似つかぬあのやうな男と。それも、たつた一月。(中略)おお、なんたる早業、これがどうして許せるものか……いそいそと不義の床に駆けつける、そのあさましさ! よくないぞ、このままではすむまいぞ、いや、待つた、こればかりは口が裂けても、黙つてをらねばならぬ」
この最初の独白に、既に、ハムレットの真骨頂が余すところなく示されてゐる。
ガートルートは「不義の床」に行つたわけではない。前夫の死後一ヶ月で再婚するのは、当時の、そして今も、一般的な風習からして、早すぎるとは言へても、いはゆる不貞と同じだとは誰も言はない。ハムレットにはそれも許せない。母が、よりにもよつてあんな男と。それを皆が認め、祝ひさへするとは。彼は、「このままではすむまいぞ」と物騒なことまで口にする。
この段階では誰も、劇中の人物たちも劇を見てゐる者たちも、この感情は、息子のものとして多少は共感できるとしても、正義に適つたものだとは言はないだらう。それはわかつてゐるからこそ、「口が裂けても、黙つてをらねばならぬ」のだが、その分彼の怒りは内攻し、その矛先は、だらしない母ガートルードをはるかに超えて、世界全体にまで向けられる。
「この世の営みいつさいが、つくづく厭になつた」
と、この独白の最初に彼は言つてゐた。この男の感情は、登場したときから過剰なのである。
その夜ハムレットは、亡霊から真相を明かされる。
新王こそ、先王を暗殺した張本人なのだつた。先王の霊は、仇討を依頼する、ただし、母を責めてはならぬ、と条件をつけて。
今やハムレットの憎しみは明確な理由と対象が与へられた。あとはまつすぐに、使命を果たせばよい。オレステスは、仇討の相手が実母だつたにもかかはらず、さうしたのだ。他人からみてもそれが正義と言へるのかどうか、考へるのは他人に任せればよい。「オレステイア三部作」はそのやうな道筋を示してゐる。
しかしハムレットは、この道を辿るにしては、複雑なものを抱へ過ぎてゐる。彼は、非道な方法で新王となつたクローディアスその人より、非道な王位継承を結果的に良しとしたデンマーク王国全体に疑惑の目を向ける。ガートルートはその代表者なのである。
彼女を初め、誰もが真相を知らないのだから、で済む話ではない。王の人格は王国全体の性質を決定すると考へられるのであれば、王たるに相応しくない男が、王に相応しくない方法で現に王位についたデンマークは、それだけで腐つた国と呼ばれてよい。
さらに話を複雑にする要素があつて、それはハムレット自身がデンマークの王子なのだから、腐つた体制の一翼を担つてゐる、とも見られることである。これはまた、ハムレットの、それまでの悲劇のヒーローとは違つた、特殊な位置である。
オイディプスもオレステスも、生まれからすれば正当な王位継承者なのに、自力で回復するまでは、継承権を奪はれてゐた。ハムレットは、先王の死後すぐに王位を継ぐべきであつたのに、クローディアスに妨げられたのだらうか。そこはよくわからないが、前述の戴冠式直後の場で、他ならぬクローディアスが、ハムレットこそ自分の次の王となるべき者、と宣言したのである。あるいはこれは、彼がガートルートを我がものにするための条件だつたのかも知れない。
これらを勘案し、さらに、知らなかつたではすまいない、といふほどに厳しい見方をするなら、ハムレットは、クローディアスとガートルートの次ぐらゐには、責任を問はれるべき存在だとされねばならない。
もう少しさかのぼつて考へることもできる。悲劇のヒーローとは、状況が強いてくる「お前は何者だ」といふ問ひに、全身で向き合ふ者である。
では、ハムレットとは誰か? デンマークの王子だ。誰が、どのやうにしてさう決めたのか? 先王ハムレットがノルウエーのフォーチンブラスと争ひ、一対一の決闘によつてその地位を得た。それを息子に譲るのなら、自然なこととして、全員ではないとしても(これまた父と同じ名を持つフォーチンブラスは、デンマークの王位奪還を狙つてゐる)、多くの者が納得し、何よりハムレット自身が納得し、「お前は何者だ」の問ひは、彼に関する限り、そこで終はつたであらう。
その継承の間に叔父が割り込み、母もそれを良しとしてしまつたために、問ひは続いた。そして、続けば続くほど、この問ひは呪はしいものになつていかざるを得ない。
ハムレットは、問ひに答へられぬままに、問ひ返し続ける。お前は何者だ。女郎屋の亭主か。違ふのか。ではせめて、その程度には正直であつてほしいものだな。お前は何者だ。美しい女か。では、亭主に角を生えさせぬやうに、尼寺へ行くがいい。デンマークとは何だ。牢獄だ。世界は牢獄だと言つていいのだらう。しかしデンマークは、中でも、最もたちの悪い牢獄だ、少なくとも俺にとつては……。
彼は諧謔を弄んでゐるのか、あるいはさう見せかけて、彼にとつての真実を伝へようとするのか。おそらく自分にも定かではないだらう。どちらにもせよ、周囲にとつては、自分で持て余さざるを得ない自分を、臆面もなく人前にさらすような輩は、気違ひとしか扱ひやうがない。身分が高いために、捕へてどこかに押し込めるやうなことは簡単にできないのが厄介なところである。
別の見方では、本来は世直しに着手すべき立場の者としては、ハムレットはひどく女々しいふるまひをしてゐる。彼自身も時にさう感じ、自分を叱咤する。
とはいへ、現実に復讐に着手する前に、冷静に考へて、やつておくべきことはある。亡霊の告げたことは真実かどうか、確認しなければならない。彼はマルティン・ルターが教授をしてゐたこともあるウィッテンベルグ大学で学んでゐたのだから、幽霊の存在にはもともと懐疑的であつたはずだ。
かくて第三幕の、宮廷内での芝居の上演がある。芝居の題名は「ゴンザーゴ殺し」。ゴンザーゴと呼ばれる王が暗殺され、その犯人が、遺された妃を、言葉巧みに誑かし、まんまと我が物とする、といふ筋だ。ハムレットはそこに新たな科白を追加し、亡霊から聞いた、実際のできごとへと芝居をより近づける。この芝居を見たときの王の様子から、彼が実際に罪を犯したものであるかどうか、窺はうとするのが、一応、目的だとされる。
しかし、王夫妻といつしよに、大勢の廷臣たちの前で演じられ、さらに芝居をよく知つてゐる野次馬よろしく、ハムレットが解説的な野次を飛ばすものだから、この上演は、彼がやつてきたことの集大成、即ち、諧謔を弄ぶやうに見せて、彼だけが知つてゐるデンマーク王国の醜聞を暗示するものとなる。
さらにそれ以上のものも潜んでゐるやうだ。劇中の王を殺すのは、王の弟ではなく、甥になつてゐる。これは何を示すのか。自分がこれから叔父に対してなさうとすることを予言してゐるのか、それとも、先の王の殺害に関しては、自分もまた完全に潔白なわけではないと言ひたいのか。
我々はかういふところに、この複雑な人物の核心を見るべきなのだらう。ギリシャ悲劇にも、シェイクスピア劇にも、予言に拠つて行動し、予言に因つて滅ぶヒーローはゐる。オイディプスの場合でもマクベスの場合でも、予言とは彼らの隠れた欲望を外在化させて見せたものと考へることもできる。だからわかりやすい。
一方ハムレットは、ヒーローであると同時に、自分自身とデンマーク全体の、予言者でもあるのだ。「オレステイア三部作」第一部の「アガメムノン」に登場するカッサンドルは、アポロンから正真な予言の能力を授けられたのだが、彼女の言葉は狂気のものとしか人々には受け取られない。この事情は、ハムレット自身についてもいくらか当て嵌まる。
ただし、あくまで「いくらか」である。すべてが見えてしまつた者は、ヒーローたり得ない。もう何も行動する必要がないからだ。ハムレットの言動にはいかにも予言者めいたところがたくさんあるが、彼自身がどこまで本気でさうしてゐるのか、明らかではない。あるいは、行動するために、敢へて明らかにはしないのかも知れない。
芝居の後、ガートルートに呼ばれたハムレットは、彼女の部屋へ行く途中で、自分の犯した罪の恐ろしさに打ちのめされて、祈りを捧げるクローディアスを見る。今ならたやすく彼を殺せる。さう思ふのだが、実行に移せない。父は罪を告白する前に殺されたので、今煉獄の炎に焼かれてゐるのに、祈つてゐる最中のクローディアスを殺したのでは、こちらは真直ぐに天国へ行つてしまふ、あまりに釣合ひが取れないではないか、といふのがその理由である。
さうしてハムレットが去つてから、我々は、クローディアスが、「心をともなはぬ言葉が、どうして天にとどかうぞ」とひとりごちるのを聞く。ハムレットの見込みは大外れだつたのだ。しかし観客は、彼の迂闊さを嗤ひはしない。これだけ大掛かりな復讐劇が、ただの偶然によつて幕が降りたとしたら、それこそ納得しやうがないのだから。
次に、ガートルートの部屋で、ハムレットは不実な母をさんざんに詰り、あはや殺しさうにさへなるので、壁掛の後に隠れて様子を窺つてゐた者がつい大声を出してしまふ。ハムレットは、壁掛の上から、その者を剣で刺し殺す。それは王か、と見れば、かつて彼が宿屋の亭主並みに正直であつてくれれば、と諷した、クローディアスの忠臣ポローニアスだつた。こんなところでクローディアスが死んだのでは話にならない、いや、芝居にならないのは前と同じ。
それにしても、ポローニアスは、自分は「直接、まつすぐを狙わず、間接かつ適確に的を射当てるコツを知つてゐる」と自負してゐた。それは本当はハムレットの特技だつたやうだ。彼はいつもことごとく的を外してばかりゐるやうに見える。さうしながら、一歩一歩、最後の大目的、つまり、彼自身とクローディアスを含めて、先の王殺しに関りを持つ者全員を犠牲とする、デンマークの大浄化へと近づくのだから。
ハムレットは境目に立つ人物なのだらう。彼は、たやすく亡霊や、そのお告げを信じることはできない。しかし、窮極のところで、自分の運命を、自分が他の何者でもない、自分自身にしかなれない瞬間がいつか来ることを、信じてゐる。
「一羽の雀が落ちるのも神の摂理。来るべきものは、いま来なくても、いずれは来る――いま来なければ、あとには来ない――あとに来なければ、いま来るだけのこと」
我々にとつて、亡霊も予言も、もはや信ずるに足るものではない。それでも、運命がどうしたかうしたとは口にするが、それが何なのかは、皆目わかつてゐない。私にももちろんわからないが、なんとなく、次のやうなことは言へさうな気がする。
「自分とは何か」の問ひには、つひに答へは得られないだらう。もしこの問ひがもはや尽き果てた、と感じられるときが来たら、そこで我々は自分の運命と、「自分自身」と出会つてゐるのだらう。いずれにしても、道は真直ぐであるはずはない。我々がこの世の中に生きるとは、人と人のあひだの、隘路を通ることでしかないのだから。あつちにぶつかり、こつちにぶつかり、躓いたり転んだりした果てに、いつかそのやうな瞬間が訪れると期待できるものだらうか?
確信は持てない。我々は迷信をなくし、次いで「神の摂理」への信頼をもなくしたハムレットなのである。現代世界にも悲惨は満ち溢れてゐる。けれどそれから悲劇はもはや生まれない。悲劇といふジャンルは、人間が、「私は私だ。私は私以外の何者でもない」と断言できるほど偉大になり得る可能性に根拠を置いてゐる。さういふものは運命観といつしよに、とうに見失はれてゐるからだ。
 蜷川幸雄演出「オレステス」、平成21年シアターコクーン
蜷川幸雄演出「オレステス」、平成21年シアターコクーン次のやうにも考へられるであらう。「お前は何者か」には、なるほど、究極の解答はない。それがわかつてゐても、この問ひがやめられないのは、人が、人と人の「あひだ」で生きなければならないからだ。完全に孤立した、一人だけの人間といふものは、もしゐたとしても、彼がなんであり、何をなすか、は全く問題にならないであらう。
言ひ換へると、個人の「意味」は、なんであれ、「あひだ」にしか見出されない。「あひだ」は、個人に先行してゐる。それなら、人間の本質、と呼べるやうなものもまた、「あひだ」にしかないことになる。「人+間」がhuman beingそのものの意味にもなる日本語は、この点たいへん示唆的である。
ただし、個々人がゐないとすれば、「あひだ」がないこともまた、単純な事実である。「あひだ」の意味は、それを成り立たせる両端の個人(あるひは、集団対個人)のありかたによつて、いかやうにも変はつていく。それが、「お前は何者か」の問が立ち現れてくる所以である。だからこの問は、戯れではないとしたら、必ず「私(たち)にとつて」が前提になつてゐる。会社にとつて、お前は何か。家族にとつて、お前は何か。国家にとつて、お前は何か、など。
また、「すべきこと」/「してはないらないこと」を定めるのもまた、「あひだ」に国家などの枠を嵌めた社会である。人と人のあひだが一定不変ではないとすれば、社会もまた一定不変であるはずがない。それなら、「すべきこと」/「してはならないこと」の基準もまた、変はる。同じ行為が、善になるときも悪とされるときもある。後者の場合、社会は、どういうふうに個人に責任を負はせられるのか。個人は、どういふふうに責任を取る「自分」を示せるのか。
ギリシャ神話の体系の中で、テーバイ王家の悲劇と並んで、アレゴスの、アトレウス家の人々の物語はきはめて有名で、多くの悲劇作家によつて取り上げられた。しかし、その中心人物オレステスは、前者のオイディプスほどには人の記憶に残つてゐない。どちらかといふと、彼の姉のはうが知られてをり、「エレクトラ・コンプレックス」なる術語にもなつてゐる。
彼らの父親は、トロイ攻めのギリシャ連合軍総大将アガメムノン。戦争が終つて凱旋帰国してから、従兄のアイギストスと通じた妻(エレクトラとオレステスの母)クリュタイメストラによつて殺害される。エレクトラは、父親のために、母親への復讐を果たさうとする。オレステスはその道具に過ぎない、わけではないけれど、なんとなくそのやうな印象が持たれてしまふ。
別の神話で、彼はエレクトラの上の姉イピゲネイアに助けられたりもする。彼の仇討ち劇のきつかけを作り、事実討たれる母はもちろん女。彼女を殺害したことで今度は彼が復讐の神(悔恨の念を擬人化したものと言はれる)につきまとはれるのだが、これは三人の女の姿をしてゐる。最初から最後まで、女によつて運命を決められる男であるやうだ。
それ以上に次のことは重要である。オイディプスは、自分では知らないうちに母親と交るのに、オレステスは、自分が誰を殺すのか、事前に充分に知つてゐる。まつしぐらにさうするわけではない。アイスキュロス「供養する女たち」でも、エウリピデス「エレクトラ」でも、事前に戸惑ふ様子は描かれてゐる。いかにも、アルゴスの正当な王子として、父の仇は討たねばならないだらう。しかしそのために、母を殺した者になるのはどうか。この迷ひそのものはもちろん正当な、悪く言へば平凡なものである。そのために、仇討ちの実行へと彼の背中を押す者として、エレクトラが必要とされた、とも見ることができる。
しかし、ひとたびやつてしまつた以上は、彼はある原理「不当に殺された父の仇は討たねばならない」のために他の原理「母を殺してはならない」を明白に捨てたのであつて、それ以外の者ではありやうがない。事前にどれほど躊躇しようと、事後にどれほど後悔しようと、彼が現に為した行為、母殺し、の前ではものの数ではない。周囲すべてにさうみなされるので、彼自身もまた、自分のやつたことの正当性を、少くともその不可避性を主張する。一方の正義を代表するのがオレステスなのであつて、その単純明快さが、彼の人物像から受ける印象を弱めるのだ。
オレステスのしたことは正当か否か。悲劇作品の中にもいくつかの論点が見られる。エウリピデス「オレステス」に出てゐるのはとりわけ興味深い。クリュタイメストラの父、即ちオレステスの祖父テュンダレオスが次のやうに言ふ。
「誰かが誰かを殺す。殺した者は、殺された者の復讐のために、他の誰かに殺される。そのまた復讐のためにその他の誰かも殺される……などといふことが続いたら、この復讐の連鎖は果てしなく続くだらう。さういふことにならぬやうに、法があり、非道なことを裁くのは個人ではなく、法だといふことにしたのだ」
これは、仇討ちなどの私刑を禁じた、近代法の精神に合致したものだと言へやう。ところが、これを唱へたテュンダレオスは、オレステスを憎むあまり、彼に死刑の判決がくだるやう、審理に当つた人々を煽動するのだ。つまり彼は、法の厳正中立性、それによる正義の実現など、本当は信じてゐないのである。
法による判断が、さうでないものより優れてゐると考へられる根拠は、一つしかない。それは非個人的だといふところだ。現実の行為以前に、「してはならないこと」が定められてゐて、それが適用される(罪刑法定主義)のだから、ある人(々)の時々の感情や都合によつて左右されることは少い分、「公正」と呼ばれるものに近づくだらうと期待されるわけだ。
夫殺しと母殺しと、どちらが罪が重いか、わかつたものではないが、とりあへず、オレステスは憎いので、ここは後のはうが重罪だとしてをかう、などといふことになつたら、個人への好悪の念によつて判断が左右されることになり、ついには「してはいけないこと」の概念も常に揺らぐ。まだしもそれは防げるなら、こちらを採る意味はある。
それでも、人が判断する以上、感情が完全に消えるわけはない。判断する人間の数を増やせば、その弊害は減るだらうと思へはするが、ゼロにはならない。エウリピデスが伝へてゐるアレゴスでの裁判では、判決は参加者の多数決によつて決まつたらしい。すると、煽動者の暗躍する余地も高くなる。
その状態で人を罪に落とすのはやはり問題がある、といふことで、現在のアメリカの陪審員制度は、全員一致の評決のみを有効としてゐる。それでも全く公正といふわけにはいかず、裁判は、陪審員にどういふ人間が選ばれたか、その時点で決定する、などと言はれてゐる。
結局法は、究極の正義や公正を保証するものではなく、まして個人の救済を目指すものではない。さういふことをこの世で完璧に実現することは不可能だ、といふ断念のうへで、それでも「してはならないこと」はあるはずだといふ信念と、社会の秩序は守られなければならないといふ実際上の都合、この二点の便宜のために定められるのが法なのである。二つの対立する正義が登場した時、どちらが上か、などと決定できるやうなものではもともとないのだ。
ことはアテネで改めて裁判にかけられる。アポロンがさう命じたのだ。この神は、このたびは予言だけでなく、オレステスに復讐を命じ、その後彼を庇護するまでの積極性を見せてゐる。
アテネにはアポロンの姉アテナがゐる。アポロンは、知恵と防衛を象徴し、アテネといふ都市国家の名前の由来ともなつたこの女神に、オレステスの裁きを委ねたのである。アイスキュロス「慈しみの女神たち」にこの顛末が描かれてゐる。エウリピデスはこの作品を知つてゐて、アレゴスでの裁きとそれから起こる騒動を、これの前史として、創作したのだ。
さて、最終決着を任されたアテナだが、これはもう彼女一人の手には余るとして、アテネの賢明な市民たちから成る陪審員団を招集する。彼らは劇中一言も発せず、劇の大半は、検事役の復讐の女神たちと、弁護士役のアポロンの論戦によつて占められてゐる。
女神たちはかう主張する。「我々は非道な行ひを為した者をどこまでも苦しめるのが役割なのであつて、もしオレステスが許されるやうなことがあれば、自分たちの存在意義がなくなるばかりか、人倫が地に墜ちることにならう」
これにはオレステス自身が反論する。「非道を責めるといふなら、なぜクリュタイメストラの罪を不問に付したのか」。女神たちは答へる。「彼女とアガメムノンの間には血の繋りがなかつたからだ」
夫婦関係より、血縁関係のはうが上であり、母殺しは夫殺しより重罪だといふわけだ。今も賛成する人はゐるかも知れない。しかしさうだとしても、夫殺しもやはり罪なのであれば、それを放つておいてよいとは言へまい。クリュタイメストラがしかるべく罰せられてゐたとしたら、オレステスが手を汚す必要もなかつたのだ。その情状を無視して、彼だけを罰するのは、やはり片手落ちといふものだ。
一方、アポロンは次のやうに論じる。「血縁関係の中で、重んじられなければならないのは父とのそれであつて、母との関係は二義的なものである。ゆゑに、父を殺した母を仇敵としたオレステスの行為は正当である」。こちらの、父系のみを重んじる原理は、先のオレステス有罪論以上に、現代で素直に受け入れられることはないであらう。
選ばれたアテネの市民たちは、どちらの側からも、致命的な欠陥を含む理屈を聞かされるだけではなく、自分たちの言ひ分を通さないなら、以後この市を呪ふぞ、などと脅しまでかけられてから、評決に臨む。結果は、有罪と無罪と、同数の票になつた。
その場合どうするかは、アテナはあらかじめ言明してゐた。彼女自身の一票によつて、すべての決定とする。そのうへ、「自分には母はなく、父ゼウスの頭部から直接生まれたのだから、アポロンの父系優先主義に賛成する」と、つまり「ひいき」するとまで公言してゐたのだつた。かくてオレステスは無罪となる。
これは欺瞞であり、それくらゐなら最初からアテナ一人の判断でことを決したはうがましだつたらうか。必ずしもさうは言へまい。肝心なのは形式なのである。一人の人間(この場合神も含まれる)の意向ではなく、多くの人間が参加したうへでの決定のはうが、「社会的正義」の名に相応しい。それを欺瞞と言ふなら、民主主義制度自体もまた、欺瞞であるしかない。そして我々は、社会を営むのに、このやうな欺瞞以上のものを、まだ発見してゐないのである。
最後にアテナに残された仕事は、ぶつぶつ不平を言ふことをやめない復讐の女神たちを宥めることだ。「お前たちもそんなことだけをしてゐたのでは嫌はれるばかりだ、人を許すことも覚えたらどうだ」。
驚くべきことに、この説得が効を奏して、復讐の女神は慈しみの女神に変貌し、劇はめでたしめでたしで終はる。
これについても、そんなんでいいのか、と思はず聞きたくなるかも知れない。しかしここにも一定の智恵があることは認めざるを得ないと思ふ。万人が納得する正義が実現し難いとき、人間に(この場合も神を含む)できることは、許すことだけなのだ。そのはうがまだしも、ずつと憎しみと争ひが続くよりはいい。もちろん、いつでも、誰でもを、許すわけにはいかないのであるが。
以上は「オレステイア(オレステス物語)三部作」と呼ばれる作品群の締めくくりなのだが、オレステス個人の影はひどく薄くなつてゐることは認められるであらう。彼は無責任なわけではなく、恐ろしい女神たちに悩まされたり、裁判の被告になつたりと、充分に自分のしたことに対応してゐる。しかし、本当の問題はそこにはない。
不完全な人間が作る社会は、やつぱり不完全だといふ実情が露はになつた。その狭間に落ちた者は、もはや自分自身の運命の主人として振る舞ふわけにはいかない。彼は英雄ではなく、犠牲者になるしかない。たぶんそれがわかつたからであらう、後代の、シェイクスピアやラシーヌなどの悲劇作家は、このやうな者を主人公とはしなかつた。
現代では悲劇のヒーローに足る人物を見つけ出すことは難しいであらう。一方、オレステスの場合のやうな不条理に陥る者なら、ゐる。橋本忍脚本の「私は貝になりたい」は、テレビドラマの傑作として名高く、リメイクもされ、近年映画化もされた。戦地で、上官の命令に従つて捕虜を射殺した元日本軍の二等兵が、戦後その行為のために戦犯となり、アメリカ軍によつて死刑に処される。これはフィクションだが、事実同じやうな目にあつた人は確実にゐる。
深海にゐる貝ではなく、人と人のあひだで生きなくてはならない人間は、時として、悲劇作品以上の悲劇を生きなければならない。できれば救済せねばならぬのは、かういふ人間たちであらう。
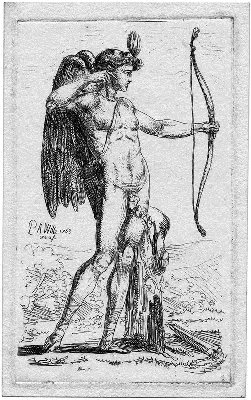 Apollo Shooting an Arrow from his Bow, 1763, by Pierre Alexandre Wille
Apollo Shooting an Arrow from his Bow, 1763, by Pierre Alexandre Wille「お前は何者だ」とは、近代に特有な問ひなのだらうか。古代ギリシャ時代、デルポイのアポロンの神殿には「汝自身を知れ」といふ格言が刻まれてゐたさうだ。すると人間は、二千年以上前から、他の何者でもない、自分自身になり、それを他人にも示せ、と要請されてゐたもののやうである。
が、必ずしもさうではない。アポロンの神殿の碑文には、もう一つ、「度を越すなかれ」ともあつたとされてゐる。それと同じやうな意味だとすれば、「汝自身を知れ」とは、「分際を弁へろ」といふ意味に近いと推察される。神ならぬ人間の身が、すべてを知り、行ふことなどできない。そのことをまづ、よく知るべきだ、と。それなら、たいへん妥当な、古代人の智恵と言へる。
それでも、この言葉は前のやうな意味にも読めてしまふ。それも相当古い時代から、さうだつたやうだ。これこそ言葉の持つ曖昧さであり、アイロニイであらう。それもまた、人間の曖昧さの一部である。
「汝自身を知れ」の作者の候補にも挙げられてゐる、この時代最も有名なソフィスト(弁論家)はまた、「無知の知」と呼ばれる技法を使つた。彼自身の陳述(「ソクラテスの弁明」)によれば、それはこんなふうに始まつた。
あるとき彼の友人が、デルポイにあるアポロンの神殿に、彼・ソクラテスより賢い人間はゐるだらうか、と尋ねに行つた。そこの巫女は、ソクラテス以上に賢い人間はゐない、といふ神託を告げた。それを伝へ聞いた彼は、どういふことか、自分は何も知りはしないのに、と思ひ悩んだ。そして、ことの真偽を自ら確かめるべく、知者として評判の高い政治家のところへ出かけ、彼を仔細に眺めて、問答もしてみた。その結果次のやうな感想を抱いた。
「さて、私たちのどちらかがほんたうに美しく善なるものを知つてゐるとは思へないが、私のはうが彼よりはまだましである。といふのは、彼は何にも知らないのに知つてゐると思つてゐるが、私は何も知らないが知つてゐるとも思つてゐないのだからと。この後の方の点で、私はその人より少しばかり優れてゐると思へるのです」
ソクラテスはその後多くの、知恵者を自認する人と会つたが、いつも同じ発見をするばかりだつた。そこで彼は、アポロンのお告げの真意はそこにあるのだらうと確信するに至つた。私は何も知らないが、自分が知らないといふことは知つてゐる。正にその意味で、ギリシャ随一の智者なのである。即ち、他の者は誰も、自分は知つてゐると思ひ込んでゐればゐるほど、知らないのだ、と。
同時に彼は、この「無知の知」をひろめることこそ、智者たる自分に、神から与へられた使命だとも思ひみなす。ソクラテスは誰彼かまはず議論(問答)をしかけ、その際、相手の「知つてゐる」確信の根拠を問ひ質し、それがいかに曖昧であるかを明らかにした。
これは議論の必勝法だらう。「知つてゐる」には根拠が必要だが、あるいは根拠を尋ねることができるが、「知らない」には根拠の必要はないのだから。つまり、反論のしやうがないのだから。それだけに、いかにも嫌らしい。こんなことばかりやり続けてゐたら、多くの人に嫌はれ、死に追ひやられたのも当然ではないかとさへ思へてくる。
実際、ソクラテスは、多くの若者が自分の真似をし始めて、自分に智恵があると思ひ込んでゐる者たちの浅薄さを暴露していつた、とも述べてゐる。ディベートの技法としてこれを見れば、ごく未熟な者にさへ使へる程度のものだ、といふことであらう。それに、独善を突くといふのは、いかにも若者がよろこびさうなやりかたである。ソクラテスが告発された事由の一つに、「若者を惑はせた」といふのも入つてゐるのだが、これまた正当とは言はぬまでも、ゆゑなしとはしない、ぐらゐには言へさうな気がする。
それだけではない。ソクラテスとその取り巻きがどれくらゐ自覚してゐたかは定かではないけれど、治世の観点から見たら、ここにはもつとやつかいな問題がある。「大人たちは、善いことや美しいことを知つてゐるやうな顔をしてゐるが、本当は何もわかつてゐない」。多くの場合、これは真実であらう。で、あればこそ、それが白日の下に曝されたとき、この世の中はどうなつてしまふのか。何をしようと、しまいと、価値に差などない、あつたとしても、誰もそれを確かには知らない、それだけが真実だとみなされたとしたら? そんな社会では、誰も安心して暮すことなどできないではないか。
それなら、絶対にまちがひのない真善美が見つかるまで、人は待つべきなのか? それこそ、およそ非現実的である。絶対の真善美は、人間には容易に、あるいは決して、見つからない、これがそもそもの出発点だつたはずではないか。それならば、さほど異論が出さうにないものをとりあへずの真善美とみなし、確実な基準はないが、ある「かのやうな」顔をして、人を裁き、人の世に秩序をもたらすのがいはゆる大人の役割ではないのか?
ソクラテスには秩序を破壊するつもりなどなかつたらう。そもそも彼は、自分は、当時の多くのギリシャ人(といふよりアテネ人)がさうみなしてゐたやうな、ソフィストではない、と強調してゐる。彼らの知の無根拠を明らかにすることに専心するのだから、むしろ反ソフィストなのだ、と。後生もそれを認め、ソクラテスは「フィロソフィア」(知を愛する)の徒である、とされた。本当の知とは何か、人間は知らないし、原理的にそこに到達することもできない、が、それを愛することはできる。即ち真知は、ここではなく、どこかにある。それを信じ、愛することは大事だ。そしてそれが「(どこかに)在る」ことを保全するためにも、「知らない」ことを知るのは必須なのである。美しいもの・善なるものについても、同じことが言へる。そして、このやうな意味で本当に知ることを愛せる者こそ、人の世を治めるに相応しい、と。
それは本当だらうか。それもまた、人間には完全にはわからないことの一つであらう。確かに言ひ得るのは、結局、どういふ方向であれ、知ること、知らうとすること、過剰に知ることを求めること、の大いなる危さ、に尽きる。現にそれはソクラテスに死をもたらした。ましてそれを人に強制するのは、「知ること」の内容が「自分は本当には知つてゐない」だとしても、充分に「度を越した」ふるまひと言ふべきであらう。
ただし、特定の誰かに、ではなく、状況に、「汝自身を知れ」と強制されると思はれるときはある。それも、この言葉の元の意味を遙かに超えた次元まで、と見える場合も少くない。本稿第1回ではいくつかそのやうな例を挙げた。ギリシャ人もまた、その危険性を察知してゐて、ソフィストたちの問答とは別の形式で表現してゐる。
私はやはり西欧文芸の登場人物のうち、最も有名な男について語らう。彼は父親を殺し、母親を娶つた。そこから、すべての男子に内在するといふ、「父に取つて代つて、家中の女を独占しようとする」欲望に、彼の名が冠されたことも、誰でも知つてゐる。この奇妙なお伽噺、と私には思へるものが、真理であるとして、西欧社会で広く受け入れられたからである。
しかし伝説においても、この伝説に材を取つた文芸作品においても、それは結果論に過ぎない。彼・オイディプスは、そのやうな目的に従つて行動する者とはされてゐない。
最初に予言があつた。それは彼の出生とともにあつた。この赤ん坊が成人すれば、このやうなことをなすであらうといふ。予言したのは、ソクラテスの場合と同じく、デルポイに祀られてゐたアポロンである。この神様は、といふより予言といふものはいつも、結果しか示さない。
本当は人間にとつてより重大なのは、過程なのだ。即ち、「どのやうにしてそのやうな未来(結果)に辿り着くのか」なのだ。なぜなら、人間は、いつも、行為そのものより、その意味を、「なぜさうなるのか・なつたのか」を気にかけるものだから。結果だけ教へられることは、解答といふより、謎を与へられたやうなものだ。そして、謎を与へられた人間は、考へるしかない。たとへ、さうするのは危険極りないことだと知つてゐたとしても。かくして、予言は、多くの場合、人間にとつて最も恐るべき罠となる。
だから予言する神・アポロンとは、ニーチェが言つたやうな秩序を維持する原理などではない(「悲劇の誕生」)。ディオニソス以上に、破壊をもたらす神なのだ。伝説の中のアポロンは現に多くの場合そのやうな者として語られてゐる。それは、あくまで明晰に、未来を知らうとする者、あるいは明晰さそのものの運命を言ひ当ててゐる。
ソフォクレス「オイディプス王」では、開幕の時点で決定的な行為はすべてなされ終つてゐる。オイディプスが主人公として劇中でなす唯一の行為は、認識することである。彼は、王として、知らねばならなかつた。自分が治める都市国家・テーバイを襲つた疫病の原因を、とことん追求すべき責任は、余人に言はれるまでもなく、深く自覚してゐた。この追求はやがて、「私(オイディプス)とは何か」にすり替はつていく。ところが、これは正しい筋道であつた。オイディプスこそが、疫病の原因であつたからだ。様々に揺れながら、最初に提出された一点に収斂していく劇行為は、そのまま最も緊密な劇構造を形成し、ためにこの作品は、「詩学」(アリストテレス)以来、ギリシャ悲劇を代表する傑作とされてゐる。
しかし我々は、オイディプスが発見し認識したものに、もつと心を動かされぬわけにはいかない。「おお、結婚よ、お前はおれを生み、同じ女から子を世に送り、父親、兄弟、息子の、また花嫁、妻、母のおぞましい縁を、さうだ、人のあひだでこのうへもない屈辱をつくり出した」。同じ男が同じ女の息子であると同時に夫、同じ子どもたちの父であると同時に兄。世に「ぞつとするほど猥褻」なものがあるとすれば、このやうな関係性の混乱をおいて他にない。なるほど、人間の行為は、可能性のうちあるものを実現させる。その可能性の中には、人間関係の網の目からなるこの世の秩序をひつくり返してしまふものも含まれる。それが開示されたのだ。
ここには次の要素もある。オイディプスは探偵であると同時に犯人である。呪ひをかける者であると同時にその当の呪ひをかけられる者。正当な王位継承者であると同時に簒奪者。Aであると同時に非A。彼は、対立する二者のどちらでもあることによつて、どちらであることも否定し、人間存在の本源としてはこれ以外にないやうに思はれるcrisis(危機・分かれ道)に立つ。オイディプスが実父であるテーバイの先王ライオスを殺した場所が三叉路であつたことは、これをよく象徴してゐる。
さらに言ひ換へると、彼は、対立することによつてお互を成立せしめてゐる二者に同時になることによつて、両者が成立する根拠をつき崩し、人間は最初何者でもなく、最後もまた何者でもないことを最もよく示す者である。彼が知ることを義務とし、知ることに専心した「汝自身」とはさういふ者であつた。
また彼は厄災とそこからの救ひを同時にもたらす者でもあつた。当初テーバイにとつて単なる旅人であつたオイディプスが王になつたのは、スフィンクスの謎を解いたからである。女人の顔と、獅子の体と、鷲の翼を持つこの妖怪は、謎々歌を歌ひ、それが解かれるまではテーバイの市民を順次屠つていつた。この謎々は、太古の文献には次のやうに記されてゐるさうだ。
「地上に、声は一つなのに、二本足でも、四本足でも、三本足でもあるものがゐて、地上と空中と海中のすべての生物の中で、ただ一つだけ性質を変へる。しかも、もつとも多くの足で歩くときに、足の速さがもつとも劣る」
この答へは周知の如く「人間」。オイディプスによつてこれを言ひ当てられたスフィンクスは、自ら高いところから身を投げて死んだ。しかし、思ふに、これが人間には決して解き得ぬ謎だと考へられたのは、実は「人間」といふ答への先まで謎が続くからではないだらうか。「では、人間とは何か。なぜあらゆる生物の中でこれだけが性質を変へるのか」といふふうに。
これからすると、スフィンクスはオイディプスに敗れて死ぬのではない。彼女は、オイディプスこそ、自分の後を継いで、この恐るべき謎かけを完遂するに相応しい者だと認めて、役割を譲つたのだ。現に彼の存在は、スフィンクスへの生贄に劣らず剣呑な、疫病をもたらした。謎は続いたのである。
その最終解答を出すのもまた、オイディプスその人以外にはない。彼は自ら望まぬまま、しかし紛れもなく彼自身の行為によつて、救済者から殺戮者へ、それからまた救済者へと、「性質」を変へて見せた。これ以上の解答はない。即ち、「人間とは何か」に対する、解答不能といふ解答。
【「悲劇論ノート」は、6年前、佐藤通雅氏の個人誌『路上』114号~117号に連載させていただいたエッセイです。学生時代からこだわりのあったテーマですので、少しずつ手直ししながら採録し、さらに完成を目指したいと考えます】

The Deer Hunter, 1978, directed by Michael Cimino
人間にはすべてを知りすべてを見通すことはできない。元来不完全な存在だからだ。だからこそ、生きていくためには何かしら行動する必要がある。そして行動するためには、自分は何かを知つてゐて、何かができると、あるいはしなければならないと、思ひ込む必要がある。その結果、露になるのは、人間の不完全さである。
かくして、「お前は何者だ」といふ問ひは、常に最も呪はしいものとしてある。「お前は何を知つてゐるのか」「お前には何ができるのか」は、その変形である。この問ひの背景には、人間は何者でもないことは許されない、といふ含意があり、さらに、その含意は人間の世の中で広く受け入れられてゐるはずだといふ含意もある。しかし本当に共有されてゐるとしても、それはいつも、人の人に対する悪意とともにある。だいたい、好意を抱いてゐる相手に「お前は何者だ」などと問ふ者はゐない。
含意の中身をもう少し詳しく尋ねてみよう。我々は本来何者でもない。だからこそ、後づけで、何者かにはなれるであらう。さうであれば、なるのがその者の責任である。お前はAになれたし、B・C・D……にもなれた。それなのにAになつたのは、あるいはならなかつたのは、お前の責任である、と。「責任」と、それを担ふべき「主体」の概念がここから発生する。主体はある、すべての人に備はつてゐる、いや、備はつてゐるべきだ、といふのが近代社会を成立させるために必須の含意だとすれば、なるほど近代人は「お前は何者だ」といふ問ひから自由ではあり得ないはずである。
日本映画「トウキョウソナタ」(黒沢清監督)の主人公は、「あなたは会社のために何ができるのですか?」と問はれ、答へることができず、リストラされ、同じやうにして、別の会社への再就職も拒まれる。家では長男から、「あんたは俺たちを守つてゐると言ふが、毎日何をしてるんだ?」と問はれ、やはり答へられない。
彼は「こつちはなんでも受け入れるつもりでゐるのに、誰も受け入れてくれない」と嘆きかつ怒るのだが、「すべてを受け入れる」などといふのは人間にはできないことの一つであらう。彼が言つてゐるのは、「自分は今は何者でもないから、何者かにしてくれ」といふことなのである。
そんな者は、誰も受け入れはしない。現に「何者か」ではあつて、それが「何であるか」を他人に示すまでがその人間の責任とされるから。逆に言ふと、示せない人間は、「責任ある主体」とはみなされない。さういふ社会的な含意がある。あるいは、あるとみなされる局面はある。四十六歳までそれを知らずにきたのは、やはり彼の「責任」である。あるいは、さうみなされてもしかたがない。さういふ含意がある。
アメリカ映画「ディア・ハンター」(マイケル・チミノ監督)の主人公は、逆に、何も受け入れられないといつた様子の友人に、一本のナイフを示しながらかう言ふ。「これを見ろ。これはこれだ。これはこれ以外の何者でもない。お前も今日からお前自身になるんだ」。
もちろんさう言はれてなれるものではない。とりわけ、「自分自身」などといふ途方もないものには。
しかし、「さうなる努力」ぐらゐならできるだらう。していけないはずはない。一本のナイフのやうに、一本の木のやうに、単純素朴に、明確に、隙間なく、「そこにあるもの」になりたいといふのは、多くの男性に共通した望みではないのか? 必ずしも「責任」のためばかりではなく、むしろ、そのやうに他から強いられる存在であることから逃れるためにも。
しかしまた、そんな思ひこそが、罠なのかも知れない。一本のナイフは、「俺は一本のナイフにならう」などと努力することなどない。人間は努力ならできる、といふこと自体が、だから努力しなければならないと感じられること自体が、人間はただ「そこにあるもの」にはなれない何よりの証拠ではないのか。さうであるなら、どれほどの「努力」を積み上げた後でも、やはり、「お前は何者だ」と問はれる可能性は残る。呪ひは続くのである。
「嘔吐」(J・P・サルトル作)の主人公は、自分の吐き気の原因を探つて、それは「ある(或る)モノがある(在る)」ことの知覚に由来することを発見する。河原の石はある。公園の木はある。自分の手さへ、ある。それが「在る」ことの意味はわからないが、「意味」などといふものとも関りなく、ただ、ある。「自分」はそのやうなものとしては、ない。強いて言へば、「或るもの」が「在る」と見て、感じる自分はある、それ以外にはない。では「自分」とは吐き気のことか。そのやうである。「本来の自分」とはつまり、そんなものだ。
では、後から「なる」はうはどうか。はつきりと言はれてゐるわけではないが、こんな例が出てくる。現存する知識をすべて我がものにしようとして、図書館に通ひ、タイトルのABC順に並んでゐる本を片端から読んでゐる男。自分を教育しようといふわけだ。しかしそれは、図書館の本の不完全なコピーが彼の頭の中に蓄へられていくといふだけのことである。もつと奇妙なことに、彼が詰め込んだ知識のために、かへつて彼が空つぽである感じは強まるやうだ。後に彼は、図書館内で少年に淫らな行為をしかけたとして、出入りを止められるのだが、「男色家」のはうが、「博識な男」といふよりまだしも彼に与へられる名として相応しいやうである。
「無常といふ事」で小林秀雄は、「生きてゐる人間とは、人間になりつつある一種の動物」ではないかと述べてゐる。「(生きてゐる人間は)何を考へてゐるのやら、何を言ひ出すのやら、仕出来すのやら、自分の事にせよ他人事にせよ、解つた例が」ないから。「はつきりとしつかりとして」ゐるのは死んだ人間だけだ、と。
さういへば、「嘔吐」の主人公ロカンタンも、ある歴史上の人物が、自分などよりずつと確かに存在してゐると感じて、伝記を書かうとしてゐる。なるほど、死んだ人間だけが「私は私だ。私は私以外の何者でもない」と断言できるのかも知れない。
それはなぜかと言へば、死といふ個体にとつての終末を迎えた人間は、もはや何かを新たに「言ひ出」したり「仕出来」す可能性はないからだ。可能性が消えたとき、彼が言つたこと・やつたことは、決して変更がきかないといふ意味で、正に彼自身のものであつて、それ以外のなにものでもない、と見えてくるのである。
小林秀雄は、それでも生きていかねばならない人間に、様々な意味がある「時間」の中でも、「過去から未来に向つて飴の様に延びた時間といふ蒼ざめた思想」を超克することを勧めてゐる。その内部にある限り、生きてゐる人間は「どうにも仕方のない代物」であることを免れない。彼が出した処方箋は「上手に思ひ出す」ことだ。過去も現在も関りなく、確かに「生きてゐる」ことの実感。それがあれば、「ある充ち足りた」「自分が生きてゐる証拠だけが充満し、その一つ一つがはつきりとわかつてゐる様な」時間がまざまざと現出する、と。
これとは少し違ふが、サルトルは、「完璧な瞬間」を求める女を描いてゐる。あるべきものだけがあり、なすべきことだけがなされてゐるやうな状態のことである。しかし女が語るのは、失敗例ばかりだ。それが訪れると思へた次の瞬間には、必ずあるべきでないものがあり、なすべきではないことがなされて、邪魔をするからだ。
例へば彼女が初めてロカンタンに抱擁されたときのこと。二人はいらくさの上に座つてゐた。いらくさは彼女の腿を刺し、痛かつた。ちよつと動くたびに、新たな痛みに襲はれた。女の願望では、このときは性的な恍惚感のためにすべてが存在してゐるべきだつた。いらくさの痛みに耐へるなどといふ余計なことがあるべきではなかつた。いや、その存在を感じてもいけなかつたのだ。けれど現実に、いらくさはそこにあり、痛覚といふ手段で、その存在を主張した。それですべては台無しになつた。
「思ひ出」のやうに純粋に内面的なものではなく、芸術作品のやうに一定の形式の枠内での完成が期されるものでもなく、現実を生きる人間の行為として完璧なものを作りださうとするなら、かうなるのが当然なのである。行為とは未来を作り出すことだが、さうであるなら、人間の内外にある可能性が、好ましいものも、さうでないものも、彼が企図したことといつしよに、ある場合には企図に反して、現出してくるのを完全に避けることなどできないから。
本稿では小林秀雄の示唆した方向に考へを進めることはしない。「人間になりつつある一種の動物」、それこそ「人間」に他ならないのだ、とサルトルなら言ふだらう。曖昧で、だらしないまま、覚束ない足取りで未来へ向かふ現実の中の人間、それがここでの主題である。

The Deer Hunter, 1978, directed by Michael Cimino
人間にはすべてを知りすべてを見通すことはできない。元来不完全な存在だからだ。だからこそ、生きていくためには何かしら行動する必要がある。そして行動するためには、自分は何かを知つてゐて、何かができると、あるいはしなければならないと、思ひ込む必要がある。その結果、露になるのは、人間の不完全さである。
かくして、「お前は何者だ」といふ問ひは、常に最も呪はしいものとしてある。「お前は何を知つてゐるのか」「お前には何ができるのか」は、その変形である。この問ひの背景には、人間は何者でもないことは許されない、といふ含意があり、さらに、その含意は人間の世の中で広く受け入れられてゐるはずだといふ含意もある。しかし本当に共有されてゐるとしても、それはいつも、人の人に対する悪意とともにある。だいたい、好意を抱いてゐる相手に「お前は何者だ」などと問ふ者はゐない。
含意の中身をもう少し詳しく尋ねてみよう。我々は本来何者でもない。だからこそ、後づけで、何者かにはなれるであらう。さうであれば、なるのがその者の責任である。お前はAになれたし、B・C・D……にもなれた。それなのにAになつたのは、あるいはならなかつたのは、お前の責任である、と。「責任」と、それを担ふべき「主体」の概念がここから発生する。主体はある、すべての人に備はつてゐる、いや、備はつてゐるべきだ、といふのが近代社会を成立させるために必須の含意だとすれば、なるほど近代人は「お前は何者だ」といふ問ひから自由ではあり得ないはずである。
日本映画「トウキョウソナタ」(黒沢清監督)の主人公は、「あなたは会社のために何ができるのですか?」と問はれ、答へることができず、リストラされ、同じやうにして、別の会社への再就職も拒まれる。家では長男から、「あんたは俺たちを守つてゐると言ふが、毎日何をしてるんだ?」と問はれ、やはり答へられない。
彼は「こつちはなんでも受け入れるつもりでゐるのに、誰も受け入れてくれない」と嘆きかつ怒るのだが、「すべてを受け入れる」などといふのは人間にはできないことの一つであらう。彼が言つてゐるのは、「自分は今は何者でもないから、何者かにしてくれ」といふことなのである。
そんな者は、誰も受け入れはしない。現に「何者か」ではあつて、それが「何であるか」を他人に示すまでがその人間の責任とされるから。逆に言ふと、示せない人間は、「責任ある主体」とはみなされない。さういふ社会的な含意がある。あるいは、あるとみなされる局面はある。四十六歳までそれを知らずにきたのは、やはり彼の「責任」である。あるいは、さうみなされてもしかたがない。さういふ含意がある。
アメリカ映画「ディア・ハンター」(マイケル・チミノ監督)の主人公は、逆に、何も受け入れられないといつた様子の友人に、一本のナイフを示しながらかう言ふ。「これを見ろ。これはこれだ。これはこれ以外の何者でもない。お前も今日からお前自身になるんだ」。
もちろんさう言はれてなれるものではない。とりわけ、「自分自身」などといふ途方もないものには。
しかし、「さうなる努力」ぐらゐならできるだらう。していけないはずはない。一本のナイフのやうに、一本の木のやうに、単純素朴に、明確に、隙間なく、「そこにあるもの」になりたいといふのは、多くの男性に共通した望みではないのか? 必ずしも「責任」のためばかりではなく、むしろ、そのやうに他から強いられる存在であることから逃れるためにも。
しかしまた、そんな思ひこそが、罠なのかも知れない。一本のナイフは、「俺は一本のナイフにならう」などと努力することなどない。人間は努力ならできる、といふこと自体が、だから努力しなければならないと感じられること自体が、人間はただ「そこにあるもの」にはなれない何よりの証拠ではないのか。さうであるなら、どれほどの「努力」を積み上げた後でも、やはり、「お前は何者だ」と問はれる可能性は残る。呪ひは続くのである。
「嘔吐」(J・P・サルトル作)の主人公は、自分の吐き気の原因を探つて、それは「ある(或る)モノがある(在る)」ことの知覚に由来することを発見する。河原の石はある。公園の木はある。自分の手さへ、ある。それが「在る」ことの意味はわからないが、「意味」などといふものとも関りなく、ただ、ある。「自分」はそのやうなものとしては、ない。強いて言へば、「或るもの」が「在る」と見て、感じる自分はある、それ以外にはない。では「自分」とは吐き気のことか。そのやうである。「本来の自分」とはつまり、そんなものだ。
では、後から「なる」はうはどうか。はつきりと言はれてゐるわけではないが、こんな例が出てくる。現存する知識をすべて我がものにしようとして、図書館に通ひ、タイトルのABC順に並んでゐる本を片端から読んでゐる男。自分を教育しようといふわけだ。しかしそれは、図書館の本の不完全なコピーが彼の頭の中に蓄へられていくといふだけのことである。もつと奇妙なことに、彼が詰め込んだ知識のために、かへつて彼が空つぽである感じは強まるやうだ。後に彼は、図書館内で少年に淫らな行為をしかけたとして、出入りを止められるのだが、「男色家」のはうが、「博識な男」といふよりまだしも彼に与へられる名として相応しいやうである。
「無常といふ事」で小林秀雄は、「生きてゐる人間とは、人間になりつつある一種の動物」ではないかと述べてゐる。「(生きてゐる人間は)何を考へてゐるのやら、何を言ひ出すのやら、仕出来すのやら、自分の事にせよ他人事にせよ、解つた例が」ないから。「はつきりとしつかりとして」ゐるのは死んだ人間だけだ、と。
さういへば、「嘔吐」の主人公ロカンタンも、ある歴史上の人物が、自分などよりずつと確かに存在してゐると感じて、伝記を書かうとしてゐる。なるほど、死んだ人間だけが「私は私だ。私は私以外の何者でもない」と断言できるのかも知れない。
それはなぜかと言へば、死といふ個体にとつての終末を迎えた人間は、もはや何かを新たに「言ひ出」したり「仕出来」す可能性はないからだ。可能性が消えたとき、彼が言つたこと・やつたことは、決して変更がきかないといふ意味で、正に彼自身のものであつて、それ以外のなにものでもない、と見えてくるのである。
小林秀雄は、それでも生きていかねばならない人間に、様々な意味がある「時間」の中でも、「過去から未来に向つて飴の様に延びた時間といふ蒼ざめた思想」を超克することを勧めてゐる。その内部にある限り、生きてゐる人間は「どうにも仕方のない代物」であることを免れない。彼が出した処方箋は「上手に思ひ出す」ことだ。過去も現在も関りなく、確かに「生きてゐる」ことの実感。それがあれば、「ある充ち足りた」「自分が生きてゐる証拠だけが充満し、その一つ一つがはつきりとわかつてゐる様な」時間がまざまざと現出する、と。
これとは少し違ふが、サルトルは、「完璧な瞬間」を求める女を描いてゐる。あるべきものだけがあり、なすべきことだけがなされてゐるやうな状態のことである。しかし女が語るのは、失敗例ばかりだ。それが訪れると思へた次の瞬間には、必ずあるべきでないものがあり、なすべきではないことがなされて、邪魔をするからだ。
例へば彼女が初めてロカンタンに抱擁されたときのこと。二人はいらくさの上に座つてゐた。いらくさは彼女の腿を刺し、痛かつた。ちよつと動くたびに、新たな痛みに襲はれた。女の願望では、このときは性的な恍惚感のためにすべてが存在してゐるべきだつた。いらくさの痛みに耐へるなどといふ余計なことがあるべきではなかつた。いや、その存在を感じてもいけなかつたのだ。けれど現実に、いらくさはそこにあり、痛覚といふ手段で、その存在を主張した。それですべては台無しになつた。
「思ひ出」のやうに純粋に内面的なものではなく、芸術作品のやうに一定の形式の枠内での完成が期されるものでもなく、現実を生きる人間の行為として完璧なものを作りださうとするなら、かうなるのが当然なのである。行為とは未来を作り出すことだが、さうであるなら、人間の内外にある可能性が、好ましいものも、さうでないものも、彼が企図したことといつしよに、ある場合には企図に反して、現出してくるのを完全に避けることなどできないから。
本稿では小林秀雄の示唆した方向に考へを進めることはしない。「人間になりつつある一種の動物」、それこそ「人間」に他ならないのだ、とサルトルなら言ふだらう。曖昧で、だらしないまま、覚束ない足取りで未来へ向かふ現実の中の人間、それがここでの主題である。














