メインテキスト:西尾幹二『日本の教育 ドイツの教育』新潮選書昭和57年
同『日本の教育 智恵と矛盾』(中公叢書昭和60年)
同『教育と自由 中教審報告から大学改革へ』(新潮選書平成4年)

【以下の文章は佐藤幹夫さんの個人誌『飢餓陣営』vol.60(終刊号)に掲載させていただいたものに加筆訂正したものです。このブログへの転載を許可して頂いた佐藤氏には感謝申し上げます。】
昨年の十一月一日に西尾幹二先生が亡くなり、今年の二月一日にお別れの会があった。三百人ほどの出席者数だったろうか、たいへんな盛況で、それだけで故人の人気のほどが偲ばれた。
会場に入るとまず大きな花輪が目に入り、それには「石破茂」と名前が大書きされていた。内閣総理大臣の肩書きが書かれていなかったのは、好感度アップポイントだろう。石破氏のメッセージは会の途中でも読み上げられた。それで思い出したが、氏と西尾幹二先生とは対談本を出していたのだった。『座シテ死セズ』(恒文社平成15年)。当時石破氏は、第一次小泉内閣の防衛庁長官として初入閣した直後だった。西尾先生は憲法改正などのセンシティヴな話題は慎重に避けながら、自民党の若手防衛族を温かく見守ろうとする態度が印象的で、これは先生の最も魅力的な美質の現われだ。
その後先生は、政治家の中では高市早苗氏との仲を深めた。会は追悼演説の連続で進行したのだが、高市氏は藤岡信勝氏の次に登壇して話をした。石破氏も来席すれば、ついこの間自民党総理総裁選を争った両雄の、呉越同舟の図が見られたわけだが。まあこれは余計な話。
会はこのように、二十人近い保守系の著名人が、それぞれ自分と西尾先生の関わりや、その人なりの西尾論を語った。全体として、(エアコンの効きが悪くて少し寒かったが)とてもよい会だった。
が、以下はどうしても黙っている気になれない。
それは小川榮太郞氏のお話。その部分の前後関係をできるだけ詳細に記す。
第二次安倍政権ができたとき、小川氏は何かの集まりで、この内閣に関しては「是々非々」ではなくて、「是々是々」で支えなくてはいけない、と発言したら、後のかほうから「政事について是々是々でいくなんてことがあるものか」と怒鳴られた。それが西尾先生だった。先生とお会いするのはこれが初めてだったが、「私は福田恆存の最後の弟子なので」それが誰なのかはすぐにわかった。
その後小川氏は、西尾先生からとても優しい電話をいただき、懇意にさせていただいたのだと言う。その関係性については私は何も知らない。問題は。小川氏はいつどんな形で福田恆存先生の弟子になったのか、だ。
第二次安倍政権発足時と言えば平成24年で、福田先生はとうにお亡くなりになられている。またそれ以前から福田先生自身からも、周囲の人々からも、小川榮太郞氏の名を聞いたことはない。小川氏は、福田先生とも面識はなかったのではないかと思う(違っていたら訂正しますから、ご教示下さい)。
たぶんこんなところか。西尾幹二先生が評論家としては福田恆存先生の一番弟子(最初の弟子とは言えない)だったことは、知っている人は知っている。そこで初めて顔を合わせた西尾先生に怒鳴られた話に、実は自分は福田先生の最後の弟子であった、という因縁話見たいのを盛り込み、かつ自分を大きく見せようとしたのではないか。
私淑ということはある。その人の生前に会ったことはなくても、著作を通じて思想やものの考え方に感銘を受け、自分一人の師とすることに決めた、と。かくいう私もそれに近い。しかしそれなら、「最後の」はおかしい。今後も福田思想を受け継ごうとする人がいないと、どうして言えるのか。
以上は福田恆存先生に思い入れのない人にとっては、なんということもない話である。個人的に、近ごろ保守界隈にも駄法螺が横行するようになったのだな、とちょっとため息が出てしまうだけだ。
ただここで、西尾先生の「人づきあい」のありかたが改めて頭に浮かんだ。先生はとても優しくて、私のような者に対しても決して偉ぶらず、気さくにお話して下さった。開けっぴろげで、懐が深かった。もちろんそれは一面であって、かなり辛辣な人物評を下すこともあったのだが、それをもあまり隠さないのは、やっぱり根本的な人の良さ、というしかない。
このような性格がよい方向にだけ働くとは限らない。特に、多くの人といっしょに、何事かをやろうとするとき。先生は昔から、書斎で思索に耽るだけではだめだと、実際に世の中を変えんとする「実行の世界」に憧れるところがあった。それはつまり広義の政治であって、好むと好まざるとにかかわらず、集団の毒に身を浸すことである。失礼ながら、先生には、あれほどの知識と知力がありながら、その見通しには足りないところがあったようにお見受けする。
ここでは、追悼にはあまり相応しくないが、私自身が関わりを持つことになった教育の分野について書いておく。以下、敬称は略す。
平成2(1990)年西尾は第十四期中央教育審議会の委員となり、翌3年の1月に出た『中央教育審議会審議経過報告』(以下『報告』と略記する)の大部分を執筆した。それを知った私が、一読の上で批判文(「第二章 公的な教育言語」拙著『学校はいかに語られたか』JICC出版局平成四年刊所収)を書き、それが縁で西尾幹二の知遇を得ることになった。
まず『報告』が出た直後にあったことについて、西尾自身が著書『教育と自由 中教審報告から大学改革へ』で簡潔に書いている。『報告』中の「大人の競争を肩代わりする子どもたち」という小見出しで始まる部分は、彼の旧著『日本の教育 智恵と矛盾』中に収録された文章と、題名からしてほぼそのままだった。どこかのマスコミが、これを暴露(というのは大げさだが、西尾自身がそう書いている)すると、彼一人に執筆を任せた他の『報告』の起草委員が騒ぎ出した。騒ぎを収拾したのは元文部事務次官の佐野文一郎で、「審議会の文章は委員のうちの誰かが書くものであれば、委員の一人の著書と内容が似ていても別に問題はあるまい」と言って皆を窘めたという。
いかにも、「報告」の執筆を起草委員中の一人に任せたのは別に問題ないだろう。にしても、中教審のお歴々は、その任せた人物の、教育に関する著作ぐらい、事前に目を通しておいてもよかったのではないかな、とは思う。しかし中教審とは、元来その程度の集まりなのである。
現在の日本の学校には問題がある。(当時)文部省はそれをなんとかする責任がある。だから、有識者と言われる人々を集め、なんとかする方策を求めて話し合ってもらう。しかし一方で、「社会的な成功」についての人々の欲望が密接に絡み合っている制度が、そう簡単にどうにかなるものではない。それでも教育に関する言説は、特に公のものは、そのような生々しい浮世(憂き世)の性(さが)とは別次元の、「理想の教育・学校」があり得る、という思い込みを決して離れてはならない。これを大前提として交わされる。
そういう言説の大元を作るべきとされている場が審議会であろう。特に中教審を初めとする文部省・文科省関係のものは、下の方で実際の教育行政や教育そのものに携わっている者たちから見たら、何やら偉そうな人たちが、雲の上で、実際にはどこにもない「すばらしい教育」に関する美しい言葉を並べているだけ、地上の一般庶民にはなんの関係もない、という感覚に自然になる。事実、大半の教師は、中教審の報告も答申も読んでいない。私にしても、これに西尾幹二が密接に関わっていると知らなかったら、決して目を通すことはなかったろう。
文部官僚、今の文科官僚は、実務もしているのだから、現場の実情を少しは知っている。その上で、教育の理想論は保持することを使命としている。それだけに、その理想論を机上で並べるだけの先生方は、尊敬するより、むしろ滑稽に見えることが多いのではないだろうか。名誉職として、官僚たちと調子を合わせるだけの先生より、真剣に何かをやろうとする真面目な人ほど、ピエロになる。西尾幹二のこのときの立ち位置は、ほぼそんなものであった。
そのような場所で活動した後の感想は、やはり『教育と自由』に採録されている中教審委員としての最後のスピーチに率直に出ている。時期的には、『報告』が出る少し前から、中教審の最後の成果である答申(『新しい時代に対応する教育の諸制度の改革』平成三年四月十九日)が出来るまでに中教審内部で演じられたドラマの、西尾側からの報告である。できるだけ簡潔に記すと。
西尾の基本的な認識は、日本の学校教育は平等と効率をずっと追求し続けてきたために、袋小路に陥った、というものだ。従って、これを打開するためには、平等と効率のどちらかか、あるいは両方を引き下げるしかない、と基本的な方針として『答申』に書くべきだ。そう唱えると、審議会会長の清水司(元早大総長)を初めとした面々は、この最後の結論に至るまでの分析には賛成していたのに、「引き下げる」という表現には反対した。
それでは、「引き下げる」から一歩下がって、日本の教育が陥っている袋小路を正直に描き出し、「そう簡単に解決は望めない」「希望はほとんどない」と明記したら、とさらに西尾が提案すると、またしても止められた。「望めない」とか「希望は…ない」とかいう強い否定表現は答申には出せない、と言われて。
ここで審議会的な文章と西尾のような人物の著作との違いが浮き彫りになっている。前者は美しい夢を語り、できるだけ誰をも傷つけないようなものを目指す。すると、現実を改革する力はなくなる。現実である以上、変えるには一定の犠牲や努力を要するという意味で、なんらかのコストがかかる。何ものもタダでは手に入らないのだ。
繰り返すことになるが、西尾はこのとき、我が国の教育行政そのものの矛盾に正面からぶつかったのだ。その本務は、学校なら学校の現実を変革するのではなく、教育に対する美しいが空虚な夢を国民に見せ続けるところにある。理想の教育はどこかにあり、自分たちはそれを探し求めている、というポーズこそが大事なのだ。中教審はそのための言葉を作ってくれればいい。それ以外は余計だ。
いや、現に実現した改革案もあるではないか、という疑問を持つ向きは、学校教育にそれなりの関心はあるのだろうから、その改革案がやがてどうなったか考えてもらいたい。教員免許更新制度はどうなった? 民間人校長は? ゆとり教育は? この最後のものなど、弊害が論われたからまだいい。それ以外は、いつの間にかなくなって、誰もが思い出したくもない、という顔をしている。こんなものにまともにつきあったらバカを見るのが落ちだ。それで、西尾もバカを見た。
より具体的に言うと、教育改革案のかなりの部分が、すばらしい教育が行われるべき学校で、かえって酷い目に合ったと思っている人々を宥めるために使われる。例えば高校・大学入試。試験の点数のみで、他は一切関係なく、つまり出自や財産や容貌は完全に度外視して合格が決まるのは、この上なく平等だと言える。また、受け入れ側は、点数のみで決められるのは効率的だ。その結果陥った袋小路とは? ある学校へ入れなくて悔しい思いをする人がいる。しかし、どういうやり方をしようとも、落ちる人がいる以上は悔しい思いが消えることはないのだが。
このへんを詳述することが本稿の目的ではないので、簡単にすます。西尾も一見中教審と合致するような意見を言っていたことがあり、当然それは『報告』に取り入れられた。代表的なところを約言するとこうなるだろうか。子どもを縛り付けるいわゆる「学力」のみの競争は弱めて、それぞれの個性が伸ばせるような自由を与えよう、と。
改めて書くと、西尾のオリジナルとはとうてい言えない。この頃が初めてでも終わりでもない、教育論議の中でずっと言われ続けてきた言葉だ。個性とか自由とかいう抽象語のレベルなら、大切であることに、まずどこからも異論は出ないから、西尾と審議会とでも一致したような気にもなる。しかしそれを現場に降ろす段になると。
現場の教師として実際に取り組んだり、見聞した限りでは、やはり労多くして功少ない試みだという感想になるしかない。だいたい、多様な授業のための予算や人員(教員)確保のための資金はそれほど下りない。例えば、陶芸の授業を始めることになった。窯を作り、材料を揃えるまでの予算は貰えた。その上で、安い手当で教えに来てくれる陶芸家を近所で見つける。それは教員の仕事になるのだ。いつも、いつまでもうまくいくと思いますか?
県の教育行政担当者と会って話した経験から実感したが、目に見える成果はあまり期待できない「個性」なんてもののために、多額の予算をつけていられるか、というのが官僚たちのホンネとみていい。だったら最初からやらないに越したことはないのだが、それでは上のほうはやることがなくなってしまうからな。ざっとこういうのが、西尾を初めとする審議会の、雲の上のお歴々が知らない地上の事情なのである。
次にこの『報告』で最も話題になったことを見ておこう。特定大学への同一高校からの入学者数を制限する、という案。私は最初これを、審議会内部の妥協の産物であって、西尾個人はそんなに乗り気ではないのではないか、と思っていたのだが、『日本の教育改造案』(別冊宝島平成7年)所収のインタビューで直接当人と話してみたら、かなり本気だった。
文部省が用意した各種の報告のうち、有力(偏差値上位)大学に入る学生に、出身高校による顕著な偏りが見られる事実は、審議会の面々にとって非常に衝撃的だったのだ。東大を例にすると、平成2年度で五十名以上の合格者を出した高等学校は十五校、これは東大合格者出身高校のうち三%ほどを占めるにすぎないのに、この十五校の出身者が東大入学者数の三十四%以上に達し、しかもこのような寡占状態は年々昂進する傾向がある。
これはなんとかせねばならぬ由々しき事態だ、という空気になったものらしい。けれども、これを招いた一因は前述したきれい事の文教政策にある、ということにはあまり注意が向けられなかった。
上の十五校とは、二校を除いてすべて私立の、それもたいてい中高一貫教育校である。これも当時から今まで、多少とも大学受験の実態を知っている人の間では常識である。昭和三十年代までは名門校として知られていた元旧制中学に代って、努力を積み重ねて今日の名声を得た。その努力とは、「個性」や「自由」がどうのではない、そんなものには目もくれず、受験競争を勝ち抜く力をつけさせようとするものだ。例えば、私立側が宣伝したのでよく知られている、中学校から高二までの5年間で高三までのカリキュラムはすべて消化し、最後の一年は専ら受験勉強に当てる、などの方策は、学習指導要領により強く縛られている公立高校では無理なことだ。
このようなやり方が成功したとみなされると、より多く優秀な生徒が集まる。その結果が東大などの合格者寡占状態なのである。それがあまりにあからさまになったので、外部から制限をかけるのだという。姑息という言葉が自然に頭に浮かんだ(この言葉には元来「ずるい」の意味合いはない。為念)。こういう騒ぎになるのは、審議会の委員を含めた世のたいていの人が、たいがいの個性よりは有力大学への進学のほうが価値が高いと本音の部分では思っている証左なのである。それでいてそのことは隠す、というか、あまり目立たないようにしなければならない。目立たないようにするのが教育論の第一の役割だとされている。こんな場所では、真面目にやればやるほど、前述したように滑稽なピエロになるしかなかった。
そのために、答申からは、右の同一高校からの大学進学者制限案を初め、具体的な施策は消えて、いつものように当り障りのないものになった。西尾も、「中間報告(『報告』のこと)では、第四章を除き、私が文章の隅々にまで責任を持ったが、最終答申では重要な幾個所かを除いて私には権限がなく、相談も受けなかった」(『教育と自由』)と冷たいものである。これが中央教育審議会で西尾幹二がしたことの最終的な成果だった。
西尾が教育について不見識であったとは思わない。次の三つの言葉など、私には全く違和感はない。
「徳は教えようがない」は古代ローマの哲人セネカの有名な言葉だが、百の道徳論を積んでも一人の有徳の人間を作れるとは限らない、というほどの意味で、教育にもまたこのペシミスムが必要である。
教育はつまるところ自己教育である。学校はそのための手援けをする以上のことはなし得ないし、またすべきでもない。(以上『日本の教育 ドイツの教育』より)
現代の教育を考えるに当って、われわれはどこまで絶望できるか、その能力が問われているともいえる。しかし大概の人は絶望しないで、解決策があるかのように語りたがる。ことに教育界の人間はそうである。(『教育と自由』)
なるほど、いずれも否定的な表現で書かれており、その種のものは「教育の専門家」の文章中ではついぞお目にかからないものであることはよくわかる。
とはいえ、かく言う西尾自身が、持ち前の人の良さに加えて、教育現場の現実の壁にぶつかったことはないので、ペシミスムが足りないところはあった。そこで中教審に入ると、昔から教育界を支配している言語作法に妥協し、しかも妥協の産物さえ最終的には捨て去られるのを目にしなければならなかったのである
私の個人的な心情で、学校教育については遠慮も妥協も出来ないので、つい批判めいた言い方になってしまった。それは別にしても、西尾幹二先生は組織向きの人ではなかったと思う。その後、「新しい歴史教科書を作る会」の会長に担ぎ出された結果、組織内の勢力争いに巻き込まれて、余計な疵を負った、と拝察される。いや、それもまた、先生の持って生まれた宿命だったとも言えるかも知れないが。
これ以外だと、昭和の終わり頃、日本はドイツと違って戦後処理をきちんとしていない、という妄説や、最近ようやく多くの人の目に映じるようになった移民の問題について、「朝まで生テレビ」などで、左翼の論客を相手に孤立無援で戦っていた先生のお姿が今も心に浮かぶ。この時の西尾先生には、尊敬しか感じない。私たちの時代にこのような知識人がいてくれたことは、まことに有難いことであった。ご冥福をお祈り致します。











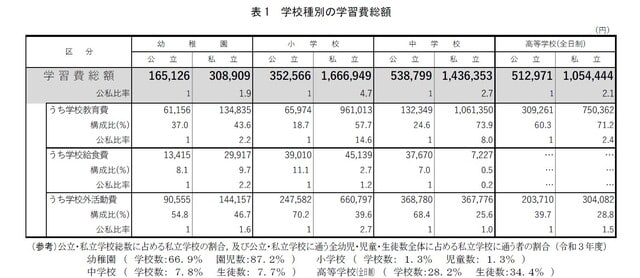
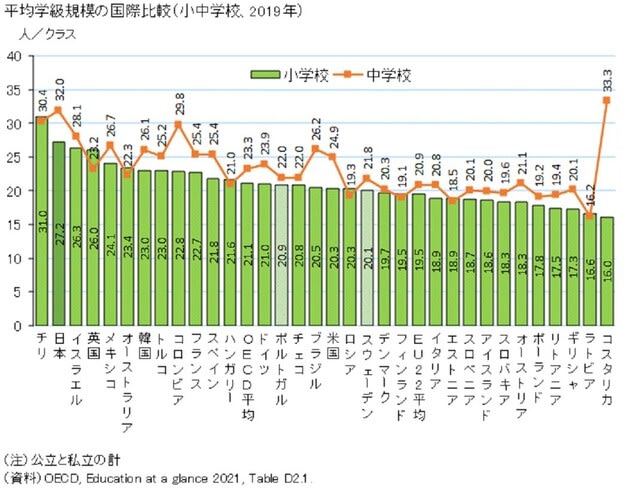




 Yahooニュース令和5年2月15日より
Yahooニュース令和5年2月15日より


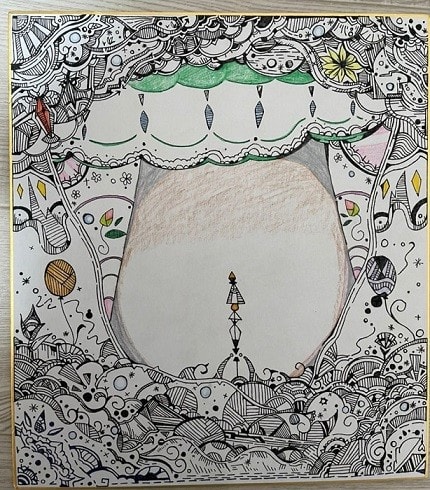 広瀬爽彩さんの描いた絵。Twitterより
広瀬爽彩さんの描いた絵。Twitterより 平成7年のTVCM
平成7年のTVCM



 テレビ東京ドラマ「鈴木先生」2011
テレビ東京ドラマ「鈴木先生」2011



