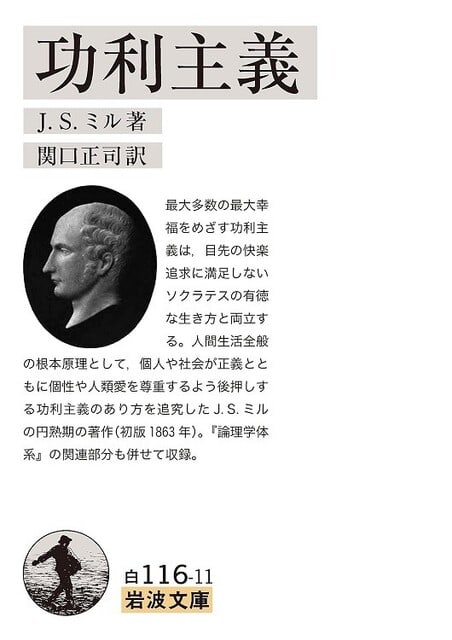
メインテキスト:小浜逸郎『倫理の起源』(ポット出版プラス令和元年)
サブテキスト:ジョン・スチュアート・ミル/関口正司訳『功利主義』(原著の出版年は1861年、岩波文庫令和3年)
Ⅵ 理と情
この人間の二大行動原理については、『倫理の起源』(以下、本書、と呼ぶ)では二つの、典型的な、ある意味で極論が紹介されている。それ自体非常に面白いので、以下にまた自分の言葉で述べる。
まず当ブログでずいぶん以前に述べたカントの嘘に関する考え。通称「ウソ論文」、正式名称は「人間愛から嘘をつく権利という、誤った考えについて」には次のような例が出ている。
Aの家に殺し屋Cに追われた友人Bが来て、匿ってくれるように頼む。Bを家に入れてから、Cが来て、Bは来なかったか、と訪ねる。この時AがCに、「Bは来なかった」と言ってはいけないか?
いけない。なぜなら、それはウソだから。
【上記の例はカントを批判したフランスの哲学者バンジャマン・コンスタンが、「カントたちの説だと、こういうバカなことになるよ」、と例示するために拵えたもので、「ウソ論文」はコンスタンに対する再批判として書かれている。しかし、カントは「自分はこういうことを言った覚えはないが、自分の考えとしてもさしつかえない」としている。などなどの細かいことは、以下では省いて大雑把なことだけ記すので、そのへんの詳細は最近出た『カントの「嘘論文」を読む』(令和6年白澤社発行/現代書館発売)などに当って下さい。】
「なんだよ、それは」とたいていの人が言うだろう。小浜が言うように、「カントという哲学者はなんてバカなやつなんだと直感的に思」(P.192)う人も多いと思う。
より軽い、日常的な場面を考えよう。ある女性が男にデートに誘われた。行きたくなかった。「その日は用事がありますから」と言って断った。その実、用事がなかったら、それはウソということで、悪なのか。「あなたが嫌いだから、行きません」というような、いわゆるホンネをいつもぶつけ合わねばならないのか。
そもそも、「あなたが嫌い」という感情は、「事実」と呼ぶに相応しいのだろうか。そのときの「本心」ではあったとしても、男心も女心も、変りやすい。明日はどうなるのか、本人にもわからない、その場限りかも知れないものを、いちいち明らかにして、どうなるというのか。
というような考えこそ、カント先生からしたら、最も忌むべきものだったようだ。人間は理性的な存在であり、自分の言動すべてに責任を持つ、持てる……少なくともそうなるべく努力すべき者なのだ。
この場合の「責任」とは、結果に関するものではない。上の例で「Bはいる」といっても、BがAもCも気づかないうちに家から去っていたら、殺害を免れるかも知れない。同じ状況でAが嘘をついても、BはCと外で出くわし、殺されるかも知れない(やや強引な例のようだが、これはカント先生自身が書いていること)。
つまり、未来を完全に予測できない人間が、結末について責任を問われるべきではないが、真実や信念について忠実であることなら、できるはずだ。だから、すべきなのだ。
もう一つ、人間関係で一番大事なのは、他人を、自分の欲望を達成するための道具扱いしてはならない、ということだ。ウソをつくのは、結局は、相手を自分の都合のいいように動かそうとしてのことだろう。その「都合」が正しいものであっても、「相手」が悪人であっても、そのことに変わりはない。だから、誰も、どんなウソでも、つく権利はない……。
この理念が他にもまして重要かどうかも、議論が分かれるだろう。たとえそう認めたとしても、現実にはやっぱり無理な話ではありそうだ。
第一に、カント先生自身は例外だったかも知れないが、普通の人間にいつも「正しくあれ」などと要求するところ、いやそれ以前に、いつも「正しさ」を気にかけるように要求するところが無理だ。誰しも、普段あまり深く考えないでふるまい、後からその理由を問われた時に、改めて首尾一貫した動機を考え出す、というのが実情に近い。「自由意志から行為へと言ういう因果関係は、じつは逆なのである」(P.193)と小浜が言う通り。
カント風の「自由で自律的な個人」の観念に基づいている近代刑法(だから、良い・悪いの判断がつかないとされる心神喪失状態の犯罪は罰せられない。刑法第三九条一項)にも、「嘘つき罪」はない。嘘は、それによって不当な利益を得ようとする動機が明らかなとき、罰の対象になる(詐欺罪)。
そもそも、いわゆる社交辞令もダメなのだとすれば、どんな共同体も保たれないだろう。コンスタンの批判の要点もそこにあった。
そんなことを、いかに象牙の塔に籠もった哲学者先生とはいえ、全く知らなかったはずはない。むしろ、だからこそ、人倫と、ひいては人格を、なし崩しの後退から守るために、「嘘はいけない」という道徳律を強く言わなければならない必要性を感じたのだろう。
事実、それは、子どもを教育する時などに、絶えず言われ続けている。そのことはまた、人の世から嘘は決して消えないことの証左でもある。
上は友情という「情」と、正直という「理」が対立した場合には、後者のほうを優先すべき、としたものだが、世の中にはこれと反対の主張もある。「論語」の次の箇所。
葉公(しょうこう)孔子に語(つ)げて曰く、吾が党に直躬(ちょっきゅう)なる者有り。その父、羊を攘(ぬす)みて、子これを証せり、と。孔子曰く、吾が党の直なる者は、是に異なり。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直は其の中に在り、と。(子路十八)
親や子が悪事を働いたとしても、それは匿す。それこそ、正しく、まっすぐ(直)な道である、と言う。人情の自然のようだが、こう断言されると、それはそれでまた、不安になってこないだろうか。子が悪いことをしたときには、親はむしろ世間ではそれがどういう扱いを受けるか、実地に教えてやるべきではないだろうか、など。
予め結論を言うと、こういう場合にいつも当てはまる普遍妥当な解答はない。一口に親子と言っても、同じ人間は二人といないのだから、同じ親子関係も二つはない。当然その間に流れる感情も独自のもの。また、匿すべきものも、盗みから殺人から過失犯から信用失墜行為まで、千差万別にある。
ただ、一般に、親子の情と呼ばれ得るような感情は人間社会に広くあることは認められているから、それを頭から無視することはしづらい、という事情があるだけだ。それで現在日本の刑法にも、それを汲んだ規定がある。第百五条(親族による犯罪に関する特例)「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」。
「前二条」とは、第百三条犯人蔵匿等、第百四条証拠隠滅等。犯人を匿したり逃がしたり、証拠を隠したり破損したりして、犯罪者の発見を、したがって処罰を困難にしても、その犯罪者の親族である場合には、罪に問われないことがあり得る、ということである。
ここで親族というのが、民法の定める六親等の血族(姻族なら三親等)だとすると、はとこ(あるいは、またいとこ。祖父母の兄弟の孫)まで、あるいは従姉妹の孫までだから、ずいぶん広い。顔を見たこともない、という場合も多いだろう。
ただ、たとえ一親等の親子でも、必ず免責されるわけではない。そうなるかどうかは、裁判官の判断次第。犯罪があまりに凶悪だとか、親愛の情からと言うより、金をもらって逃亡を手伝ったような場合は、危うい。逆に、どれほど親愛や恩義を感じていたとしても、また、罪を犯した者にどれほど同情の余地があろうと、親族でなければこの規定は関係ない。
こういうことを文字の上で眺めているときは、せいぜい、まあそんなものかな、で終わりになる。その程度の納得でも、なかったとしたら、こういう規定は定着しない。しかし、具体的な場面にぶつかったら、このような区別が合理的なものだと思えるかどうかは別問題になる。
六親等までならよくて、七親等以上はダメ、親類ならよくて、親友ではダメ、などという線引きに明確な理由があるか、と言われるなら、そんなものはない。ただ、一元的な正義の観念をどこまでも押し通そうとするのも、人情だけで世の中を治めようとするのも、どちらも無理で、どこかに制限を設けねばならない必要性があるだけだ。
つまりこれらの原理は、一方が一方を制限するところに存在意義がある。前述した小浜の「私的・公的という対概念は、互いに他方の「否定態」としてしか成立しない」という言葉は、そういう意味であろう。
その限度自体も、絶えず揺れ動くから、いつでもどこでも誰でもを完全に納得させることは原理的に不可能。すべては、不完全な人間同士が作る「世の中」を成り立たせるための工夫であり、それ以上ではない。
Ⅶ 公と私
上の問題もまた、共同態の中で自己意識を持って生きる人間が必然的に直面する矛盾の一種である。ここまで拙論につきあってくださった人にはもうおわかりのことと思うが、私が本書を読みながら終始気になったのはこの一点だ。
理と情もそうであるように、公と私なら、公の方が高級であり、価値が高い、となんとなく考えられている。また、男女だと、男が主に担うの前者、女は後者で、これは「女・子ども」を軽んじる理由になっている。
このような見方の修正を図ることが本書の主要な目的の一つであり、そのことには私も基本的に同意する。ただ、その理念上の、また実際上の困難は、小浜以上に気にかかってしまうのである。それについては充分に、ではなくても繰り返し述べたから、もう控えよう。
本シリーズの最後にあたって、「公共性」の概念を中心として、既述との重複は気にせずに、小浜倫理学の核心と考えられるものを改めて略述しておく。
小浜は最初に、良心の起源を、幼児が家庭内かその代わりになる場所で、多くは親から受ける叱責だとしている。このとき明示的に「出て行け」とは言われなくても、年長者の怒りは、当の子どもが現にいる共同体=家庭から放逐される恐怖を呼ぶ。それは文字通り死活問題なので、やがて成長して、自分の親を他人の親と比較して客観視・相対化できるようになり、反抗もできるようになっても、深層心理に刷り込まれた恐怖心は消えない。悪いことは、共同体を失う恐怖を呼び起こすから、ブレーキになる。そうならないときもあるが、まあ、だいたいは。
つまり、良心は一定の共同体の人間関係から身につくものであり、それは他の、思いやり・勇気・正直、などの徳目も、必ずしも親だけではなく、友人や教師などの他の大人との関わりの中で身につけていくものだろう。だから、倫理は共同態から生まれる、と言えるのである。
しかし、倫理、と改めて言われると、具体的な人間関係とは別次元にあるような気がしないだろうか。それは言葉の抽象性によるところが大きい。「人に迷惑をかけてはならない」と言われる場合の人(他人)の範囲は、無限定である。実際には、バタフライ効果とやらを最大限考えて、「風が吹けば桶屋が儲かる」式のこじつけ連鎖反応まで入れるのでなければ、世界中の全人間に迷惑をかけられる人などめったにいないわけだが、そんなことをわざわざことわる要もない。
とは言え、抽象化され一般化された徳目は、その分人間の現実を離れる。よい例が前述の、カントの嘘に関する要求だ。繰り返すことになるが、どんな時にも嘘はいけない、ということを実行したら、身辺の共同態を壊してしまいかねない。それでもよい。カントは、時に嘘をつかなくてはやっていけない弱い人間が、自分たちを守るために作り出したような共同態に価値を認めなかったのだから。
人間は個人として、常に正義と公正を気にかけるべき存在だ。……いや、そう言われても、そんな人間こそ、現実にはめったにいないのだから、観念的ではないかと思えるのだが……。いやいや、ここで「弱いのは仕方ない」などと認めてしまったら、弱いからこそ、人間はどこまでも堕落してしまいかねない。道徳律は、自分の行いを反省するための鑑(かがみ)としてこそ必要なのではないか?
と、いうような道徳観は、昔から今まで、人間世界に普通にある。おかげで、道徳というと、高いところから一方的に降りてくるお説教のことだという感覚も、普通にある。
倫理道徳を現にある人間から離れた理念として考えられがちな理由は他にもある。例えば、「人に迷惑をかけてはならない」を一歩進めて、「人には親切にしなければならない」とした場合。これまたいつも、完全にできるものではないが、できるだけそうしましょう、ぐらいには納得できる。それでもなお。
親切にする対象は、遠くの人より身近な人が、身近な中でもいっしょに生活している家族が優先されることになるだろう。単純に親切な行いをする機会の多さからしても、親愛の情の深さからしても、それがごく自然であり、正しい、とも考えられている。孔子の言葉はそれを踏まえている。
それでよくない場合はあるか? 次の例を考えよう。川で二人の子どもが溺れていた。Aは自分の子どもで、Bはそうではなかった。この場合、Aを優先して助けるのは正しいのか? この問いはかつてベストセラーになったマイケル・サンデル『これからの正義の話をしよう』(原題は『Justice』)に載っていて、正しい、とされている。西洋でも、そう思われている場合が少なくない。ということだ。
だがしかし、結果として、Bが救ってもらえないことになったとしたら、Bの親にしたら、素直に「それが正しい」とは感じないだろう。その人の置かれた立場によって、価値観が一八〇度変ってくることもあり得る。情とはそういうものだ。
では、人の世の価値はついに相対的であるしかないか? 人間の実感に即する限り、そうとしか言えない。ならば、結局のところ、人間の世界から殺人がすっかりなくなることはないだろう。ある人間は、自分の置かれた状況に応じて、他の人間を殺してもよい、あるいは殺さねばならない理由を考え出すだろうから。
それでも、ではなく、それだからこそ、「人命は大事だ」と言い続ける必要があるのではないか、という考え方も出てくる。そうでないと、人の世は殺人が日常的に横行するような場になってしまいかねない、という心配から。これまた、用心のために、上から降りてくるお説教としての道徳であり、公的に正しいとされる。
最大の問題点は、以上のような道徳はタテマエというのに非常に近く、身勝手な本心を隠し、自分にとって都合のいいように使い回される可能性が常にあるところだ。いわゆる、偽善というやつ。
前回言ったように、「愛国心は悪党の最後の逃げ場」になり得るのだし、「世間」という日本特有とも言われる観念については、太宰治が次のように言っている。
世間とは、いつたい、何の事でせう。人間の複数でせうか。どこに、その世間といふものの実体があるのでせう。けれども、何しろ、強く、きびしく、こはいもの、とばかり思つてこれまで生きて来たのですが、しかし、堀木にそう言はれて、ふと、
「世間といふのは、君ぢやないか」
といふ言葉が、舌の先まで出かかつて、堀木を怒らせるのがイヤで、ひつこめました。(「人間失格」)
上の文中の堀木とは、一時は太宰が師と仰いだ井伏鱒二のことらしいが、そうであってもなくても、小説中のこの人物が「世間が許さない」と言うのには特別の悪意はない。だいたい、それこそ世間にありふれた道徳を説いているなら、文学者にしてもなお、自分の内面を見つめる必要などめったに感じないものだろう。それが一番やっかいなところかも知れない。
もっと言えば、権力者など、社会的な上位者こそこういうタテマエを振り回しがちなのも当然であろう。それこそが「教育」だと思い込んでいる人も少なくない。この場合、言われていることの内容より、それを「言い聞かせる」行為が即ち相手に対する上位の証であり、そこで証される上下関係こそ社会秩序を作るようにも感じられる。
最悪の場合、権力者とその側近たちが、抽象的な徳目に自分勝手な内容を盛り込み、それを「正しい善」であるとか「公共」であると言い立てて、国民を抑圧して誤った方向へ導く、なんぞということも、歴史上決して珍しくなかった。
小浜は、上のような行き方を、そもそもの最初から、人間性の本質を不当に軽んじた一種の転倒であるとする。そして、その端的な例として、プラトン/カントを初めとした西洋の大思想家を批判するのだが、最後には、その弊を脱したものとして、功利主義に、とりわけJ・S・ミルには共感を示している。
ミルと言えば、私などには馴染み深い徹底した自由主義・個人主義ではなく、『功利主義』の、次の言葉が引き合いに出される。「功利主義が正しい行為の基準とするのは、行為者個人の幸福ではなく、関係者全部の幸福なのである」。
ここだけみると、これは例えばカントの、「汝の意志の格率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」と同じような「命令」に見えるが、少し違う。
功利主義の格率から出てくる「命令」(なんて言葉を使うのがカントの悪影響かも知れない。ここは、当為、正しい方向、ぐらいの意味)は二つ挙げられている。その二つ目には、教育や世論の力で「各個人に、自分の幸福と社会全体の善とは切っても切れない関係があると思わせるようにすること」とある。またしても、「思わせるようにする」という言い方だと、実際はそうでもないのに空想的なキレイゴトを刷り込む、というふうに見えるが、よく考えてみれば、個人の幸福が社会と密接な繋がりがあるのは当然至極なのだ。
小浜は次のように言っている。
しかしいずれにしても、ここでミルが言いたいことは、「社会的諸関係のアンサンブル」(マルクス)としての本性をもつ人間は、その社会的諸関係を時間的・空間的に拡大して自分の視野の中に収めるようになればなるほど、その全体の「幸福」に配慮せざるを得なくなるということである。できるだけ広範囲の人々の利益や幸福に気配りすることが、結局は身のためでもあることがわかってくる。文明がよりよく発展することは、健全な公共精神が育つための条件の一つである、ということであろう。(P.281-282)
私の言葉でなるべく平易に言うとこうなる。
人間は必ず共同態の、人間関係の中で生きていくものだ。それなら、範囲の違いはあっても、誰か他の人といっしょに幸福になるしかない。よほどのサイコパスでもなければ、周りの人全員が不幸で苦しんでいるのに、自分だけ満足して喜んでいる、などということはあり得ない。非常に自己中心的な、自分大好き人間であっても、否むしろそういう者こそ、被自己承認欲求を満たすこと、つまり他人から認められ称賛されることを強く望んでいる。そのためには、他人にとって有益な何かを成し遂げなくてはならない。
そして、ここがいかにも功利主義なのだが、幸福とは各種の欲求が満たされた状態を言う。この点で、ミルはそうではないが(「満足した豚であるより……不満足なソクラテスであるほうがよい」は『功利主義中』の言葉)、小浜は欲求の対象に上下の区別をつける必要は認めない。優れた芸術作品に接したときのいわゆる精神的な喜びも、おいしい食物を食べたときの快楽も、人に満足をもたらし、幸福な状態に導く点で変わりはない。そしてどちらも、安寧な生活がなければ存分に味わってもいられないことからすれば、人の幸福のためには何が一番重要であるかは、自ずとわかろうというものだ。
この認識が充分に広く・深く行き渡るならば、「法律と社会の仕組みが、各人の幸福や〔もっと実際的にいえば〕利益を、できるだけ全体の利益と調和するように組み立て」ることも可能であろう。これは、先ほどの引用では省いた功利主義の「格率」から出てくる「命令」の第一である。
もちろんこの実現は簡単なことではない。「社会的諸関係を時間的・空間的に拡大して自分の視野の中に収める」ことが充分にできるために、人類はどれほどの知見と思慮を重ねていかねばならないことか。20世紀からこっちの世界の歴史を少し見ただけでも、ミルや小浜の言うところは単なる夢物語に過ぎないように思えてくるだろう
「けれども」と小浜は言う「非常に長い目で見れば、これらの数多い失敗の経験こそが「相互にうまくやる」交渉の技術と叡智とをゆっくりと培っていくはずである」(P.282)。「非常に長い目」とは、1000年単位のスケールだとも。
1000年先の未来など想像することもできないし、今まで当の小浜の言葉も援用して縷々述べてきた〈公〉と〈私〉のアポリアがどういう形で解けるのか、さっぱりわからないので、小浜に完全に同意することはできない。いや、同意も何も、「この課題の具体的な追究はすでに個別学としての倫理学の範疇を越えている」(P.468)というのが本書の最後の文なので、それはこちらで考えていくしかないとされているのである。
それでも、個人のささやかな幸福を犠牲にしてでも実現・実行すべき「公」や「正義」の概念が、この世にどれほどの悲惨をもたらしてきたかを考えただけでも、日々の幸福な営みをこそ第一として、そこから公共性を編み上げていくという方向性には、賛成せざるを得ない。人間の不幸をすっかりなくしてしまうことなど不可能だとは思うが、多少はましな未来を目指すためには、これを第一原則とするしかないであろう。
……と、思いながら、やはり気になってしまう。人は安寧な暮らしだけで満足できるのだろうか? そうでないとしたら、真理だの正義だの、神聖なものだの民族のアイデンティティだのといった、観念的な、「自分を超えたもの」→「自分をより高く大きな世界へ導いてくれそうなもの」への希求は消えない。それはどういう形になるのか? それもまた、政治や倫理学の範囲の問題ではない、と言われればその通りかも知れないので、それまたこちらで独自に考えていくしかないのだろう。



















