メインテキスト:小林秀雄『人生について』(中公文庫昭和53年、改版令和元年)
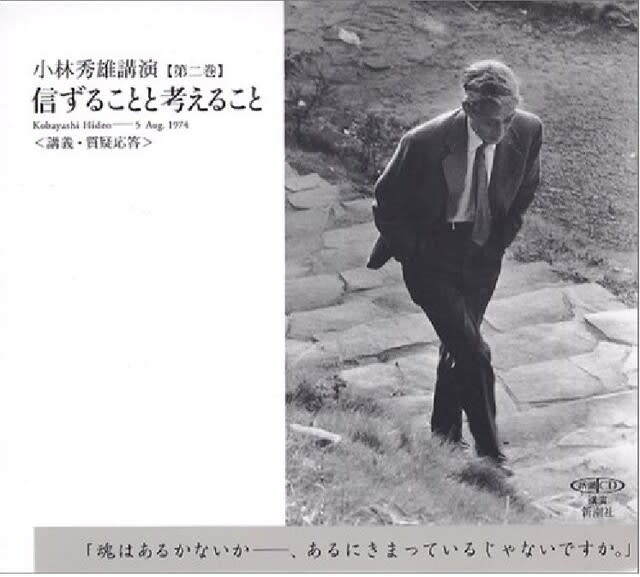
遅蒔きながら、明けましてお目出度う御座います。
お正月に相応しい話題はないかな、と漫然と考えておりましたら、いつの間にか小林さんの「信ずることと知ること」を思い出しました。相応しいかどうかわかりませんけど、それに因んだお話しをしてみます。
これは昭和49年8月に、九州の霧島で行われた講演で、大学生になりたての私は長路はるばる聴きに行ったのです。この頃はまだ、熱烈な小林ファンでしたから。
講演は超能力の話(小林さんは「念力」と言っていました)から始まりました。この年ユリ・ゲラーが初来日して、日本の、主にTVで、たいへんな話題になっていたのです。小林さんはゲラーの能力を信じていたようで、これにはちょっとびっくりしました。私はあんなのは怪しい奴だと当時から思っていましたから。しかしそれはほんのマクラで、話題はベルクソンから柳田國男へと進み、古今亭志ん生そっくりの語り口で、小林さんの真価を存分に発揮したよい講演でした。
今回はそのうち、ベルクソン(小林さんは当時の日本の一般的な呼び方で「ベルグソン」と言っています)にまつわるところを紹介します。
1913年にロンドン心霊研究会で行った講演(「生きている人のまぼろしと心霊研究」というタイトルで、白水社『ベルクソン全集』第五巻に所収)中で、彼はこんな話をしている。
ある会合で、いわゆる「正夢」が話題になった。一人の兵士が戦死する。同時刻に、遠く離れた母国にいる夫人が、その様子をまざまざと夢に見た。後でそのとき一緒にいた戦友から話を聴くと、その範囲では、夫人の夢は現実と寸分たがわず一致していたことがわかった。
これに対して高名な医師が次のように言った。私もその夫人を直接知っている。人格的にとても立派で、嘘をつくような人ではないから、その夢を見た話は信じよう。また、同種の話はこれまでにたくさんある。しかし、ここに困ったことがあって、現実とはなんの関わりもない夢のほうがはるかに多いのだ。その大多数の事例を考えずに、例外的に当った場合のみを取り上げるのはいかがなものか。
これを傍で聴いていた若い女性が、「先生の話はとても論理的で正しいのですけれど、でも私にはどうしても先生が間違っていると思えるのです」と言い、それをまた傍で聴いていたベルクソンは、私はこの娘さんのほうが正しいと思った、ということです。
こういうところを土台にして、小林さんはベルクソン哲学を祖述しようとして、それには失敗した、と本人が認めるに到るのですが、上だけでも非常に印象深くて示唆的です。
一番大雑把に言うと、人間の世界には科学的な真理と文学的(仮称)真実があるんだ、ということになりましょうか。
近代科学は計量可能なことしか問題にしない、と小林さんが言うところを、ちょっと私の言葉で言ってみます。この方面の知識には乏しいので、以前にも書いたことの繰り返しになりますが。
空中に放り出された物質は例外なく下に落ちる。計ってみると、そのものの重さや大きさには関わらず、落下速度も加速度も、原則として一定。これは、現在でも立派な大人でも誤解している場合があるぐらい不思議なことだ。一方、空に浮かんでいる月はいつまでたっても落ちてこないという不思議もある。これらすべての現象を作り出す力を、仮に重力とか引力とか名付ける。本当にそんなものがあるかどうか、わかったものではないが、ともかくあることにして、観察と計量に基づき、その力の働き方を法則としてまとめる。うまくまとまった法則を使えば、ある条件下では次に何が起こるか、地球上のみならず宇宙空間でも正確に予測することができ、また人為的に条件を作り出して、人間の生活に役立てることもできる。
こういったことの積み重ねの結果できた、たとえばパソコンを、私も今現に使っているので、これを悪く言うことはできません。どうも小林さんには、文学的な真理・価値を擁護しようとするあまり、こちらを軽視しすぎる傾向があり(科学的なことがわからなかった、という意味ではありません)、その悪影響を私も多分に受けています。いやもちろん、悪いのは私の怠惰と軽率のほうであるのは明かなんですが。
科学的な真理が軽視された場合の害は、超能力・超常現象の話にはつきものです。
普通に擦っただけでは曲ったりしないスプーンが曲るのは、いかにも不思議です。しかし、ある特定の人にだけそれが繰り返してできるのは、その人が、本当はやり方をうまく隠しているからではないか、とまずは疑った方がよい。
この「やり方」にも一種の法則はあるでしょうが、実際を隠した虚構を人目に見せるのが最初からの狙いなので、「トリック」と呼ばれるわけです。
娯楽としてのトリックは、「手品」あるいは「魔術」という芸です。昔の手品師は「種も仕掛け(=トリック)もありません」と言いながらやったようで、観客はだまされることまで含めて楽しんでいたのだから、それでいいのですが、「いや、これはトリックではなく、特殊な能力でやっている」と、虚構をもう一段引き上げると、罪作りにもなる。
あの当時、日本でもたくさんの超能力少年が出て来て、TVで紹介されたのですが、彼らはその後どうなったのか。それから、「空中浮遊」の超能力を看板にして多くの信者を獲得したあの教団のことを思い浮かべたら、「簡単には信じない」という素直でない心は、小林さんは嫌っていましたが、それも大事なんだな、と思わずにはいられません。
ベルクソンや小林さんが言っているのはもちろんそんなことではありません。
遠いところで亡くなった夫の姿をまざまざと見る。その根底には夫婦で過ごしたすべての時間と感情とが横たわっていることでしょう。よそから思いやれるのはそこまでであって、それ以上の内実に立ち入ることなどできません。どれくらいの年月をどう過ごせばそういう夢を見るのか、などと計量することなどもちろん不可能。他の夢と比べてどうこう言うのも、現実と見比べて合っているか間違っているか、などというのも無意味です。
全く個人的な、一回限りの体験がそこにある、としか言いようがない。小林さんはさらにこう言います。このような体験を不思議だとか不気味だとか言うのは、後から振り返った場合の「解釈」である。小林さん自身の体験として、ご母堂が亡くなられた後、大きな螢を見て、母は螢になったのだな、とそれこそ素直に、ごく自然に信じられた、と「感想」(中断したベルクソン論の第一章)には書かれています。
こういうのが「解釈を拒絶して動かないもの」(「無常といふ事」)なんでしょう。それを除いた人生には、究極のところ意味も価値も無い。言い換えると、正夢を見たことが「事実」であるかどうか、科学的な証明は不可能ですが、だから無意味だというなら、個人も、人生も、結局無意味だということになってしまう。
小林さんの文学的な営為は、全体として、個人としての人間の価値を闡明しようとするものだ、と言ってよいでしょう。いつの時代でもそうなんでしょうが、近現代でも、様々な形で、それを無視し、踏みにじろうとする動きは、人間集団の中から絶えず出て来ますので。
私はこれこそ最も貴重だと信じる者です。しかし、ここでまた、素朴かも知れませんけど、大きな問題が出て来ます。純粋に個人的な、他所からは決して窺い知れない切実な体験が万人にあるのはそうであるとして、ではそれを他へ伝えようとする試みはいったいなんなのか。それ自体が一種の背理としか言いようがないのではないか、という。
これに対する明確な答えは、小林さんの著作からは読み取れませんでしたが、『人生について』に収録されている「人形」という短いエッセイが、多少の参考になりそうな気がします。
エッセイと言い条、文庫で二頁と五行、極小のショートショートの味わいのある、不思議な掌編です。ずいぶん前に読んだ覚えがあるんですが、いつぞや小浜逸郎さんが「あれはいいね」とおっしゃるのを聞くまではすっかり忘れていました。
それくらいだから話はいたって簡単。「私」が急行列車の食堂車で、四人がけのテーブルで一人で夕飯を食べていると、六十年配の上品な老夫婦がやって来て、テーブルの向こう側に座った。
細君のほうは、大きな人形を抱えていた。背広にネクタイ、外套を羽織っていて、外套と同じ柄の鳥打ち帽をかぶっている。服装はまだ新しいが、人形のほうはずっとだいぶ年数を経ている。
帽子が床に落ちた。細君が目配せすると、夫が拾い上げ、「私」と目を合わせると、軽く目配せした。「どうも失礼」というふうに。
夫婦のスープとパンが運ばれてくると、細君はスプーンで掬って、まず人形の口元に運び、それから自分の口にいれる。それをずっと繰り返した。「私」は自分の手元にあったバター皿からバターを細君のパン皿に入れてやった。細君は気づかない。夫が「これは恐縮」と礼を言った。
ところへ、大学生ぐらいの娘が来て、「私」の隣に座った。彼女は「若い女性の鋭敏」ですぐに場に順応した。それで何をしたのかは書いてないが、つまり何も言わず、目の前の夫婦をジロジロ見たりもせず、普通に食事をしたのだろう。
いや、「普通に」って……。
私が文中の「私」の立場だったとしたら? お婆さんがママゴトをしてる、微笑ましいなあ……とは思わなかったでしょうねえ。怖くてその場を逃げ出す、が一番ありそうです。
筆者の小林さんは、イコール文中の「私」とは限りませんが、最後に、
「異様な会食は、極く当り前に。静かに、敢へて言へば、和やかに終つたのだが、もし、誰かが、人形について余計な発言でもしたら、どうなつたであらうか」
と、書いています。普通に、静かに食事をする以外は、すべて「余計な」ことだと言いたいらしい。
普通の小説なら、「私」は、夫から話を聞くなり何かで、この夫婦の事情を知ることになり、それこそが作品の本体になるでしょう。それが「余計なこと」なら、近代文学は余計なことばかり書いていることになります。
けれど、そういう好奇心も人間には普通なんですから、読者の興味をつなぐためには欠かせない要素になるのは仕方ないことだと言えるでしょう。
それに第一、「私」も簡単になら思いを巡らしています。この人形は息子に違いない。古びたさまからして、相当前から、彼女の手元にあるのだろう。息子は戦死したのか(この文章の初出は昭和37年10月6日朝日新聞PR版)。夫は妻の乱心を鎮めるためにこの人形を与えたのだが、彼女が回復することはなく、爾来こうして人形ぐるみで連れて歩いているのか。まあそんなところだろうか。
これは「推察」であり、「解釈」です。先のほうでは、次の推量もあります。
「もしかしたら、彼女は、全く正気なのかも知れない。身についてしまつた習慣的行為かも知れない。とすれば、これまでになるのには、周囲のあさはかな好奇心とすいぶん戦はねばならなかつたらう。それほど彼女の悲しみは深いのか」
「あさはか」と言って、そんなことですましていられるのは、畢竟「私」がこの老婦人にとって所詮ゆきずりの他人にしかすぎないからだ、と「周囲」からは言われるかも知れません。
その「周囲」の人々は、夫に対しては、彼をも狂気とみなすか、そうでなければ「無責任」だと非難したかも。「どうして医者にみせないのか」と。こういうところでは、昭和37年当時より現在のほうが、見る目が厳しくなっているように思いますが。
それで、医者にかかったとすれば? たぶん、統合失調症とか分裂病とか、なんらかの診断名がついたでしょう。それによって夫人は、この社会の中で一定の「立場」が与えられたような感じになり、人々は安心したわけでしょう。
言い換えると、理解出来ない行為の理解できなさには理由があるのだ、と納得させてもらえるような気にはなる。
それによって、夫婦がより幸せになるかどうかはわからない。だから精神医療は無意味だとまでは言いません。社会の安寧秩序を守る決まりごとのうちには、そういったことも含まれるのですから。
ただ、それとは関係のないところに、彼女の深い悲しみはある。それは誰にも、どうすることもできない。絶対に彼女一人のものだ。それを認めることが、つまり彼女を認めるということに他ならない。それで。
夫は妻のやることに合わせる。食堂車でたまたま同席した「私」と若い女性は、好奇な目を向けず、何も穿鑿がましいことはしなかった。敢えて言えば、「そういうもんだろう」というだけ。「黙ってやり過ごす」のと変わらない。
そのうえで、少しの穿鑿がましい「解釈」も加えながら、一人の人間の内部にはどれほど大きなものが秘められているかを、それには畢竟直接手は触れられない悲しみも含めて示すことができるなら、文学の存在価値もある、と言える。そうではありませんか?
【冒頭の写真は、「「信ずることと知ること」を解題して『信ずることと考えること―講義・質疑応答 (新潮CD講演 小林秀雄講演 第2巻)』としてCD化したものです。このうち、今回話題にしたベルクソンに関するところを、N GOという人がYou Tubeにアップしてくれています。
https://www.youtube.com/watch?v=NI02GR0FpeA】
【「信じることと知ること」の題名でfrom_nagatoという人がアップしてくださった講演録もあるのですが、こちらは昭和51年に東京の三百人劇場で行われたもので、私はこちらも直に聞きました。内容は二年前の講演の、柳田國男に関するところを「前にも話したことがあるが」と、ほぼ繰り返したものです。
些末で僭越な訂正をしますと、柳田が幼少期を過ごした茨城県の村「布川」を、小林さんは「ぬのかわ」と言っていますが、これは「ふかわ」が正しいのです。わりあいと近所なので、たまたま知っていました。
https://www.youtube.com/watch?v=D4GKZr0jMfE】
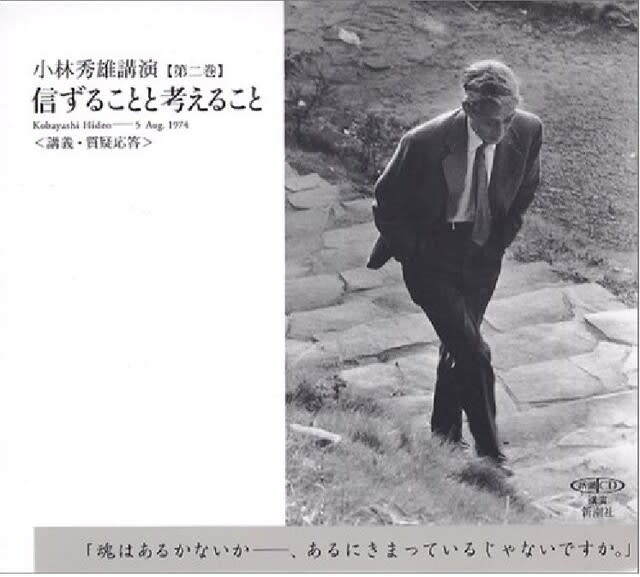
遅蒔きながら、明けましてお目出度う御座います。
お正月に相応しい話題はないかな、と漫然と考えておりましたら、いつの間にか小林さんの「信ずることと知ること」を思い出しました。相応しいかどうかわかりませんけど、それに因んだお話しをしてみます。
これは昭和49年8月に、九州の霧島で行われた講演で、大学生になりたての私は長路はるばる聴きに行ったのです。この頃はまだ、熱烈な小林ファンでしたから。
講演は超能力の話(小林さんは「念力」と言っていました)から始まりました。この年ユリ・ゲラーが初来日して、日本の、主にTVで、たいへんな話題になっていたのです。小林さんはゲラーの能力を信じていたようで、これにはちょっとびっくりしました。私はあんなのは怪しい奴だと当時から思っていましたから。しかしそれはほんのマクラで、話題はベルクソンから柳田國男へと進み、古今亭志ん生そっくりの語り口で、小林さんの真価を存分に発揮したよい講演でした。
今回はそのうち、ベルクソン(小林さんは当時の日本の一般的な呼び方で「ベルグソン」と言っています)にまつわるところを紹介します。
1913年にロンドン心霊研究会で行った講演(「生きている人のまぼろしと心霊研究」というタイトルで、白水社『ベルクソン全集』第五巻に所収)中で、彼はこんな話をしている。
ある会合で、いわゆる「正夢」が話題になった。一人の兵士が戦死する。同時刻に、遠く離れた母国にいる夫人が、その様子をまざまざと夢に見た。後でそのとき一緒にいた戦友から話を聴くと、その範囲では、夫人の夢は現実と寸分たがわず一致していたことがわかった。
これに対して高名な医師が次のように言った。私もその夫人を直接知っている。人格的にとても立派で、嘘をつくような人ではないから、その夢を見た話は信じよう。また、同種の話はこれまでにたくさんある。しかし、ここに困ったことがあって、現実とはなんの関わりもない夢のほうがはるかに多いのだ。その大多数の事例を考えずに、例外的に当った場合のみを取り上げるのはいかがなものか。
これを傍で聴いていた若い女性が、「先生の話はとても論理的で正しいのですけれど、でも私にはどうしても先生が間違っていると思えるのです」と言い、それをまた傍で聴いていたベルクソンは、私はこの娘さんのほうが正しいと思った、ということです。
こういうところを土台にして、小林さんはベルクソン哲学を祖述しようとして、それには失敗した、と本人が認めるに到るのですが、上だけでも非常に印象深くて示唆的です。
一番大雑把に言うと、人間の世界には科学的な真理と文学的(仮称)真実があるんだ、ということになりましょうか。
近代科学は計量可能なことしか問題にしない、と小林さんが言うところを、ちょっと私の言葉で言ってみます。この方面の知識には乏しいので、以前にも書いたことの繰り返しになりますが。
空中に放り出された物質は例外なく下に落ちる。計ってみると、そのものの重さや大きさには関わらず、落下速度も加速度も、原則として一定。これは、現在でも立派な大人でも誤解している場合があるぐらい不思議なことだ。一方、空に浮かんでいる月はいつまでたっても落ちてこないという不思議もある。これらすべての現象を作り出す力を、仮に重力とか引力とか名付ける。本当にそんなものがあるかどうか、わかったものではないが、ともかくあることにして、観察と計量に基づき、その力の働き方を法則としてまとめる。うまくまとまった法則を使えば、ある条件下では次に何が起こるか、地球上のみならず宇宙空間でも正確に予測することができ、また人為的に条件を作り出して、人間の生活に役立てることもできる。
こういったことの積み重ねの結果できた、たとえばパソコンを、私も今現に使っているので、これを悪く言うことはできません。どうも小林さんには、文学的な真理・価値を擁護しようとするあまり、こちらを軽視しすぎる傾向があり(科学的なことがわからなかった、という意味ではありません)、その悪影響を私も多分に受けています。いやもちろん、悪いのは私の怠惰と軽率のほうであるのは明かなんですが。
科学的な真理が軽視された場合の害は、超能力・超常現象の話にはつきものです。
普通に擦っただけでは曲ったりしないスプーンが曲るのは、いかにも不思議です。しかし、ある特定の人にだけそれが繰り返してできるのは、その人が、本当はやり方をうまく隠しているからではないか、とまずは疑った方がよい。
この「やり方」にも一種の法則はあるでしょうが、実際を隠した虚構を人目に見せるのが最初からの狙いなので、「トリック」と呼ばれるわけです。
娯楽としてのトリックは、「手品」あるいは「魔術」という芸です。昔の手品師は「種も仕掛け(=トリック)もありません」と言いながらやったようで、観客はだまされることまで含めて楽しんでいたのだから、それでいいのですが、「いや、これはトリックではなく、特殊な能力でやっている」と、虚構をもう一段引き上げると、罪作りにもなる。
あの当時、日本でもたくさんの超能力少年が出て来て、TVで紹介されたのですが、彼らはその後どうなったのか。それから、「空中浮遊」の超能力を看板にして多くの信者を獲得したあの教団のことを思い浮かべたら、「簡単には信じない」という素直でない心は、小林さんは嫌っていましたが、それも大事なんだな、と思わずにはいられません。
ベルクソンや小林さんが言っているのはもちろんそんなことではありません。
遠いところで亡くなった夫の姿をまざまざと見る。その根底には夫婦で過ごしたすべての時間と感情とが横たわっていることでしょう。よそから思いやれるのはそこまでであって、それ以上の内実に立ち入ることなどできません。どれくらいの年月をどう過ごせばそういう夢を見るのか、などと計量することなどもちろん不可能。他の夢と比べてどうこう言うのも、現実と見比べて合っているか間違っているか、などというのも無意味です。
全く個人的な、一回限りの体験がそこにある、としか言いようがない。小林さんはさらにこう言います。このような体験を不思議だとか不気味だとか言うのは、後から振り返った場合の「解釈」である。小林さん自身の体験として、ご母堂が亡くなられた後、大きな螢を見て、母は螢になったのだな、とそれこそ素直に、ごく自然に信じられた、と「感想」(中断したベルクソン論の第一章)には書かれています。
こういうのが「解釈を拒絶して動かないもの」(「無常といふ事」)なんでしょう。それを除いた人生には、究極のところ意味も価値も無い。言い換えると、正夢を見たことが「事実」であるかどうか、科学的な証明は不可能ですが、だから無意味だというなら、個人も、人生も、結局無意味だということになってしまう。
小林さんの文学的な営為は、全体として、個人としての人間の価値を闡明しようとするものだ、と言ってよいでしょう。いつの時代でもそうなんでしょうが、近現代でも、様々な形で、それを無視し、踏みにじろうとする動きは、人間集団の中から絶えず出て来ますので。
私はこれこそ最も貴重だと信じる者です。しかし、ここでまた、素朴かも知れませんけど、大きな問題が出て来ます。純粋に個人的な、他所からは決して窺い知れない切実な体験が万人にあるのはそうであるとして、ではそれを他へ伝えようとする試みはいったいなんなのか。それ自体が一種の背理としか言いようがないのではないか、という。
これに対する明確な答えは、小林さんの著作からは読み取れませんでしたが、『人生について』に収録されている「人形」という短いエッセイが、多少の参考になりそうな気がします。
エッセイと言い条、文庫で二頁と五行、極小のショートショートの味わいのある、不思議な掌編です。ずいぶん前に読んだ覚えがあるんですが、いつぞや小浜逸郎さんが「あれはいいね」とおっしゃるのを聞くまではすっかり忘れていました。
それくらいだから話はいたって簡単。「私」が急行列車の食堂車で、四人がけのテーブルで一人で夕飯を食べていると、六十年配の上品な老夫婦がやって来て、テーブルの向こう側に座った。
細君のほうは、大きな人形を抱えていた。背広にネクタイ、外套を羽織っていて、外套と同じ柄の鳥打ち帽をかぶっている。服装はまだ新しいが、人形のほうはずっとだいぶ年数を経ている。
帽子が床に落ちた。細君が目配せすると、夫が拾い上げ、「私」と目を合わせると、軽く目配せした。「どうも失礼」というふうに。
夫婦のスープとパンが運ばれてくると、細君はスプーンで掬って、まず人形の口元に運び、それから自分の口にいれる。それをずっと繰り返した。「私」は自分の手元にあったバター皿からバターを細君のパン皿に入れてやった。細君は気づかない。夫が「これは恐縮」と礼を言った。
ところへ、大学生ぐらいの娘が来て、「私」の隣に座った。彼女は「若い女性の鋭敏」ですぐに場に順応した。それで何をしたのかは書いてないが、つまり何も言わず、目の前の夫婦をジロジロ見たりもせず、普通に食事をしたのだろう。
いや、「普通に」って……。
私が文中の「私」の立場だったとしたら? お婆さんがママゴトをしてる、微笑ましいなあ……とは思わなかったでしょうねえ。怖くてその場を逃げ出す、が一番ありそうです。
筆者の小林さんは、イコール文中の「私」とは限りませんが、最後に、
「異様な会食は、極く当り前に。静かに、敢へて言へば、和やかに終つたのだが、もし、誰かが、人形について余計な発言でもしたら、どうなつたであらうか」
と、書いています。普通に、静かに食事をする以外は、すべて「余計な」ことだと言いたいらしい。
普通の小説なら、「私」は、夫から話を聞くなり何かで、この夫婦の事情を知ることになり、それこそが作品の本体になるでしょう。それが「余計なこと」なら、近代文学は余計なことばかり書いていることになります。
けれど、そういう好奇心も人間には普通なんですから、読者の興味をつなぐためには欠かせない要素になるのは仕方ないことだと言えるでしょう。
それに第一、「私」も簡単になら思いを巡らしています。この人形は息子に違いない。古びたさまからして、相当前から、彼女の手元にあるのだろう。息子は戦死したのか(この文章の初出は昭和37年10月6日朝日新聞PR版)。夫は妻の乱心を鎮めるためにこの人形を与えたのだが、彼女が回復することはなく、爾来こうして人形ぐるみで連れて歩いているのか。まあそんなところだろうか。
これは「推察」であり、「解釈」です。先のほうでは、次の推量もあります。
「もしかしたら、彼女は、全く正気なのかも知れない。身についてしまつた習慣的行為かも知れない。とすれば、これまでになるのには、周囲のあさはかな好奇心とすいぶん戦はねばならなかつたらう。それほど彼女の悲しみは深いのか」
「あさはか」と言って、そんなことですましていられるのは、畢竟「私」がこの老婦人にとって所詮ゆきずりの他人にしかすぎないからだ、と「周囲」からは言われるかも知れません。
その「周囲」の人々は、夫に対しては、彼をも狂気とみなすか、そうでなければ「無責任」だと非難したかも。「どうして医者にみせないのか」と。こういうところでは、昭和37年当時より現在のほうが、見る目が厳しくなっているように思いますが。
それで、医者にかかったとすれば? たぶん、統合失調症とか分裂病とか、なんらかの診断名がついたでしょう。それによって夫人は、この社会の中で一定の「立場」が与えられたような感じになり、人々は安心したわけでしょう。
言い換えると、理解出来ない行為の理解できなさには理由があるのだ、と納得させてもらえるような気にはなる。
それによって、夫婦がより幸せになるかどうかはわからない。だから精神医療は無意味だとまでは言いません。社会の安寧秩序を守る決まりごとのうちには、そういったことも含まれるのですから。
ただ、それとは関係のないところに、彼女の深い悲しみはある。それは誰にも、どうすることもできない。絶対に彼女一人のものだ。それを認めることが、つまり彼女を認めるということに他ならない。それで。
夫は妻のやることに合わせる。食堂車でたまたま同席した「私」と若い女性は、好奇な目を向けず、何も穿鑿がましいことはしなかった。敢えて言えば、「そういうもんだろう」というだけ。「黙ってやり過ごす」のと変わらない。
そのうえで、少しの穿鑿がましい「解釈」も加えながら、一人の人間の内部にはどれほど大きなものが秘められているかを、それには畢竟直接手は触れられない悲しみも含めて示すことができるなら、文学の存在価値もある、と言える。そうではありませんか?
【冒頭の写真は、「「信ずることと知ること」を解題して『信ずることと考えること―講義・質疑応答 (新潮CD講演 小林秀雄講演 第2巻)』としてCD化したものです。このうち、今回話題にしたベルクソンに関するところを、N GOという人がYou Tubeにアップしてくれています。
https://www.youtube.com/watch?v=NI02GR0FpeA】
【「信じることと知ること」の題名でfrom_nagatoという人がアップしてくださった講演録もあるのですが、こちらは昭和51年に東京の三百人劇場で行われたもので、私はこちらも直に聞きました。内容は二年前の講演の、柳田國男に関するところを「前にも話したことがあるが」と、ほぼ繰り返したものです。
些末で僭越な訂正をしますと、柳田が幼少期を過ごした茨城県の村「布川」を、小林さんは「ぬのかわ」と言っていますが、これは「ふかわ」が正しいのです。わりあいと近所なので、たまたま知っていました。
https://www.youtube.com/watch?v=D4GKZr0jMfE】















