爽やかな秋晴れの昨日、久し振りに美術館に出かけました。
千葉市美術館で先月から開催されている 「田中一村 ~ 新たなる全貌」展。猛暑が一段落してからにしよう、とチャンスを窺っていましたが、やっとその日の到来です。しかしまだしつこく日中の日差しは強烈で、日傘を忘れたのでシミの増えることを気にしつつ、駅から美術館までの、あまり好みでない区間を、必死でこっちの日陰あっちの日陰、と飛び歩きながら行きました。画像は美術館兼市役所の入口です。太い柱に巻いてあるポスターを柱二つ分入れると一方の絵が見にくくなるので別々に撮ってくっつけてみたものです。

田中一村(1908-77)は、栃木県に生まれ、千葉市に20年住み、
奄美大島に渡って亜熱帯植物を題材にした日本画を描き、生前
それらの作品を公表する機会もなく無名のまま没した画家です。
没後の1980年代、テレビの美術番組での紹介が空前の反響を呼び
広く全国に知られるようになりました。
パンフレットにはこのような説明がありましたが、私がこの画家を知ったのは去年か一昨年、友人を通してでした。田中一村記念美術館に行くだけの目的で奄美大島まで飛んで行き、日帰りした彼女から、行った甲斐があった!という話をきいていたので、新聞で展覧会があるのを知り、この画家の絵との出会いにワクワクしていました。
美術館に着いて、その混み様にびっくり。中高年がとても多いことにもびっくり。もしかしてテレビで特集でもあったのかしら・・と思ったら、先週の日曜美術館で紹介されたようですね。19日(日)の夜8時からは再放送されるとのことです。
展覧会の構成は:
第一章「東京時代」 1-1神童 「米邨(べいそん)」
1-2東京美術学校退学後の大活躍
1-3昭和初期の新展開
第二章「千葉時代」 2-1千葉へ
2-2千葉寺風景を描く
2-3「一村」への改号(昭和22年 戦後の新しい出発)
2-4公募展への挑戦
2-5襖絵の仕事
2-6やわらぎの郷 聖徳太子の天井画制作
2-7四国・九州への旅
2-8千葉との別れ
第三章「奄美時代」 3-1奄美へ
3-2スケッチについて
3-3奄美での作品
資料も含み250点、と、過去最大規模の展観で一村の画家としての実像に迫った展覧会です。神童と呼ばれただけあり、会場に入ってすぐの短冊に描かれた「蛍図」は、8才の子供が描いたとは思えません。後に続く作品でも、これが十代のときの作品か、と、画家の年齢と絵とを見合わせながら誰も彼も感心していました。
千葉時代に移り、米邨から一村へ改号するきっかけとなったのは、「白い花」が川端龍子主催の第19回青龍社展に入選してから。しかしその後出品した「秋晴」と「波」のうち、「波」が入選し、自信作だった「秋晴」が落選したことで「波」の入選を辞退。川端龍子と意見が合わなくなり青龍社から離れます。このあたりが一村の性格というか、生き方を象徴しているように思えました。その後の公募展は落選が続き、中央画壇からも離れ、奄美大島へ、と移住することになります。こんなことはきっとwikiで全部わかることですね。
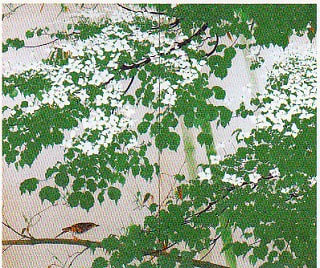 (白い花)
(白い花)
見ていてゾクゾクする絵も沢山あるし、あれっ、と思う絵もありましたが、奄美時代はハッとするような南国の風景画が続き圧巻でした。左下は奄美時代の最大の作品である「不喰芋と蘇鉄」。美術館入口の柱の絵の一つです。

《背景が神の時間と言われる夕暮れの空
クワズ芋は花芽から実が朽ちるまでの姿が描かれ、
四季を表わすとともに、誕生から死までの時間の
経過もこめられているかのようだ》
との解説を読んで、はじめてそうだったのか~、と尽々見つめてしまいましたが、皆さん同じ思いのようで、ここで流れが止って渋滞でした。この隣には入口の柱の左側の絵「アダンの海辺」があり、それにも色々な意味が含まれているようです。
生計を立てるため、地元の紬工場で染色工として働きながら最後まで絵を描き続け、お世話になった人には描いた絵をお返しにし、生前一度も作品を公表することなく無名で独身のまま没した田中一村。もし彼が中央画壇に認められていたら、きっと奄美大島には行っていなかったかもしれないし、このような南国の風景は描き得なかっただろうし、「孤高の画家」などとは言われなかったし、・・・と考えて行くと、人生ってアッ、と思ったときはすでに遅しだし、だからと言って戻って別の道に進んだほうが良いとは限らない。最後は自分との対話のみかも。
奄美の美術館に行った友人からお土産に貰った絵ハガキの絵はこんなでした。
「奄美の杜①」~ビロウ・コンロンカに蝶~
又、そのとき貰ったパンフレットに書かれていた一村の言葉は;
私の繪の最終決定版の繪がヒューマニティで
あろうが、悪魔的であろうが、畫の正道であ
るとも邪道であるとも何と批評されても私は
満足なのです。それは見せる為に描いたので
はなく私の良心を納得させる為にやったので
すから・・・・・・。(田中一村の手紙より)
見応えのある展覧会でした。
一村さんについてもっと知りたくなりました。
美しい独身のお姉様のことも知りたくなりました。
蛇足:
このとこるずっとマウスの調子が悪く、目指している場所にすんなり動いてくれずイライラしていたのですが、今日とうとう動かなくなりました。マウスが使えないとパソコンが使えないんだ、と初めて認識。寿命だったのでしょうか。慌てて息子の使っていないPCからマウスだけ拝借して、やっと投稿にこぎつけました。スイスイと動くマウスは快適だ~、と、あたり前のことを喜んでいます。次はパソコン本体かなぁ。その前にデフラグとかクリーンアップをやってみようと思っているのですが、私、出来るかどうか。














 ★グイド・レーニ「アタランテとヒッポメネス」
★グイド・レーニ「アタランテとヒッポメネス」

 これで終りにしたいところですが、先月、最終日の6月27日に「
これで終りにしたいところですが、先月、最終日の6月27日に「
















 )
)


 ひと休みみしようとデパートの屋上に出たら、いつものベーグルカフェがビアホールになっていました。一人でビールを頼む勇気はありませんでしたので、コーヒーと出来あいのサンドイッチを注文。コーヒーも紙コップなので、それなりのお値段です。屋上はデパオクっていうのでしょうかね?
ひと休みみしようとデパートの屋上に出たら、いつものベーグルカフェがビアホールになっていました。一人でビールを頼む勇気はありませんでしたので、コーヒーと出来あいのサンドイッチを注文。コーヒーも紙コップなので、それなりのお値段です。屋上はデパオクっていうのでしょうかね?



 サッカーワールドカップ2010
サッカーワールドカップ2010 


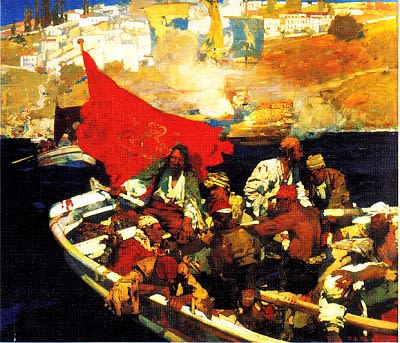



























 このあと別館に移動しました。
このあと別館に移動しました。










 まるでオバケ屋敷に紛れ込んだような階段。
まるでオバケ屋敷に紛れ込んだような階段。





 「赤い服の女」のところに直行したかったけど、大使の旧執務室が自由に見れるとのことなので、もう少し本館内を見てからにする。
「赤い服の女」のところに直行したかったけど、大使の旧執務室が自由に見れるとのことなので、もう少し本館内を見てからにする。


































