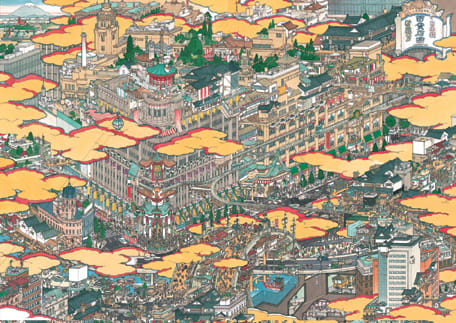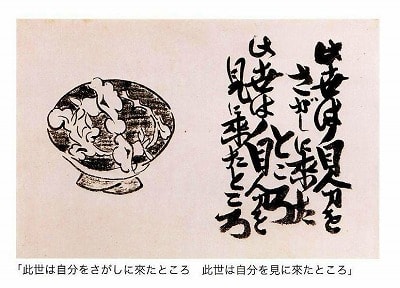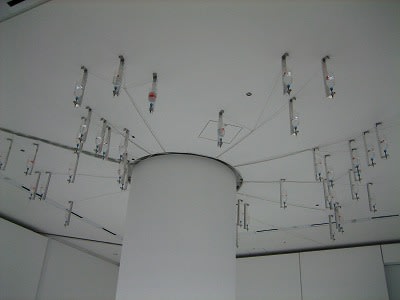グレーな空模様の、そのうえ雨まで降り出した先週の金曜日。
ちょうど今日のような天気だったかな。
ウキウキ~♪ワクワク~♪雨に唄えば♪的 気分だった私は
南青山にあるギャラリー、Space Yuiで開催中の「ぷっくり布箱」展を見に行ってきました。
以前、Camelliaさんのブログ記事で知って、先生の作品をHPを通して購入。
もちろん、Came-chanがご自身のブログで見せて下さった、沢山の布箱作品に惚れちゃったから。
デジカメを、また忘れてしまったので、ブログ用に現地で写真を撮ることは、残念ながら出来ませんでした。
入口をはいったところには、Cameーchanブログでも事前に拝見していたミニミニ布箱がたくさん!
ギャラリーの方が、先生いらっしゃいますよ~と、紹介してくださり、
ドキドキしながら、どうしてこの展示会を知ったかを、さらっと話しました。
初めて見る、たくさんの素晴らしい「ぷっくり布箱」の数々でしたが、
今日という日の記念に何を持ち帰ろうか、すっごく悩みました。
だいたいMy予算でおおざっぱに諦めるものは諦め、
手ごろなものの中でどうするか、ですけど、布の柄がどれも魅力的なんです。
自分用にもほしいし、プレゼントにしても喜ばれそう♪
で・・・選んだのは・・・やっぱり私、欲張りなのかなぁ。
三段腹、いえ、三段重でした!

中は、というと、

八ッとするような黄緑色。

ある御祝いに、とも思いましたが、手放したくなくなっちゃった~。
先生は随分前に、NHKテレビでお見受けしましたが、その何倍もステキな方でした。
ピーターパンみたいで!
青山は、ブラっとするだけでも退屈しません。
今回は、骨董通りで、すっごくおいしそうなアップルパイのお店を見つけました。
その名は、Granny Smith
ふらふらっと店内に吸い込まれ、家用にテイクアウト。
お家でお茶とともに、と、思ったけど・・・
その近くに「MUJIカフェ」もあったのです。

MUJIで食べ、(ケータイでパチリ)

家では、夕食後のデザートに、カスタード味と、チェリー味のアップルパイを!
夫と、半分ずつにして、両方の味見ができました。美味しかったぁ~
ますます3段腹から4段へ、と、腹ばかりが肥えていって、いいの~?
だめ~!
また、青山をいっぱい歩こうっと。




























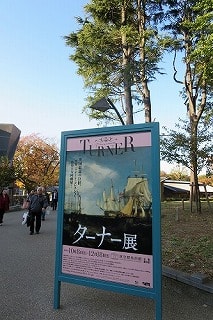





















 )
)