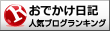とんでもない、世界に足を突っ込んだ。
群馬地方に、足を運んで5年近く、
一カ所の寺に、神社に幾度も訪ね、
出かけるからと言えば、
群馬ですかと、言われ、
群馬地方に、足を運んで5年近く、
一カ所の寺に、神社に幾度も訪ね、
出かけるからと言えば、
群馬ですかと、言われ、
私の顔は群馬県でした。
今日のブログ、編集トップで、
つい先に見てしまい、
気持ちが広くなりました。
絵、榛名山麓に広がる、のどかな町、箕郷町に住む、
今日のブログ、編集トップで、
つい先に見てしまい、
気持ちが広くなりました。
絵、榛名山麓に広がる、のどかな町、箕郷町に住む、
師匠が幼いころ
間違い・・師匠からの指摘です
20代でお兄さん2人と描いた絵が👇

拡大すれば、なんと、なんとです。


師匠が描いた格子天井の絵は、何枚もあります。
次回以降に展示いたします。
次回以降に展示いたします。
お寺さんの名は、
私の仕事が終わるまで、
私の仕事が終わるまで、
おまちくださいますよう。
でもちょっとだけ写真で・・・。




👇 内陣と外陣の欄間の彫刻、
もしも、墨書が見つかればと、
滑舌の悪い私の申し出に、電話の向こう、
メリハリのある声は、
興味があります、ご自由に・・・と。
もしも、墨書が見つかればと、
滑舌の悪い私の申し出に、電話の向こう、
メリハリのある声は、
興味があります、ご自由に・・・と。
繊細な、埃払いの仕事です。
師匠を超えての対応に、心は痛むのですが、
約束してしまって、後戻りはできません。
約束してしまって、後戻りはできません。
でも、いいよね、師匠のお姉さんが嫁いだお寺。
甥御のご住職、互いの歴史観に気が合いまして・・。
甥御のご住職、互いの歴史観に気が合いまして・・。
ゴメン・・師匠。
その彫刻が👇





榛東村に行く途中で、浅間山
赤城山
間違いは、師匠からの指摘
電柱のあるのも、写真に構えが無くて
いい‼
電柱のあるのも、写真に構えが無くて
いい‼
写真で見る、師匠の旦那さん
実物は、芯の通った
いい、男だった
実物は、芯の通った
いい、男だった
迷惑文・抹消には忌憚なく申しつけを