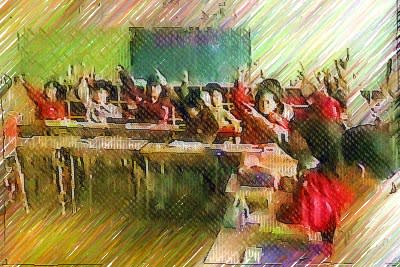
50回浜松授業研究の会 2月14日
石井先生が、授業のあるべき姿について、今までの実践の手の内をさらけ出して語ってくださった。
あまりにも私たちの実践とレベルの違ったものだった。
ああ、授業次第で、子供とは、ここまで純粋な姿になり、ここまで追求する子供になるのかと恥ずかしくなる。
子供のレベルがどうの、最近の親はどうのと、ごたくを並べる前に、
もう一度初心に返って、教師のいろはから、純粋にその道を進まねばと思い知らされた。

追求方式の授業の基本
国語は言葉をどれだけきちんと読むかで、真実に迫れるかがちがう。
初めのイメージ(思い込み)を真実性の高いイメージに変える。

手順
1 場面を分けてラベリングする
・場面ごとこ「 ~が した」とまとめる。
2 変だ おかしい という言葉のある文を選ぶ
①ふつうは ~なのにここでは...
②前は~だったのに、ここでは
変だおかしいがみつからないのは、読み方が浅い。
おかしいのは、言動に含まれている。
例えば大造じいさんは、打ちたくて仕方なかったのに、打てるのに打てない。
最初は物語を、場面に 場面を文に 文を単語に 最終的には言葉にこだわる
3 単語.文節に分ける
変だおおかしいを見つけるのはカン。
○気になる言葉をみつける。
・なくてもいいのにある言葉
・ふつうは~と描くのに、ここではこうかいてある。
・他では~と描いてあるのに、ここでは~と書いてある。言葉が変わるのはおかしい。
・逆説の言葉には、ドラマが含まれている。要注意
こういう視点を持っていると、重要な言葉にたどり着く。

4 問題をつくる
子どもが作るための力を子どもにつけていく。
・人物レベル
変だ、おかしい言動の理由を問う
・言葉レベル
文節・単語の意味を問う
5 問題を解決する
どれだけ、子どもたちのもっていいる生活概念を科学的概念に変えられるか。
・辞書で文節・単語の意味を調べて、科学的概念を習得する。
・科学的概念に代えた、文節・単語の意味を適用して論証する。(推理)

実践
4月に短い教材で行う。
俳句はとても有効。
雪とけて 村いっぱいの 子どもかな
雪/とけて 村/いっぱい/の 子ども/かな
切ると、着目する。
思うと考える乃違い。思うは一つのことを思い続ける。
考えるは2つ以上のものを比較して、どちらがいいか選択する。
雪で問題を作って。
①頭より上?
②腰ぐらい
③足跡のつくぐらい?
雪だけで、問題をどんどんつくる。
当然役に立たない問題も出てくるが、その中で、こういう問題は良い問題で、
こういう問題はよくないと分かっていく。ありとあらゆることをやって、だんだん精選していく。

村って何人ぐらいいるの? どれぐらい雪が溶けたの?
ただの雪っておかしい。
対立問題も教えた。
どれぐらい積もったの。
1m 2m 3mなど具体的に
とけては、どのぐらいでとけたの?
とけての「て」クラス全体の文化になっていく。
いっぱいっは俳句の重要な言葉
いっぱいには、たくさんでない意味もある。
いっぱいは隙間なくあふれるぐらい。
村に1000人いても隙間をふさぐのは無理。
じゃあ、いっぱいの意味はと子どもたちと考えていく。
授業の中で、教師も困る。子どももひかなくなる。
かなに行き着く。感動とのっている。
このとき、感動は互換だと気付いた。
舌 におい 触覚が消えた。
耳か目が残って、実践してみて修練していった。

こういうビデオを見て、自分にないものがここにあるとカルチャーショックを感じる。そうでないと、教師も変わらない。
|
51回 |
4月11日 | 土 | 9:00 | 15:00 | 天竜壬生ホール | 第1会議室 |
| 52回 | 5月9日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第1会議室 |










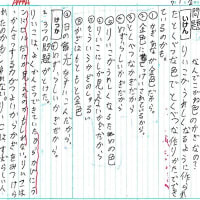
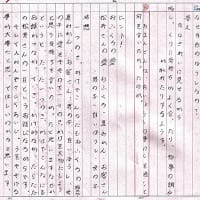
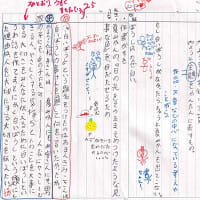
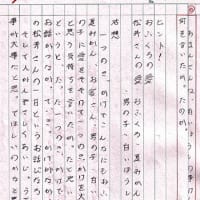
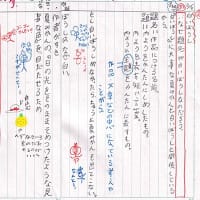
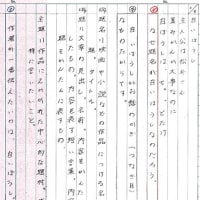
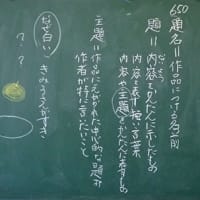
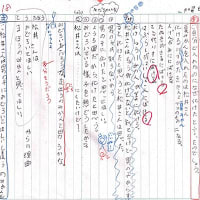
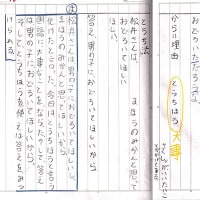
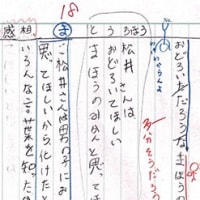
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます