入玉模様の将棋は、頭がクラクラする。
前回は佐藤康光九段の「三冠王」をかけた死闘について語ったが(→こちら)、今回の舞台は名人戦。
将棋の終盤というのはスリリングで、詰むや詰まざるやのスプリント勝負もドキドキするが、玉が上部に逃げ出す形の競り合いも、迫力満点である。
特に秒読みで入玉模様になると、駒の配置がゴチャゴチャしてわけがわからなくなり、まともな手筋が通じないカオスの世界に突入。
解説するプロですら、
「どひゃあ!」
「ひええ!」
「そっちですか!」
など奇声をあげるハメに。
そんな見る分には楽しい、入るか捕まるかの攻防だが、指している方はけっこう得手不得手が分かれるところで、たとえば谷川浩司九段が好んでないところは有名な話。
「光速の寄せ」を売り物にする、切れ味で勝負の谷川九段からすると、ドロドロした入玉形は力が発揮しにくいのかもしれない。
また、先崎学九段もエッセイの中、であまり好きではないようなことを書いており、これは苦手というよりも、
「どれだけ駒を失っても相手の王様だけ仕留めればいい、というのが将棋の本質なのに、寄らないとなったとたんに《じゃあ駒数で点数勝負にしましょう》というのは、おかしい気がする」
こういう
「別のゲームになってしまう違和感」
を持つ人は多いだろうし、そこはうなずける部分はある。
一方、得意なのは昔の丸山忠久九段や、島朗九段。
テレビで人気の、桐谷広人七段もなにげにスペシャリストだった。
そんな、得手不得手がわかれる入玉だが、なにげに達人として存在したのが、中原誠十六世名人。
「自然流」と呼ばれ、攻めにも受けにもバランスの取れた棋風の中原だが、敵陣へのトライもまたお手のものだった。
特に不得意派の筆頭だった谷川九段は、大舞台で戦うことが多かったせいか、何度か痛い目に合っているのを見たもの。
このあたりは、もしかしたら「ねらい撃ち」の意識はあったかもしれない。
舞台は1985年、第43期名人戦の第1局。
相矢倉から先手の谷川が攻めかかるも、中原も当時愛用していた、△22銀型の菊水矢倉で「前進流」をいなしにかかる。
谷川の切っ先が、何度も届いたように見えながら、中原もギリギリの受けでくずれない。
いつしか後手の玉は、手に乗って上部に脱出。
ついに、入玉が見えてきた。
だが、相手は「光速の寄せ」谷川浩司だ。手をつくして細い攻めをつなげ、ついに後手玉をあと一歩まで追いつめる。
むかえた、この局面。
▲48飛と打って、一目先手勝ちだ。

△28に合駒すると、▲27角と打って、△29玉に▲22竜と銀を取る。
△同金、▲38銀、△39玉に▲49飛でピッタリ詰み。
図から合駒せず単に△29玉ともぐりこんでも、▲47角と打って、今度は▲31竜と金を取る筋で寄るため、やはり先手勝ちはゆるがない。
とにかく、△22と△31に落ちている、質駒の存在がメチャクチャに大きく、どうやっても捕獲されているように見えるのだが、なんとここで見事なしのぎがあった。
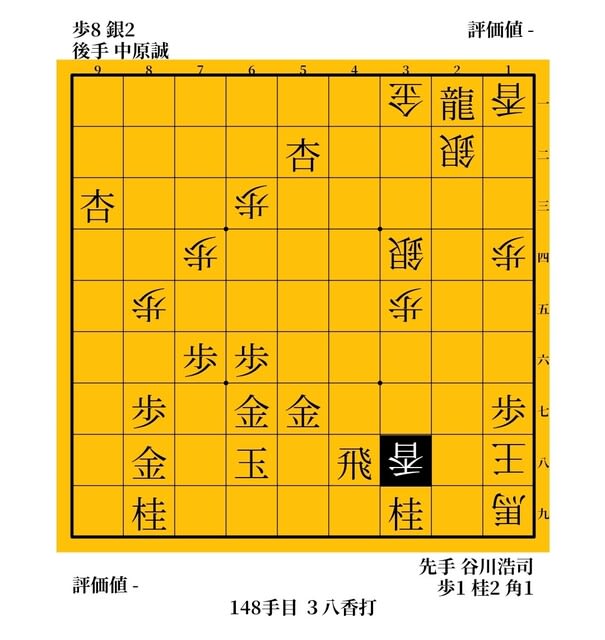
△38香と中合するのが、接近戦の手筋。
これがいかにも入玉戦のアヤで、これがもし敵陣での攻防なら、この形は「▲同飛成」となるから、後手玉は簡単に寄りである。
だが自陣での戦いだと、これには「▲同飛」と生飛車のままになるのだ。
すかさず△29玉と死角にもぐって、後手玉に寄りがなくなってしまう。
それは負けなので、先手は香を取らずに▲27角と王手するも、一回△28玉と寄るのが、綱渡りのようで正解。
▲38飛と取らせて、やはり死角の△29玉にかわせば、これ以上の手がない。
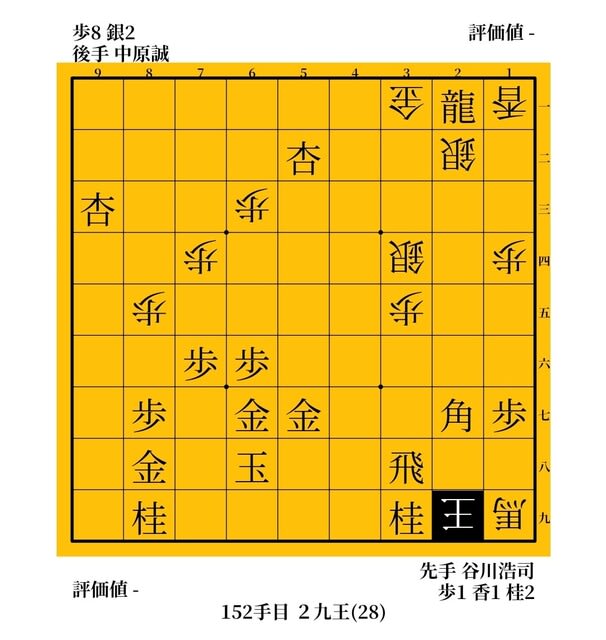
以下、先手も▲22竜、△同金、▲18銀。
せまいところで懸命に食いつくが、冷静に△同馬、▲同飛に△28歩と、コルクで栓をして盤石。

後手玉は、歩しか味方がいないが、これで先手の攻めは切れている。
ここで先手の桂馬と香車が、まったく宝の持ち腐れになっているところも、自陣で戦う際の泣き所だ。
これで勢いに乗った中原は、4勝2敗のスコアで名人を奪取する。
「名人は危うきに遊ぶ」という、古い言葉を実践する形になったのだった。
(続く→こちら)















