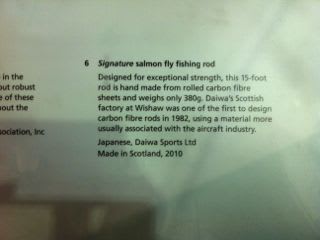これまで、数知れずこのブログに登場してきながら、愛用のテレスコピックタモを全く紹介しておりませんでした。
Sharpe's of Aberdeen製のtelescopic folding net ''Seaforth''です。

これはViscount Grey 10'6''で釣ったブラウントラウト46cm。相棒のネットは伸ばされております。

このネット、ネット部分を広げずに畳んだままですと54cmの長さ。

ネット部分は金属製のアーム2つとそのアームの間に取り付けられた太い合成繊維製のロープ、そして網よりなります。

金属製のアームを広げるアームとロープが三角形を作り、ネットとして使える様になります。

肝心の金属製アームを広げてかつ固定する機構はシンプル。

アームを向かって上方に起こしていって、

斜めに切り込まれたところまでアームを起こしてあげるとそれ以上は動きません。

そこをバネ仕掛けのキャップで覆えばしっかり固定されます。

また、取手にはフックがついているので、釣りバックの金属リングにフックをかけると、右肩から左腰に斜めに釣りバックをしょいながらネットも同時に持ち運び可能です。日本の渓流溯行には向きませんが、忍野のように川岸が高い川、英仏のチョークストリームでは重宝します。

上の写真は2005年にEtrachseeで尺上のアルプスイワナをKiller Bugで釣った際のもので、曲がっているのは1967年製のPalakona Perfection 9'です。これで見て取れる様に竹竿で魚を上げる際、ティップ部分を労るためにはテニスラケット型よりもテレスコピックが有利なのは明らかでしょう。
このSeaforthは伸ばさなければ88cmのネットとして使えますし、最大限に伸ばせば129cmのネットになります。私が買ったのは1997年。John Norrisの通販でした。来年で20年選手となりますが、多少くたびれてはいてもこれからも全然問題なく使えると思います。
但し、Sharpe'sはこのFoldingバージョンの生産を止めてしまったようで、今の製品ラインアップにはもう入っておりません。私の愛用品は何故か製造中止になってしまう確率が高いようで残念です。
Sharpe's of Aberdeen製のtelescopic folding net ''Seaforth''です。

これはViscount Grey 10'6''で釣ったブラウントラウト46cm。相棒のネットは伸ばされております。

このネット、ネット部分を広げずに畳んだままですと54cmの長さ。

ネット部分は金属製のアーム2つとそのアームの間に取り付けられた太い合成繊維製のロープ、そして網よりなります。

金属製のアームを広げるアームとロープが三角形を作り、ネットとして使える様になります。

肝心の金属製アームを広げてかつ固定する機構はシンプル。

アームを向かって上方に起こしていって、

斜めに切り込まれたところまでアームを起こしてあげるとそれ以上は動きません。

そこをバネ仕掛けのキャップで覆えばしっかり固定されます。

また、取手にはフックがついているので、釣りバックの金属リングにフックをかけると、右肩から左腰に斜めに釣りバックをしょいながらネットも同時に持ち運び可能です。日本の渓流溯行には向きませんが、忍野のように川岸が高い川、英仏のチョークストリームでは重宝します。

上の写真は2005年にEtrachseeで尺上のアルプスイワナをKiller Bugで釣った際のもので、曲がっているのは1967年製のPalakona Perfection 9'です。これで見て取れる様に竹竿で魚を上げる際、ティップ部分を労るためにはテニスラケット型よりもテレスコピックが有利なのは明らかでしょう。
このSeaforthは伸ばさなければ88cmのネットとして使えますし、最大限に伸ばせば129cmのネットになります。私が買ったのは1997年。John Norrisの通販でした。来年で20年選手となりますが、多少くたびれてはいてもこれからも全然問題なく使えると思います。
但し、Sharpe'sはこのFoldingバージョンの生産を止めてしまったようで、今の製品ラインアップにはもう入っておりません。私の愛用品は何故か製造中止になってしまう確率が高いようで残念です。