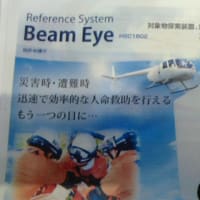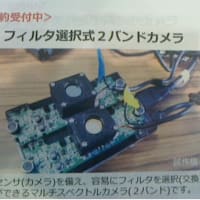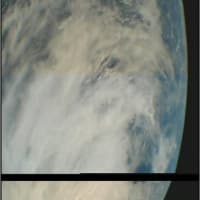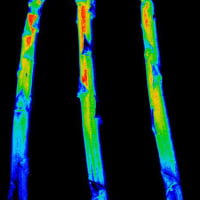タイトル:なにわアカデミー:/26大阪府立大「小型宇宙機システム研究センター」/大阪
本文:
◇学生の手で衛星開発--雷観測「まいど1号」に関与、「設計コンテスト」にも参加東大阪市の中小企業などでつくる「東大阪宇宙開発協同組合」が開発した雷観測衛星「まいど1号」(打ち上げ成功後に正式命名)が来年1月に宇宙へ飛び立つ。その設計にかかわった大阪府立大工学部は、
05年に「小型宇宙機システム研究センター」(センター長・大久保博志教授)を作った。航空宇宙工学科の学部生と大学院生計30人あまりが、衛星の設計や運用など、宇宙開発の初歩を実地で体験している。
センターはさまざまな計画を並行して進めており、それぞれに10人前後の学生、院生が参加している。その一つが「衛星設計コンテスト」への参加だ。
コンテストは、日本機械学会や宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが毎年、高校から大学院までの学生を対象に実施している。小型衛星を設計し、模型も作って設計の完成度や独創性を競う。
府立大チームは今年のコンテストに「ソラマメ」と名づけた放射線観測衛星で臨んだ。
宇宙空間の放射線は衛星などの故障の原因になる。「ソラマメ」のねらいは、放射線を精密に観測して変動を予測し、故障対策に役立てることだ。
設計によると、本体部分は40センチ角の立方体で、重さは22・9キロ。高度700キロで地球を回る。放射線は、最短1000分の1秒間隔で観測する。
11月2日に東京都で開かれたコンテストに向け4月から9人の学生が準備を始めた。毎日午後10時過ぎまで議論や勉強を続け、設計に必要な知識のほか放射線に関する物理も学んだ。7月の第1次締め切り前は徹夜だった。
努力の結果、「地球電磁気・地球惑星圏学会賞」を獲得した。2年生の田中康平さん(21)は「みんなで一つの物を作るのが楽しく、授業とは違うことを学べた」と話す。
ジュースの空き缶サイズの模擬人工衛星「カン(缶)サット」も作っている。本物の衛星同様に通信機やカメラを積み、小型ロケットで高度数百メートル~数キロに打ち上げて地上に落とす。これで衛星制御や通信の手法を学ぶ。
府立大は昨年9月、米国・ネバダ州でカンサットの国際コンテストに参加。落下地点の正確さを競う競技に出場し、日本、米国、韓国から参加した11チームの中で優勝した。米国までの旅費は、参加した学生たちがアルバイトで稼いだ。
「まいど1号」の打ち上げ後には、センターの学生たちが、学内のコンピューターで「まいど」の働きを確かめ、衛星の姿勢も制御する。「まいど」が1日2回、日本上空を通過する際に電波を送って指令する。約20人の学生が、この操作を練習中だ。
コンテストなどに挑戦しながら宇宙開発を学ぶことについて、大久保センター長は「目標が明確でやる気が増すし、学年にこだわらず必要な知識を習得できる。チームで計画を立て、役割分担することも学べる」と効果を説明している。【高木昭午】
◇大阪府立大小型宇宙機システム研究センター
「まいど1号」設計への参加をきっかけに、府立大発の新たな人工衛星の実現を目指して設立された。JAXAとも協力しており、関西の宇宙開発・研究の拠点の一つ。燃料を使わず窒素ガスを噴出して飛ぶ「非燃焼型ロケット」の開発などもしている。
毎日新聞 2008年12月9日 地方版
URL:http://mainichi.jp/area/osaka/news/20081209ddlk27100601000c.html
本文:
◇学生の手で衛星開発--雷観測「まいど1号」に関与、「設計コンテスト」にも参加東大阪市の中小企業などでつくる「東大阪宇宙開発協同組合」が開発した雷観測衛星「まいど1号」(打ち上げ成功後に正式命名)が来年1月に宇宙へ飛び立つ。その設計にかかわった大阪府立大工学部は、
05年に「小型宇宙機システム研究センター」(センター長・大久保博志教授)を作った。航空宇宙工学科の学部生と大学院生計30人あまりが、衛星の設計や運用など、宇宙開発の初歩を実地で体験している。
センターはさまざまな計画を並行して進めており、それぞれに10人前後の学生、院生が参加している。その一つが「衛星設計コンテスト」への参加だ。
コンテストは、日本機械学会や宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが毎年、高校から大学院までの学生を対象に実施している。小型衛星を設計し、模型も作って設計の完成度や独創性を競う。
府立大チームは今年のコンテストに「ソラマメ」と名づけた放射線観測衛星で臨んだ。
宇宙空間の放射線は衛星などの故障の原因になる。「ソラマメ」のねらいは、放射線を精密に観測して変動を予測し、故障対策に役立てることだ。
設計によると、本体部分は40センチ角の立方体で、重さは22・9キロ。高度700キロで地球を回る。放射線は、最短1000分の1秒間隔で観測する。
11月2日に東京都で開かれたコンテストに向け4月から9人の学生が準備を始めた。毎日午後10時過ぎまで議論や勉強を続け、設計に必要な知識のほか放射線に関する物理も学んだ。7月の第1次締め切り前は徹夜だった。
努力の結果、「地球電磁気・地球惑星圏学会賞」を獲得した。2年生の田中康平さん(21)は「みんなで一つの物を作るのが楽しく、授業とは違うことを学べた」と話す。
ジュースの空き缶サイズの模擬人工衛星「カン(缶)サット」も作っている。本物の衛星同様に通信機やカメラを積み、小型ロケットで高度数百メートル~数キロに打ち上げて地上に落とす。これで衛星制御や通信の手法を学ぶ。
府立大は昨年9月、米国・ネバダ州でカンサットの国際コンテストに参加。落下地点の正確さを競う競技に出場し、日本、米国、韓国から参加した11チームの中で優勝した。米国までの旅費は、参加した学生たちがアルバイトで稼いだ。
「まいど1号」の打ち上げ後には、センターの学生たちが、学内のコンピューターで「まいど」の働きを確かめ、衛星の姿勢も制御する。「まいど」が1日2回、日本上空を通過する際に電波を送って指令する。約20人の学生が、この操作を練習中だ。
コンテストなどに挑戦しながら宇宙開発を学ぶことについて、大久保センター長は「目標が明確でやる気が増すし、学年にこだわらず必要な知識を習得できる。チームで計画を立て、役割分担することも学べる」と効果を説明している。【高木昭午】
◇大阪府立大小型宇宙機システム研究センター
「まいど1号」設計への参加をきっかけに、府立大発の新たな人工衛星の実現を目指して設立された。JAXAとも協力しており、関西の宇宙開発・研究の拠点の一つ。燃料を使わず窒素ガスを噴出して飛ぶ「非燃焼型ロケット」の開発などもしている。
毎日新聞 2008年12月9日 地方版
URL:http://mainichi.jp/area/osaka/news/20081209ddlk27100601000c.html