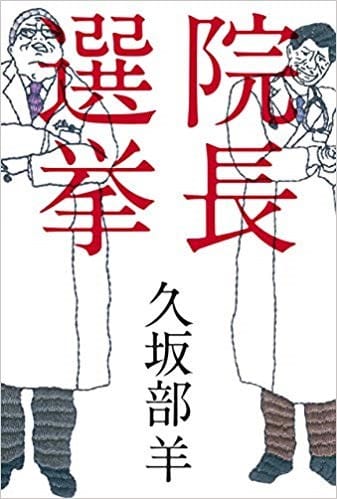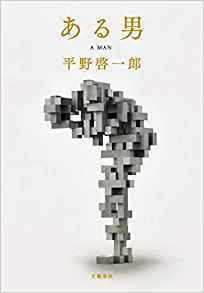本屋さんでちょっと気になるタイトルだったので手にとって少し立ち読みして
「これは面白そう…」となって買ったのがこの本。
実際に読んでみてなかなか面白かったわね。
東京芸大ってどんなところだろう、と高校生みたいな気持ちで読んだんだけど
芸大を知るきっかけとしては十分な1冊だったと思う。
芸大生の妻を持つ筆者が自分の妻に聞いた芸大の様子に「!」となり、
妻と一緒に大学内を見学したり、芸大の学祭に行って自分でみた内容が前半に語られて
途中からは通っている学生とのインタビューが載せられているので
前半部分とはちょっと違う作りになっていて、読み手としてはどっちか統一してほしいかな、
という気もしなくはなかった。
特にインタビュー部分は、人数をもう少し削って、その代わりすごく興味深い人の話を掘り下げて聞いたり
数年にわたってその様子を追いかけていく方が面白いんじゃないかな、という気はしたけれど、
実際にはさらりと終わっていたのがちょっと勿体無い。
芸大の不思議な話や面白いエピソードはとにかく驚きもあったし、苦笑せずにはいられないけれども
たぶんこの本に出てくるような人たちは、どこのカテゴリにもいて、
たぶん京大も東大に比べたらものすごく面白い人がたくさんいるだろうし、だから芸大だけが特別ということもないし
「最後の秘境」とまで大袈裟な話ではないと思う。
だけど、音楽や美術を志している人たちってあまり身近にはいないから
(それでも私が高校生のときはクラスに何人か美術系や音楽系に進んだ人もいたけれど)
しかもプロを目指している人とか、その人たちがそれまでどんなふうに生きてきて、どんなことを思いながら
生活しているのかとかそのあたりが全然知られていないこともあって、とても面白かったと思う。
芸大祭の様子がものすごく興味深くて、私も実際に行ってみたいな、という気持ちになったわ。
もっと芸大のことを知ってもらいたいという話も中にあったけれど(学長の話も含めて)
ほんとそう思う。東京に住んでいる間に行っておきたかったな、と思う。
うちには高校生の息子がいるわけだけれど、芸大志望ではないし、芸大行けそうなセンスもないし。
でも、美校目指すような子がいたら楽しいかもな〜とちょっと思ったりして(笑)
いずれにせよ、芸大ってこんなところなんだ〜と知るきっかけとしては最高に面白かった。
「これは面白そう…」となって買ったのがこの本。
実際に読んでみてなかなか面白かったわね。
東京芸大ってどんなところだろう、と高校生みたいな気持ちで読んだんだけど
芸大を知るきっかけとしては十分な1冊だったと思う。
芸大生の妻を持つ筆者が自分の妻に聞いた芸大の様子に「!」となり、
妻と一緒に大学内を見学したり、芸大の学祭に行って自分でみた内容が前半に語られて
途中からは通っている学生とのインタビューが載せられているので
前半部分とはちょっと違う作りになっていて、読み手としてはどっちか統一してほしいかな、
という気もしなくはなかった。
特にインタビュー部分は、人数をもう少し削って、その代わりすごく興味深い人の話を掘り下げて聞いたり
数年にわたってその様子を追いかけていく方が面白いんじゃないかな、という気はしたけれど、
実際にはさらりと終わっていたのがちょっと勿体無い。
芸大の不思議な話や面白いエピソードはとにかく驚きもあったし、苦笑せずにはいられないけれども
たぶんこの本に出てくるような人たちは、どこのカテゴリにもいて、
たぶん京大も東大に比べたらものすごく面白い人がたくさんいるだろうし、だから芸大だけが特別ということもないし
「最後の秘境」とまで大袈裟な話ではないと思う。
だけど、音楽や美術を志している人たちってあまり身近にはいないから
(それでも私が高校生のときはクラスに何人か美術系や音楽系に進んだ人もいたけれど)
しかもプロを目指している人とか、その人たちがそれまでどんなふうに生きてきて、どんなことを思いながら
生活しているのかとかそのあたりが全然知られていないこともあって、とても面白かったと思う。
芸大祭の様子がものすごく興味深くて、私も実際に行ってみたいな、という気持ちになったわ。
もっと芸大のことを知ってもらいたいという話も中にあったけれど(学長の話も含めて)
ほんとそう思う。東京に住んでいる間に行っておきたかったな、と思う。
うちには高校生の息子がいるわけだけれど、芸大志望ではないし、芸大行けそうなセンスもないし。
でも、美校目指すような子がいたら楽しいかもな〜とちょっと思ったりして(笑)
いずれにせよ、芸大ってこんなところなんだ〜と知るきっかけとしては最高に面白かった。