
タイトル:歌舞伎の話
著者:戸板康二
カバーデザイン・装幀:蟹江征治
発行:講談社/講談社学術文庫1691
発行日:2005年1月10日(1950年に角川書店より刊行された書籍の文庫化)
内容:
わが国古来の伝統演劇・歌舞伎とはいかなる芸術か。著者ならではの薀蓄を随所にちりばめつつ、批評(鑑賞の基準)、歴史、役柄、演技、劇場、脚本、芸術性、大衆性という八つの角度から、独特の様式をもつ歌舞伎という芸能の本質と魅力を検証し、あわせて現代文化における歌舞伎の位置を探る。歌舞伎評論の第一人者が説く、歌舞伎への正しい認識と鑑賞法。
(本書カバー裏解説より)
購入日:2008年1月26日
購入店:本当です。(*注;古本屋の店名です)
購入理由:
歌舞伎を知るのにいい本はないかとのんびり探していた。どこかの書店や府中市美術館ミュージアムショップなどでこの本をたびたび見かけ、参考になりそうな本だな、と思い記憶に残っていた。そして、実際に歌舞伎を見に行った日の帰りのこと。ふと思い立ってよく行く古本屋を数件まわってこの本がないか探してみようと思い立った。本というのは探すと見つからないものだが、2店目にして見事発見して購入。おまけにもう一冊歌舞伎関係で気になっていた本も見つけ、歌舞伎運がいい日であった。こうして偶然本と出会うと、いまこの本を読めということなんだな、と思う。自分が読む本を選択しているのではなく、本が読む者を選択している。奇妙な話だがそんなふうに思うことがある。
この文庫本のもととなる単行本が出たのは1950年。かなり古いが、もともと伝統芸能ゆえ、カタカナ文字が出てくるわけでもないから、本としての内容は古くならないだろう。それに、こうして文庫化されるのだから、歌舞伎界ではかなり名作なのかもしれない。だが、歌舞伎初心者の私は当然今回初めて知った。歌舞伎における評論というのは未知のジャンルで、どのようなものかわからないが、まずはこうして偶然出会えた本をナビゲイターに歌舞伎の世界へとさらに進もうと思う。
著者:戸板康二
カバーデザイン・装幀:蟹江征治
発行:講談社/講談社学術文庫1691
発行日:2005年1月10日(1950年に角川書店より刊行された書籍の文庫化)
内容:
わが国古来の伝統演劇・歌舞伎とはいかなる芸術か。著者ならではの薀蓄を随所にちりばめつつ、批評(鑑賞の基準)、歴史、役柄、演技、劇場、脚本、芸術性、大衆性という八つの角度から、独特の様式をもつ歌舞伎という芸能の本質と魅力を検証し、あわせて現代文化における歌舞伎の位置を探る。歌舞伎評論の第一人者が説く、歌舞伎への正しい認識と鑑賞法。
(本書カバー裏解説より)
購入日:2008年1月26日
購入店:本当です。(*注;古本屋の店名です)
購入理由:
歌舞伎を知るのにいい本はないかとのんびり探していた。どこかの書店や府中市美術館ミュージアムショップなどでこの本をたびたび見かけ、参考になりそうな本だな、と思い記憶に残っていた。そして、実際に歌舞伎を見に行った日の帰りのこと。ふと思い立ってよく行く古本屋を数件まわってこの本がないか探してみようと思い立った。本というのは探すと見つからないものだが、2店目にして見事発見して購入。おまけにもう一冊歌舞伎関係で気になっていた本も見つけ、歌舞伎運がいい日であった。こうして偶然本と出会うと、いまこの本を読めということなんだな、と思う。自分が読む本を選択しているのではなく、本が読む者を選択している。奇妙な話だがそんなふうに思うことがある。
この文庫本のもととなる単行本が出たのは1950年。かなり古いが、もともと伝統芸能ゆえ、カタカナ文字が出てくるわけでもないから、本としての内容は古くならないだろう。それに、こうして文庫化されるのだから、歌舞伎界ではかなり名作なのかもしれない。だが、歌舞伎初心者の私は当然今回初めて知った。歌舞伎における評論というのは未知のジャンルで、どのようなものかわからないが、まずはこうして偶然出会えた本をナビゲイターに歌舞伎の世界へとさらに進もうと思う。











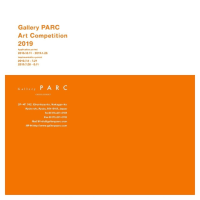

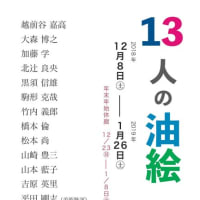


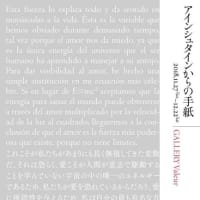

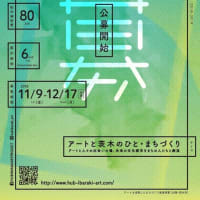
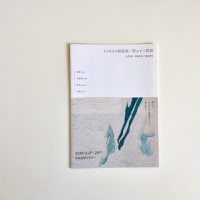
小金沢です。
歌舞伎、観たことはないのですが、評論は一冊だけ読んだことがあります。
服部幸雄『さかさまの幽霊』がその本で、これは歌舞伎の記号論です。巻末には歌舞伎から見た暁斎論が掲載されており、卒論を書くときはそれはそれは影響を受けたものです(というか、俺が書きたいことはここに全部書かれてしまっている!と思い絶望しました)。
ちくま学芸文庫から出ているので、見かけた際はぜひ手にとって見てください。抜群に面白い名著ですよ。