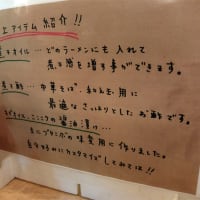Glenn Gould 1/4 Goldberg Variations (HQ audio - 1981)
ゴルトベルク変奏曲、グレン・グールド、1981年。
わたくしは「大バッハ」が嫌いなのです。大嫌いです。
「クラシック好き」を任じてましたので、若い頃にはたくさんCDを購入し、なるべく親しもうと努力もしましたが、長じて偉大なる「変ヘンデル」の魅力に目覚めるにつれ、「大バッハ」が嫌いになった。「こいつなにが楽しくてこんな栄養もカロリーも効用も何も無いこんにゃくみたいな音楽を大量に作っているの?」「苦痛だ」って。「ブリタニアの幸いなる大ヘンデルは鰤であり鯛であり鯱であるのにこいつはなんなの!?」って。
小さい頃はあんなに大好きであったロ短調ミサ曲もマタイ受難曲もブランデンブルク協奏曲群もうるさく感じるようになり、30を超えると大バッハの曲で聴くのは「ゴルトベルク」と「パルティータ第2番」と「音楽の捧げ物」ぐらいになってしまった。
翻りますが、大バッハの「ゴルトベルク変奏曲」って誠にいい曲ですよね。
古今の作品のうち、ここまで均衡に選り研ぎ澄まされた曲ってありましょうか。聴いたらひどく興奮する。建築的な香りがする。ドイツみたいな燻製された腸詰め肉の焦がれた感じがする。さすがクラシックです。クラシックばんざい。私は大バッハは大嫌いなんですけど、多分この曲は別次元線の別バッハが作った物なのでしょうね。
私の初ゴルトベルクは記憶が疎かなんですけど、若い頃住んだ九州長崎で、初めて買った20枚のクラシックの初コレクションには含まれてはいなかったと思う。何かの本で「バッハはグレン・グールドが凄い」と読んでから買った。わたくしの初ゴルトベルクはグレン・グールドの81年盤でした。マタイ受難曲のリヒター盤は高校生の時から聴いていた。
長崎にはどこにも丘の上に華麗な教会があった。(リアスの港の奥々には魚面の民が潜んでいそうな深い淵の数々がありました)。隠れキリスト教に多大な興味を抱いていた私は教会群を遠くから眺めることがとても好きで(結局一回しか中に足を踏み入れることが無かったけど)、私の記憶の中の長崎県の思い出の景色にはゴルトベルク変奏曲('81年)が大音量で流れている。っていっても、30年も経ってるので記憶がもうかなり薄くもなっちゃってるんですけど。私の記憶の大バッハといったら長崎の九十九島と松浦半島とハウステンボスと富士市なんだが。(富士市に住んでいたときグレン・グールドの30枚組のバッハ全集を買ったから)
で、ゴルトベルク変奏曲といったら私にとっては81年のグレン・グールドとかあり得なくて、それ以外は聴いたことが無いのです。大全集に含まれているので1955年盤は持ってはいますけど、ほとんど聴いたことが無いのです。で、今の時代、捜してみるとあるんですね。動くグレン・グールドの映像が。凄いですね。(探してみたことはなかったので)今さらながらにびっくりしています。さすがに1955年のグールトの動く映像は無いでしょうね。
(1955年盤)
81年盤とは正反対の雰囲気だと思い込んでいましたけど、今聴いてみますとそんなに違和感ないですね。もっと駆け足風の演奏だと思ってた。
若い頃の私はグールド以外は聴こうとは思わなかったのですが、唯一お店に行くたびに探していたのは、吉田秀和だか宇野功芳だかがどこかの本で紹介していた(何の本だっけ)「弦楽三重奏版の」ゴルトベルク変奏曲で、(ネット通販なんて無い時代だったから、結局見つけることはできなかった)、でも現在はネットの世界で聴き比べ放題なんですね。確か探していたのは、ドミトリー・シトコヴェツキー、ジェラール・コセ、ミッシャ・マイスキーの3人の演奏だったと思うけど。
(これはアケミ・メルセル-ニーヴェーナー、ディルク・メルセル-ニーヴェーナー、ウルリッヒ・ホーンさん)
あった(驚き)。1985年。
最新の画像[もっと見る]