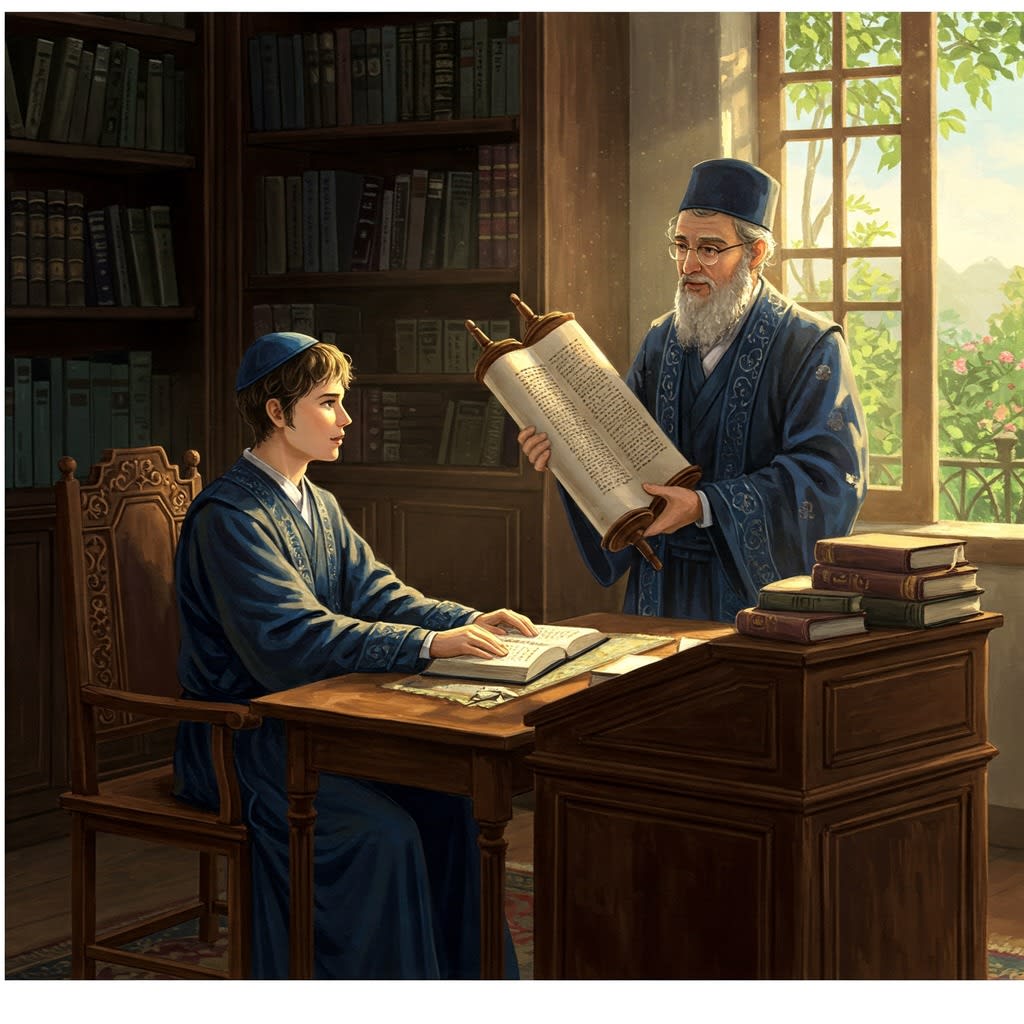◎屍解もするし、白日昇天もする
『董奉、字は君異といい、侯官県の人である。その時、同県に長余姓という者がいて、年なお幼い時に或る機会から董奉に面会したことがあった。その時、董奉は既に三十余であった 。その後五十年経て、長余姓がある他の栄職に就いて再び侯官県を通った時、その地の役人共皆彼の許に往いて拝謁したことがある 。
その時、董奉もその中に居ったが、長余姓は彼を見て驚き、「足下は恐らく仙道を得られたのではあるまいか、という訳は、自分が年なお幼くて郷里に居た時に足下に面会したことがある 。それは足下もまた記憶して居られることであろう 。その時足下は最早可なりの年頃であったが、今日お目にかかって見ると、足下は炯々として昔のままで少しも年老った容子がない 。如何にも不思議なことである」と話した 。
その時、董奉はわざととぼけた振をして、「自分でも不思議に思っている」由を語り、「これもこの様な伴運と自分が持って生れたものであろう」と言って笑った 。
ここに交州の刺史を為て居た杜登というものが病死して、既に三日許り経過してあったが、その時会々董奉が交州に遊隠して居たので、三つの丸薬を彼の口に含ませ、側の人に命じて彼の頭を挙げ、その身体を揺らしめると、暫時たって、彼は忽ち蘇生し、目を開き、手足を動し、顔色ももとのように精彩になり、半日程たつと起き上り、その後四日程経つと談笑少しも昔に異らなかった 。
そして人に語っていうには、初め死んで息が絶えた時は精神恍惚としてあたかも夢のようであったが、暫時すると、黒衣を着た人が数十人遣って来て、自分を露車(はだかぐるま)の上に載せ、何処へか曳いて行ったかと思うと堅固な朱塗の門のある庭に着き、或る獄屋に投げ込むと直ぐと戸を閉じて外から土を以て封じたようである 。獄屋は一軒立の小屋というよりも寧ろ室という方が近く、一人はいる広さで、暫時すると、一人の男が遣って来て、「自分は太一帝の使者であるが帝の勅によって此処まで汝を迎ひに来たのである」といった時、誰やらが鍬をもって外を頻りに掘る様子であったが、暫時して戸が開き、自分は戸の外へ連れ出された 。
見れば割符の処に赤い蓋を附けた馬車が一輛あって、三人の男が乗って居た 。その中の節(わりふ)を持て居た一人の男が自分の名を呼んで車にのせ、彼処から曳いて前の朱塗門の処へ着いたかと思った時、自分は始て蘇生したのである 。
是に於て杜燮は中庭に立派な一の高楼を築いて、そこに董奉を住まわせ厚く彼を待遇してあったが、董奉はただ脯(ほしし。干し肉)と棗ばかりを食べて居た 。酒は非常に好きで日に三度飲んで居た 。そして彼は時々杜燮の許へ来て共に飲食をすることもあったが、その挙動極めて軽く、自分の居間を出たかと思うと影の動くようにスーッと進み来て、何時の間にか杜燮の座敷に来て居る 。帰る時も矢張り同様であった 。
董奉はしばらく杜燮の許に滞留して居たが、ある日暇を告げてそこを立去ろうとすると、杜燮は痛く別離を惜しんで、為めに大船を造って遣ろうとした 。董奉はそれを押留めて、「自分は旅行をするのに決して船は用いぬ、唯一箇の棺さへあれば充分である」といったので、そこて杜燮は彼の言葉通り早速一の棺を用意さすと、翌日になって董奉にわかに変死した 。
そこでその屍体を棺に入れて埋葬すると、七日程経て、岩昌の方から還て来た人があって、杜燮に彼方で董奉に面会したことを話した 。杜燮これを聞いて不審の余り董奉の棺を掘り出して中を開いて見ると、屍体は何時の間にか消え失せて、中には唯一枚の丹書のみが残って居た 。
董奉はその後盛山の麓へ一軒の小屋を建てそこに住んで居たが、ここに一人のらい病患者が居て、今や将に息が絶えなんとした時、彼に治療を乞うた 。その時董奉は彼を空室の中へ坐らしめ、五重にたたんだ布を以てその目を塞ぎ、人のその側に近寄ることを堅く禁じて居た 。暫時たつと彼の患者は苦しい声を出して、「誰れか来て自分をなめるようであるが如何にも痛んで堪まらぬ 。
その舌は目には見えぬが長さは一尺位あって、その息づかいの様子から察するに、この者は何んだか牛のやうな物に相違ない」と叫んで居たが、件の怪しい物は彼の身体を充分に舐め終ると何処へか立去っていった 。その時董奉は彼の側へ進みよってその布を解いてやり、水などへて飲ましめ、「是で最早よろしいが、唯風に当ては不可ぬから」と戒しめ、その心得を丁寧に訴へて去ると、十日の間は皮が剥がれて居るので、全身真っ赤に色づき、疼痛収まらなかったが、水浴して居る中に痛も次第に滅して、二十余日程経つと皮も自然に生じて来て、病は跡形もなく癒って了ったそうである 。
その後天下大に旱(ひで)り、百穀ほとんど枯れ尽した時、県令の丁土産というもの酒脯(さけさかな)を備へて董奉の許を訪づれ、尊敬を厚くし詞を丁寧にして、天下の為めに雨を祈らんことを乞うた 。董奉は顔に微笑を含んで、唯一言、「雨か、よし分った、造作もないことだ」といって、その天井を仰ぎ、「だが、然し御覧の通りの粗末な家で雨さへ凌げぬ有様だから」と言うのを聞いて丁土産は直ちに董奉の心中を悟り、早速人を遣して彼の家を改め作らしめ壁を塗るために人を走らせて水を持って来させようとした 。これを見て、「日が暮れたら水が自然に得られるだろう」と言って堅くその事を押留めたが、その夜になると果して大雨が降って来た 。
彼は水を呪て病を治すに妙を得てあったが、それも謝礼としてびた一文得るでもなかった 。唯だ重症の患者の中で病の重かった者は謝礼として杏五株、軽い者は唯一株だけ自分の家のあたりに植えしめた 。
このようにして数年経つ中に、杏樹七万株以上に及び葉繁り幹太り、何時しか立派な一の森林が出来上って、山中に居る諸の禽獣共がその林へ来ては終日遊びまわるので、木の下には草一本だに生えず、あたかも耕したように清浄にしてあった 。そして杏が熟する時になると彼はそこに一箇の大きな倉を作り、杏を求めるものがあれば、米と杏とを交換せしめた 。
中に悪心のものがあって、余計に杏を取ることがあると、一頭の虎が何処からともなく現はれ出て、その悪者の跡を追駈ける 。その時若し余計に取った丈けの杏をその場に投げ棄てれば虎も亦そこから後へ引きかえすのであったが、そうではなくて、持って家へ持ち帰れば、その者は直ちに死んでしまう 。その時若し盗んだ杏を董奉の処へ持て行って罪を謝し過を悔いると、その者は忽たちまち又蘇生する 。それが為めに杏を買う者の中に詐偽を働くものや偸盗をするものは一人も無くなった 。
董奉は、その得た米を件の倉に積み、貧窮の者があれば施し与え、旅人にも分け与えた 。それが為めに毎年三千斛位費してあったけれど、なお残余があったそうである 。
ここに県令丁氏の親戚の家に一人の娘が居て、或妖神の為めに魅られて心神錯乱し、あらゆる手段を尽したけれど少しも効能なかつた 。董奉之れを聞て不憫に思い、一度その女子の為めに病を祓ってやると、翌日長さ一丈六尺程もあろうかと思われる、一頭の死んだ大白虎が何処からともなく件の病人の家の前門に這い出て来た 。それと同時に女の病も直ちに平癒してしまった 。
そこで彼女の両親はその恩を謝する為めに、件の娘を董奉に妻し、夫婦仲睦まじく琴瑟相和してあったが、如何なる訳か、その間に子供が一人も無かった 。その後董奉は上帝から碧虚太一真人の位を授けられ、日中に昇天してしまったが、跡に残った妻は矢張り彼の杏を売って生活を立てて居た 。そしてその杏を食み、あるいは騙して余分に取る者があると何処ともなく虎が現われてその者を追跡することは、董奉が居た時と少しも異ならなかった 。その後人々はその杏を植えた場所に一の祠をたて、永く董奉を祀った 。』
董奉は、屍解もするし、白日昇天もするが、それでも人間を助けに世に出て来るのは奇特なことである。
杏の林を守るのに虎がいなければいけないというのは、中国人であって、日本なら虎は不要。中国人が多数移民してくるのなら、虎が必要だが、日本全体としては、民度の下落である。