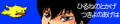まりさんにお誘いいただき、お友達グループで、高松市美術館の「ルネ・ラリック展」にいきました。ここは、私の職場の目と鼻の先なのに、今まで一度も行ったことがありませんでした。
(公衆電話をかけにいったことが1度だけ(^_^;) )
ルネ・ラリック…実は、千石原にラリック美術館があるってことぐらいしか知らなかったのですが、アールヌーヴォー~アールデコの時代の、ジュエリー、ガラス工芸品、建築装飾などのデザイナー。
さっぱり予備知識のない状態での鑑賞となりましたが、作品をみて、パネルを読んでいくうちに、時代背景が浮かび上がってきて、同じ時代を生きた音楽や絵画の巨匠たちがお互いに影響を与え、触発されあっていたことなどに思いを馳せて、かなり楽しむことができました。
中でも、1925年にパリで開催された「アール・デコ博覧会」の様子が写真などで紹介されていて、とても興味深いものでした。
Takも連れていったのですが、彼はルネ・ラリック展より、美術館の随所に常設されている現代彫刻のほうが面白かった様子。
「どれが好き?」「何に見える?」
…などといいながら、結構一緒に楽しめる。
Takは、年末の上京の折にも、父親に「ダリ回顧展」に連れていってもらっている。
1日遊んで疲れて、おんぶされて半分は寝てたらしいけど、お土産に持って帰ってきたダリの画集は、Takのお気に入りなのです。
私も、小学2年生の頃、学校から「パウル・クレー展」に行ったときのことは、とても印象に残っているのです。
オトナなのに、こんな子供みたいな絵を描くのがいいのか… でも、色や、デザインがとってもおもしろくて、好きになって、もう一度見たくて、2度行った覚えがあります。
私が最初に覚えた画家の名前だったかも。
てことは、Takの場合は「ダリ」だな(^_^;)
いつか「箱根彫刻の森」や「美ヶ原高原美術館」なんかにいったら、きっと楽しいだろうな~~。
うん。行こう! 高知四万十の次は、美ヶ原だな。
(公衆電話をかけにいったことが1度だけ(^_^;) )
ルネ・ラリック…実は、千石原にラリック美術館があるってことぐらいしか知らなかったのですが、アールヌーヴォー~アールデコの時代の、ジュエリー、ガラス工芸品、建築装飾などのデザイナー。
さっぱり予備知識のない状態での鑑賞となりましたが、作品をみて、パネルを読んでいくうちに、時代背景が浮かび上がってきて、同じ時代を生きた音楽や絵画の巨匠たちがお互いに影響を与え、触発されあっていたことなどに思いを馳せて、かなり楽しむことができました。
中でも、1925年にパリで開催された「アール・デコ博覧会」の様子が写真などで紹介されていて、とても興味深いものでした。
Takも連れていったのですが、彼はルネ・ラリック展より、美術館の随所に常設されている現代彫刻のほうが面白かった様子。
「どれが好き?」「何に見える?」
…などといいながら、結構一緒に楽しめる。
Takは、年末の上京の折にも、父親に「ダリ回顧展」に連れていってもらっている。

1日遊んで疲れて、おんぶされて半分は寝てたらしいけど、お土産に持って帰ってきたダリの画集は、Takのお気に入りなのです。
私も、小学2年生の頃、学校から「パウル・クレー展」に行ったときのことは、とても印象に残っているのです。
オトナなのに、こんな子供みたいな絵を描くのがいいのか… でも、色や、デザインがとってもおもしろくて、好きになって、もう一度見たくて、2度行った覚えがあります。
私が最初に覚えた画家の名前だったかも。
てことは、Takの場合は「ダリ」だな(^_^;)
いつか「箱根彫刻の森」や「美ヶ原高原美術館」なんかにいったら、きっと楽しいだろうな~~。
うん。行こう! 高知四万十の次は、美ヶ原だな。