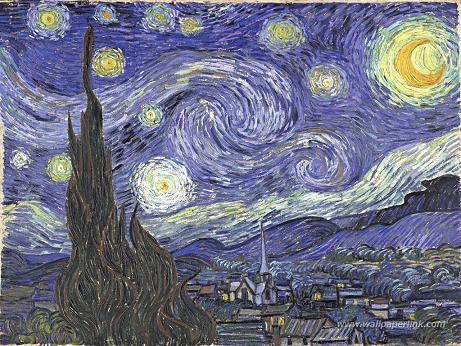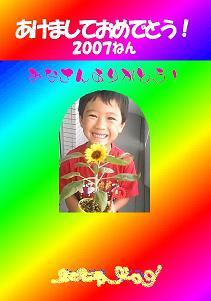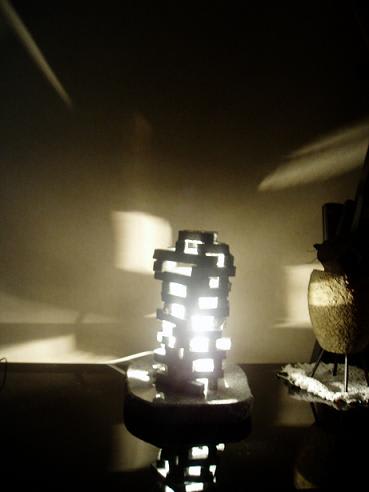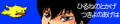今日は、Takがお世話になっている教会のチャペルコンサートに、親子でいってきました。
蜷川いづみさんというバイオリニストの方のソロで、久々にクラシックのコンサートを聴きました。
素晴しかった。スゴかった。
チャペルといっても、コミセンのようなところで、ホール的残響など一切なく、バイオリンから出る生音のみ。
これほど演奏者そのものをさらけ出すというのは、ある意味、残酷でもあるかもしれない。
でも、聴き手としては、それが、ものすごく良かったのでした。
バイオリンは、弓で弦を擦って音を出す楽器…って当たり前だけど、
声楽ととても似ている。音の作り方が。
弓で音を奏でてから切るまで。
その全てに責任をもって、精魂込めなくてはいけないのです。
音はリアル。如実。
私は、ものすごく感動したのですが、すべて語るにはあまりにも長くなりまくりそうなので、ひとつだけ。
「音を切る」こと。
自分が創った音を、奏で終えて、静寂へと受け渡す瞬間。
曲の終わりはもちろんだけど、曲のなかには、音符と休符があるワケで、
その「切れ目」をどうするか。どうやって音を始めて、どうやって終わるか。
まるで命のようだ。
音楽は緊張と弛緩の連続で、音が生きているのがものすごく伝わってくる。
ピアノの音を聴いているときは、きらきらした星のように、泡のように、飛沫のように音が押し寄せたり輝いたりしているのに対して、バイオリンの音は、風だったり、波だったり、渦だったり…
音楽は生き物だ。ホントに生きて迫ってくるなあ…
私も音楽に携わっていてよかったなあ…
そんなことを思いながら、感動しながら聴きました。
Takもずっと目を輝かせて、蜷川さんの姿を見ていました。
時には一緒に体を動かしたり。
終わったとき、「ものすごく良かった、感動した」と言ってました。
子供と一緒に感動できるって、嬉しいもんだなあ。
「よし、こんど、バイオリンのCD買おう。一緒に聴こうね。」

クリスチャンの蜷川さんは、ご自分がその道を歩まれるようになった経緯を、コンサートの途中で話されました。
そして、それから聖歌を何曲か続けて演奏されました。
私には、どんな意味の歌なのかはわかりませんでしたが、彼女の神さまへの限りない感謝や、敬虔な気持ちが音になって溢れ出しているのが伝わってきました。
音楽って、ほんとうに生きて、創り手から、演奏者へ、そして、聴き手へと伝わっていくもんだ。
幸せな宵でありました。
外に出たら、中秋の名月が煌々とわたしたちの故郷を照らしていました。
第一発見者?はTakでした(*^_^*)
冒頭の画像は、さぬきブログのおともだち、「まっき~」さんよりお借りしました♪