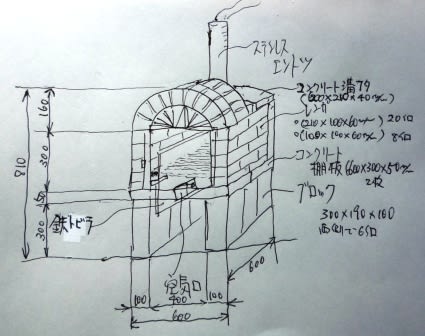・・・窯の横にちょっとした物置を兼ねた調理台を作ることを思いつきました。
物置などは我が家のような庭の狭い家の場合は一つ作ると何かをなくさないと段々と庭が狭くなってきます。
今回は以前に作った庭の物入れを再利用して調理台を作ることにしました。

「以前に作った庭の物入れ」
・・・基本、これを活用して、縦長に使うことにしました。

「横置きの物置を縦置きにして、長さを短くした」
・・・形は良いのですが、金具が少しさびてきているのと、扉が汚れているので、金具は新しいものに、扉はカンナがけして色を塗りなおした。

「リニューアルした調理台」
…天板はプラスティック板を張って、掃除しやすくした。
水がたまらないように水抜きの穴も設けました

・・・下の物入れには物置に使っていた時のバーベキュ・コンロなどが入っています。