◇ 『まいまいつぶろ』
著者: 村木 嵐 2023.5 幻冬舎 刊 
これは徳川幕府第九代将軍家重の物語である。家斉は幼名を長福丸と言った。
生来 右脚が不自由で、言語障害を持ち父親の吉宗も我が子が「何を言っているの
か分からぬ」と嘆いたことがある。
老中を初め取り巻きの誰もが家重は吉宗の後を継いで第十代将軍となるのは無
理で、弟君で英邁間違いなしの宗武がふさわしいと信じ込んでいた。
そこに誰ひとり理解できなかった家重の話す言葉を理解できる者が現れた。町奉行
大岡越前守忠相の遠縁の子大岡兵庫(幼名:のちに忠光)である。
誰しも家重の言葉と称し偽りを述べたりするのではなどと危ぶんだが、「家重殿の口
代りに徹し、決して耳と目になってはならぬ」と忠相に釘を刺され、終生これを守った。
家重は兵庫によってようやく思いを伝える言葉を口にできない辛さから抜け出すこ
とができた。
そして二人は終生心を許した間柄となった。
しかし幕僚の中には老中松平乗邑など頑なに吉宗の次男宗武を将軍にしたい者が
おり、折にふれ宗重の身体的障害を誹り侮る言葉を口にしていたが、兵庫はこれを家
重に伝えることはしなかった。
圧巻は吉宗が次代将軍を家重と決めた時である。吉宗の覚悟に側近の老中筆頭松
平乗邑が異を唱えた。理由は家重が将軍となった時、将軍の言葉を伝える宗光がか
つての側用人のごとき立場となり、政を司る側近が将軍と直に話が出来なくなる。従っ
て次期将軍は宗武にすべきというのである。
宗光は家重の側室となり、竹千代(後の家治)を産んだ「幸:正室比宮の侍女」を家
重に推薦したではないか。一事が万事、「一度味を占めた軽輩者が次はどんな大そ
れたことを致すか」・・・。「上様は家重さまを将軍とされるからには宗光を遠ざけて下
され」と迫った。
吉宗は「家重、そのほう何か申さぬか」と問いかける。
家重は何か叫んだ。宗光はその言葉を皆に伝える「忠光を、遠ざけるくらいなら、私
は将軍を・・・」宗光は絶句する。
忠義面をした乗邑は続きを言えと迫る。将軍襲職を辞退すると言えばそうなるからで
ある。吉宗も顔面蒼白となった。
そこで幼い家治が発言する。「私は子ゆえ父の言葉は少しは分かります。父は、宗光
を遠ざけよう。権臣にするくらいなら、私は将軍ゆえ」父はそう仰せになりました。「これは
私が権臣などを作るかどうかみておれ、と啖呵を切られたということでございますよね。」
幼いながら利発な家治の言葉で吉宗の顔も立って、乗邑の策謀も潰えた。
この場面こそ作家冥利に尽きるくだりではないか。
作者の家重と忠光に対する眼差しは一貫して優しく、心地よい。
忠光は48歳の時、岩槻藩二万石の藩主となり、家重退隠の年に亡くなった。その明く
る年家重も逝去した。
「まいまいつぶろ」とはカタツムリのこと。長福丸は幼少時お目見えなど
の折、席から退場時、失禁の跡が残った。周囲の心無い者はこれを「まいま
いつぶろ」と誹った。
(以上この項終わり)
最新の画像[もっと見る]
-
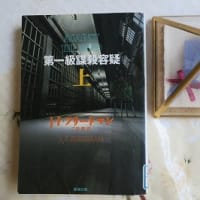 J・F・フリードマ ンの『第一級謀殺容疑』<上>
10時間前
J・F・フリードマ ンの『第一級謀殺容疑』<上>
10時間前
-
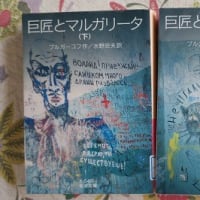 ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(下)』
2週間前
ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(下)』
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
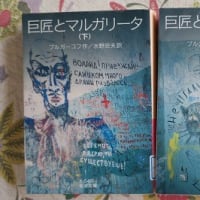 ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
3週間前
ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます