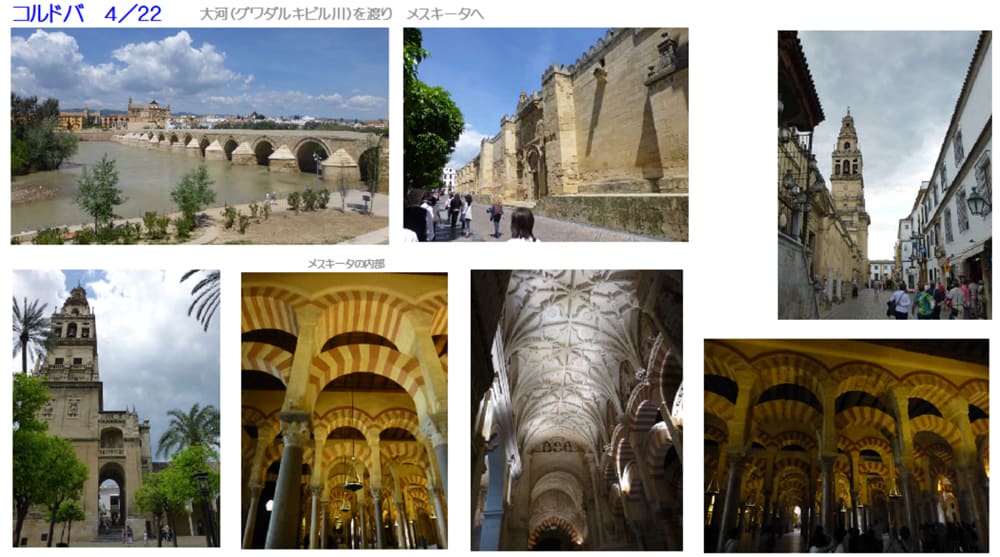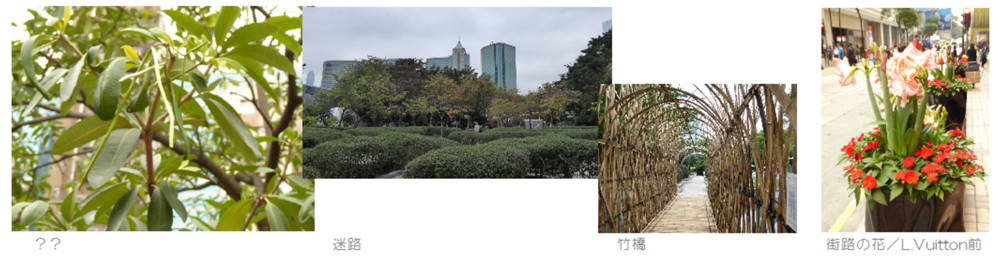ベルサイユ宮殿は1682年にフランス王ルイ14世(1638~1715、在位1643~1715)が建てた
フランスの宮殿である。パリの南西22キロに位置する。
その歴史は、最初に1624年にルイ13世が狩猟の館として建て、1661年からルイ14世が宮殿の
増築、セーヌ川から庭園に水を引く造園工事を行わせた。1699年からマンサールによる増築
や鏡の間の増築が行われた。(天井画はル・ブラン作)
この宮殿では、太陽王ルイ14世がその豪壮な宮殿と庭園を築き上げ、王や諸侯を招待して
「王の中の王」であることを見せつけた。絶対王政の象徴であり、世界でもっとも華麗な宮殿
といわれる。
また、付随する庭園はアンドレ・ルノートンによって造園された。宮殿も合わせた敷地面積
は1000ヘクタール(東京ドーム220個分以上)で、当時はこの10倍の面積があったそうである。
末尾に「鏡の間」の解説記事を写真ともに付加した。









以上。
ベルサイユ宮殿の雄大な庭園も必見です!!===> https://blog.goo.ne.jp/ms_blog_trecking120/e/47ab6769ec36216a88be53a175d6c46f