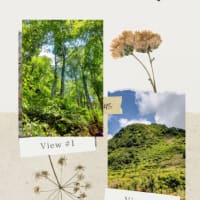サクラソウ

スズラン

牡丹


快晴、朝日のなかで咲く花たちがこれほど輝いて見えたことは、長い人生のなかで初めて味わうような気がする。例年であれば、連休後に咲く花たちが、もう咲き始めた。年々、気温が高くなり、花の咲く時期も早まっているのだが、今年はその傾向をさらに強く押しすすめているようだ。根本順吉に『江戸晴雨攷』という本がある。この本は江戸時代の気象を、当時の文人の日記を渉猟して再現したものだ。そのなかの一項に「江戸の生物季節」というのがある。江戸時代の季節の花が、新暦の何月に咲いたかを見ることができる。
3月30日 彼岸桜(東叡寺、山王)枝垂桜(東叡寺、谷中、日暮里)
4月5日 一重桜(山王、小石川、白山社)
4月9日 山吹(大森、蒲田山本園中)
4月12日 桃(隅田川の堤、上野坊中)
4月15日 八重桜(東叡寺、谷中、日暮里)
4月20日 桜草(戸田の原、千住)梨花(生麦村、川崎の先)
5月6日 ツツジキリシマ(根津権現境内)
5月8日 牡丹(深川永代寺、寺島村)カキツバタ(根津権現、寺島村)
5月18日 フジ(亀戸天満宮、茗荷谷伝明寺)
この一覧を見ただけで、江戸の花は今よりもひと月も遅くに咲きだしたことが分かる。北国であるここ山形で、4月中にフジが咲き、ツツジや牡丹、サクラソウ、アヤメが咲いている。江戸でもそうであったが、花はその種によって、順序を決めて咲いていく。今年が異例なのは、一切順序をなくし一斉に咲いたことだ。2日ほど前からカッコウが啼いた。江戸ではホトトギスが立夏の頃に鳴いている。