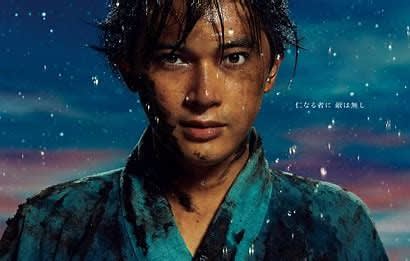
お金とは何か? 貨幣の誕生
そもそもお金とは何であるのか? 紙の紙幣やコイン、そうした「お金」はそもそもどうやって誕生して、そのシステムを作り上げていったのか? お金のきほんのき、です。
お金がお金である理由
ここに、日銀発行の紙幣があるとします。一万円や五千円、千円と書いてあり、肖像画も印刷していて、例えば一万円なら日本国中どこにいっても一万円分の商品やサービスと交換してくれます。でも、これはただの紙切れですよね? でも、私たちは誰もがお金として使用している。何故か? これはそれを発行している政府・国家や中央銀行(日本では日本銀行)を信用しているからです。
逆に、信用もしていない国の紙幣など誰も欲しくない。何故なら、その国の政府が倒れれば、すぐにでも「ただの紙切れ」になる可能性があるからです。
また、日本国内でEUの公式通貨のユーロも韓国のウオンも使えない。
ユーロやウオンが信用できないというんじゃなくて、あくまで日本国内での使用ですが。でも、例えば北朝鮮の紙幣……持ちたいですか? そういうことです。
お金っていうのは共同幻想であるからなんです。
世界中でアメリカのドルが価値が高い、とか、今、物凄い円安ですが、これも世界中で円の価値が安いと思っているから円安になる。まあ、為替相場な訳ですが。
では、どうして紙幣やお金・硬貨などができたのか?
それは意外と単純なことです。
お金が発明されてないときに、わたしたちはどうしていたか?
物々交換をしていた訳です。
山とかに住んでいた人は獲物を取り、肉を食べていた。でも、たまには魚も食べたい。逆に、海の近くに住んでいるひとは魚ばかり食べていた。たまには、肉も食べたい。そこで、それぞれ魚や肉を持ち寄って、物々交換をした訳です。それが市場に市、であったわけです。
ですが、考えてください。
肉も魚もすぐに交換しないと腐りますよね? 冷蔵庫もない時代ですから。
そこで、最初は稲が交換のために使われだした。
稲のネが、のちに値、値段に変化します。
でも、中国ではきれいな貝(子安貝・こやすがい)を加工したのを通貨の替わりに使っていた。そして、布の紙幣(「紙幣」の幣は「布」のこと。貝から買・貴・貯・財・資・貧の言葉が生まれた)―――――でも、稲もいつかは腐る。布も汚れたり破れたりする。貝もいっぱいとれれば価値が値崩れする。
そこで、稲や布や貝に替わって、金や銀や銅や宝石が使われだしたのです。
昔の戦国時代とかの日本は世界一銀のとれる国だったので、世界中の商品が買えたと言いますね。また、紙幣や通貨を塩で払っていたのが古代ローマ帝国です。
塩がサラリウム、そしてサラリー(給料)へと言葉が変化したという。
また、紙幣が出始めたときも、通貨が出始めたときも、その紙幣や通貨は金と繋がっていて、この紙幣ではいくらの金と交換できる――――というのが信用になっていた。
そういう交換する商売が、両替商。これがやがて銀行にかわる訳ですね。
両替商は「預かり証」を発行してその価値を保障した。預かり証が紙幣へと発展する。
いつでも金と交換できる紙幣を兌換紙幣(だかん・しへい)といい、そういうシステムを金本位制度と呼びます。
ですが、金と交換する程度の紙幣しか印刷できないのも不便です。経済が発展してくると、より沢山の紙幣が必要になります。世界中でも金の埋蔵量はそんなにないですから、これからは金と交換しない紙幣にしよう、ということになりました。
つまり、兌換制度・金本位制度をやめた訳です。それが日本では1934年(昭和七年)のことです。これで、今の日本銀行券である(金と交換できない・不換紙幣・ふかん・しへい)紙幣ができたのです。
まさに、紙ですが、これが我々が信用している限り、お金として流通し、使用していくことになる。まさに、これこそがお金です。
ちなみに、紙幣は日本銀行券で、日本銀行(日銀)が発行しているのですが、硬貨(補助貨幣ともいう。紙幣では足りない分を補助する貨幣という意味で、あくまで補助のためが硬貨)は日銀ではなく日本国と書いてある通り、政府が発行しています。具体的には大阪の造幣局でつくられています。春は桜並木がきれいな名所で有名な場所ですね。五百円硬貨を一枚つくるのに42円かかり、その差額が造幣局の利益になります。
また、2024年は新紙幣(新日銀券)発行年でもありました。
新しい一万円札(紙幣・肖像画は日本経済の父・渋沢栄一)と五千円札(紙幣・肖像画は女子教育者のパイオニア・津田梅子)と千円札(紙幣・肖像画は破傷風菌の治療薬の医学博士・北里柴三郎)が新しいデザインで登場しました。
何故、数年おきに紙幣のデザインを新しくするのか? まずは紙幣の偽造防止というのもありますね。まあ、偽造の割合は10000枚に1枚というのですが。
それでも、偽造紙幣などつかまされたら大変ですし。
紙幣偽造はかなり重い罪なんですが。
それとタンス預金対策というのもあります。タンス預金の紙幣を新しくするのに流通させる。つまり、経済を回していくということです。貯め込まれているだけでは経済が回らないので。何故、肖像画というか人の顔なのか? については、人間は人の顔の微妙な変化にはすぐに気付くからだといいます。つまり、偽札の不自然さを気づきやすいようにという配慮なんですね。よく考えていますよね。
需要と供給はどのようにして決まるのか?
私たちが普段口にする食べ物。そうですね、例えば牛肉の値段はどうやって決まるのか?
例えば、牛肉を食べたい人が増えると供給側(売る方)は高い値段で売ることが出来ます。また、牛肉を食べたい人が増えなくても飼育問題とかで牛肉の取る分(売る分)が少なくなるとやはり値段は高くなります。逆に、牛肉が多すぎたり、牛肉を食べたいひとが減ると値段は下がる訳ですね。
需要とは「欲しい・買いたい」と買い手が思うことで、供給とは「提供します・売ります」と売り手が思うことで、これがいわゆる経済活動です。
経済には「需要曲線と供給曲線」というものがあります。
ものを売る側からすれば、値段が安い時は作って売っても儲からないので、あまり作りません。これは供給が少ないということ。でも、欲しいという需要が増えると、値段が高くても買う人が出てきます。すると、高く売れるならもっと生産を増やそうと考え、供給が増えていく。
一方で、ものを買う側で考えると、何か欲しい物があっても、値段が高いときには買う人は少ない。これは「需要が少ない」状態。でも、値段が下がると、その値段でなら買いたいというひとが増える。これが「需要が多い」状態です。
この需要と供給が釣り合うところで「物の値段」というのが決まるということですね。
日本経済もこの需要と供給で読み解くことができます。
経済をどうにかするには金利の上げ下げとお金じゃぶじゃぶの政策しかない。
逆に言えば、経済政策は結局、このふたつしかない。
つまり、金融政策と財政政策です。
日本経済の回復の足を引っ張ってきたのが「需要ギャップ(ズレ)」でした。
最近まで日本はデフレで、物価が安く、インフレターゲット目標が2%とか言っていたが、世界的なインフレや物価高、また、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ侵攻などで物価が上がってきている。また、記録的な円安で、日本人による海外旅行などでは割高になり「当分の間、海外旅行も国内旅行も無理だ」みたいなフェーズ(笑)になったりしている。
逆に、円安で「安い」と、インバウンド(訪日外国人)需要で日本への観光客が増加の一方である。日本経済の回復にはこのインバウンドが重要になっていますね。
(あとで説明いたしますので諦めないで)
「需要ギャップ(ズレ)」に話題を戻します。
工場で製品をいっぱい作っても「それが欲しい」という需要がないと売れませんから、工場は生産を減らしたり、そこで働く従業員の仕事がなくなり、リストラにあうかも知れません。失業者が増えれば景気も悪化するのです。
供給を減らす、または需要を増やす……逆に言えば、そうすることによって需要と供給をぴたっと一致させれば経済は上手くいく訳ですね。
こういう需要ギャップを何とかする解消する方法を考えるのが政府の仕事であったりします。例えば、公共事業で道路や橋をつくることで、その作業をする人の雇用は増え、消費は増える。だから、馬鹿な政治家、アイデアのない政治家ほど公共事業ばかりする訳です。経済政策など何もわからず、取り合えず公共事業さえすれば、雇用も消費も増えるのですから。供給を減らすときは工場を閉鎖する企業に補助金を出したり、失業者に補償金を渡したり、再教育を施すなどする政策になる訳ですね。
こうして「需要ギャップ」を解消する策を講じる訳です。
決算とは何だろう?
毎年三月になると企業の決算のことが話題になる。その企業にとっての通信簿のようなものだけど、その決算について学んでみよう。
企業が一年ごとに収入と支出を計算し、利益(または損失)を算出することを「決算」といいます。企業は毎年の義務として「決算書」をつくらねばなりません。
上場企業は決算(年に一度)のほか、中間決算(半年に一度)や四半期決算(三か月に一度)を発表する義務があります。上場企業は決算書を作ることで、「今期はここまで努力して結果を出しました。でもまだこれだけ課題もあります」と情報をオープンにして、「どうかうちの会社に投資してください」と、投資家にアピールするわけですね。
日本は四月から新年度ですから、三月に決算をまとめる企業が多いです。決算が三月だと、株主総会の準備に二か月くらいかかるので、六月に一斉に株主総会が開催されるというカラクリです。
企業の一定の儲けを表すのが「損益計算書」です。決算書と一口に言っても、実際は「損益(そんえき)計算書(会計の期間中にどれだけ儲けたか)」「貸借(たいしゃく)対照表(決算日時時点での企業の財務状況・「資産の部」「負債の部」のバランス具合)」「キャッシュフロー計算書(一定期間にどれぐらいの現金が入り、いくらの現金がでていくか)」という三つの書類(「財務三俵(さんぴょう)」)に大きく分かれています。
しかし、計算方法は難しい、というか企業の会計係や財務課などのひとがやればいいことですので、詳しく計算方法が知りたいひとは専門書(会計説明本)を買いましょう!
ここではつまり、説明を省く、ということです。がっかりしましたか?
でも、何もかもすべてわかるひとなどいないように、この記事群も何でもかんでもわかるようなオールマイティな記事ではないということ。それは当たり前のことでしょう?
紙幣発行の手順
日本の紙幣は日本銀行券ですが、これは「借用証書」なんです。
銀行は担保(お金を借りた)として、社債や手形、国債などを日本銀行に渡す(借金の担保)、すると、日本銀行は国債や手形、社債、などを預かった「借用証書」として、紙幣を銀行に渡します。その紙幣が世の中に回って、経済が動いているということですね。
銀行はお金を預金者から預かって、その金で、会社に投資したり、国債を買ったり、投資してお金を増やします。日銀は最後の貸し手。最後は日銀が何とかする。
日本銀行券は「借用証書」だけども、おカネとして日本国中で使えます。
前の項目でも書きましたが、我々、日本人がこの紙幣を信じているからどこででも使えるんですよね。だって、日本国内で、EUのユーロ紙幣は使えないでしょ?
そういうことが紙幣のおカネの仕組みであるのですよね。

















