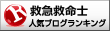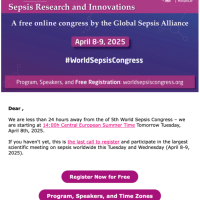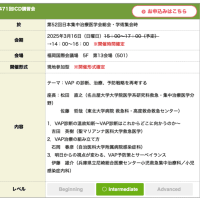急性期管理におけるアルブミン輸液の意義
名古屋大学医学系研究科 救急・集中治療医学分野
教授 松田直之
はじめに
アルブミンは,肝臓で合成される血漿タンパク質です。血液より血球細胞を除いた血漿中に最も多く含まれるタンパク質であり,血漿膠質浸透圧の維持,血液中の物質の運搬などの役割を担っています。かつては第二次世界大戦などの戦時における外傷や熱傷に使用され,現在も輸液製剤としてショックや周術期管理に使用されていました1)。一方,現在は,輸液療法においてアルブミンの厳格使用が推奨されています。この背景にある観点は,①アルブミン投与の意義の再評価と,②アルブミンの国内自給の2つである。アルブミンを輸液として用いる場合の効能と効果,およびアルブミン精製に関する自給が論点となっています。
米国における53病院の施設調査では,University Health System Consortiumのガイドラインに対して,成人の57.8%,小児の52.2%に不適切なアルブミン使用がありました2)。また,日本では,アルブミン使用量の増加によりアルブミンの国内自給が追いつかず,アルブミンを海外から輸入している状況にあります。2003年7月に施行された「安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律」(血液法)では,倫理性と国際的公平性の観点から,血液製剤は国内自給を基本とし,さらに国内での安定供給を原則とされています。この血液法は,アルブミンにおいても国内需給を目標とした使用制限としています。2006 年に厚生労働省は,アルブミン使用量(g)/赤血球製剤使用量(単位)比が 2 以下となる血液製剤の使用を提案し,保健請求における輸血管理料が新設されました3)。しかし,私たちが経験するようにアルブミン使用量を赤血球使用量で標準化する指針が適切とならない病態は,周術期,敗血症,急性膵炎のような全身性炎症症候群4)でたくさんあるのが現状です。
基盤として考慮しなければならないこととして,免疫グロブリン製剤とアルブミン製剤が製造過程において同一血漿より分離精製されることです。日本では静注用免疫グロブリン製剤の使用量がアルブミン製剤より低いため,アルブミン製造を増加させることにより,静注用免疫グロブリン製剤が生産過剰となる可能性があります。国内のアルブミン製造に関与する各社は,免疫グロブリン製剤の供給に必要とする原料血漿量の範疇でアルブミン製剤を製造しているため,年間あたり現在必要としている約165万Lのアルブミン製剤の不足分を海外より輸入しており,血液法上の問題があります。
以上のように,日本には多くの薬剤と同様に,アルブミン自給における供給不可の背景が存在しています。この背景の中で,アルブミンの生理的機能を,基礎と臨床の側面より把握することが大切ですし,遺伝子組み換えアルブミン製剤やiPSによる合成肝臓の応用が期待されます。その上で,アルブミンの生理学的機能などを理解して,適正使用を考えることが期待されます。
アルブミンの生理学的機能
アルブミン(albumin)は,分子量約66,500のハート型の立体構造を持つ血漿タンパク質です。凝固因子を除いた血清レベルでは,血清総タンパク質(正常:6.7~8.3 g/dL)の約50-60%(正常:3.3~5.2 g/dL)を占め,血漿膠質浸透圧を維持する機能を持つています。肝臓でアミノ酸を原料として1日量 約0.2 g/kg体重のアルブミンが産生されますが,この量は1日のタンパク質合成量の約20-25%にあたるとされています。成人では1日量で約10 -14 gが産生され,この合成と分泌は約30分と極めて速いことも知られています5, 6)。体重1 kgあたり4~5gが体内に貯蔵され,この約40%が血管内に存在し,transcapillary filtration(毛細管濾過)として約60%が血管外に分布しているとされています。このアルブミンの主な生理的機能は,①細胞間質環境の維持,②担体作用,③膠質浸透圧形成,④酵素様作用です。
1.アルブミンの構造
ヒトアルブミン(Gene ID: 213)の遺伝子座は,4q13.3に存在し,約17,159 の塩基からできています7)。この遺伝子は,図1のように15のエクソンと14のイントロンにより構成されています。肝細胞は,プレプロアルブミンを転写した後,アミノ酸を原料として609個のアミノ残基のプレプロアルブミン(表1)を翻訳し,小胞体でN末端の18塩基を切断したプロアルブミンとし,さらにゴルジ体でN末端の6残基を切断し,585残基のアミノ残基としてアルブミンを血中に分泌させます。アルブミンは,アミノ酸供給により増加することに加えて,ホルモンでは甲状腺ホルモン8)や糖質コルチコイド9)により転写が維持されています。
アルブミンの構造は,Ⅰ領域,Ⅱ領域,Ⅲ領域の3つの領域(ドメイン)と各aとbの2つの副領域(サブドメイン)で区分されます(図2)。そして,アルブミンの2次構造は,βシートを持たないαヘリックス構造です。さらに,アルブミンは,正常状態では糖鎖を持たない単純タンパクですが,35個のシステイン残基(Cys)のうち34位のCys(34Cys)を除いたすべてがジスルフィド結合をすることで構造が安定化している特徴があります。
2.アルブミン分子の高次構造
アルブミンの基盤形状は,ハート型であり,柔軟で,さまざまな分子と結合できる特徴があります。補足説明となりますが,タンパク質は,20種のアミノ酸のカルボキシル基(-COOH)とアミノ基(-NH2)のペプチド結合(-CONH-)による鎖状なアミノ酸結合体(ポリペプチド)です。このポリペプチドの折りたたまれ方には,一定の規則があります。αヘリックス構造は,ポリペプチドがらせん状に時計回りに巻かれた構造になっているものです。アルブミン分子では約67%のアミノ酸がαヘリックス構造の形成に関与しています。一方,βシート構造は,平行に配列した2本以上のポリペプチド鎖が水素結合することにより,側方から直線的にペプチド鎖が固定化される構造です。アルブミン分子には,βシート構造が認められない特徴があります。このようなアルブミンの高次構造をX線構造解析したデータなどをデータベースで確認すると,アルブミン分子はαヘリックス構造などが分子内で独立した球形構造を形成していることが確認できます。このタンパク質の2次構造の単位をドメインと呼びますが,アルブミンはドメインⅠ,Ⅱ,Ⅲの3つのドメインで構成されます。このドメインとドメインの間は,ループ上のポリペプチド鎖でつながれており,ドメインの中にポリペプチド鎖の基盤集合単位として,サブユニット構造があります。アルブミン分子には,各3つのドメインの中にaとbの2つのサブユニットがあります。このような構造として,アルブミンの形状はハート型であり,柔軟で,さまざまな分子と結合できる特徴を持つことになります。参考:Protein Data Bank Human Albumin
3.アルブミンの半減期とアミノ酸変異
Gamsjägerら10)の外科系集中治療室3,591例の解析では,アルブミンの血漿除去半減期は約11.8日であり,従来のヒトにおける計測の17日〜21日(約19日)より短縮していると報告されています。周術期などの急性期病態では,アミノ酸供給の低下によりアルブミンの産生が低下しやすいですが,放射性同位元素などを用いた研究でアルブミン半減期が短縮することが確認されています。
アルブミン消失半減期が救急・集中治療領域の急性期管理において短縮している理由として,① 血管透過性亢進に伴う組織間隙への移動,② 胸水・腹水・腸液への流出,③ 尿中クリアランスの増加,そして,④ アミノ酸変異の影響が知られています。ヒトアルブミンは変異として,これまで60種類以上の遺伝子多型が知られていますが,転写や転写後修飾における変異により,さまざまな表現形があるとされています。例えば,アルブミンのC末端のアミノ残基の欠失,さらに63Aspや177Cysのアミノ酸変異は,血漿アルブミン濃度の低下の原因となることが知られています。特に,Cys残基のアミノ酸変異は,アルブミン構造の安定性が障害され,血漿除去半減期が短縮する原因とされています。
さらに,周術期にアルブミン半減期を減少させる要因として,neonatal Fc receptor(FcRn)が関与することも知られています。FcRnは齧歯類の新生児小腸に高発現し,1989年に母乳の吸収に関与する受容体としてクローニングされた。アルブミンは166Hisにおいて局所pH6~6.5でFcRnと結合し,pH7.4で解離することが確認されています11)。これが,気管支上皮細胞,腸粘膜細胞,さらに血管内皮細胞などの上皮系細胞においてトランスサイトーシスを誘導し,アルブミン除去を高めている可能性があります12)。
4.アルブミンによる循環血液量の維持
アルブミンは,血管内膠質浸透圧を維持する分子として,1 gあたり20 mLの水保持能力をもつとされています。具体的には,5%アルブミン液250 mLは,12.5 gのアルブミンを含有しており,250 mLの血管内水分量を維持できる計算となります。また,25%アルブミン液50 mLは,12.5 gのアルブミンを含有しており,250 mLの血管内水分量を維持できる計算となり,血管外より血管内に200 mLの水を回収できる可能性があります。このような観点から,ショックなどで循環血液量が不足している際には,5%アルブミン液を使用し,手術後の回復期などで細胞間質液を血管内へ回収する場合には20%アルブミン液,あるいは25%アルブミン液を用いる方策が行われてきました。しかし,2005年頃より,アルブミンの使用制限が一般的になってきました。アルブミンの適正使用については,臨床研究データの確認に加えて,実臨床において1)アルブミンが減少している原因の評価,2)アルブミン補充の意義,3)診療のゴールの設定が重要と考えています。
5.アルブミンの担体機能
アルブミンのⅠ,Ⅱ,Ⅲの3つの各ドメインは,さまざまな薬物,脂質,アミノ酸,Ca2+,Zn2+,メタロ化タンパク,プロスタグランジン,活性酸素種などの炎症性分子やさまざまな分子と結合し(図2),血中遊離濃度を調節し,蛋白機能調節や解毒などに関与します。特に,アルブミンのドメインⅡaにはドラッグサイトⅠ,ドメインⅢaにはドラッグサイトⅡが存在し,さらに脂肪酸や胆汁酸は独自の結合部位としてFA1~FA9までの9領域があることが確認されています。
麻酔領域で使用する薬剤の解析も進んでおり,デスフルラン,セボフルラン,イソフルランなどの吸入麻酔薬の多くは,アルブミンのドラックサイトⅠやⅡ,主にドメインⅡaとⅡbと結合し,1分子のアルブミンに対して約3分子が結合できることが確認されています13)。吸入麻酔薬は,他の分子のアルブミンの結合性を調節することや,チロシン残基などにおける脂肪酸とアルブミンの結合を抑制することでアルブミン2量体化を促進させること14)なども報告されています。また,集中治療領域におけるフェンタニルやプロポフォールは主にアルブミンのドメインⅠbに結合し,ジアゼパムは主にドメインⅢbに結合します。さらに,アルブミンのドメインⅡaに結合する多くの分子は,ドメイン1bにも親和性を持つため,ドメインⅡaの飽和状態ではドメインⅠaとの結合を高めることが知られています。
このように,アルブミンは多くの生体内分子を補綴する作用を持つが明らかとなっています。
6.アルブミンの多面性のある生理作用
アルブミンは,多くの酵素活性学的生理作用(表3)を持ちます。例えば,アルブミン分子のサブドメインⅡaに存在するLys199などのリジン残基は,望ましくないことにペニシリン系抗菌薬などのβ-ラクタム系抗菌薬のβ-ラクタム環などの不活化作用を持っています。さらに,Tyr411はpH低下に依存して,結合したタンパクに対してエラスターゼ活性を高めます。アルブミンは,分子との結合領域の特徴により,タンパクの構造修飾15),脂肪酸分解16),ソマン17)などの解毒,細胞外に漏出されたRNA18)やプロスタグランジン19)など炎症性分子などのdamage-associated moleculeの分解,プロドラックの分解,さらに,活性酸素種の消去に関与します。また,アルブミンと結合するビリルビンは,活性酸素種を除去するラジカルスカベンジャーとしての作用を持ちますが,アルブミンとの結合により活性酸素種の除去力を高める事も知られています。
このようにアルブミンは,効能として多くの生理作用を持っており,低アルブミン血症では周術期の病態に会わせた個々の患者さんの状態評価が必要となります。
臨床研究から評価するアルブミン製剤の意義
1998年に発表されたアルブミン輸液に関するCochraneレポート20)は,輸液補正におけるアルブミン製剤の危険性を示唆する衝撃的なものだったかもしれません。このレポートは,British Medical Journalに発表され,それまでの32の臨床研究をまとめたシステマティックレビューでした。外傷や手術後などの患者1,419例の解析として,アルブミン製剤と晶質液で死亡率に差を認めず,さらに熱傷についてはアルブミンを使用することで死亡率が約2.4倍に上昇するというものでした。このレビュー以降は2010年にかけてまでにも救急・集中治療の急性期や周術期の病態生理学に対する研究が進展し,これらの多様性を考慮したアルブミン輸液の是非が,討議されるようになりました。
2003年のVincent先生たち21)は,90のアルブミンに関するコフォート研究を評価し,最終的に解析できる9つの集中治療データとして535名を抽出しています。このデータでは,ショック,感染症,多臓器不全などの合併症罹患率が,低アルブミン血症では約2.37倍,心臓手術で1.52倍,非心臓手術で1.73倍,腎不全患者で2.02倍に有意に上昇することが示されていました。逆に言えば,重症症例ではアルブミン値が低下することになります。この報告などにより,血清アルブミン値の低下は急性期病態における独立した予後規定因子として認識されるようになり,さらに血清アルブミン値 2.5 g/dL未満で合併症発症率が増加することが明らかとされています。
以上の背景を踏まえて, 4%アルブミン製剤と生理食塩水を比較する輸液蘇生の2重盲検前向き臨床研究として,2001年11月から2003年6月までの20か月間において,オーストラリア,ニュージーランド,カナダの16の大学関連病院の集中治療室でSaline versus Albumin Fluid Evaluation (SAFE) Study22)が施行され,この研究は非常に有名な研究として他の追従のない状況です。このSAFE Studyにおいて,Acute Physiology and Chronic Health Evaluation(APACHE)Ⅱスコアが19点レベルのアルブミン群3,473例と生理的食塩液群3,460例の2群が比較解析され,28日死亡率はともに21%レベルで,統計学的にも有意差を認めないという結果となりました。サブグループ解析では,頭部外傷においてアルブミン使用群で高い死亡率が認められ,重症敗血症では低い死亡率が認められたという結果でした。
このSAFE study22)の結果を受け,SAFE studyの頭部外傷に関するポストホック試験23)として,多重比較試験の結果が公表されています。SAFE studyにおけるAPACHEⅡスコア20レベルの頭部外傷患者460名の解析おいて,頭部外傷患者の1年死亡率はアルブミン群で33.2%,生理的食塩水群で20.4%であり,アルブミン投与で有意に死亡率が高く,アルブミン投与による相対リスクは1.63(95%信頼区間:1.17-2.26)でした。さらに,Glasgow Coma Scale 3~8の重症頭部外傷では,1年死亡率がアルブミン群で41.8%,生理的食塩水群で22.2%であり,アルブミン投与による相対リスクは1.88(95%信頼区間:1.31-2.70)でした。また,1年後の神経学的予後は,アルブミン投与により有意に損なわれることが明確とされました。頭部外傷24, 25)の診療では,初期の適切な輸液管理が必要であり,輸液不足による血圧低下を阻止することが大切です。その一方で,本研究結果を受けて,頭部外傷管理ではアルブミン投与が避けられ,晶質液輸液を原則とするようになりました。脳血管関門の波状によるアルブミンの頭蓋内間質への移行に加えて,アルブミン1分子に含まれるグルタミン酸の含有量が62分子(表2)と極めて多いことを考慮すれば,急性期の頭部外傷におけるアルブミン輸液は避けるべきものと考えられるようになりました。
一方,SAFE studyの重症敗血症に対するポストホック試験26)では,敗血症の28日死亡率に有意に影響を与える因子として,①年齢,②APACHEⅡスコア,③心拍数,④血清アルブミン濃度の4つが同定されました。重症敗血症では,アルブミンは0.1 g/dL減少する毎に1.05倍に死亡率を高めるものとされ,アルブミン輸液は生理的食塩水に比較して28日死亡率を0.71倍に減少させると解析されました。手術中においてはハイドロキシエチルスターチ(HES)のような代用血漿製剤が,循環血液量を維持する目的で使用されていますが,重症敗血症のような全身性炎症,サイトカインストームの状況では急性腎傷害罹患率上昇と凝固線溶障害助長のために代用血漿製剤は使用しないことが原則です27)。また,炎症性手術での使用については,使用には注意が必要となるでしょう。手術後に炎症活性が高まる食道癌,肝門部胆管癌,膵腫瘍,心臓血管外科のような手術では,HESではなく,アルブミン輸液の選択が望ましいと考えられます。アルブミン1分子には,セリン24分子,チロシン18分子,スレオニン27分子などの血管内皮細胞や上皮系細胞の必要とするアミノ酸が適切に含有されている点が興味深いところです(表2)。術後患者の集中治療管理では,2006年のDubois study28)のように,アルブミンの適正補充が多臓器不全を改善させる報告もあります。
以上を検証する目的で,2013年の現在,1,350例の重症敗血症と敗血症性ショックを対象とした大規模な前向き他施設共同試験ALBumin Italian Outcome Sepsis study(ALBIOS)29)が施行されています。アルブミンにより,敗血症の循環動態は安定化しますが,晶質液でも適切に管理できる技法も一般に育っています。ALBIOSの結果により,敗血症などの全身性炎症病態におけるより適切なアルブミン使用を,再び詳細に論じることができると考えています。特に,本邦においては高齢者の低栄養状態における急性期アルブミン投与の意義を診療と哲学の両面より考える必要があるのが現状です。
おわりに
本稿では,アルブミンの生理作用を基盤として,アルブミンの役割とアルブミン輸液の意義を説明しています。その炎症性重症度において,アルブミンを使用するかどうかを含めて輸液製剤を使い分ける工夫が必要となります。これまでの臨床研究において,重症頭部外傷ではアルブミン輸液を差し控えること,全身性炎症や重症敗血症においてはアルブミン輸液も選択の一つとなることを説明しました。日本国内におけるアルブミン需給問題に対しては,前向きな取り組みが必要となります。アルブミン分子は,翻訳後修飾により2次構造や3次構造を独特に形成する特徴があり,アルブミンは興味深い薬剤担体としても解説しました。今後も,アルブミンに対する研究を推進させることや理解を深めることが必要と考えています。
文 献
- Peters T. Historical perspective All about albumin. San Diego, California: Academic Press Limited; 1996. pp. 1–8.
- Tanzi M, Gardner M, Megellas M, Lucio S, Restino M. Evaluation of the appropriate use of albumin in adult and pediatric patients. Am J Health Syst Pharm 2003;60:1330-5.
- 日本赤十字社: 輸血管理料. 輸血情報 2006;0604-99.
- Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest 1992;101:1644-55.
- Hafkenscheid JC, Yap SH, van Tongeren JH. Measurement of the rate of synthesis of albumin with 14C-carbonate: a simplified method. Z Klin Chem Klin Biochem 1973;11:147–51.
- Ballmer PE, McNurlan MA, Milne E, et al. Measurement of albumin synthesis in humans: a new approach employing stable isotopes. Am J Physiol. 1990;259:E797–803.
- Minghetti PP, et al. Molecular structure of the human albumin gene is revealed by nucleotide sequence within q11-22 of chromosome 4. J Biol Chem 1986; 261:6747-57.
- Lewallen CG, Rall JE, Berman M. Studies of iodoalbumin metabolism. II. The effects of thyroid hormone. J Clin Invest 1959;38:88-101.
- Strling K. The effect of Cushing's syndrome upon serum albumin metabolism. J Clin Invest 1960;39:1900-8.
- Gamsjäger T, Brenner L, Sitzwohl C, et al. Half-lives of albumin and cholinesterase in critically ill patients. Clin Chem Lab Med 2008;46:1140-2.
- Roopenian DC, Akilesh S. FcRn: the neonatal Fc receptor comes of age. Nat Rev Immunol 2007;7:715-25.
- Kim KJ, Malik AB. Protein transport across the lung epithelial barrier. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2003;284:L247-59.
- Sawas AH, Pentyala SN, Rebecchi MJ. Binding of volatile anesthetics to serum albumin: measurements of enthalpy and solvent contributions. Biochemistry 2004;43:12675-85.
- Pieters BJ, Fibuch EE, Eklund JD, et al. Inhaled Anesthetics Promote Albumin Dimerization through Reciprocal Exchange of Subdomains. Biochem Res Int 2010:516704.
- Ahmed N, Dobler D, Dean M, et al. Peptide mapping identifies hotspot site of modification in human serum albumin by methylglyoxal involved in ligand binding and esterase activity. J Biol Chem 2005;280:5724-32.
- Cha MK, Kim IH. Disulfide between Cys392 and Cys438 of human serum albumin is redox-active, which is responsible for the thioredoxin-supported lipid peroxidase activity. Arch Biochem Biophys 2006;445:19-25.
- Li B, Nachon F, Froment MT, et al. Binding and hydrolysis of soman by human serum albumin. Chem Res Toxicol 2008;21:421-31.
- Tamkovich NV, Popova TV, Knorre DG, et al. RNA-hydrolyzing activity of human serum albumin and its recombinant analogue. Bioorg Med Chem Lett 2010;20:1427-31.
- Yang J, Petersen CE, Ha CE, et al. Structural insights into human serum albumin-mediated prostaglandin catalysis. Protein Sci 2002;11:538-45.
- Albuman albumin administration in critically ill patients:systematic review of randomised controlled trials. Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. BMJ 1998;317:235-40.
- Vincent JL, Dubois MJ, Navickis RJ, Wilkes MM. Hypoalbuminemia in acute illness: is there a rationale for intervention? A meta-analysis of cohort studies and controlled trials. Ann Surg. 2003;237:319–34.
- Finfer S, Bellomo R, Boyce N, et al. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med. 2004;350:2247–56.
- Myburgh J, Cooper J, Finfer S, et al. Saline or albumin for fluid resuscitation in patients with traumatic brain injury. N Engl J Med. 2007;357:874–84.
- Brain Trauma Foundation, American Association of Neurological Surgeons, Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Resuscitation of blood pressure and oxygenation. J Neurotrauma 2000;17:471-478
- Cooper DJ, Myles PS, McDermott FT, et al. Prehospital hypertonic saline resuscitation of patients with hypotension and severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1350-1357
- Finfer S, McEvoy S, Bellomo R, et al. Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of patients with severe sepsis. Intensive Care Med 2011;37:86-96.
- Haase N, Perner A, Hennings LI, et al. Hydroxyethyl starch 130/0.38-0.45 versus crystalloid or albumin in patients with sepsis: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ 2013;346:f839.
- Dubois MJ, Orellana-Jimenez C, Melot C, et al. Albumin administration improves organ function in critically ill hypoalbuminemic patients: a prospective, randomized, controlled, pilot study. Crit Care Med. 2006;34:2536–40.
- EudraCT number 2008-003281-25, ClinicalTrials.gov number NCT00707122.
図と表の解説

図1 プレプロアルブミン遺伝子の転写と翻訳
DNAのヒト遺伝子座chromosome 4q13.3(Gene ID: 213)に,プレプロアルブミンの15のエクソンと14のイントロンは存在する。肝細胞内において,核内でのプレプロアルブミンmRNAへの転写後に,粗面小胞体における翻訳と,ゴルジ体における翻訳後修飾を受けて,プロアルブミンを経て,585アミノ残基のアルブミンとして血液中に分泌される。

図2 アルブミンの構造
アルブミンは,3つのドメインと,各AとBの2つのサブドメインにより,大きく6つの部位として機能が評価されている。

図3 アルブミンの担体機能
アルブミンの6つのサブドメインの中で,主に薬物などの担体機能を果たすのは図の3つの領域である。これらは,代表的な薬物の名前として,ジゴキシンサイト,ワルファリンサイト,ジアゼパムサイトなどとも呼ばれている。アルブミンのドメインⅡaに親和性を持つ薬物などは,ドメインIbも親和性を持つことが知られている。

表1 プレプロアルブミンのアミノ酸配列
本配列は,ワシントン大学のバイオテクニカル情報センターの2012年10月19日に公開したヒトのプレプロアミノ酸のアミノ酸配列である。肝細胞の小胞体において,N末端の18塩基(点線)が切断されてプロアルブミンとなり,さらにN末端の6残基(下線)が切断されて585残基のアミノ残基としてアルブミンが精製される。

表2 ヒトアルブミンの1分子中のアミノ酸含有数

表3 ヒトアルブミンの酵素様作用