“Opinion”
*レモン問題に触れる契機
私は今までの業歴の中で中古車時代がとても面白かった。特にオークション展開をやったので、人との交流も多く、その中で現在も情報交換をしている仲間がいる。主に中古車の価格問題を担当して居る連中であり、いつも面白い情報はメールで転送してくれる。‘01年10月一本のメールの中に“中古車市場はレモンの市場“と言うメールマガジンの記事と、それのベースになった同志社大学商学部二村教授の”レモンの市場”と言う講演の記事が載っていた。始めは「えっ!何これ...」と言う感じで読んでみた。メールを送って呉れた仲間に聞いてみたが、「何でしょうね...解りませんョ」との事、これが「レモン問題」に触れた契機である。
* その後、色々調べて見た。
*-1 私自身「レモン」の言葉の中に「欠陥車」の意味がある事は全然知らなかった。レモンは「酸っぱいけれど爽やか」と言うイメージで良いイメージの方が強い。自動車の仕事を40数年やっていて、しかも中古車の輸出も手掛けているし、外国人との付き合いも国内ディーラーの人間としては多い方である。それなのに聞いた事も無いので、色んな人に聞いて見た。その結果を表にして見る。
*-2
A、レモンに欠陥車と言う意味がある事を知っているか?
B、レモンの反対語はピーチと言う事を知っているか?(ピーチは皮が柔らかく外から中味の状態が解るので)
C、ジョージ・アカロフ(ノーベル賞学者)の“中古車市場はレモンの市場”と言う理論を知っているか?
D、アメリカにレモン法と言う法律がある事を知っているか?
* ( A=知っている △=聞いたような気がする X=知らない)
(1)国内自動車販売に携わっている人は殆ど「レモンもレモンの市場」も知らない。
(2)学者は専門分野では当然詳しい。しかし,自動車流通分野の特に中古車市場の実態は余り解っていない。
(3) #7,#8,の元会社役員は海外経験も相当豊富にある人だが、「ピーチ」はスラングの「いい女!」と言う意味で覚えているとの事であった。
(4)アメリカの自動車修理業者のMatt(年齢33歳位) 家業の外車(アメリカでの輸入車)修理業を40年やっているが、“LemonLaw“は知らない」と言う。要するにアメリカでは欠陥車はもう法律通りの処理が当たり前で、「Lemon Lawは昔の話で、今アメリカでは忘れられて余り問題になって居ない」と言う事のようである。
(5)きっとこの問題は、日本の自動車メーカーの人で20年位前に現地へ行って居た人は「知っている筈だ」と思っていたが、アメリカトヨタ、アメリカニッサンのサービス関係の人は知っている人が多かった。但し、「経済学」としての話は知って居ない。現在でも年間相当数のレモン法上の欠陥車は発生するが、消費者との間は法律に沿って処理(車両交換等)され、それらの車は修理された後、「レモン車」と明記されて中古車市場に出されている。レモン法制定時にアメリカに居た人によると、当時、アメリカでは日本車を中心とする輸入車が増加しつつあった。これを防ぐ意図で「輸入車は品質が劣る筈だ」と言うことで、輸入車の増加を抑える意図で、消費者保護の名を借りて法律を制定した。処が、輸入車の品質が良くなりこの法律は「アメリカ製の車の首をしめてしまった」と言う話も在るそうだ。又、レモン法制定の契機はサンディエゴ郊外の「レモングローブ」で一人の女性の活動から始まったと言う話があるが、「レモン法」の名前はその地名から付けられたではなく、レモンの「欠陥車」と言う意味から名付けられたそうだ。
(6)その後、「2,3月の月刊自動車販売を見て色々解ったよ」と言う声を聞いたが、その中に公正取引協議会の1989年の「消費者問題の実情調査報告書」にレモン法が出ていると言う話があった。しかし、それ以降この報告を参考に日本国内の消費者問題を検討したと言う話も余り聞いていない。1996年の同じく公取協の「価格、品質表示の実態調査」の中で、“オレンジトヨタ”と言うディーラーを訪問した記事が載っている。この社名はまさに日本人的発想で「レモンは酸っぱい」「オレンジは甘い」と言う事から「レモンが欠陥車ならせめてオレンジ車を...」と言う意味で付けられた名前なのだろう。この辺に米国と日本の感覚、文化のギャップを感じさせられた。
(7)私自身は80年代に公取協のワーキング・スタッフを5年間務めていたが、その時代はプライスボード(品質説明書)の内容を統一する事のみしか考えられず、特に修復歴の欄を設ける事に時間を割いた記憶がある。又、NAA(Nissan Auto Auction)東京の新会場設立時に運営委員長をしていたが、この時は車両状態表の正確な記入を重点的に指導した。これは売り手側の情報開示であるが、当時、「情報の非対称性」や「逆選択」の理論等を知っていれば「中古車市場が外部からどんな見方をされて居るか?」正確な情報を伝える必要性を説く上で随分参考に成ったと思う。
(8)今問題に成っている「メーター巻き戻し」もこれに関わる大きな問題で業界の情報開示(品質表示)に付いてモラルアップした自主的対策が必要である。
(9)しかし、雪印や全農問題が起こり、日本の消費者問題(表示について)は不信感が充満し、全く地に落ちた状況と言えよう。人は供給者と消費者の二面を持っているので、全ての経済活動は全て自分達自身に返って来る問題である。特に雪印問題等のように、会社が無くなれば働く人が一番困る訳で、日頃から働く場を失わない様、労働組合も会社側に対し経営協議会等通じてチェック機能を働かせる事が大事だ。経営者だけでなく、組合の指導部を含めた問題意識の欠如による責任も大きい。
(10)本文作成に当たって、諸先生方、特に慶応義塾大学経済学経済学部丸山教授(バークレー校留学時代ジョージ・アカロフ教授と旧知)とのご尊縁、ご指導に感謝致します。
☆さて、ここで言いたいことは、先週のブログで書いた、「No Work No Pay」を知らない選挙運動員の事である。「自分の推す政党の根本的思想も知らない」「TPP問題の自動車の問題も解らない」「公安委員長がスピード違反の原則論を知らない」自動車屋は恐ろしい急成長に押しまくられて、レモン法も知らない」このgapは如何してこんなに大きくなったのだろう?大局観の無いリーダーにこの20年引っ張られて来た結果だろう。
* ( ○=知っている △=聞いたような気がする X=知らない)
A |
B |
C |
D |
R/M | |
#1中古車会社役員(K大経) |
X |
X |
X |
X |
業界歴40年英会話勉強している |
#2中古車会社社長(R大経) |
X |
X |
X |
X |
業界歴50年 輸出歴25年 |
#3T元会社役員(K大法) |
最新の画像[もっと見る]
|











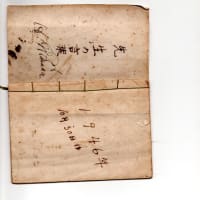
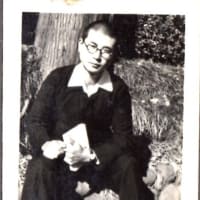



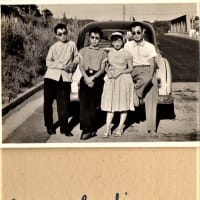
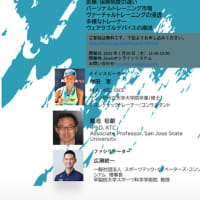


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます