久女の師、高浜虚子は久女の死から2年8ヶ月後に『文体』という雑誌に、久女が昭和9年に虚子に出したとする手紙のうち19通を選んで、創作「国子の手紙」を発表しています。この作品は現在、『高浜虚子全集第7巻小説3』に納められているので、誰でも読むことが出来ます。
虚子は創作と言っていますが、久女と彼女の長女昌子さんからの手紙に、虚子が短い解説を幾つか付けたもので構成された小説で、とても創作とは言えない不思議な奇妙な作品です。虚子は創作ということにして、周到にあらかじめ逃げ道を作っておいたと言えなくもないでしょう。 <高浜虚子 1874-1959>
<高浜虚子 1874-1959>
虚子が久女からの手紙が不愉快だったとしても、死者に鞭打つ様なこんな大げさな形式をとって、私信を発表する必要が、何故あったのでしょうか。
彼はこの「国子の手紙」の中で、一言も同人除名の理由には触れず、ただ「常軌を逸していた」「狂人」という点のみを強調し、久女が狂っていたという風説を流すのだけが目的であった様に思えます。
普通に読むと、この久女の手紙は尋常な人が書いたものとは思えません。少なくともその頃の俳壇事情について、また当時の杉田久女の置かれた位置や心境について、ある程度知っていなければこの手紙の意味するものは解らないと思います。
久女がこれらの手紙を虚子に出したとされる昭和9年は、久女の才能が全開したといわれている時期ですが、昭和8年、昭和9年と二度の上京をして師の虚子に序文を懇願しても、虚子は序文を与えず、出版広告まで出た句集出版を久女の意志で中止したとされている年です。
久女にすれば、いくら考えてみても敬慕する師、虚子から序文を貰えない理由が判りませんでした。それで妥協の出来ない一途な性格の久女は、「国子の手紙」にみられるような尋常ではない身もだえする様な凄まじい手紙を、虚子あてに書く様になったのだと思います。
この様な手紙を受け取った虚子は、久女がこんな手紙を書くようになった理由は判っていたはずですが、それでも序文を与えることは決してしませんでした。そればかりか、彼女から来たこれらの手紙を〈これはおかしい、尋常ではない〉とし、散逸させずにとりのけていた様です。
久女の本音が臆面もなく出ている、泣訴、哀願、強訴のこれらの手紙を〈これはおかしい、尋常ではない〉として、とりのけておくという虚子の心の動きを、私は非常に興味深く思います。なぜ弟子の久女がこの様な手紙を書くようになったのかと考える心というか、そういうものは、虚子の中には全くなかったようです。
田辺聖子さんはその著書『花衣ぬぐやまつわる...』のなかで、〈虚子のある種の「おそろしさ」を、久女は知らずに虚子に憧れ、虚子の愛顧するものを羨んだのである。私は久女の世間知らずというか、ある種の無智を、哀れまずにはいられない〉と書いておられます。私も同感です。
次回は創作「国子の手紙」の内容について少し触れてみようと思います。















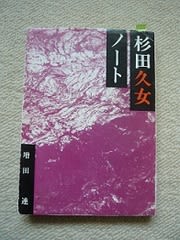 <増田連著『杉田久女ノート』>
<増田連著『杉田久女ノート』>