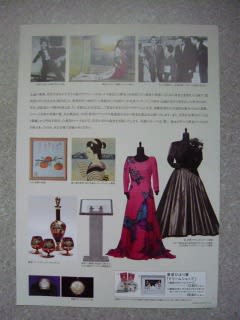昨日、佐賀県唐津市に住む友人から宅急便で椎茸が送られて来ました。
 <届いた椎茸>
<届いた椎茸>
友人は定年退職した後、椎茸栽培に取り組み、4年で 佐賀県しいたけ品評会で優秀賞を受賞するまでになられました。
送られて来た椎茸は傘の径が15センチ程もある新鮮なジャンボ椎茸で、ビックリするほど肉厚で、品評会での優秀賞受賞の名にたがわない、それはそれは立派なものです。
昨日はさっそく、軽く塩を振りグリルで焼いて酢じょう油で、今日はしいたけの裏表にバターとお醤油を塗り、グリルで焼きレモンをかけて頂きました。今までスーパーなどで買っていたものと違い、味といい香りといい、食感といい、格別の美味しさでした。
友人によると、椎茸には原木椎茸と菌床椎茸の2種類があるそうです。
友人が栽培しているのは原木椎茸ですが、これは原木にキノコ菌を人の手で植え(ほだ木)、キノコを発生させる方法です。原木椎茸の特徴は、農薬や肥料を使わず自然の中で育つので、味や香りが良いこと、丈夫で肉厚である事などで、収穫の時期は11月~4月までだそうです。日本全国で原木椎茸の取り扱いは2割程度らしく、原木椎茸の栽培には大変な体力が必要で、栽培の最初の数年はかなりの資金を必要とするのだそうです。
菌床椎茸は薬品などを使い大量に工場生産するので1年中収穫出来るそうで、普通スーパーなどで売られているのは大部分が菌床椎茸だそうです。
椎茸といえばヘルシーで低カロリーというイメージで、和風、洋風どちらにも使える食材なので、これから需要はますます増えるのではと思います。美味しい原木椎茸ありがとうございました。
![]()
にほんブログ村←ランキングに参加中! クリックよろしく~(^-^)
.
.
.