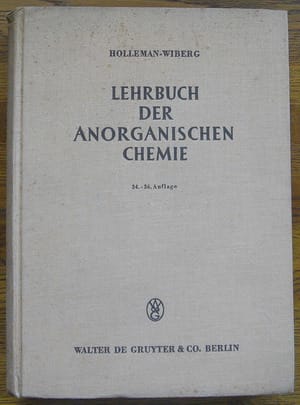ガレージの棚に突っ込んでいた本を整理していると、古ぼけた本が目についた。ドイツ語で書かれた無機化学の教科書である。手にとって眺めているとこの本にまつわるいくつかのことが甦ってきた。
私が大学に入学したのは昭和28年(1953)で選んだのは理学部だったが、入学してからの2年間は教養課程ということで教養科目などは学部に関係なく皆一緒に受けていたし、物理、化学などの理系の講義も自分で教師を自由に選べたので、医学部、薬学部、工学部の連中と一緒になることが多かった。たとえば有機化学なども何人かの教師が開講していて、私は評判のよい薬学部から出講のKT助教授の講義を受けたのである。私が教養課程で一番感銘を受けた講義で、やる気満々の先生の学問にかける情熱が講義を通して伝わってきた。ちなみにこのKT先生は後に東北大学教授を経て晩年は星薬科大学学長を務められた。
KT先生の熱気に煽られてか、この有機化学のクラスで知り合った仲間四五人で、当時出版されたばかりの(と思っているのであるが)井本稔著「有機電子論」をテキストに勉強会を始めたのである。姓が同じYさんが二人おり、一人は医学部でもう一人は工学部だった。二人とも見るからに賢そうで口を開けば確かに頭のいいことがよく分かり、私は一生懸命背伸びをして話に加わったものである。
もちろん同じ理学部でよく顔を合わせる連中とは交流も生まれ、親しい友人も出来た。その内の一人MKさんは大学院修士課程を修了してからM新聞社に入社し、科学記者としてのユニークな経歴を切り開き、日本における科学ジャーナリストの草分けとなった人である。多くの著書、翻訳書がある。
UMさんはなかなか思索的な人で、私のイメージにある旧制高校生のような雰囲気を漂わせていた。彼に刺激されて手を伸ばした教養主義的な本を読んでは、顔を合わせるとよく議論したものである。UMさん、MKさんはまともに2年間の教養課程を終えて理学部化学科に進学したが、私はとある事情から1年留年したので、彼らと再会したのは一年後、私が理学部に進学してからである。
その再会したUMさんから入手したのがこの無機化学の教科書である。彼は本に関する情報にとても詳しくて、無機化学ならこれを読むべし、と私に薦めてくれたのである。
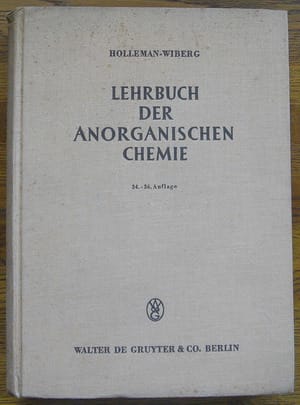
今この本を見ると、22、23版への序文を著者の一人Egon Wibergが1942年11月にミュンヘンで記しており、34、35版への序言は1954年11月、同じくミュンヘンでしたためている。第二次大戦の最中から戦後にかけて版を重ねていたことになる。そしてこの34、35版がベルリンで出版されたのが1955年となっているから、UMさんは出版されたばかりの本を手に入れていたことになる。ドイツにいる知り合いに送って貰ったとか聞いたような気がする。この本を彼から格安値段で譲り受けたのである。私はこの本を手に持っているだけで、650頁分の知識が頭の中に流れ込むような気分になったものである。
中身は化学だからドイツ語もなんとなく分かってくる。飛ばし読みながらでもこの本で勉強したおかげで、大学院入試の時は特に勉強しなくてもドイツ語をクリアすることができた。UMさんは卒業後大手の化学繊維メーカーに就職した。その後、同じ会社に就職した私の弟が彼にお世話になる偶然もあったが、いつしか音信は途絶えてしまった。
年月が流れた。
1970年代、私は阪大理学部の助手になっていた。有難いことに科学研究費の重点領域だったと思うが、京大医学部のHO先生が班長である研究班に班員として加えていただき、班会議のために京大医学部まで出かけた。そこで教養時代の勉強仲間、医学部のYSさんに出会ったのである。YSさんは臨床ではなく基礎医学を選び、生化学のHO先生の門を叩き、HO先生が阪大から京大に移られたときに同行したのである。やがて助教授に昇進し研究班の事務方を務めたYSさんにはいろいろとお世話になった。そしてどういう運命のいたずらか私が京大に移るに当たり、YSさんにもアドバイスを頂いたのである。赴任の挨拶にうかがった時、HO先生は学部長になっておられた。
京都に移って何年か経ったある日、講義を終えて後片付けをしていると男子学生が私の所にやってきた。「失礼ですが、先生は阪大のご出身ですか」と尋ねた。そうだ、と答えると「UMを覚えておられますか」と重ねて聞く。もちろん私はUMさんのことをすぐに思い出した。「私の父です」と彼がいう。そうしたことで、かれこれ30年ぶりにUMさんと再会し旧交を温めたのである。
縁は異なものと思い出した話はこれでお終いなのであるが、ことのついでに「出来る人は出来る」で締めくくりたい。というのも息子のU君の話で感じることがあったからである。
その頃入試制度が変わって、東大と京大の医学部を両方受験することが可能であった。当然両方とも合格する受験生が何人も出て来る。合格者がどちらを選ぶか、その去就が注目されて、東大を蹴って京大を選ぶ学生が数人出たきたことが世間でも一時話題になった。このU君がなんとその一人だったのである。
U君の話などを聞いて思ったのは、「出来る人は出来る」というごく当たり前のことなのである。受験生を持つ親には少々むかつく話かもしれないが、出来る人は世間で難関といわれるようなところでもスイスイと突破してしまう。通って当たり前なのである。そういう人が同一年齢人口に一定の割合で必ず存在するのである。
同じことが研究者の卵にも云える。毎年研究生活に足を踏み入れてくる若者のなかに、必ず一定の割合で将来大成する人材が存在する。優れた研究指導者なら、これは見所があると思う若者に必ず出会うはずである。そういう研究者のもとには自然と有能な若者が集まってくるからである。能力を見抜いたら指導者のすることはただ一つ、その若者に思う存分力を振るわせることである。独創的な科学はただの凡才からは生まれない。余計な口出しの代わりに必要な研究費をどんどん注ぎ込む。各種のCOEプログラムのリーダーにはそれが可能であろう。そういう風にお金が使われるのなら、私のCOEプログラム批判の矛先も少しは鈍ることだろう。