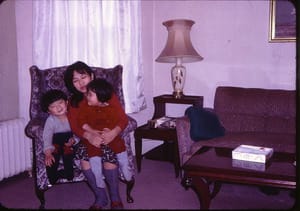1966年の夏、アメリカ東海岸にあるエール大学に留学することが決まり、渡米することになった。その当時私の所属する大学の研究室では、最初の1年は現職扱いで、2年目は休職扱いで海外留学2年が慣例的に認められていたのである。留学と云っても受け入れ先の教授の科学研究費に認められている人件費で雇用されるのであって、Research Associateなる職種で研究に従事するのであった。森鴎外のように国費で留学させて貰うのではなく、自前の出稼ぎ的側面があった。
太平洋を船で渡りアメリカ大陸を汽車で横断するという夢をかねてから暖めていた私は、またとないチャンスとばかりに船の便を探して商船三井の『さくら丸』を見つけたのである。アメリカでの契約は9月からだったので確か7月の終わり頃に神戸を出帆するさくら丸は時期的に最適であった。
私の記憶では、その頃のアメリカ航路の客船として有名だったのは、アメリカの船会社「アメリカン・プレジデント・ラインズ」 のプレジデント・クリーブランド号やプレジデント・ウィルソン号であった。そして大阪商船の「ぶらじる丸」に「あるぜんちな丸」は南米移民船として建造されたが、もちろんアメリカ航路にも使われていた。
一方1962年に見本市船として建造されたのが「さくら丸」で、輸出振興目的で世界各国に出かけて産業巡行見本市の動く展示場となっていた。


いろいろな日本製品を陳列して諸外国に寄港しては、各国の人達に見ていただくのである。要するにメイド・イン・ジャパン製品の売り込み船、日本はまだそのような時代だったのである。
見本市船として使われていない間は、商船三井が移民船として南米まで運航していた。この「さくら丸」が時期的にはちょうど都合がいいのである。神戸の海岸通りにある商船三井のビルに出向き、いろいろと説明を聞いた上乗船予約をした。
何をどう考えてそうなったのか、今では記憶が定かでない。BRIDGE DECK、すなわち船橋楼甲板にある一等船客室を海側と内側の二部屋を続きで予約した。夫婦に子供二人で一部屋は窮屈だろうとその時思ってのであろうが、考えてみたら贅沢な話ではあった。デッキプランが手元に残っているが、117号室(海)と127号室(内)に斜線を入れているのでこの二部屋を占めたのであろう。右舷にあった。
それぞれの部屋にベッドが二台にソファー、洗面台にクローゼットがあり、シャワー室が二部屋を繋ぐ形で設けられていた。それぞれの部屋から入れるように扉は2カ所にあるが、一方が使っているときは他方をロックするようになっていた。もちろんわが家族にとってはこれが通路になった。
私は日記をつける習性もなく、記録をとり続けるほど几帳面でもないので日時のことは分からない。手元に残した品々が当時の記憶を甦らせる手助けになるのであるが、この品々もかなりの部分がさる阪神大震災以来未だに行方不明である。従って神戸を出帆した日も不明であるが、航行中に娘の8月8日の誕生日を船で祝っていただいたことははっきりと覚えているので、だいたい7月末かな、と見当をつけたのである。ところが私と同じ「さくら丸」に乗船された方のウエブサイトを探し当てることが出来た(http://40anos.nikkeybrasil.com.br/jp/biografia.php?cod=122)。
そこに《1966年9月サントス着のさくら丸120名以上の移住者を乗せて来たさくら丸の40年目の同船者会を計画 『さくら丸 私達の40年』を計画したい》との一文があった。同じ船でジアデマ市に渡りそこで定住された方が、さくら丸の同船者会の計画を呼びかけられているのである。呼びかけた方の写真が掲載されているが、40年の歳月の重みがあった。
1966年の前半に大きな航空事故が相次いだ。2月4日には全日空ボーイング727型機が羽田空港着陸直前に東京湾に墜落して、133人死亡という当時として世界航空史上最大の遭難を引き起こした。3月4日にはカナダ航空DC8型機が濃霧で羽田空港防潮堤に激突炎上して、64人の死者を出した。さらに翌3月5日にはBOACボーイング707型機が富士山付近で空中分解し、124人が全員死亡したのである。
このように航空事故が相次いだものだから、私が船で渡米するというとその慎重さを変に感心されたり、『こわがり』を揶揄する友人もいた。しかし私の動機は航空機事故とは一切関係なく、敗戦後引き揚げ船こがね丸で朝鮮から博多の港に戻ってきたときの思い出にあったのである。 続く
太平洋を船で渡りアメリカ大陸を汽車で横断するという夢をかねてから暖めていた私は、またとないチャンスとばかりに船の便を探して商船三井の『さくら丸』を見つけたのである。アメリカでの契約は9月からだったので確か7月の終わり頃に神戸を出帆するさくら丸は時期的に最適であった。
私の記憶では、その頃のアメリカ航路の客船として有名だったのは、アメリカの船会社「アメリカン・プレジデント・ラインズ」 のプレジデント・クリーブランド号やプレジデント・ウィルソン号であった。そして大阪商船の「ぶらじる丸」に「あるぜんちな丸」は南米移民船として建造されたが、もちろんアメリカ航路にも使われていた。
一方1962年に見本市船として建造されたのが「さくら丸」で、輸出振興目的で世界各国に出かけて産業巡行見本市の動く展示場となっていた。


いろいろな日本製品を陳列して諸外国に寄港しては、各国の人達に見ていただくのである。要するにメイド・イン・ジャパン製品の売り込み船、日本はまだそのような時代だったのである。
見本市船として使われていない間は、商船三井が移民船として南米まで運航していた。この「さくら丸」が時期的にはちょうど都合がいいのである。神戸の海岸通りにある商船三井のビルに出向き、いろいろと説明を聞いた上乗船予約をした。
何をどう考えてそうなったのか、今では記憶が定かでない。BRIDGE DECK、すなわち船橋楼甲板にある一等船客室を海側と内側の二部屋を続きで予約した。夫婦に子供二人で一部屋は窮屈だろうとその時思ってのであろうが、考えてみたら贅沢な話ではあった。デッキプランが手元に残っているが、117号室(海)と127号室(内)に斜線を入れているのでこの二部屋を占めたのであろう。右舷にあった。
それぞれの部屋にベッドが二台にソファー、洗面台にクローゼットがあり、シャワー室が二部屋を繋ぐ形で設けられていた。それぞれの部屋から入れるように扉は2カ所にあるが、一方が使っているときは他方をロックするようになっていた。もちろんわが家族にとってはこれが通路になった。
私は日記をつける習性もなく、記録をとり続けるほど几帳面でもないので日時のことは分からない。手元に残した品々が当時の記憶を甦らせる手助けになるのであるが、この品々もかなりの部分がさる阪神大震災以来未だに行方不明である。従って神戸を出帆した日も不明であるが、航行中に娘の8月8日の誕生日を船で祝っていただいたことははっきりと覚えているので、だいたい7月末かな、と見当をつけたのである。ところが私と同じ「さくら丸」に乗船された方のウエブサイトを探し当てることが出来た(http://40anos.nikkeybrasil.com.br/jp/biografia.php?cod=122)。
そこに《1966年9月サントス着のさくら丸120名以上の移住者を乗せて来たさくら丸の40年目の同船者会を計画 『さくら丸 私達の40年』を計画したい》との一文があった。同じ船でジアデマ市に渡りそこで定住された方が、さくら丸の同船者会の計画を呼びかけられているのである。呼びかけた方の写真が掲載されているが、40年の歳月の重みがあった。
1966年の前半に大きな航空事故が相次いだ。2月4日には全日空ボーイング727型機が羽田空港着陸直前に東京湾に墜落して、133人死亡という当時として世界航空史上最大の遭難を引き起こした。3月4日にはカナダ航空DC8型機が濃霧で羽田空港防潮堤に激突炎上して、64人の死者を出した。さらに翌3月5日にはBOACボーイング707型機が富士山付近で空中分解し、124人が全員死亡したのである。
このように航空事故が相次いだものだから、私が船で渡米するというとその慎重さを変に感心されたり、『こわがり』を揶揄する友人もいた。しかし私の動機は航空機事故とは一切関係なく、敗戦後引き揚げ船こがね丸で朝鮮から博多の港に戻ってきたときの思い出にあったのである。 続く