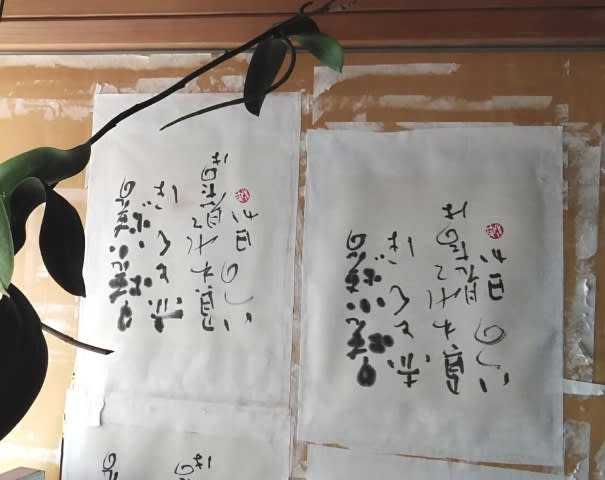ネックスピーカーのようなもの 試作1号
ネックスピーカーのようなもの 試作1号
先日テレビで、今年流行ったものを紹介する番組を見た。
その中で気になったのがネックスピーカー。
家族に邪魔にならない様に、テレビやステレオを聴くときは、やはりイヤホーンを使う。
でもちょっと厄介。
ポケットラジオならばいいけれど、そうではない場合は、動きが制限される。
そして、なんといっても耳が痒くなるのが問題だ。
何かよい対策はないものかと、常々感じていたので、これだ!と思った。
しかし、例によって、こんな高価なものは買えない。
ならば、作るか。
そう、やはり作るしかない!
というわけで、試作1号がこれ。
材料は、廃材の段ボール箱と何かの芯、そして、いつものダイソー300円スピーカーユニットだけ。
難しいのは、段ボールを立体的に組み立てること。
一応スピーカーだから、箱の中の空間が大切だ。
スピーカー自体は慣れたもの。
ちょっと調べれば、いろいろのネックスピーカーの写真や仕様が分かるので、形とスピーカーユニットの位置を参考にさせてもらった。
筒は変形の四角形。
スピーカーからの音が、耳の方に向く様に、角度をつけてある。
高音はスピーカーユニット近くから、低音は、先の方の穴から出る仕組みだ。
ただ、実際に実物を見ても、体験もしていないので、何とも言えないところだ。
それに、なんといっても、費用324円なので、bluetoothe なんて搭載できないから、コードがどうしても付いている。
完全に自由に動き回れるわけではない。
でも、これは延長コードで何とかなるとする。
で、スピーカーユニットの組み込みとコードの接続、全体の組み立てを平行して行い、一応組上がって、ボンドの乾くのを待っているところ。
乾いたら、仕上げとして、継ぎ目の補強に和紙を貼っていこうと思っている。
音?
ちゃんと実験しましたよ。
肩に掛ければ、耳元で鳴ってくれます。
これでテレビの映画もちょっと変わることでしょう。
少なくとも、耳の痒いのには効果がある。