前回は手技療法は触診が「命」と書きましたが、その触診の感覚をいかに鍛えていくのかというのが今回のテーマです。
触診 によって、腫れや熱感、圧痛や硬結など大切な情報をとらえることができますが、その中のひとつに、関節がうまく動いていないという 「可動制限」 があります。
によって、腫れや熱感、圧痛や硬結など大切な情報をとらえることができますが、その中のひとつに、関節がうまく動いていないという 「可動制限」 があります。
肩や肘などの大きな関節なら、視診である程度わかりますが、脊椎のような小さな関節が連続しているものではどうでしょう?
一部の椎間関節が動かなくたって、脊柱の他の部分でカバーするだけの余裕がありますから、部分的な可動制限は目立たないこともあります。
でも、この一部が動かないために不快な症状を出したり、他の部位にムリをかけることもになります。
脊柱のモビライゼーションは、このような分節的な可動制限に対して有効なテクニックですが、どこにどのような制限があるのか分からなければ使うことはできません
そこで、脊椎の分節的な可動性を感じとる感覚を磨く必要があるわけです
まずは、頚椎からはじめましょう。触れる指は人差し指や中指など、使いやすい指でかまいません。

後頭部に触れて、指を下方にすべらせると第2頚椎の棘突起に触れます。これは大きいからわかりやすいですね。
さらに下にすべらせると第3・4頚椎と続くはずですが、これらは棘突起が小さいのでなかなか分かりにくいと思います

頚椎を屈曲させることで触れやすくなる方もいらっしゃいます。このときのコツは、顎を引くようにして頚椎の前弯をとるように屈曲させること。頭部を前に倒すと起立筋が緊張してかえってわかりにくくなります。
続いて第5・6・7頚椎、これは触れやすいですね
それでは、この第5・6頚椎の棘突起間で動的触診(モーションパルペーション)の練習をしてみましょう
まず指を棘突起間に当てて、それから頭部を前屈してみてください。
典型的頚椎は、関節面が斜め45°で前上方に向かっているので、第5頚椎の棘突起が前上方にすべっていくのが感じられるはずです。
いかがですか?
では次に頭部を後屈しましょう。今度は第5頚椎の棘突起が、後下方にすべりおりてくるように感じられると思います。
これが動いているという感覚です
この「すべり」が起こっていない状態が脊椎可動制限の状態です。
「動いていない」という可動制限を感じとるためには、「動いている」という感覚をたくさん経験する必要があります
多くの椎間関節の正常可動域は10°以内、だいたい5°前後なので、動いているといってもほんのわずかですから、はじめのうちは???と思うかもしれません。
根気が必要です



「動いている」という感覚を養ったうえで、「動いていない」関節に出会うと、『アレッ、何か変だぞ 』という違和感を覚えます。
』という違和感を覚えます。
臨床では、この違和感が大切なんですね
そこから違和感の中身がいったい何なのか、より詳しく調べていきます。ここで、解剖学をはじめとした医学的知識がより生きてきます
とにかく、「おかしい」ところをまず見つけられないと、時間が限られる現実の臨床ではとても間に合いません
ですから学生さんは、まず下部頚椎で「動いている」という感覚をしっかり身につけて練習しましょう
次回以降は、頚胸移行部、そして腰椎に入っていきます。
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
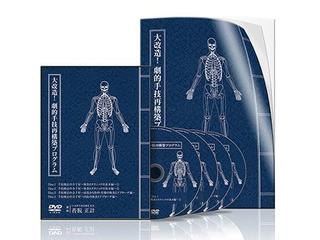
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」
触診
 によって、腫れや熱感、圧痛や硬結など大切な情報をとらえることができますが、その中のひとつに、関節がうまく動いていないという 「可動制限」 があります。
によって、腫れや熱感、圧痛や硬結など大切な情報をとらえることができますが、その中のひとつに、関節がうまく動いていないという 「可動制限」 があります。肩や肘などの大きな関節なら、視診である程度わかりますが、脊椎のような小さな関節が連続しているものではどうでしょう?
一部の椎間関節が動かなくたって、脊柱の他の部分でカバーするだけの余裕がありますから、部分的な可動制限は目立たないこともあります。
でも、この一部が動かないために不快な症状を出したり、他の部位にムリをかけることもになります。
脊柱のモビライゼーションは、このような分節的な可動制限に対して有効なテクニックですが、どこにどのような制限があるのか分からなければ使うことはできません

そこで、脊椎の分節的な可動性を感じとる感覚を磨く必要があるわけです

まずは、頚椎からはじめましょう。触れる指は人差し指や中指など、使いやすい指でかまいません。

後頭部に触れて、指を下方にすべらせると第2頚椎の棘突起に触れます。これは大きいからわかりやすいですね。
さらに下にすべらせると第3・4頚椎と続くはずですが、これらは棘突起が小さいのでなかなか分かりにくいと思います


頚椎を屈曲させることで触れやすくなる方もいらっしゃいます。このときのコツは、顎を引くようにして頚椎の前弯をとるように屈曲させること。頭部を前に倒すと起立筋が緊張してかえってわかりにくくなります。
続いて第5・6・7頚椎、これは触れやすいですね

それでは、この第5・6頚椎の棘突起間で動的触診(モーションパルペーション)の練習をしてみましょう

まず指を棘突起間に当てて、それから頭部を前屈してみてください。
典型的頚椎は、関節面が斜め45°で前上方に向かっているので、第5頚椎の棘突起が前上方にすべっていくのが感じられるはずです。
いかがですか?

では次に頭部を後屈しましょう。今度は第5頚椎の棘突起が、後下方にすべりおりてくるように感じられると思います。
これが動いているという感覚です

この「すべり」が起こっていない状態が脊椎可動制限の状態です。
「動いていない」という可動制限を感じとるためには、「動いている」という感覚をたくさん経験する必要があります

多くの椎間関節の正常可動域は10°以内、だいたい5°前後なので、動いているといってもほんのわずかですから、はじめのうちは???と思うかもしれません。
根気が必要です




「動いている」という感覚を養ったうえで、「動いていない」関節に出会うと、『アレッ、何か変だぞ
 』という違和感を覚えます。
』という違和感を覚えます。臨床では、この違和感が大切なんですね

そこから違和感の中身がいったい何なのか、より詳しく調べていきます。ここで、解剖学をはじめとした医学的知識がより生きてきます

とにかく、「おかしい」ところをまず見つけられないと、時間が限られる現実の臨床ではとても間に合いません

ですから学生さんは、まず下部頚椎で「動いている」という感覚をしっかり身につけて練習しましょう

次回以降は、頚胸移行部、そして腰椎に入っていきます。
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
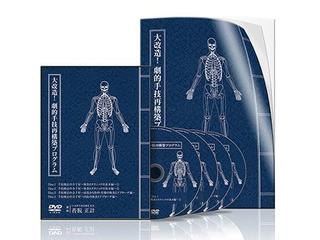
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」

















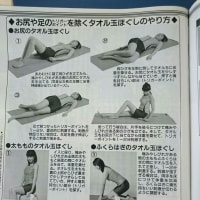


ご質問いただいた両方のケースがありえると思います。
単純化して考えると、ねじれの中心が胸腰部だと、骨盤と脊柱は同じ方向の可能性が高いかもしれません。
また、それが腰仙部に起こったとすると、反対方向の可能性が高いと思います。
ただ臨床的に重要なのは、見た目のねじれよりも、どの部位に関節機能障害が存在するかということです。
見た目のねじれは、それを見つけるための手がかりと言っていいかもしれません。
さらに大切なのは、どのような身体の使い方をしたためにそのようなねじれが起こったかを知るというだと思います。
体性機能障害の本当の原因は、ねじれではなく、生活との接点にあるからです。
ご参考になさってください。
骨盤についてなのですが俗によく骨盤が開くとか閉じるなどと表現されていますが解釈としては自分はASとへそとの距離が広がることを開くと思っているのですが間違っていないでしょうか?
ご質問につきまして、私ものりおさまと同じ意味で使っています。
ただ、この業界のややこしいところで、整体などの流派?によって、意味合いが異なるところがあるようです。
例えば、以前ある人と話していたとき、どうも話がかみ合わないのでよくよく聞いてみると、骨盤が上方に回転している状態を「開く」と表現されていました。
用語の統一が、業界の中でされていないというのが混乱を招いていると思います。
ちなみにオステオパシーではASISを指標にして、骨盤が「開いて」いる状態をアウトフレアー腸骨、「閉じて」いる状態をインフレアー腸骨と呼んでいます。
ところがカイロプラクティックでは、PSISを指標にしているので骨盤が「開いて」いる状態をIn腸骨(In=内方)、「閉じて」いる状態をEx腸骨(Exit=外方)と呼んでいます。
慣れないとややこしですよね。
骨盤を3次元でイメージするようになさるとよいと思います。
体のゆがみを見るケースで正中線?中心線?からみて判断するような記述を見かけるのですが体のどこを基準にして中心線からずれてるとかがわかるのでしょう?例えばおへそを中心と見るものなのか・・・
とてもよいところに気付かれたと思います。
中心線の基準をどこにするかというのも、あいまいですよね。
両足の真ん中とするのか?ヘソとするのか?鼻とするのか?
鼻を基準にすればヘソがずれているといえるし、ヘソを基準にすれば鼻がずれているといえる。
悩ましい問題ですが、絶対的な基準はまだないと思います。
私の解釈はその症例の中で、鼻とヘソを結ぶラインが垂直線上にきていませんよ、ということをこの著者は言いたいのだろうと理解しています。
それが治療後に垂直ラインに近づいたら、改善したといえるという、相対的な基準だと考えています。
ご参考になさってください。
骨盤の周囲を観察していて自分はまだよくわからないのですが、本を読んでいると骨盤を上から見て左に回旋しているケースが多いと書いてました。そうだと思っていたら最近読んでいる本には右回旋している人が覆いと書いてあります??混乱してきます。
先生はどのようにお考えでしょうか?
このテの情報は、いろいろなところで氾濫していて、互いに矛盾していることもあり、混乱してしまいますよね。
でもそのような話は、著者の個人的見解という程度にとどめておいたほうがよいと思います。
それぞれの視点で述べているので、必ず偏りがあるからです。
もちろん、ひとつのモデルとして参考になさるのは良いと思います。
ただそれが、先入観になってしまうなら「百害あって一利なし」でしょう。
大切なことは、目の前にいる患者さんの状態がどうであるかということを、素直に診るということだと私は思います。
機能障害は様々なので、はじめからパターンに当てはめるのではなく、現場で検証していくことが大切です。
ですから、結果的に「この患者さんの体はどうだった」というエピソードはいろいろありますが、どの偏位が多いなどということは予め考えないようにしています。
ご参考になれば幸いです。