先日のセミナーでのこと。
いつもは手技療法の実技ばかりやっていますが、ひょんなことから問診の注意点も少しお話させていただきました。
それは手技療法を行うなら「問診だけで見切ったつもりにならず、可能な限り患部に触れて状態を確認する」ということです。
視診(動作分析)についても同じことがいえるでしょう。
そして「触れる際には、問診で得た情報はいったん頭の脇に置いて触れる」つまり「先入観を持って触れない」ということ。
先入観を持って触れると手から伝わる情報を、自分の考えに都合の良いよう解釈しやすいからです。
あくまで触診で得られた情報からそれが何を意味するかを検討し、問診で得られた情報とつじつまが合うか照合していくようにします。
例えばひとつのケースとして、問診で安静時の持続痛や、視診にて多方向への運動時痛が同じ部位に出現していれば、組織破壊とそれに伴う炎症が生じていると考え、患部に対して直接介入するのは禁忌と判断するかもしれません。
でもそれだけで見切ったつもりにならず、先入観を持たずに患部に触れてその状態を確認しましょう。
(もちろん激痛で身動きがとれない時など例外はあります)
炎症が起きている部位には、熱感と共に組織の脆弱性や局所性の浮腫、もしくは腫れを伴う過緊張がみられます。
発赤は浅いところや強い炎症ならわかいやすいのですが、深部にある時は確認しにくいもの。
その時は「熱感」が手掛かりになります。
手でそっと患部に触れると、表面はさほどでもなくても、奥のほうから温かさを感じることがあります。
ちょうどストーブから離れたところで、手をかざしているような感じでしょうか。
目を閉じていても熱源がどのあたりか大よそ見当がつく、ということと似ているかもしれません。
触れずにかざしたほうがよくわかるという場合はそれでもOK。
自分のわかりやすいほうで行えばよいでしょう。
私は念のため、両方用いることもあります。
実際に触れてみて、周囲より患部の温度が高くなっているようなら、炎症を起こしている可能性はより高くはなるでしょう。
けれども、これで決定とはなりません。
問診や視診によって安静時痛と運動時痛を認めても、比較的軽度であり、触診で熱感があっても、脆弱性や強い腫張がない。
そんな時、試験的に周囲の緊張を低下させてみると、熱感が引いて安静時痛・運動時痛が軽減することもあります。
結果的にこの場合の症状は、炎症より充血による影響が大きかったのかもしれません。
あるいは、安静時痛や運動時痛があり、触診で熱感を患部の認めても脆弱性や強い腫脹はないという同じ状況に加え、、局所的な緊張を触知できるなら、それは活動性のトリガーポイントによる症状のこともあります。
この場合は、患部に対して刺激量を考慮しつつ、直接的にアプローチしていくことも私は検討します。
適応と禁忌の鑑別についてはグレーゾーンも少なくありません。
だからこそ簡単に見切らず、必ず患部に触れてその状態を確認すべきです。
患者さんの心情としても、患部の状態を確認しないまま治療を進めて改善感が乏しかった場合、不安や不信感を持ってしまうこともあるかもしれません。
遠隔的なアプローチをする場合、特にそうでしょう。
「問診で8割は決まる」という話もあるくらい、問診は非常に重要なもの。
けれども手技療法を用いるのであれば、触診による情報も重視されるべきであり、そのための触診能力は高めておかなければならないと思います。
いつもは手技療法の実技ばかりやっていますが、ひょんなことから問診の注意点も少しお話させていただきました。
それは手技療法を行うなら「問診だけで見切ったつもりにならず、可能な限り患部に触れて状態を確認する」ということです。
視診(動作分析)についても同じことがいえるでしょう。
そして「触れる際には、問診で得た情報はいったん頭の脇に置いて触れる」つまり「先入観を持って触れない」ということ。
先入観を持って触れると手から伝わる情報を、自分の考えに都合の良いよう解釈しやすいからです。
あくまで触診で得られた情報からそれが何を意味するかを検討し、問診で得られた情報とつじつまが合うか照合していくようにします。
例えばひとつのケースとして、問診で安静時の持続痛や、視診にて多方向への運動時痛が同じ部位に出現していれば、組織破壊とそれに伴う炎症が生じていると考え、患部に対して直接介入するのは禁忌と判断するかもしれません。
でもそれだけで見切ったつもりにならず、先入観を持たずに患部に触れてその状態を確認しましょう。
(もちろん激痛で身動きがとれない時など例外はあります)
炎症が起きている部位には、熱感と共に組織の脆弱性や局所性の浮腫、もしくは腫れを伴う過緊張がみられます。
発赤は浅いところや強い炎症ならわかいやすいのですが、深部にある時は確認しにくいもの。
その時は「熱感」が手掛かりになります。
手でそっと患部に触れると、表面はさほどでもなくても、奥のほうから温かさを感じることがあります。
ちょうどストーブから離れたところで、手をかざしているような感じでしょうか。
目を閉じていても熱源がどのあたりか大よそ見当がつく、ということと似ているかもしれません。
触れずにかざしたほうがよくわかるという場合はそれでもOK。
自分のわかりやすいほうで行えばよいでしょう。
私は念のため、両方用いることもあります。
実際に触れてみて、周囲より患部の温度が高くなっているようなら、炎症を起こしている可能性はより高くはなるでしょう。
けれども、これで決定とはなりません。
問診や視診によって安静時痛と運動時痛を認めても、比較的軽度であり、触診で熱感があっても、脆弱性や強い腫張がない。
そんな時、試験的に周囲の緊張を低下させてみると、熱感が引いて安静時痛・運動時痛が軽減することもあります。
結果的にこの場合の症状は、炎症より充血による影響が大きかったのかもしれません。
あるいは、安静時痛や運動時痛があり、触診で熱感を患部の認めても脆弱性や強い腫脹はないという同じ状況に加え、、局所的な緊張を触知できるなら、それは活動性のトリガーポイントによる症状のこともあります。
この場合は、患部に対して刺激量を考慮しつつ、直接的にアプローチしていくことも私は検討します。
適応と禁忌の鑑別についてはグレーゾーンも少なくありません。
だからこそ簡単に見切らず、必ず患部に触れてその状態を確認すべきです。
患者さんの心情としても、患部の状態を確認しないまま治療を進めて改善感が乏しかった場合、不安や不信感を持ってしまうこともあるかもしれません。
遠隔的なアプローチをする場合、特にそうでしょう。
「問診で8割は決まる」という話もあるくらい、問診は非常に重要なもの。
けれども手技療法を用いるのであれば、触診による情報も重視されるべきであり、そのための触診能力は高めておかなければならないと思います。

















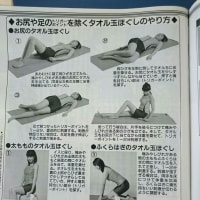


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます