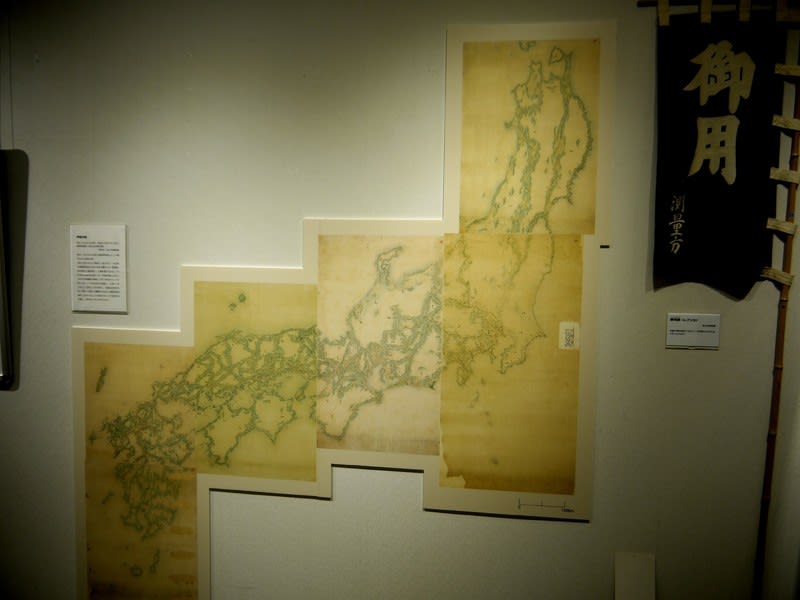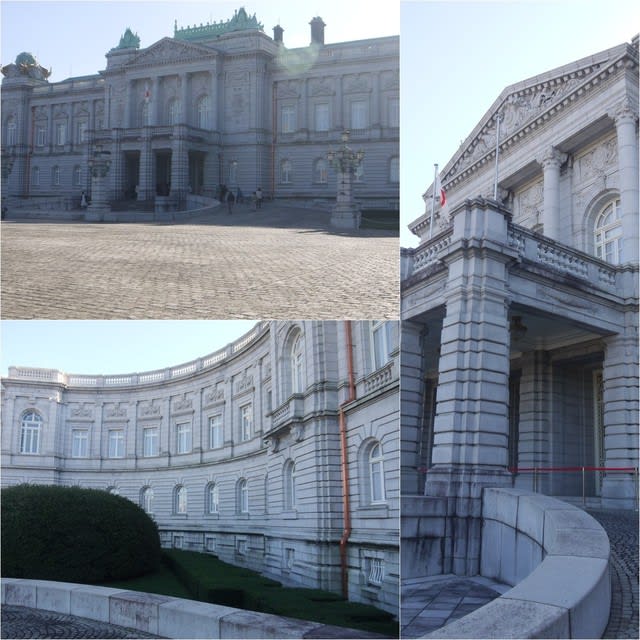博物館内常設展の写真撮影については、撮影スポットを4ヶ所設けているので、その場所での画像のみUPします。館内では遺跡展示、江戸時代、昭和など年代にそって展示しており、常設展示解説シートがあり子どもの学習活動の参考資料が充実している。

江戸四宿の一つ内藤新宿は、日本橋を起点とした甲州街道の最初の宿場です。はじめ下・上高井戸宿(しもかみたかいど)が最初の宿場でしたが日本橋から4里(約15km)と遠いため、元禄11年(1698)江戸浅草阿部川町の名主喜兵衛(のち喜六)らが、茅野原(かやのはら)だったこの辺りを開発しました。こうして日本橋から2里のところに宿場集落ができ町の一部が内藤家の屋敷地でしたので内藤新宿といわれました。五街道は、道中奉行が管理し、脇住還は各藩や代官所が管理しました。幕府は、五街道の各宿場に人馬、荷物、乗物などの利用について細かい規定をし、大名といえどもこの規定に従うよう定めました。


※「江戸名所図会」の「淀橋水車」
左に「淀橋」左下に「淀橋水車」が描かれ、江戸近郊の農村である。
商人は職人とともに町の代表的な一員でした。江戸時代には、「士農工商」といわれ、武士、農民、職人よりも低く位置づけられていましたが、しだいに江戸の経済を支える存在となりました。展示している商家は、店蔵(見世蔵とも言う)で江戸時代から明治時代に盛んに建てられました。店蔵は周りを漆喰で覆った防火建築です。火災がおこると二階の扉や一階の防火戸を閉め、隙間は出入りの左官が土でふさいだといわれています。本来は、物資の貯蔵、保存する蔵ですが、江戸の商人は自らの財産をまもるため、住居や店舗にもその工法を使うようになりました。東京の蔵造り建築は関東大震災で非常にもろかったことが原因でこれを境に急速に少なくなりました。

「チンチン電車」の名で親しまれた昭和のはじめの東京市電は、その路線が網の目のように広がり、市民の足として活躍する大通りの主役でした。特に新宿は、郊外から都心に向かう通勤者の乗り換え利用客が多く、昭和2年(1927)には乗降客が東京駅を抜いて日本一になっています。
昭和5年には、市電としては初めての半鋼製の大型ボギー車5000形が製造されて、11・12系統を走りました。
昭和10年(1935)の新聞に、東京の盛り場での騒音調査をした結果が掲載され。電車、バス、円タクで新宿が一番の騒々しい場所で、特に市電が通る時がひどく市電を「わめく鬼」とまで言われました。

昭和10年頃の落合に、住んでいた若いサラリーマンの住居が展示してあります。
大正の末から昭和の初めにかけて、山手線の外側に、サラリーマンの住宅が建ち並びます。
これは、新宿・渋谷・池袋などを起点とした郊外電車の交通網が形成され、それに合わせて鉄道会社が沿線の宅地開発を進めたためです。当時、関東大震災で被害の大きかった下町の人々や、地方から東京へやってきた新市民がすでに住宅不足で飽和状態だった旧市域(本所・深川から山手線の内側)から郊外の沿線に移り住みました。
目白文化村、田園調布、大泉学園、成城学園、国立などがあります。本格的な洋風住宅が多く建てられました。そうした住宅にあこがれ、小規模な和風住宅の玄関脇に洋間の応接をつけた「文化住宅」が流行していました。


かつて私が若いころ母と一緒に新宿駅に降りたとき、戦前の新宿しか知らない母があまりの変貌ぶりに驚いていたことを思い出す。毎年、何かが変わっていく新宿である。