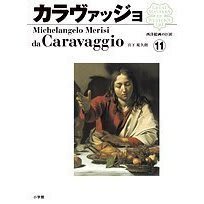お正月は本をまとめ読みするのに最適なので、積読(つんどく)状態で溜まっていた本を片付けることにした。中でも読み難かったアーウィン・パノフスキー著『ルネサンスの春』(原題:Renaissance and Renascences in Western Art)をようやく読み終えた。読んだからと言って、ちゃんと理解できたわけではないし、大体わかったという程度なのがド素人的に哀しい(^^;;;

『ルネサンスの春』を読み始めたのは、授業で薦められたこともあるが、一昨年のゲッティ美術館「Florence at the Dawn of the Renaissance」展を観て以来、ルネサンスとは何なのだ?というモヤモヤが頭に渦巻いていたからだ。(参照:一昨年のブログ)
もちろんモヤモヤ解消のため、ルネサンス関係の本を幾つか読んでみたりはしたのだが、残念ながらどうも私のモヤモヤのツボからズレていて解決しなかった。そして、ようやく巡り合ったのがこの『ルネサンスの春』だった。
嬉しくも、読んでスッキリしたことが2点ある。ひとつは、古典古代の文化がルネサンスまで全く途絶えていたわけではなく、波のように、カロリング・ルネサンスや12世紀の早期ルネサンスがあったこと。もうひとつは、ジョット後の14世紀後半になると、フィレンツェとシエナでは根本的な「様式と嗜好の変化」があり、古典古代の様式からも離れて行ったということ。私的に14世紀後半はジョッテスキよりも国際ゴシックが受けたということなんじゃないかと勝手に理解し手打ちしたのだ。
パノフスキーは言う。「そこで、14世紀末には、イタリア美術は北方美術とほとんど同じくらい根本的に、古代から隔絶していた。そして、真のルネサンスは、いわば零から誕生したのである。」
まぁ、なんて明快に言ってくれるのだろう(笑)。パノフスキーの時代から随分経つから、現代の通説では違う解釈になっている可能性がある。でも、ジョット以後のジョッテスキ作品にがっかりした私は、これでかなりスッキリしたのだった。お粗末(^^;;;

『ルネサンスの春』を読み始めたのは、授業で薦められたこともあるが、一昨年のゲッティ美術館「Florence at the Dawn of the Renaissance」展を観て以来、ルネサンスとは何なのだ?というモヤモヤが頭に渦巻いていたからだ。(参照:一昨年のブログ)
もちろんモヤモヤ解消のため、ルネサンス関係の本を幾つか読んでみたりはしたのだが、残念ながらどうも私のモヤモヤのツボからズレていて解決しなかった。そして、ようやく巡り合ったのがこの『ルネサンスの春』だった。
嬉しくも、読んでスッキリしたことが2点ある。ひとつは、古典古代の文化がルネサンスまで全く途絶えていたわけではなく、波のように、カロリング・ルネサンスや12世紀の早期ルネサンスがあったこと。もうひとつは、ジョット後の14世紀後半になると、フィレンツェとシエナでは根本的な「様式と嗜好の変化」があり、古典古代の様式からも離れて行ったということ。私的に14世紀後半はジョッテスキよりも国際ゴシックが受けたということなんじゃないかと勝手に理解し手打ちしたのだ。
パノフスキーは言う。「そこで、14世紀末には、イタリア美術は北方美術とほとんど同じくらい根本的に、古代から隔絶していた。そして、真のルネサンスは、いわば零から誕生したのである。」
まぁ、なんて明快に言ってくれるのだろう(笑)。パノフスキーの時代から随分経つから、現代の通説では違う解釈になっている可能性がある。でも、ジョット以後のジョッテスキ作品にがっかりした私は、これでかなりスッキリしたのだった。お粗末(^^;;;