「雁と雁の子」 [父・水上勉との日々]
著者 窪島誠一郎 平凡社 刊 2005.8.8 初版第一刷 157頁 1600円
ー帯ー
いまは亡き、父への手紙 劇的な「邂逅」から27年、はじめて語られる父への想い
水上 勉 私の好きな作家の一人だ。氏の故郷である若狭。私ももう半世紀も昔か、4歳から12歳まで同じ若狭湾の西のはずれ、丹後の宮津で過ごしたことがある。
氏の作品には、そのどれを読んでもといってもそれほど多くを読んだわけではないが、故郷、若狭の独特の風土が色濃く感じられる。
「うらにし」といわれると日本海特有の気候、夏から冬にかけてカラッと晴れる日は少なく、照ったり曇ったり、かと思うとしとしとと雨になったりと、鬱陶しい日が続く。
そうした中で暮らしていると人の心もまた、うつうつとして、うらみっぽく、陰があって、といって人柄が悪いというわけではないのだが、どことなく言いたいことを言わずに自分のうちにためこんでしまうと言うふうになる。
氏の作品には、そんな若狭人の湿っぽい恨み節が嫋嫋綿綿として伝わってくるように感じられる。
だからこそ、しみじみと氏の語り口に惹かれて一冊を読んでしまうのである。
27年前、劇的な「邂逅」と報じられた、大作家「水上 勉」が、まだ無名の若き日に心ならずも生ませ、貧しさ故に他人に渡してしまい、あの戦争で消息不明となった我が子に戦後30年余りもたって再会した事件。
この事実をもとに、昭和55年3月、氏は「冬の光景」(毎日新聞社刊)を上梓した。
その出版広告文には次のように記されている。
ー男と女の結びつき、親と子の絆とは所詮なんなのだろうかー死んだと思っていたわが子とのおもいもかけない30余年ぶりの邂逅ー「私」はふさがりかけていた傷口を自らおしあけ、指先を血にそめながら、古い暦をめくりはじめた。
内容は、この紹介文のとおりだった。重いものが伝わってきた。「事実は小説より奇なり」とはこのことかと思った。氏の作品の多くに感じる「人間の哀しみ」の原点がここにあるのかと思った。
よく自分をここまで丸裸にしてさらけだせるものだと思った。それがこちら側の心を打つ。自分の中にもあるいやらしさや狡さを白日のもとにさらけ出さされる思いがする。
この本に基づいてTVドラマ化されたのも視た。中村賀津男が窪島氏の養父の貧相ではあるが実直小心なな靴職人を好演していて印象に残った。
それ以来、新聞の文化欄やコラム等で二人の記事が出ると関心をもって見てきた。
今回も、本書についての新聞の書評(日経か?)を読んで早速買って読んでみた。
とても興味深かった。実の子でありながら、その実父に30過ぎて再会してみるとついに「お父さん」とは呼べないのである。甘えられないのである。
親と子の絆について深く考えさせられた。所詮、家族とは「血」有無ではなく、共に日々を泣いたり笑ったりして暮らす中でこそ育まれるものでしかないのではないか。
だからこそ、子のない人や独り暮らしの人が犬や猫など、他人がみれば単なるペットでしかなくても、その当人にしてみれば「家族」同様となってしまうのではないか。
「雁と雁の子」文中P.152から
最初の心筋梗塞で倒れた頃、一度だけ「せいちゃんは僕のこと恨んでいるだろうな」とおっしゃるんです。しらばっくれて「何をですか」と聞いたら、「捨てたんだからな、お前を」というんです。
これが、実の父と子の会話である。
上掲、「冬の光景」の中で「せいちゃん」ができたことについて次のような一節がある。
…
その稲取増子が、急に私よりは倍ぐらいの身長と体重をもつ巨体に見えはじめ、のしかかる重さで気になりだしたのは、妊娠を告げられた日からだった。正直、夏の末に越してきて間もなかった私は、このアパートで彼女と知り合い、秋半ばにはもうそれを宣告されたので、間尺にあわぬようなきがしたのである。
俺の子か、と問いたかったのを押しころしていたように思う。彼女より一寸ぐらい背丈のひくい痩せっぽちの私には、彼女の「産みますよ」といったことばには威圧感があり、私は上目づかいに、背丈のたかい彼女のしたくちびるのあたりをみすえているしかなかった。
父、水上 勉 にとって、窪島誠一郎氏が「信濃デッサン館」や最近良く取り上げられる戦没画学生の遺作を収蔵した「無言館」等の設立者というような”優等生?”でなく、多額の借金を抱え著名な父の昔の非情を詰り、ゆすりたかりするような子であったら、あるいはもっと気がらくになれたのではないかという想像してみた。
また、子である窪島氏も、「父が著名な大作家でなかったら」どうであったろうかと思うのである。
ちなみに私は、4歳のときあの戦争で父をフイリッピンの戦野で失い、「父」を知らない。だから、よけいに「本書」にはある羨ましさを感じてもいる。
著者 窪島誠一郎 平凡社 刊 2005.8.8 初版第一刷 157頁 1600円
ー帯ー
いまは亡き、父への手紙 劇的な「邂逅」から27年、はじめて語られる父への想い
水上 勉 私の好きな作家の一人だ。氏の故郷である若狭。私ももう半世紀も昔か、4歳から12歳まで同じ若狭湾の西のはずれ、丹後の宮津で過ごしたことがある。
氏の作品には、そのどれを読んでもといってもそれほど多くを読んだわけではないが、故郷、若狭の独特の風土が色濃く感じられる。
「うらにし」といわれると日本海特有の気候、夏から冬にかけてカラッと晴れる日は少なく、照ったり曇ったり、かと思うとしとしとと雨になったりと、鬱陶しい日が続く。
そうした中で暮らしていると人の心もまた、うつうつとして、うらみっぽく、陰があって、といって人柄が悪いというわけではないのだが、どことなく言いたいことを言わずに自分のうちにためこんでしまうと言うふうになる。
氏の作品には、そんな若狭人の湿っぽい恨み節が嫋嫋綿綿として伝わってくるように感じられる。
だからこそ、しみじみと氏の語り口に惹かれて一冊を読んでしまうのである。
27年前、劇的な「邂逅」と報じられた、大作家「水上 勉」が、まだ無名の若き日に心ならずも生ませ、貧しさ故に他人に渡してしまい、あの戦争で消息不明となった我が子に戦後30年余りもたって再会した事件。
この事実をもとに、昭和55年3月、氏は「冬の光景」(毎日新聞社刊)を上梓した。
その出版広告文には次のように記されている。
ー男と女の結びつき、親と子の絆とは所詮なんなのだろうかー死んだと思っていたわが子とのおもいもかけない30余年ぶりの邂逅ー「私」はふさがりかけていた傷口を自らおしあけ、指先を血にそめながら、古い暦をめくりはじめた。
内容は、この紹介文のとおりだった。重いものが伝わってきた。「事実は小説より奇なり」とはこのことかと思った。氏の作品の多くに感じる「人間の哀しみ」の原点がここにあるのかと思った。
よく自分をここまで丸裸にしてさらけだせるものだと思った。それがこちら側の心を打つ。自分の中にもあるいやらしさや狡さを白日のもとにさらけ出さされる思いがする。
この本に基づいてTVドラマ化されたのも視た。中村賀津男が窪島氏の養父の貧相ではあるが実直小心なな靴職人を好演していて印象に残った。
それ以来、新聞の文化欄やコラム等で二人の記事が出ると関心をもって見てきた。
今回も、本書についての新聞の書評(日経か?)を読んで早速買って読んでみた。
とても興味深かった。実の子でありながら、その実父に30過ぎて再会してみるとついに「お父さん」とは呼べないのである。甘えられないのである。
親と子の絆について深く考えさせられた。所詮、家族とは「血」有無ではなく、共に日々を泣いたり笑ったりして暮らす中でこそ育まれるものでしかないのではないか。
だからこそ、子のない人や独り暮らしの人が犬や猫など、他人がみれば単なるペットでしかなくても、その当人にしてみれば「家族」同様となってしまうのではないか。
「雁と雁の子」文中P.152から
最初の心筋梗塞で倒れた頃、一度だけ「せいちゃんは僕のこと恨んでいるだろうな」とおっしゃるんです。しらばっくれて「何をですか」と聞いたら、「捨てたんだからな、お前を」というんです。
これが、実の父と子の会話である。
上掲、「冬の光景」の中で「せいちゃん」ができたことについて次のような一節がある。
…
その稲取増子が、急に私よりは倍ぐらいの身長と体重をもつ巨体に見えはじめ、のしかかる重さで気になりだしたのは、妊娠を告げられた日からだった。正直、夏の末に越してきて間もなかった私は、このアパートで彼女と知り合い、秋半ばにはもうそれを宣告されたので、間尺にあわぬようなきがしたのである。
俺の子か、と問いたかったのを押しころしていたように思う。彼女より一寸ぐらい背丈のひくい痩せっぽちの私には、彼女の「産みますよ」といったことばには威圧感があり、私は上目づかいに、背丈のたかい彼女のしたくちびるのあたりをみすえているしかなかった。
父、水上 勉 にとって、窪島誠一郎氏が「信濃デッサン館」や最近良く取り上げられる戦没画学生の遺作を収蔵した「無言館」等の設立者というような”優等生?”でなく、多額の借金を抱え著名な父の昔の非情を詰り、ゆすりたかりするような子であったら、あるいはもっと気がらくになれたのではないかという想像してみた。
また、子である窪島氏も、「父が著名な大作家でなかったら」どうであったろうかと思うのである。
ちなみに私は、4歳のときあの戦争で父をフイリッピンの戦野で失い、「父」を知らない。だから、よけいに「本書」にはある羨ましさを感じてもいる。



















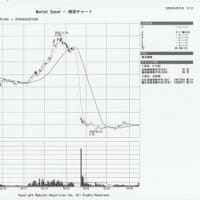
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます